東アジア討論室
混み入った議論と一対一の論争は討論室で行いましょう。
投稿の大項目はスレッドで投稿してください。
そのスレッドに対するはレスとして投稿してください。
レスに対する意見もレスとして投稿してください。
スレッド作成での留意事項
●(新規作成の)スレッドには、タイトル(内容の紹介)と自分の名前を入れて下さい。
●みんなの関心事項については、「会」として、スレを(追加で)設けることもあります。
要望事項
●「返信・引用」を使う場合は、不要なところは削除したうえで、お使いください。(1回のみ)
●「返信・引用」は、多用すると、返信の返信となると、誰の発言か分かりにくいので、控えて下さい。
●また、文章では、適当なところで、右側に「改行マーク」を入れて下さい。(一行、45文字程度)
●また、一文(~。)の長さは、長くて3行まで、(およそ、150文字以内:推奨100文字以内)にして下さい。
●文章は、残ることを念頭に、マナーに気を付けて、楽しく(議論は熱く)投稿しましょう。
(スレ)「蚕・絹・機織」について - 米田
2022/08/13 (Sat) 11:05:10
(常陸国風土記:P-028)
:綺日女命・常陸国_筑紫の日向→三野(美濃)
:綺(日女)=神機(姫)=かむはた(ひめ)
(常陸国風土記:P-028)
:古老がいうことには、
:「すめみまの命(皇孫瓊瓊杵命)が天からお降りになったとき、
:御服(みぞ)を織るために従って降った神、み名は、綺日女命は、
:もと筑紫の日向の二所(ふたがみ)の峯より、
:三野(美濃)の国の引津根の丘においでになった。
:後、みまき天皇(崇神天皇)のみ世になって、長幡部の遠祖多弖
:(たて)命は、三野(美濃)を去って、久慈に移り、
:機殿(はたどの)を造り立てて初めてこれを織った。
:その織るところの布はひとりでに衣裳(きもの)となり、
:あらためて裁ち縫う必要がなく、これを内幡(うつはた)
:(完全な服:はた)といっている。」
:あるひとはこうもいう、
:「絁(あしぎぬ:太絹)を織るときにあたって、容易に人に見られて
:しまうので、家のとびらを閉じきって暗闇のなかで織った。云々。」
*****
ここでは、「蚕・絹・機織」は、半島から伝わって来たと仮説を立てて、
おもに半島から九州への伝播について、検証・考察をしたいと思います。
Re: (スレ)「蚕・絹・機織」について - 石見介
2025/05/14 (Wed) 14:42:55
米田さん
縄文(人)系、弥生(人)系の定義を、系譜によって行うとは、流石にそれはないだろうと思い、質問したのですが・・・。
時代区分は、歴史学のこんぽんですから、基本的に、若干の研究者による相違はあっても、おおみね共通しており、その土俵上での、我々古代史愛好家も、議論しています。
おそらく、『桓檀古記』の系譜かと思われますが、系譜自体の資料批判も、問題でしょう。
基本的な学術用語は、数学に於ける「公理」のようなものですから、せめてそれは順守されないと、討論は、換算に不可能になってしまいます。
編集未済
Re: (スレ)「蚕・絹・機織」について - 米田
2025/05/13 (Tue) 23:22:16
 ┌
┌
│〉朴氏は、もともと縄文人の系統ですから、〈
│ の根拠は、何でしょうか?
└
:するどいご指摘、ありがとうございます。
┌
│BC 2392年(BC24世紀)復解の 61世孫で
│ある豊が蘇城(吉林省)の河伯に封ざれ、
│BC 209年豊の 69世孫蘇伯孫が辰韓を建国したと言う。
└
:私の中の「弥生人」は、弥生時代中期から後期に
:倭国にやって来た連中をイメージしています。
:(加耶とか、AD42年生の金首露のイメージが強いです。)
:縄文時代も弥生時代も古墳時代も、何回も、移住があったと思います。
:
:そうすると、BC210年よりも古くから、半島南部・倭国に
:住んでいた連中を、どう呼ぼうかと考えた結果、
:「縄文人の系統」としました。実際には、
:「縄文人の血が強く残っている初期の弥生人」の方が
:正確かもしれませんです。
:もっと正確な表現があるかも知れません。
*****
(タイトル)加耶の変遷から見た倭国の統一
:米田喜彦_2015-08-30(加筆修正)/抜粋(2025-05-13)
ここで、各部族(族長)の流れを、
ウィキペディアや三国史記などから調べてみます。
①金氏は、帯素の従兄弟が玄菟郡の掾那部に属しています。
夫余王の帯素が亡くなった後も、金氏として、生き残っていたようです。
②羽(于)氏です。朱蒙は、もしかすると、許氏かもしれません。
紀元前1世紀に、突然現れて、馬韓地方を治めていきます。
また、隋の時代の宇文 化及(うぶん かきゅう)は、隋末の混乱期に
独立して皇帝を僭称し、「許」を建国していることから、「宇文氏」も、
「羽(于)氏」=「宇文氏」=「許氏」ではないかと、推測しています。
③朴氏です。赫居世(BC69頃生)もと倭人で半島にやって来た。
(朴氏・瓢公)
新羅第53代国王、神徳王は、第8代阿達羅王の23代孫と云われています。
新羅本紀には、阿達羅王の子どもは出てきませんが、倭国の卑弥呼が、
173年に(倭国に)来訪させたとありますから、倭国の方で子どもが
生まれている可能性が考えられます。朴氏には、
婆娑王(子孫・朴堤上)の系統と、阿達羅王の系統があります。
婆娑王の系統は、朴堤上の代で没落しています。ですので、朴氏の王族の
系統としては、7世紀には阿達羅王の子孫が残っていると考えられます。
ここで、「蘇」について、少し書きます。
※
伯孫の 29世孫慶は新羅真徳女王の時、最高官職である上大等となった。
‥‥この時代、新羅の王族には、金氏と朴氏しかいませんので、
この「蘇氏」は、「朴氏」の可能性が高いです。もちろん、
小野妹子(蘇因高)も、「蘇我」も、「蘇」の一族と考えられます。
「神統譜・中臣氏」によると、「天御中主神」を初代(1代目)と
すると、30代目は、「藤原鎌足(614年生)」になります。
ですので伯孫の 29世孫「慶」は、「藤原鎌足」又は、「鎌足の父」の
可能性が考えられます。
※:「小野妹子」<ウィキペディア>より
:『日本書紀』によると大唐に派遣され、大禮(冠位十二階の位)
:「蘇因高」と呼ばれた。
:推古天皇15年(607年)、鞍作福利らと大唐(当時の中国は隋の時代)
:に渡る。「小野妹子」=「蘇因高」ですから、
:「小野妹子」は、「蘇」氏のひとりと考えられます。
※
:「蘇我」は、「我は蘇氏である」と読めそうな気がします。
:ですので、「蘇我-妹子」は、「蘇我-馬子」ではないかと、
:想像(妄想)しております。
┌(:追記:2025年)
│ウィキペディア2015.08.28.略掲
│《本貫は晉州蘇氏のみである。
│BC 4241年(BC43世紀)東九夷風夷の子孫である赤帝祝融が
│風州倍谷に都邑を決め、全土にムクゲ[蘇]を植えて姓を蘇、
│名前を復解としたことが蘇氏のはじまりだという。
│BC 2392年(BC24世紀)復解の 61世孫である豊が
│蘇城(吉林省)の河伯に封ざれ、
│BC 209年豊の 69世孫蘇伯孫が辰韓を建国したと言う。
└
※
BC 209年豊の 69世孫蘇伯孫が辰韓を建国したと言う。
‥‥「不死の妙薬を求めて紀元前219年に出航した徐福の船は‥‥。」
BC209年だと「蘇伯孫」は、徐福の船に、乗っていた可能性が
高いと思います。
(:追記:2025年:蘇氏は、徐福より前から在地の可能性が高い。)
徐福は方士ですから、徐福の一行の中には、国を建てて、
王になった人たちもいたと思われます。
ここからは、私の想像ですが、赫居世は、「もと倭人」ですから、
「朴氏」は、「于氏(:解氏から修正)」の「狗」と一緒に、
銅剣文化圏の西日本と、半島南部に広く住んでいたと考えられます。
Re: (スレ)「蚕・絹・機織」について - 石見介
2025/05/13 (Tue) 15:17:05
米田さん
5月8日23時ご投稿のコメント内の、
〉朴氏は、もともと縄文人の系統ですから、〈
の根拠は、何でしょうか?
Re: (スレ)「蚕・絹・機織」について - 米田
2025/05/12 (Mon) 12:51:29
<伝承を疑ってみる>
:伝承は、それなりに正しいと思っています。
:ただ、伝承を信じることには、やや疑問を感じています。
:
:この前、テレビで「ひっこし大名」というのをやっていました。
:一人の不運な大名が、何度も国替えを命じられます。
:国替えをしたこと自体は、事実だろうと思いますが、正確に
:調べたことはありませんが、江戸の初期(取りつぶし)を除けば、
:ほとんどの大名(潘)は、「国替え」を経験していないはずです
:
:「のぼうの城」という映画もありました。豊臣秀吉の小田原攻めで、
:(城主は)豊臣側に内通していたにも拘らず、(城代が)城の明け
:渡しを拒否して豊臣側と戦をした(たった一つの)お城の話です。
:
:つまり、例外的な出来事として、人々の心に強く残ったので、
:伝承として永く伝えられたのです。
:ですので私は、伝承というのは、例外的な事象だろうと考えています。
:
:そうすると、「天の岩戸」の話や、「卑弥呼の長命・独身」の話や
:「天孫降臨」・「国譲り」の話の中で、当時として何が普通なことで、
:何が例外的なことなのかを、分けた方が良いと考えています。
*****
「神無月」
:出雲では、出雲大社ほかいくつかの神社で旧暦10月に「神在月」の
:神事が行われる。
:旧暦10月10日の夜、記紀神話において国譲りが行われたとされる
:稲佐浜で、全国から参集する神々を迎える「神迎祭」が行われる。
*****
:「国譲り」の話の中で、天照大神は、天稚彦に豊葦原中国への赴任を
:命じています。そして、国神の娘を娶って、8年住んでいました。
:
:出雲の「神有月」は、何かと云うと、「収穫祭」であり、
:「縁談の相談の場」でもあります。
:「縁談」の話がまとまると、若い男子は、娘の住んでいる国に
:向かいます。つまり、ある国に赴任するということは、その国の
:娘を娶って、その地で暮らすことを意味しています。
:
:魏志倭人伝に出てくる官の「卑狗→彦」や「弥弥→耳」は、
:この赴任した(天稚彦のような)若い神様ではないだろうか。
:
:古事記の神武東征を基準にすると、
:岡田宮(1年)+多祁理宮(7年)=8年
:高島宮(8年)
:もしかすると、8年ごとに定期異動があったかも知れません。
:投馬国(薩摩の国)も、赴任先のひとつだろうと考えています。
:その投馬国で、手研耳命が生まれました。
:その後、ヤマトの国で、(おそらく)卑弥呼が生まれました。
:(古事記では、日子八井命の名前で登場しています。)
:そうすると、神武東征は、たんなる定期異動の話だったのではないか。
:それを、国の始まりの話という壮大な話に作り上げ(脚色し)たのは、
:日本書紀の(陰の)編纂者だったような気がします。
:
:そのように見てくると、「国譲り」の話の中で、娘の父親である
:大国主命に対して、国を譲れと云うのは、例外的な事例に思えます。
:そこには、自分の子や孫に、国を譲れという、横紙破り的な、
:理不尽さを感じます。そこには、「おおひるめ」「わかひるめ」から
:「天照大神」に、「国母」が代わった事が、大きいと思います。
:
:つまり、「天の岩戸」は、「おおひるめ」「わかひるめ」のラインから
:「天照大神」のラインに代わった(入れ替わった)と見てよいと
:思います。普通であれば、母から娘へと代替わりをするはずが、
:何らかの都合で「例外的」に、国母が変更になった。
スサノオ──┬─大国主命─────────┬──〇〇〇〇
スサノオ──│───────┐
おおひるめ─┘─ワカヒルメ_─┴─天鈿女命─┘──〇〇〇〇
おおひるめ─┬─〇〇〇〇(この子の出産直後に、おおひるめは死亡。)
〇〇〇〇──┘──────┐
────────天照大神─┴──〇〇〇〇
:おおひるめは、第一夫人。天照大神は、第二夫人。
:「天の岩戸」の時点では、天鈿女命は、乳飲み子と考えられる。
:(記紀は、この天鈿女命を色っぽい女性に、脚色しています。)
:神様たちは、誰が「天鈿女命」を引き取るかを相談して、
:結局、猿田彦が、引き取ることになって、地上界に降っていった。
:本来は、「天鈿女命」の天下りが、「天孫降臨」だったが、
:日本書紀は、男系の話にすり替えられているので、書紀編纂用に
:似たような「天孫降臨」の話を、各部族から集めたために、
:複数の「天孫降臨」の話が、存在するようになった。
:例外的な事象を(正しいという理由だけで)つなげていって
:出来上がった話が、真実であるかのような論理の組み立てが
:多いような気がします。
:(脚色された部分に、だまされているような気がします。)
Re: (スレ)「蚕・絹・機織」について - 米田
2025/05/08 (Thu) 23:26:53
 :「天の岩戸」や「天孫降臨」などでの、登場人物(神様たち)は、
:「天の岩戸」や「天孫降臨」などでの、登場人物(神様たち)は、
:案外、人数は少ないと思っています。(せいぜい10数人程度)
:この少ない人数で、倭国を支配したモデルを探してみたところ、
:似たモデルとしては、「山内一豊」の土佐への「国替え」を
:思いつきました。
:朴氏は、もともと縄文人の系統ですから、それを除くと、
:もっと少ないかも知れません。
:考古学を見ている人からは、腕輪・足輪(貝輪)などに目が行くと
:思います。
:系図を見ている私から見ると、ひとりの人間から、(例えば)
:徳川家康にしても、桓武天皇・藤原不比等にしても、200年、300年
:すると、その子孫(男女込みで)は、数千人とか数万人に膨れ上がり
:ます。ましてや、景行天皇みたいに、子どもの数が、80子とかに
:なると、その子孫はどこまで増えるのか、分かりません。
:文献派のひとには、また違う世界が見えるのでしょう。
:「天照大神」の話として、ワカヒルメが、機織りを行う存在であり、
:スサノヲが馬に乗っている話から、紀元1世紀ころから、
:(絹の)機織りは、乗馬があったのではないか、という
:話をしたかったのですが、うまくまとめられませんでした。
*****
「山内 一豊(やまうち かずとよ/かつとよ)」wikiより
山内一豊は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。
時代:戦国時代 - 江戸時代前期
生誕:天文14年(1545年)/一説では天文15年(1546年)尾張国
死没:慶長10年9月20日(1605年11月1日)土佐国土佐郡高知高知城
土佐一国の領主として
慶長6年(1601年)、掛川から土佐に移封となり、浦戸城に入城する。
一領具足を中心とした旧長宗我部氏の家臣団は新領主に反発し、
土佐国内で多くの紛争(旧主長宗我部盛親の復帰を求めるなど)
を起こした(浦戸一揆、滝山一揆など)。
一豊はかねてから浦戸一揆に関与していた一領具足や庄屋を調査して
いたので、これらの人々のうちから、リストに載っていた73人を
捕まえて種崎の浜辺で磔にした。
一方で新規召し抱えの家臣は上方で募るなど、重要な役職を主に
外来の家臣で固めたが、有益な長宗我部旧臣は懐柔して登用した。
*****
(追加)
:紀元前1世紀(BC50年頃)の半島で、一番の軍事勢力は、
:どこかというと、楽浪郡の軍隊(騎兵)だろうと考えます。
:
:部族の自立や部族の移動もありますが、前漢(楽浪郡)の軍隊の
:存在も、研究の対象になってもよいと思うのですが、・・・。
:
:騎馬民族に一番近いのは、(楽浪郡の)騎馬兵だったかも。
Re: (スレ)「蚕・絹・機織」について - 米田
2025/05/08 (Thu) 16:16:21
 .
.
・「張氏」について
:『楽浪』(中公新書)から「帯方郡」の太守を拾い出すと、
:図のようになります。
:つまり、帯方郡の設置から帯方・楽浪郡の消滅まで、
:「張氏」が帯方郡に関わっていることが分かります。
:公孫氏とも良好な関係を持ちつつ、公孫氏滅亡後も、
:「王頎」の後を継いで、帯方郡の太守になっています。
:これは、「張氏」が、帯方の在地の勢力だと考えられます。
:
:張氏で有名なのは、「塞曹掾史・張政」です。
:掾那部に関連する記事としては、下記の通りです。
(三国史記・高句麗本紀:AD5年秋7月)
:夫餘王(金)帯素の従弟が、〔夫餘の〕国人に、云々といって、
:一万余人とひきつれて、〔高句麗に〕来降してきた。
:〔瑠璃明〕王は、彼に王の称号を与え、掾那部の支配下に
:おいた。云々、絡(らく)氏という姓を賜った。
(三国史記・高句麗本紀:256年冬11月)←(張政は半島に戻る。)
:掾那〔部の〕明臨笏覩が公主(王女)を娶り、駙馬都尉となった。
*****
:掾那部から張氏の流れ(想像図)
(金帯素の従弟の子)
___↓
_(スサノオ)__(大国主命)(許婁葛文王)
─夷毗訶之─┬─金首露───事代主命─天日方奇日方命─○─張政
─正見母主─┘(弟『惱窒靑裔』)
(大武神王)___(AD42年生)
:天日方奇日方命は、高麗国相(:166~179)で玄菟郡の皂衣だろう。
:塞曹掾史張政は、孝霊天皇で、味鄒王(&帯方郡の太守)だろう。
Re: (スレ)「蚕・絹・機織」について - 米田
2025/05/08 (Thu) 14:32:27
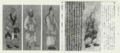 <「梁職貢図」に対する違和感:530年頃の倭人の姿>
<「梁職貢図」に対する違和感:530年頃の倭人の姿>
:4月の講演の資料(梁職貢図)を見て、考えたことを書きます。
(その1)
:この倭人は、典型的な縄文人の顔つきです。
:この倭人は、腕輪や足輪をしていることから、
:かなり身分の高い人物であることが分かります。
(その2)
:6世紀(梁の時代)でも、使者がこの姿だったことは、驚きです。
:そうは云っても、姿や顔は縄文系です。私自身は、弥生系の人間です。
:今の皇族の方々も、どちらかと云うと、弥生系のお姿です。
:どこかで、倭国の支配者は、縄文系から弥生系に代わっています。
:私の系図研究では、藤原氏(天神系・中臣氏)は、朴氏・縄文系です。
:弥生系の人物の初出は、「スサノオ(1世紀)」です。
:弥生系の天皇の初出は、「孝霊天皇(天之日矛:3世紀)」を考えています。
(その3)
:新羅の始祖「赫居世(BC69年生)」は、朴氏ですが、倭人なので縄文系です。
:百済・高句麗の始祖「朱蒙」は、(解氏ではなく、)于氏です。
(その4)
:奈勿王以降の朝鮮王朝は、金氏です。
*****
「貝輪(かいわ)」(ウィキペディアより)
:貝輪とは、貝殻で作られた腕輪のことで、特に
:古代日本で使われたものを指す。貝釧(かいくしろ)ともいう。
:
:貝輪は縄文時代からあり、サルボウなど大型二枚貝に穴を開けたも
:のが広く見つかっている。弥生時代になると、
:九州北部などで巻貝類のカサガイやオオツタノハなどに穴を開けた
:ものや、イモガイ、ゴホウラ、スイジガイなどを切って作った
:貝輪が盛行し、当時の支配階級を表すものであったと見られる。
Re: (スレ)「蚕・絹・機織」について - 米田
2022/08/22 (Mon) 09:48:48
 :前掲の「天日槍命」の続柄を修正しました。
:前掲の「天日槍命」の続柄を修正しました。
(誤):「伊是理命」の子は、おそらく「~」だろう。
(正):「伊是理命」__は、おそらく「~」だろう。
Re: (スレ)「蚕・絹・機織」について - 米田
2022/08/21 (Sun) 01:35:07
┌
│Re: 「蚕・絹・機織」について - 石見介 2022/08/19 (Fri) 22:48:31
│
│米田さん
│
│私の見た限りでは、「機織り」であって、特に絹生産が、麻と峻別
│されているというイメージはありませんでしたが、何か、絹と麻、
│樹皮(アンギン)と、差別した神話、伝承が、有りましたか?
└
┌
│「きん【錦】」の解説 - 小学館 大辞泉
│[常用漢字] [音]キン(漢) [訓]にしき
│
│1 金色の糸で美しい模様を織りなした絹織物。
│にしき。「錦衣・錦旗・錦繍 (きんしゅう) 」
│
│2 にしきのような。美しい。
│「錦鶏・錦秋・錦地 (きんち) ・錦心繍口」
└
(その1):「魏志倭人伝」
:壹与は云々。魏の朝廷(洛陽)に、云々、異文の雑錦20匹を貢献した。
(その2):「古事記」・「先代旧事本紀」
:「絹」で検索した処、ヒットしませんでした。
(その3):「日本書紀」
:「絹」の初出は、垂仁天皇紀です。
:故敦賞蘇那曷叱智、仍齎赤絹一百匹、賜任那王。
(その4):「日本書紀」
:「錦」の初出は、神武天皇紀の31年に出て来ます。
┌
│卅有一年夏四月乙酉朔、皇輿巡幸。因登腋上嗛間丘而廻望國狀曰
│「姸哉乎、國之獲矣。姸哉、此云鞅奈珥夜。雖内木錦之眞迮國、
│ 猶如蜻蛉之臀呫焉。」
└
:ただ、現代語訳になると、内木綿(うちのゆふ)として、
:(不思議なことに)「錦」が「綿」の字に変更になっています。
(その5):「神社伝承」
:彌彦神社(いやひこじんじゃ:弥彦神社)(ウィキペディアより)
:彌彦神社は、新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦にある神社。
:歴史・概史
:創建年代は不詳。祭神の天香山命は、『古事記』に「高倉下」として
:登場する。社伝によれば、命は越後国開拓の詔により
:越後国の野積の浜(現 長岡市)に上陸し、地元民に漁撈や製塩、
:稲作、養蚕などの産業を教えたとされる。
(その6):「風土記」(東洋文庫P-304)
:風土記天女の妹の「天羽衣」を盗んだ男「伊香刀美」の話。
:風土記の話(近江国の伊香の郡)によると、
:「伊香刀美」は、水浴中の天女の妹の「天羽衣」を盗んでいます。
┌
│あまの【天の】 羽衣(はごろも):精選版 日本国語大辞典
│
│① 天人の衣装。
│元来は天人の資格を表わすもので、飛行するためのものではないが、
│後世、これによって空をかけめぐるもののように解された。
└
:「天羽衣」というと、私は、「絹製品」だろうと、考えています。
<韓国の昔話「天女ときこり」と風土記の「天羽衣」の話の類似性。>
:伊賀津臣命は、韓国の昔話では、きこりになっています。
:彼は、近江の国の人です。
:韓国の昔話では、妻と子ども2人は、韓国に渡っています。
:父と子ども2人は、倭国に残っています。
伊香刀美─┐┌─(兄)意美志留(臣知人命)「後漢書韓伝」の「臣智」
_____├┼─(弟)那志登美(梨迹臣命)「倭人伝」の「難升米」
_____│├─(姉)伊是理比売(系図集覧では、伊是理命。不明)
天女の妹─┘└─(妹)奈是理比売(系図集覧では、記載なし。)
:この二つの話が、同じものだとすると、
:妻(天女の妹)と、臣知人命(臣智)と伊是理比売が、韓国に渡った。
:伊是理比売が結婚した夫の名前は(夫婦同名により)伊是理命。
:「伊是理命」は、おそらく「天日槍命(塞曹掾史張政)」だろう。
:こんなことを考えています。
<ここから先は、自作の系図がらみの妄想です。>
:「天香山命」は、「葉江」と同一人物だと考えています。
:そうすると、これを系図にすると、下記のようになります。
_______(朴氏阿達羅王)
─宇佐津臣命──御食津臣命──┬─伊賀津臣─┬─梨迹臣命
_─ニギハヤヒ─天香山命─┬─娘┘______│(難升米)
_(黒速)___(葉江)__└────天女の妹─┘(↑210±10年頃生)
****************************
┌
│(米田さんが、以前、地祇の名に「櫛」がつくことを指摘されて
│_いましたが、私は、呪物、呪具の「櫛」の意味で、玉依姫、豊玉姫
│_などと、同様な名で、天神地祇の区別ではない、と考えています。)
└
(ウィキペディアより)
┌
│櫛目文土器(くしめもんどき)または櫛文土器(くしもんどき)とは
│櫛歯状の施文具で幾何学的文様を施した土器の総称である。
│器形は尖底あるいは丸底の砲弾形が基本的である。
├
│櫛目文土器時代(くしめもんどきじだい)または櫛文土器時代
│(せつもんどきじだい)とは、朝鮮の考古学的な時代区分で、
│紀元前8000年から1500年の頃に及ぶ。
│前期から中期にかけての土器に櫛の歯のようなもので模様が
│つけられたこと(櫛目文土器)から命名されている
└
:「櫛」は、土器の文様か、女性の髪形のひとつかなと、思っています。
:名前に「櫛」が付く人物は、系図上で何らかのつながりがあるとは、
:思っていますが、系図による検証は、まだしていません。気力・根気が
:戻ってきたら、(そのうち)チャレンジしようと思っています。
Re: (スレ)「蚕・絹・機織」について - 石見介
2022/08/19 (Fri) 22:48:31
米田喜彦さん
私は、大和朝廷は、一種の宗教的信念で、水稲栽培を、支配地域に広宣流布しようとしたように見える部分がある、と考えています。
このことは、昔から言われており、適地適作よりも、かなり強引に、水稲栽培を推進するような姿勢は、司馬遼太郎あたりも、言及していたように思います。
同時に、神話的には、皇祖神としての「天照大神」、オホヒルメやその妹神であるワカヒルメが、機織りを行う存在であり、スサノヲの乱暴も、稲作と機織りという、いわば、倭国の二大生業(聖別され、他生業とは異なった宗教的意味が与えられているようにも思われる)に対する重大な違反行為として、高天原追放という処罰の原因とされていると思われます。
その機織りが、「絹」生産と関連しているとまでは、私には、断言出来ませんが、あるいは、衣服による憑依が、祭祀王としての女性の場合、自ら、織った衣服を着て、天上界の太陽神が憑依すると言った観念があったのかもしれません
神の依り代が、玉であったり、衣服であったりするのは、文化人類学的に観察される例があるようで、江上波夫氏の騎馬民族説でも、「真床覆衾」と天皇霊の関係が云々されています。
玉や衣服による憑依も、玉やその衣服を身に着けた人物に、祖神や祖霊が憑依し、託宣するという信仰の、表れでしょう。
勿論,祈念した玉串や櫛も、同様の呪物、呪具足り得ますが。
(米田さんが、以前、地祇の名に「櫛」がつくことを指摘されていましたが、私は、呪物、呪具の「櫛」の意味で、玉依姫、豊玉姫などと、同様な名で、天神地祇の区別ではない、と考えています。)
私の見た限りでは、「機織り」であって、特に絹生産が、麻と峻別されているというイメージはありませんでしたが、何か、絹と麻、樹皮(アンギン)と、差別した神話、伝承が、有りましたか?
Re: (スレ)「蚕・絹・機織」について - 米田
2022/08/16 (Tue) 14:42:03
 ┌
┌
│Re:「蚕・絹・機織」について - 福島雅彦
│ 2022/08/15 (Mon) 19:14:58
│
│>:(私は)考えていますので、「鷹取山」を
│_:持ち出すのは、年代が合わないと思います。
│
│※二上の峰の一つ「鷹取山」が年代が合わない、
│_とは理解できません。
│
│*「高取山」の麓に地名として「高取」があります。
│
│・「高取」=“다가-들”(taka-deul)=「集(たか)る野良(水田)」
│_の「古代倭語(方言と朝鮮語に片鱗を留める)」です。
│
│・低平地の葦原の荒野が、「徐福」の齎(もたら)した低湿地土木技術
│_(治水灌漑)で水耕稲作の穀倉地化した後の地名と観ます。
└
:福島さんへ、レスありがとうございます。
:
:「高天原」は、移動するという仮説に基づいた意見を述べていた
:ものですから、「鷹取山」(という名前)が移っていくのは、
:後の時代だと、考えたのです。(言葉が足りなかったようです。)
:
:「鷹取山」の名前の由来については、その前からあったと思いますし、
:「徐福」の時代以降の穀倉地化した後の地名という、見方を
:否定するつもりもありません。
:ただ、
:図のように、「BC6世紀以前」という意見もあります。
:(藤尾慎一郎[編]「再考!縄文と弥生」吉川弘文館より)
:また、「太伯の後裔」(呉の滅亡は紀元前473年)という話も
:ありますので、「徐福」だけが正しいかどうかの判断は、保留です。
Re: (スレ)「蚕・絹・機織」について - 福島雅彦
2022/08/15 (Mon) 19:14:58
>福島さんへ
>:「高天原」については、別のスレで書こうと思っていました。
>:(なかなか準備が進まなかったのですが・・・。)
:
>:もともとの「高天原」は、加耶世主「正見母主」が治めていた、
>:「大加耶(高霊伽耶)」だろうというのが、私の主張です。
:
>:で、ここでは、「鷹取山」について書きます。
>:「日本武尊」が熊襲を滅ぼしたあと、関東に征討(東征)します。
>:日本武尊(272年頃生)は、16歳頃から、ずっと、戦に明け暮れて
>:います。そうすると、285年頃から345年頃まで戦をしていたと
>:考えられます。(年代は、米田の推定です。)
:
>:(うろ覚えですが、)白崎さんの研究では、これらの山(名前)は、
>:「日本武尊」の(部隊の)足取りだそうです。
>:ですので、(「天照大神」の)「高天原」は、1世紀の中頃と
>:(私は)考えていますので、「鷹取山」を持ち出すのは、年代が合わないと思います。
※二上の峰の一つ「鷹取山」が年代が合わない、とは理解できません。
*「鷹取山」の麓に地名として「鷹取」があります。
・「鷹取」=“다가-들”(taka-deul)=「集(たか)る野良(水田)」の「古代倭語(方言と朝鮮語に片鱗を留める)」です。
・低平地の葦原の荒野が、「徐福」の齎した低湿地土木技術(治水灌漑)で水耕稲作の穀倉地化した後の地名と観ます。
>:また、私の(系図からの)研究から、下記を推測しています。
┌
│(首露王の誕生)(AD42年生)「正見母主」の子ども。
│(天稚彦の死亡)(AD95年頃)味鉏高彦根命(金閼智)の友人。
│(出雲の国譲り)(AD100年頃)事代主神が釜山のほうに国替え。
│(天孫降臨) (AD115年頃)ニギハヤヒ尊、九州北部へ
└
>:ですので、「筑紫の日向の二所(ふたがみ)の峯」への
>:「天降り」の時期は、「AD115年頃」を考えています。
※米田さんの系図に論評する知見は持ち合わせていませんが、金首露王と兄弟の伊珍阿岐王
(「大伽耶國」建国王)=「伊奘諾尊(倭人・神)とすれば整合する、かも…。
Re: (スレ)「蚕・絹・機織」について - 米田
2022/08/14 (Sun) 15:02:02
 <五穀としての「麻」について>
<五穀としての「麻」について>
┌
│「たべるご」のHPより
│たべるご トップ > 食材 > 調味料 > スパイス > 麻の実
│(ヘンプシード)の栄養とその効果・効能、おすすめの食べ方!
│2017年1月10日更新
└
麻の実(ヘンプシード)の栄養とその効果・効能、おすすめの食べ方!
最近、スーパーフードとして取り上げられることの多いヘンプシード。
なんとなく身体に良さそうだから……と、とりあえず取り入れている
人も多いのではないでしょうか。
せっかくですから、ヘンプシードにはどんな栄養があって、
どの成分がどういうことに効果的なのか知ってみませんか。
その上で、一番効果的な使い方をして、
美容と健康に思う存分役立てましょう。
ヘンプシードとは
ヘンプシードとは、日本語で言うと麻の実です。七味唐辛子に入って
いる、一番大きな丸いやつだというとピンと来る人も
多いのではないでしょうか。
いったいなぜこのヘンプシードがスーパーフードと呼ばれている
のかというと、栄養価が非常に高いから。それだけでなく、
栽培するときに農薬や肥料を必要としないので、体内に取り入れても
安全だというのも大きな理由となっているようです。
************************
┌
│「faden108」のHPより
│ホーム > お知らせ
│> 日本古来の調味料に使われている麻の実が大麻の種なのは本当?
│公開日:2021.10.24
└
七味唐辛子の麻の実は大麻の種?
古来、麻とは「大麻」のことだけを指す言葉でしたが、現在では
ジュートやリネンなど、様々な種類の麻の総称として使われています。
麻の実とはこれら麻の種の部分になりますが、七味唐辛子に使用されて
いる麻の実は噂の通り、大麻の種の部分になります。
大麻の種と知らされて、衝撃的に思われるかもしれませんが、
幻覚などを引き起こす成分が含まれているのは大麻の葉っぱや
花の部分であり、種の部分には含まれていません。
また、同じ大麻でも産業用、食用で使われるものと医療用で使われる
ものとは品種が違い、食用で使われている大麻は陶酔成分が
ほとんど含まれていないものになります。
麻の実の食品としての安全性
七味唐辛子に含まれている麻の実は、そのほとんどが食用として
使用できるように改良された品種の大麻の種を利用して作られた
ものです。産業用、食用の大麻には基準があり、大麻に含まれる
陶酔成分「THC(テトラヒドロカンナビノール)」が0.2%以下の
物しか使用できない決まりになっています。
大麻に含まれるTHCの含有率が0.3%以下だと摂取しても
陶酔作用はない、とされており、この点から見ても食用の大麻から
採れる種=麻の実が、食品として安全性が高いことがわかります。
************************
『アサ』(ウィキペディアより)
アサ(麻)は、中央アジア原産とされるアサ科アサ属の一年生の
草本であり雌雄異株である。大麻草(たいまそう)とも呼ばれる。
茎の皮の植物繊維は、綿繊維や合成繊維が普及するまで
麻繊維・麻布、として主に用いられていた。
************************
:自分で書いていて、勉強になりました。
Re: (スレ)「蚕・絹・機織」について - 米田
2022/08/14 (Sun) 14:56:50
 Re:「蚕・絹・機織」について - 石見介
Re:「蚕・絹・機織」について - 石見介
2022/08/14 (Sun) 02:09:51
┌
│引用された満州から沿海地方の記事からは、
│「五穀」の内容に、稲(水稲、陸稲)は含まれて
│いませんが、他の所謂「雑穀」類の
│何が、「五穀」なのかが、判然としません。
└
(その1)
:五穀については、東洋文庫「東アジア民族史1」(P-50)に
:比較の表がありましたので、(投稿)図にしました。
(その2)
:そもそも、「五穀」を載せたのは、「蚕・絹」の「有・無」を
:調べるためでした。「蚕・絹」は、書いてありませんでした。と
:書く代わりに、(農業生産を)原文(訳文)のまま、載せました。
:
:「有・無」を調べることで、「蚕・絹」をまったく作っていない国。
:衣服として、絹製品は持っているけれど、まったく作っていない国。
:「蚕・絹・機織」はあるけれど、(ごく少数の支配者以外は)
:だれも、(貨幣の代用か、献上品用)使っていないような国(倭国)。
:その地域差が見られて、面白かったです。
┌
│絹との関連で言えば、どうも「麻」は、「五穀」に入る様に
│読み取れますが、日中の地域差、又、時期による「五穀」の
│意味の相違を、無視して、日中の文献を比較する意味は、
│無いように思われます。半島諸国の「五穀」の定義も、
│地域と時期の相違は、当然あったでしょう。
└
:「麻」は、雑穀(食用)であることに、気が付きました。発見でした。
┌
│そうであれば、「蚕」品種や「絹」生産技術の伝播のみに、
│焦点を絞って、「日本神話」や日本での生産状況の推移を、
│考えることになります。
│
│漢籍の漠然とした引用よりは、布目順郎氏の説後の、科学的、
│文献的、考古学的な知見のご紹介が、私の希求する所です。・
│山東三眠とか、系統的な蚕の研究などは、どうなっているので
│しょうか?
│視力がそこそこあれば、自分で本を探しますが、
│現状、全く不可能なので。
└
:「絹製品」が、貨幣の代用品だった、とか、
:「倭絹」は、品質が悪くて、価値は低かった、とかの知識の断片は
:持っていましたが、それ以上の知識は、持ち合わせていません。
:日本国内で、絹を織る「機織(はたおり)」を持っていることは、
:それ自体が、女王の証(あかし)のようなもので、蜂に例えると、
:任那・倭国の中で、女王バチの巣別れのようなことが
:いくつか起こったのだろうと、想像しています。
:任那の女王は、本家筋だったのでしょうが、責稽王の時に、
:滅んだものと思われます。そして、倭国の中の、いくつかの
:分家筋の中から、時代とともに、淘汰されて、一つないし二つが
:残ったものと想像しています。
Re: (スレ)「蚕・絹・機織」について - 石見介
2022/08/14 (Sun) 02:09:51
米田喜彦さん
引用された満州から沿海地方の記事からは、「五穀」の内容に、稲(水稲、陸稲)は含まれていませんが、他の所謂「雑穀」類の何が、「五穀」なのかが、判然としません。
絹との関連で言えば、どうも「麻」は、「五穀」に入る様に読み取れますが、日中の地域差, 又、時期による「五穀」の意味の相違を、無視して、日中の文献を比較する意味は、無いように思われます。
半島諸国の「五穀」の定義も、地域と時期の相違は、当然あったでしょう。
そうであれば、「蚕」品種や「絹」生産技術の伝播のみに、焦点を絞って、「日本神話」や日本での生産状況の推移を、考えることになります。
漢籍の漠然とした引用よりは、布目順郎氏の説後の、科学的、文献的、考古学的な知見のご紹介が、私の希求する所です。・
山東三眠とか、系統的な蚕の研究などは、どうなっているのでしょうか?
視力がそこそこあれば、自分で本を探しますが、現状、全く不可能なので。
Re: (スレ)「蚕・絹・機織」について - 米田
2022/08/14 (Sun) 01:32:31
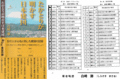 ┌
┌
│Re: 「蚕・絹・機織」について - 福島雅彦 2022/08/13 (Sat) 21:40:02
│
│米田さん、下記の地名は水縄連山(耳納山地)の事かと思います。
│
│>:もと筑紫の日向の二所(ふたがみ)の峯より、
│>:三野(美濃)の国の引津根の丘においでになった。(云々)」
│
│※筑紫の日向の二所(ふたがみ)の峯=水縄連山(耳納山地)には
│「鷹取山」と「発心山」の二つの頂きがあります。
│
│*三野(美濃)=水縄連山(耳納山地)の「水縄」と同義
│=箕尾、箕面、美濃=「水生む山」。
└
福島さんへ
:「高天原」については、別のスレで書こうと思っていました。
:(なかなか準備が進まなかったのですが・・・。)
:
:もともとの「高天原」は、加耶世主「正見母主」が治めていた、
:「大加耶(高霊伽耶)」だろうというのが、私の主張です。
:
:で、ここでは、「鷹取山」について書きます。
:「日本武尊」が熊襲を滅ぼしたあと、関東に征討(東征)します。
:日本武尊(272年頃生)は、16歳頃から、ずっと、戦に明け暮れて
:います。そうすると、285年頃から345年頃まで戦をしていたと
:考えられます。(年代は、米田の推定です。)
:
:(うろ覚えですが、)白崎さんの研究では、これらの山(名前)は、
:「日本武尊」の(部隊の)足取りだそうです。
:ですので、(「天照大神」の)「高天原」は、1世紀の中頃と
:(私は)考えていますので、「鷹取山」を持ち出すのは、
:年代が合わないと思います。
:また、私の(系図からの)研究から、下記を推測しています。
┌
│(首露王の誕生)(AD42年生)「正見母主」の子ども。
│(天稚彦の死亡)(AD95年頃)味鉏高彦根命(金閼智)の友人。
│(出雲の国譲り)(AD100年頃)事代主神が釜山のほうに国替え。
│(天孫降臨) (AD115年頃)ニギハヤヒ尊、九州北部へ
└
:ですので、「筑紫の日向の二所(ふたがみ)の峯」への
:「天降り」の時期は、「AD115年頃」を考えています。
Re: (スレ)「蚕・絹・機織」について - 福島雅彦
2022/08/13 (Sat) 21:40:02
米田さん、下記の地名は水縄連山(耳納山地)の事かと思います。
>:もと筑紫の日向の二所(ふたがみ)の峯より、
>:三野(美濃)の国の引津根の丘においでになった。(云々)」
※筑紫の日向の二所(ふたがみ)の峯=水縄連山(耳納山地)には「鷹取山」と「発心山」の二つの頂きがあります。
*三野(美濃)=水縄連山(耳納山地)の「水縄」と同義=箕尾、箕面、美濃=「水生む山」。
・「引津根の丘」が判りませんが…。
・「天照大神」と「素盞嗚尊」の確執の舞台も「水縄連山(耳納山地)」=「高天原」ですし…。
※この地は「元・浮羽郡」ですが「生葉郡」の別稱もありました⇒「生葉」=「桑の葉」=養蚕絡みかと…。
Re: (スレ)「蚕・絹・機織」について - 米田
2022/08/13 (Sat) 11:08:15
ここでは、「蚕・絹・機織」は、半島から伝わって来たと仮説を立てて、
おもに半島から九州への伝播について、検証・考察をしたいと思います。
『後漢書・挹婁伝』:五穀・麻布を産出し、云々。
『三国志・挹婁伝』:五穀や牛・馬・麻布〔を産出する〕。
『後漢書東沃沮伝』:五穀を育てるのに大変よい。
『三国志東沃沮伝』:五穀の〔生育に〕適し、云々。(貊布・魚・塩)
『後漢書・夫餘伝』:土地は五穀〔の生育〕に適し、云々。
『三国志・夫餘伝』
:土地は五穀を育てるのに適しているが、云々。
:国内では、衣服〔の色彩〕に白を尊重し、云々。
:国外に出るときは、絹織物・繍(ぬいとり)・錦織・毛織物
:などを重視する。大人は、その上に云々。
『後漢書・濊伝』
:麻を植えることや蚕を飼うことや、綿布を織ることを知っており、云々。
『三国志・濊伝』
:麻布〔を織り〕、桑を植えて蚕を飼い、緜(まわた)を作っている。
『後漢書高句驪伝』
:耕地は少なく、けんめいに耕作しても云々。 公けの場における
:衣服は、みな錦織や繍(ぬいとり)のある絹織物で、云々。
『三国志高句麗伝』
:良い耕地がないため、云々。
:十月に天を祭る。その公式の衣服は、みな錦織や繍(ぬいとり)の
:ある絹織物で、金銀で飾りたてる。
『後漢書・韓伝』
:馬韓人は、耕作や養蚕の知識があり、綿布を織ることができる。
『三国志・韓伝』
:〔五穀を〕植え蚕を飼い桑を栽培することを知っていて、
:綿布を作っている。
『晋書辰韓伝』
:〔辰韓の〕地は、五穀〔の生育〕に適している。
:その地方は桑を栽培し蚕を飼うのが盛んであり、〔人々は〕
:縑布(かとりぎぬ)を上手につくる。
『三国志弁辰伝』
:〔弁辰の〕土地は肥沃で、五穀や稲を植え〔育てる〕のに適している。
:蚕を飼い桑を植えることを知っていて、縑布(けんぷ)を作り、云々。
『後漢書・倭伝』
:土地は禾稲(いね)、麻紵(あさ)の〔栽培〕や、桑を植えて養蚕
:するのに適している。〔倭人は〕糸を績(つむ)いで布を織る技術を
:もっており、縑布(かとりぎぬ)を生産する。
『三国志倭人伝』
:男子はみな冠をかぶらず木綿で頭を巻いている。
:人々は、稲や麻を植え、桑を栽培し蚕を飼って糸を緝績(つむ)ぎ、
:細麻や縑(かとりぎぬ)や緜(まわた)を産出する。
*****
:皇孫「瓊瓊杵命」は、「宇佐津臣命」のことで、135年生頃生だろう。
:「みまき天皇(崇神天皇:272年頃生)」のみ世は、320年頃だろう。
『日本書紀・神代上』
:天照大神が神の衣服を織ろうと、神聖な機織殿にいるのをみはからい、
:云々。
:このスサノオの乱暴狼藉は、高天原(たかまがはら)の出来事です。
:この出来事は、AD44年頃(または、53年頃)、大伽耶(または出雲)
:での出来事だろうとおもいます。
:そして、この出来事のあと、下記につながるのだろうと思います。
(風土記逸文:P-343)
:豊前風土記にいう、─宮処(みやこ)の郡。
:むかし天孫がここから出発して日向の旧都に天降った。
:おそらく天照大神の神京(みやこ)である。云々。
(薩摩国:P-353)
:風土記の意味するところでは、皇祖ほのににぎ命が、日向の国
:贈於(そお)の郡、高茅穂(たかちほ)の槵生(くしふ)の峰に
:天降りになって、ここから薩摩の国のあたの郡 云々。
(常陸国風土記:P-028)
:古老がいうことには、
:「すめみまの命(皇孫瓊瓊杵命)が天からお降りになったとき、
:御服(みぞ)を織るために従って降った神、み名は、綺日女命は、
:もと筑紫の日向の二所(ふたがみ)の峯より、
:三野(美濃)の国の引津根の丘においでになった。(云々)」