東アジア討論室
混み入った議論と一対一の論争は討論室で行いましょう。
投稿の大項目はスレッドで投稿してください。
そのスレッドに対するはレスとして投稿してください。
レスに対する意見もレスとして投稿してください。
スレッド作成での留意事項
●(新規作成の)スレッドには、タイトル(内容の紹介)と自分の名前を入れて下さい。
●みんなの関心事項については、「会」として、スレを(追加で)設けることもあります。
要望事項
●「返信・引用」を使う場合は、不要なところは削除したうえで、お使いください。(1回のみ)
●「返信・引用」は、多用すると、返信の返信となると、誰の発言か分かりにくいので、控えて下さい。
●また、文章では、適当なところで、右側に「改行マーク」を入れて下さい。(一行、45文字程度)
●また、一文(~。)の長さは、長くて3行まで、(およそ、150文字以内:推奨100文字以内)にして下さい。
●文章は、残ることを念頭に、マナーに気を付けて、楽しく(議論は熱く)投稿しましょう。
スレ「7 月講演会:青柳泰介先生」 - 管理人
2024/07/03 (Wed) 14:11:07
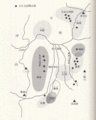 東アジアの古代文化を考える会
東アジアの古代文化を考える会
作成者: Naoko Urushibara
· 15時間 · ·2024年07月02日(火) 22:04
【7 月の講演会のご案内】⇒オンライン(ZOOM)のみ
『 葛城氏とワニ氏
~古墳時代の奈良盆地に盤踞した
二大豪族を考古学的に考える~』
■日 時 : 7 月 13 日(土)14 時~16 時半 終了予定
■講 師 : 青柳 泰介先生(橿原考古学研究所付属博物館)
■会 場 : なし(オンラインのみ)
■講師の言葉
本講演では、岸俊男が提示した古代豪族の分布図のうち、
領域の大きな標記二大豪族に焦点を当てて、
特に葛城氏の最盛期と想定されている
5世紀前半代の動向について考えてみたい。
論点は多岐にわたるが、それぞれの地域の概要を把握し、
両地域の地域設計と経済基盤をあぶり出したい。
特に、両者は文献では対照的なありかたを示しているが、
実際の遺跡のありかたも対照的である。
その背景について迫れればと考える。
ちなみに、葛城地域は磐座祭祀と家屋文鏡(家形埴輪)の
世界観を統合したものを元に開放的な地域設計をし、
経済基盤は手工業生産と農業生産になるが、
一方のワニ地域は地域設計原理は不明だが閉鎖的で、
経済基盤は木材生産と農業生産になると予想される。
Re: スレ「7 月講演会:青柳泰介先生」 - (管理人)
2025/07/02 (Wed) 09:06:16
(FB談話室からの転載です。)
東アジアの古代文化を考える会
作成者: Naoko Urushibara
· 5日 ·2025年06月26日(木)20:59
【7 月の講演会のご案内】
『ワニ氏とヤマト王権・葛城氏の確執 ~生駒山、佐紀丘陵をめぐる攻防、
_神武東征の一場面に反映か?~』―
オンラインのみ
■日 時 : 7 月 13 日(日)14 時~16 時半 終了予定
■講 師 : 青柳 泰介先生(橿原考古学研究所)
■会 場 : なし(オンラインのみ)
■講師の言葉
:前回は、奈良盆地で蟠踞した古代豪族の葛城氏とワニ氏のお話をしました。
:それぞれ盆地西南部と東北部という相対する位置に本拠地を構え、
:ヤマト王権の中では一二を争う大勢力ですが、それぞれの地域経営の仕方も
:違い、経済基盤も違うという、豪族の性格が違っていたことを指摘しました。
:
:今回は、両者の関係を別角度から見ていきたいと思います。
:すなわち、神武東征におけるクサカ争奪戦の投影です。
:攻める神武側がヤマト王権と葛城氏の連合軍、迎え撃つナガスネ彦側を
:親ワニ氏勢力と見立てて考えてみたいと思います。
:この背景には、木材生産と流通、和爾遺跡と生駒山の関係、
:富雄丸山古墳・佐紀盾列古墳群の造営契機など、4世紀後半から5世紀前半
:の奈良盆地北部での両者の確執が背景にあったと考えました。
参考文献:森浩一1993『日本神話の考古学』朝日新聞社
■参加料:ZOOM 視聴代:1000 円
■照会先:稲垣 TEL 080-4097-1757
E-mail inagaki34214590@yahoo.ne.jp
■聴講・申込方法
・ZOOM 聴講希望者は 7 月12 日(土)までにメールにて
_「氏名、メールアドレス、携帯番号(当日の連絡用)」を添えて
_稲垣 inagaki34214590@yahoo.ne.jp 宛にお申込み下さい。
1 参加料 1000 円を下記までお振込み下さい。
_みずほ銀行 九段支店 店番号532 普通預金 口座番号 8043715
_口座名 東アジアの古代文化を考える会 事務局長 嶋田晋吾
2 視聴方法 講演前日までに指定アドレスに
_講演会用の ZOOM の URL と資料が送付されます。
Re: スレ「7 月講演会:青柳泰介先生」 - 米田
2024/07/18 (Thu) 07:47:09
 ┌
┌
│『 葛城氏とワニ氏
│~古墳時代の奈良盆地に盤踞した
│ 二大豪族を考古学的に考える~』
│■日時 : 7 月 13 日(土)14 時~16 時半 終了予定
│■講師 : 青柳 泰介先生(橿原考古学研究所付属博物館)
└
:「葛城氏」に絞って、自分なりの総括を書いてみます。
:今回は、この演題は難しいため、どう向き合って良いのか、
:分かりませんでした。
:また、当日を含む「金・土・日」に外出の予定が入ったため、
:金曜日に資料が届いても、何の準備も出来ませんでした。
:当日は、講演の前半は、スマホでの視聴となってしまって、
:講演の視聴としては、万全の状態ではありませんでした。
:講演の後、「葛城氏」に対して、いろいろと考えてみました。
:以下「葛城氏」に対しての、私の考えをまとめてみました。
:和歌山の「紀ノ川」から「葛城」に連なる一帯は、
:阿波忌部氏と同族の支配者層が支配する領域でした。
:250年頃から、この「阿波忌部氏を含む一族」は、
:没落していきます。
:それまでは、部民と支配者は、地域の中で、ほぼ一体化して
:いました。それが、支配者が没落・交代するなかで、部民は、
:ほかの新しい有力な支配者の配下に組み込まれていきました。
:これが、「部民制」といわれるものと考えています。
:古い時代の支配者とのつながりは、「一宮」の「祭神」を
:みると分かります。
:支配者層の交代は、神功皇后の時代の「忍熊王の反逆」という
:形で、記録されています。いわゆる応神天皇の誕生は380年
:ですから、この政権交代は、380年頃の話になります。
:381年2月皇后は南、紀伊の国に至り、太子と日高で会った。
:この日本書紀の一文から、想像してみます。
:神功皇后の父親である「武内宿禰」は、山背・菟道の方面から
:攻めていった。
:若野毛二俣王(380年生・紀角)の父親(誉田別尊)は、
:和歌山の「紀ノ川」から「葛城」に向かって、攻めていった。
:
:「武内宿禰・神功皇后」父娘が、畿内を支配したとき、
:葛城の一帯は、紀氏(若野毛二俣王・紀角)が支配することに
:なった。
:仁徳天皇(蘇我石川)は、413年頃、難波に宮を作って、
:草香(日下)から、後背地の石川の辺りを押さえた。
:かなり粗っぽい考察(推測)ですが、
:こんなことを考えました。
Re: スレ「7 月講演会:青柳泰介先生」 - (管理人)
2024/07/03 (Wed) 14:22:32
 (ネットより)
(ネットより)
岸俊男は日本史学者で、日本古代史を専門としていました1。
彼が提示した古代豪族の分布図について、
特に領域の大きな2つの豪族に焦点を当ててみましょう。
岸俊男の研究によれば、物部氏と大伴氏が重要な豪族で
あったことがわかります。
物部氏は北方の石上神社周辺に位置し、
大伴氏は南西部周辺にいました2。
物部氏は軍事を管掌する役割を果たしており、
その戦闘力は強大であったとされています。
また、仏教崇拝問題や王位継承問題をめぐる蘇我氏と物部氏
との対立関係の中で、物部氏本宗が滅亡し、
蘇我氏が全盛時代を迎えたことも記録されています2。
岸俊男の研究は、日本古代の豪族たちの歴史的な位置づけを
理解する上で貴重な情報源となっています。
Re: スレ「7 月講演会:青柳泰介先生」 - (管理人)
2024/07/03 (Wed) 14:18:28
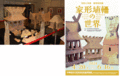 (FB談話室からの転載です。)
(FB談話室からの転載です。)
諸岡 かおり
2日 ·2024年06月25日(火) 20:06
7月13日 青柳泰介先生ZOOM講演会関連
宮山古墳の被葬者、金剛山麓で政治支配
「生前の居館を埴輪で再現」橿考研・研究員見解
6/13(木) 10:32配信 YAHOOニュース 産経新聞
天皇に次ぐ権力を握った大豪族・葛城氏のトップの墓とされる
奈良県御所市の宮山古墳(5世紀初め、墳丘長238メートル)
の被葬者について、金剛山麓に築かれた南郷遺跡群の大型建物
で政治を行った「首長」との説を、県立橿原考古学研究所
付属博物館の青柳泰介副主幹が打ち出した。
同古墳の家形埴輪(はにわ)と南郷遺跡群の建物構造が合致
する点などを挙げ、「大型建物で政務や儀式を行った人物が
宮山古墳に葬られ、生前の居館などを家形埴輪で再現した」
との見解を示した。
宮山古墳の家形埴輪。特別展では墳頂部に立てられた状況が再現
されている=奈良県橿原市の県立橿原考古学研究所付属博物館
■南郷遺跡群との関連性
宮山古墳は「王者の棺(ひつぎ)」といわれる
「長持形(ながもちがた)石棺」があり、葛城氏の始祖・
葛城襲津彦(そつひこ)の墓ともいわれる。
墳頂部から20棟分以上の家形埴輪が出土し、青柳さんは
家形埴輪の形態と、西方2~3キロに広がる南郷遺跡群の
大型建物跡の構造が類似する点に注目した。
同遺跡群は葛城氏の拠点とされ、その中の南郷安田(やしだ)
遺跡では5世紀最大の建物跡(一辺17m)と直径約40㎝の
ヒノキの丸柱が出土し、首長が政務を行った宮殿とされる。
約600m南西の極楽寺ヒビキ遺跡では、広場が設けられた
大型建物跡(同14m)と長方形の柱の痕跡が確認された。
一方の宮山古墳では、高さ1・2m以上と推定される最大の
家形埴輪が丸柱をもつ高床式であることから、
南郷安田遺跡の大型建物を埴輪で模したと推定。
別の大型の家形埴輪も、極楽寺ヒビキ遺跡の大型建物跡と
同様の長方形の柱が表現され、
同古墳と遺跡群は密接な関係があるとした。
■金剛山の聖水で祭祀
決め手ともなったのが、宮山古墳の導水施設の家形埴輪。
青柳さんは、同博物館で開催中の特別展「家形埴輪の世界」の
企画段階で宮山古墳から出土した埴輪片を再調査したところ、
木樋(もくひ)(水を送るための木製の設備)をかたどった
埴輪が小型の家形埴輪とセットになり、導水施設を表している
ことを突き止めた。
自身が発掘した同遺跡群の南郷大東遺跡では長さ4mの木樋と
建物の柱が出土し、水を流して祭祀(さいし)を行った
導水施設とされ、宮山古墳の埴輪と構造が類似。
「葛城の首長は、金剛山の清らかな湧き水を木樋に引き込んで
祭祀を営み、宮山古墳の家形埴輪に反映された」とみる。
■銅鏡に王宮の理想像
古墳時代の権威のシンボルである銅鏡との関連にも着目した。
「王の屋敷」を表現したとされる佐味田(さみた)宝塚古墳
(河合町、4世紀後半)の「家屋文鏡(かおくもんきょう)」
には宮殿や祭殿、高床式倉庫、竪穴住居の4棟が描かれ、
南郷安田遺跡などで見つかった大型建物跡や竪穴住居跡と
構造が合致するという。
鏡に描かれた高床式倉庫については、南郷遺跡群で発掘された
工房跡が相当すると指摘。
銀や銅などの素材が出土し、豪華な刀装具や馬具などの生産
拠点とされることから、高床式の宝物庫があったと推測する。
青柳さんは同古墳の被葬者について
「葛城襲津彦とは特定できない」とする一方、
「家屋文鏡にはヤマト王権の宮殿の理想的な姿が描かれ、
実際に建物として築かれたのが南郷遺跡群。死後の世界では
宮山古墳の家形埴輪として表現された」と述べた。
宮山古墳の家形埴輪や南郷安田遺跡の丸柱は同館特別展で
展示されている。16日まで。
宮山古墳の家形埴輪。
特別展では墳頂部に立てられた状況が再現されている
=奈良県橿原市の県立橿原考古学研究所付属博物館