東アジア討論室
混み入った議論と一対一の論争は討論室で行いましょう。
投稿の大項目はスレッドで投稿してください。
そのスレッドに対するはレスとして投稿してください。
レスに対する意見もレスとして投稿してください。
スレッド作成での留意事項
●(新規作成の)スレッドには、タイトル(内容の紹介)と自分の名前を入れて下さい。
●みんなの関心事項については、「会」として、スレを(追加で)設けることもあります。
要望事項
●「返信・引用」を使う場合は、不要なところは削除したうえで、お使いください。(1回のみ)
●「返信・引用」は、多用すると、返信の返信となると、誰の発言か分かりにくいので、控えて下さい。
●また、文章では、適当なところで、右側に「改行マーク」を入れて下さい。(一行、45文字程度)
●また、一文(~。)の長さは、長くて3行まで、(およそ、150文字以内:推奨100文字以内)にして下さい。
●文章は、残ることを念頭に、マナーに気を付けて、楽しく(議論は熱く)投稿しましょう。
「古事記のウソと日本書紀の齟齬」 - 米田
2025/07/06 (Sun) 01:11:44

「古事記のウソと日本書紀の齟齬」について
このスレで、書いていこうと思います。
・稗田阿礼
・太朝臣安万侶
・万葉仮名
・「天皇の歌」という虚構(脚色)
・口承(人名)の文字化での差異を見る
Re: 「古事記のウソと日本書紀の齟齬」 - 石見介
2025/07/07 (Mon) 11:44:55
米田喜彦さん
興味深いテーマですが、米田さん独自の方法論にどうしても違和感が残り、コメント出来ない可能性も、高そうです。
私の理解できると言うか、許容範囲内で、コメント可能な部分については、ご迷惑かも知れませんが、コメントさせていただきますので、ご了承お願いします。萬葉仮名や上代日本語についてのご意見、楽しみにしています。
最初の意見、と言うより異見ですが、
まず、『古事記』撰述者について
ご承知の通り、太安万侶は、その墓誌が発見されていますが、それには、『古事記』について、一切言及がありません。『先代旧事本紀』のような、明白な偽書とは異なり、『古事記』には、上代日本語の時代に著作された証拠としての、万葉仮名が、歌謡や人名、地名等の表記に使用されており、本文著述時の時代は、保証されています。
従って、「序文」のみの「偽作」説が、成立するか否かが、問題になります。
「古事記序文偽書説」については、米田さんは、どのようにお考えでしょうか?
次に、語り部とされる「稗田阿礼」について
米田さんご提示の系譜では、中臣氏の系譜に接続されていますが、これまで、私はそのような系譜は見たことがありません。
藤原鎌足が、中臣連の本宗家に近い存在だったかは、私は疑問の余地があると考えていますが、中臣連の一員であった事には、疑問は持っていません。
しかし、稗田阿礼が、中臣連の一族だとは、思えないのです。根拠をご提示お願いします。
Re: 「古事記のウソと日本書紀の齟齬」 - 米田
2025/07/07 (Mon) 07:42:12
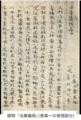 (その3):古事記は、なぜ推古天皇の時世までの記録なのか。
(その3):古事記は、なぜ推古天皇の時世までの記録なのか。
:推古天皇28年(620年)、厩戸皇子は馬子と議して『国記』
:『天皇記』『臣連伴造国造百八十部并公民等本記』を編纂した。
:稗田阿礼を推古天皇の時代の人物とすると、
:稗田阿礼が関わったであろう「原古事記」は、
:厩戸皇子が編纂した、上記の3作品だろうと、推測します。
:
:そうすると、「太朝臣安万侶」がしたことは、
:上記の作品をもとにして、日本書紀に書ききれなかったことや、
:万葉歌人たちが創作した、スサノオたちが詠ったとする
:たくさんの歌を追加することで、古事記を文学作品に
:作り上げたのだと思います。
:系図的には、日本書紀や古事記などを矛盾を含めてすべて正しい
:とした時に(系図改ざんの法則性などによって)正しい系図が
:あぶりだされてくるように作られたと思っています。
「『三経義疏』(さんぎょうぎしょ)」wikiより
:井上亘は『法華義疏』に提婆達多品の解釈が抜けていることを
:指摘した上で、その原因として『法華義疏』が鳩摩羅什が
:将来(持って来ること)・漢訳した『法華経』(『妙法蓮華経』)
:をテキストにしているからであるとする。
:
:巻一の巻頭の表紙の裏には別紙を継ぎ、
:「此是大委国上宮王私集非海彼本」と書き込まれている。
:この書き込みは
:「此れは是れ、大委国(やまとのくに)の上宮王(かみつみやの
:おおきみ)の私の集にして、海の彼かなたの本にあらず」と
:読め「日本の聖徳太子の自著であって、海外の本ではない」
:との意である。
*****
:『三経義疏』および、「書き込み」は、漢文で書かれています。
:この時代には、まだ漢文で書くことが主流であったと思われます。
Re: 「古事記のウソと日本書紀の齟齬」 - 米田
2025/07/07 (Mon) 07:41:04
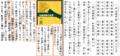 ┌
┌
│「稗田阿礼(ひえだのあれ・生没年不詳)」(wikiより)
│
│稗田阿礼は、飛鳥時代から奈良時代にかけての官人。
│『古事記』の編纂者の1人として知られる。
│暗誦する役割をもつ人たちの集団とする説もある。
│活動期間__7世紀後半から8世紀初頭
│雇用者___天武天皇←(没年686年)
└
:果たして、wikiの記述(稗田阿礼の活動時期)は正しいだろうか。
:私の予想は、NOである。
(その1):系図からのアプローチ
:下の系図は、「古代豪族系図集覧」の最初の頁の系図からです。
:一見すると、稗田阿礼は、藤原鎌足よりも二世代上の人物です。
鎌子─┬─常盤──可多能枯──御食子──藤原鎌足(614年生)
___└─忍立──稗田阿礼
___(仮に、稗田阿礼が574年生とすると、28歳は、601年。)
:この系図が正しいとすると、(一世代20年とすると、)
:稗田阿礼の生年は、574±○年が、思い浮かびます。
:そして、28歳は、601年になります。
:
:推古9年(601年):皇太子は、はじめて斑鳩に宮室を建てた。
(その2):万葉仮名からのアプローチ
:額田王(634±3年)が、薬草狩りで、恋の歌を詠んだとして、
:(万葉仮名が使われ始めるのが)650年頃。
:歌人として、日本書紀や古事記の手伝いをしたとすると、
:681年以降、(長くみても)710年頃まで。
:5・7調の歌が、スサノオの時代に作られるはずもなく、
:もし、詠われたとしても、その歌を記録する手段もなかった。
:(万葉仮名の登場は、7世紀です。)
:だいたい、スサノオに、5・7調の歌を詠む才能があったとも
:思えません。
「万葉仮名(まんようがな)」wikiより
:万葉仮名の歴史
:7世紀初めの推古期になると上宮聖徳法王帝説や金石文に
:多くの事例が見られる。
:ただし、これらの推古期遺文は年代についての異説も多い。
:7世紀中頃の木簡
:(大阪市中央区の難波宮跡出土。652年以前と推定)に
:「皮留久佐乃皮斯米之刀斯(はるくさのはじめのとし)」と
:和歌の冒頭と見られる11文字が記されている。
・天寿国繡帳(てんじゅこくしゅうちょう)wikiより
:このように天寿国繍帳の服装は推古朝、遅くとも唐風改革の
:始まる天武朝より前の服装を表しており、
:服飾史では制作時期もその頃をするのが通説となっている。
○○明年 二月廿二 日甲戌夜 半太子崩
于時多至 波奈大女 郎悲哀嘆 息白畏天
皇前曰啓 之雖恐懐 心難止使
明年二月廿二日甲戌夜半、太子崩ず。
時に多至波奈大女郎(たちばなのおおいらつめ)、悲哀嘆息し、
天皇の前に畏み白(もう)して曰く、之を啓(もう)すは
恐(かしこ)しと雖も懐う心止使(とど)め難し。
「時、武素戔嗚尊歌之曰、
_夜句茂多兔(やくもたつ)、伊弩毛夜覇餓岐(いづもやへがき)、
_兔磨語昧爾(つまごめに)、夜覇餓枳都倶盧(やへがきつくる)、
_贈廼夜覇餓岐廻(そのやへがきゑ)。」
「額田王(ぬかたのおおきみ、ぬかたのきみ)」wikiより
:額田王(生没年不詳。女性)は、飛鳥時代の日本の皇族・歌人。
:生年は不詳であるが、まず孫の葛野王が669年(天智天皇8年)
:の生まれであることは確実である。
:このことから、娘の十市皇女の生年は諸説あるが、648年
:(大化4年)から653年(白雉4年)頃の間の可能性が高い。
:更に遡って、額田王は631年(舒明天皇3年)から
:637年(同9年)頃の誕生と推定される。
_____(天武妃・万葉歌人)
___┌─額田王(634±3年)─十市皇女──葛野王(669年生)
鏡王─┤
___└─鏡女王(天智妃・万葉歌人)←(天智天皇は、626年生)
「日本書紀」wikiより
:歴史学者坂本太郎は、天武天皇10年(681年)に天皇が
:川島皇子以下12人に対して「帝紀」と「上古の諸事」の編纂を命じ
:たという『日本書紀』の記述を書紀編纂の直接の出発点と見た。
「聖徳太子(しょうとくたいし)」wikiより
:厩戸皇子は仏教を厚く信仰し、推古天皇23年(615年)までに
:『法華義疏』(伝:推古天皇23年(615年))、『勝鬘経義疏』
:(伝:推古天皇19年(611年))、『維摩経義疏』
:(伝:推古天皇21年(613年))を著した。
:これらを「三経義疏」と総称する。