東アジア討論室
混み入った議論と一対一の論争は討論室で行いましょう。
投稿の大項目はスレッドで投稿してください。
そのスレッドに対するはレスとして投稿してください。
レスに対する意見もレスとして投稿してください。
スレッド作成での留意事項
●(新規作成の)スレッドには、タイトル(内容の紹介)と自分の名前を入れて下さい。
●みんなの関心事項については、「会」として、スレを(追加で)設けることもあります。
要望事項
●「返信・引用」を使う場合は、不要なところは削除したうえで、お使いください。(1回のみ)
●「返信・引用」は、多用すると、返信の返信となると、誰の発言か分かりにくいので、控えて下さい。
●また、文章では、適当なところで、右側に「改行マーク」を入れて下さい。(一行、45文字程度)
●また、一文(~。)の長さは、長くて3行まで、(およそ、150文字以内:推奨100文字以内)にして下さい。
●文章は、残ることを念頭に、マナーに気を付けて、楽しく(議論は熱く)投稿しましょう。
各種資料(翻訳) - 米田
2023/06/18 (Sun) 15:16:37
このスレは、おもに翻訳資料を集めています。
資料庫として、ご活用下さい。
翻訳は、「Microsoft Edge 」や「Microsoft Word」に
付属している「翻訳機能」を利用しています。
Re: 各種資料(翻訳) - (管理人)
2025/04/07 (Mon) 15:00:30
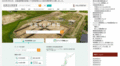
(FB談話室からの転載です。)
奈良文化財研究所
6日・2025年03月31日(月) 15:44
2025年3月31日、
全国遺跡報告総覧にて名称変更および統合検索等を公開しました。
https://www.nabunken.go.jp/nab.../2025/03/soran20250331.html
●名称変更
発掘調査報告書以外の文化財刊行物も多数含まれることから、
全国遺跡報告総覧から全国文化財総覧に名称変更しました。
https://sitereports.nabunken.go.jp/ja
●統合検索の公開
これまで刊行物PDF、書誌情報、動画、文化財イベント等を
検索する際は、それぞれ個別に検索が必要でした。
今回、統合検索を公開しました。
各コンテンツを1回で検索できるようになりました。
詳細検索を使用する場合は、従来通り個別検索をご使用ください。
●その他の改修
・文化財オンラインライブラリーのCiNii Research連携
※CiNiiへの反映は時間がかかります(4月初~中旬想定)
・文化財オンラインライブラリー、閲覧件数表示
・文化財データリポジトリ、ダウンロード数表示
・「埋蔵文化財」種別追加
●その他の改修(データ登録機関向け)※マニュアル類は準備中
・文化財オンラインライブラリー
および文化財データリポジトリの登録機能解放
・文化財位置情報のKML対応
・書誌の1PDFを論文ごとに分割する機能追加
Re: 各種資料(翻訳) - (管理人)
2025/03/17 (Mon) 22:42:06
 上宮記(古代史獺祭のサイトより)
上宮記(古代史獺祭のサイトより)
15.上宮記(逸文)
『上宮記』は7世紀頃に成立したと推定される史書。
撰者不詳。
聖徳太子の伝記とする説、上宮王家に伝来した史書とする説などが
あるがよくわかっていない。
鎌倉時代後期ころまで伝存していたらしいが、その後散逸し
現在では下記の逸文を残すのみである。
逸文の系譜様式や用字法の検討から、『上宮記』の成立は藤原宮跡木簡
より古いこと、さらに推古朝まで遡る可能性も指摘されている。
逸文(1)釈日本紀卷十三 述義九 第十七 男大迹天皇条 所引
『釈日本紀』は『日本書紀』の注釈書。全二十八巻。
鎌倉時代末期、卜部兼方(うらべかねかた)により撰述された。
下記逸文の内容は記・紀にない継体天皇の系譜である。
上宮記 (逸文1)
釋日本紀 卷十三 述義九 第十七 男大迹天皇条 注より抜粋
(上宮記曰)一云
凡牟都和希王娶俣那加都比古女子 名弟比彌[賣]麻和加
生兒若野毛二俣王 娶母母思已麻和加中比彌[賣]生兒大郎子
一名意富富等王 妹踐坂大中比彌王 弟田宮中比彌
弟布遲波良已等布斯郎女四人也
此意富富等王 娶中斯和命 生兒乎非王 娶牟義都國造
名伊自牟良君女子 名久留比彌[賣]命 生兒汗斯王
娶伊久牟尼利比古大王 生兒伊波都久和希 兒伊波智和希
兒伊波己里和氣 兒麻和加介 兒阿加波智君 兒乎波智君
娶余奴臣祖 名阿那爾比彌 生兒都奴牟斯君 妹布利比彌命也
汗斯王坐彌乎國高嶋宮時 聞此布利比彌[賣]命甚美女
遣人召上自三國坂井縣 而娶所生 伊波礼宮治天下乎富等大公王也
父汗斯王崩去而後 王母布利比彌命言曰 我獨持抱王子 无親族部之國
唯獨難養育 比陁斯奉之云 爾将下去於在祖三國命坐多加牟久之村也
獺祭註:この稿の底本は1911年国語調査委員会編「仮名源流考」
第二冊所引の前田家所有『釋日本紀』の影印によった。
原本では「ひめ」を比彌と表記しているところと比賣と表記している
ところがあり、表現がが統一していない。
上記の原文で彌[賣]とした部分はすべて原本では比賣と書かれて
いるところである。
同時代史料とみられる「天寿國繍帳銘文」などを勘案し賣は
書写のさいの書き換えとみて彌に改めたい。
古くは彌(み)と賣(め)の書き分けがなかったようで、
「ひめ」は比弥[=彌]と書かれている。
「天寿國繍帳銘文」では等已弥居加斯支移比弥乃弥己等
(とよみけかしきやひめのみこと)とあり「み」と「め」を
区別することなく同じ弥の文字があてられているのである。
後の時代の『日本書紀』では「ひめ」は比賣となり「め」と「み」が
書き分けられるようになる。
比彌は古い表記法、比賣は新しい表記法なのだ。
(上宮記に曰く、) 一(ある)に云う。
凡牟都和希王(ほむつわけのおおきみ)
俣那加都比古(くいまたなかつひこ)が女子(むすめ)、
名は弟比彌麻和加(おとひめまわか)を娶りて生める兒は
若野毛二俣王(わかのけふたまたのみこ)。
母母恩已麻和加中比彌(ももしきまわかなかひめ)を娶りて生める兒は
大郎子(おおいらつこ)、一の名は意富富等王(おほほとのみこ)
・妹(いも)踐坂大中比彌王(おしさかのおおなかのひめみこ)
・弟(おと)田宮中比彌(たみやのなかひめ)
・弟(おと)布遲波良己等布斯郎女(ふじはらのことふしのいらつめ)
四人(よたり)。
この意富富等王、中斯和命
(なかつしわのみこと)を娶りて生める兒は乎非王(おひのみこ)。
牟義都國造(むげつのくにのみやつこ)、名は伊自牟良君
(いじむらのきみ)が女子(むすめ)、名は久留比彌命
(くるひめのみこと)を娶りて生みし兒は汗斯王(うしのみこ)。
伊久牟尼利比古大王(いくむねりひこのおおきみ)が兒の
伊波都久和希(いはつくわけ)‐兒の伊波智和希(いはちわけ)
‐兒の伊波己里和氣(いはころわけ)‐兒の麻和加介(まわかけ)
‐兒の阿加波智君(あかはちのきみ)‐兒の乎波智君(おはちのきみ)、
余奴臣(よぬのおみ)の祖(みおや)名は阿那爾比彌(あなにひめ)を
娶りて生みし兒の都奴牟斯君(つぬむしのきみ)が
妹(いも)布利比彌命(ふりひめのみこと)を娶りき。
汗斯王(うしのみこ)彌乎國(みおのくに)高嶋宮(たかしまのみや)
に坐しし時に、この布利比彌命(ふりひめのみこと)
甚(いと)美(うるわし)き女(みめ)と聞き人を遣わして
三國坂井縣(みくにのさかないのあがた)より召し上げ、
娶りて生める所は、伊波礼宮(いはれのみや)に天の下治しめしし
乎富等大公王(おほとのおおきみ)なり。
父の汗斯王(うしのみこ)崩去(かむさ)りまして後に、
王(みこ)が母の布利比彌命(ふりひめのみこと)言いて曰く、
「我獨り王子(みこ)を親族部(うがら)无き國に持ち抱きて、
唯獨り養育(ひだしたてまつる)
(これを比(ひ)陁(だ)斯(し)奉(たてまつる)と云う)こと難し」
と。
爾して将に下り去りまして祖(みおや)三國命(みくにのみこと)の
坐(いま)す多加牟久(たかむく)の村に在(ま)しましき。
上宮記 (逸文2) (省略)
●上宮記 豆知識
上宮記逸文としては下記の二つが知られており
当サイトでも別ページでUPしています。
_①『釋日本紀』 卷十三 述義九 第十七 男大迹天皇 に引く
「上宮記曰 一云…」
_②『聖徳太子平氏伝雑勘文』下ノ三 上宮太子御子孫竝后等事に引く
「上宮記下巻注云…」
『釋日本紀』 卷十三 述義九 第十七 男大迹天皇 に引く
「上宮記曰 一云…」について
_①の『釋日本紀』 卷十三 述義九 第十七 男大迹天皇 に引く
「上宮記曰 一云…」の逸文は通称「上宮記曰一云」とか「上宮記一云」
などと呼称されています。
ところで当サイトでは省略しましたが『釋日本紀』では『上宮記』を
引用したあとに、文章だけではわかりにくいと考えたためか
男大迹天皇 の系譜を図(系図)にして記しています。
いまそれを簡略化して図示すると次の(系図1)のようになります。
(系図1)
① 凡牟都和希王 (応神天皇)
↓
② 若野毛二俣王
↓
③ 大郎子
↓
④ 汗斯王
↓
⑤ 乎富等大公王 (継体天皇)
しかし、実はこの 『釋日本紀』 の系図は間違っています。
「上宮記一云」にしたがって読むと 男大迹天皇 の系譜は
次の(系図2)のようになります。
(系図2)
① 凡牟都和希王 (応神天皇)
↓
② 若野毛二俣王
↓
③ 大郎子
↓
④ 乎非王
↓
⑤ 汗斯王
↓
⑥ 乎富等大公王 (継体天皇)
『古事記』では 継体天皇は 応神天皇の五世の孫とされています。
また 『日本書紀』では応神天皇の五世の孫で 彦主人王の子と
書かれています。 さてどう解釈すべきなのでしょうか。
この系図に続き『釋日本紀』には 卜部兼方 の次の文章が続きます。
参考のためにここに収録しておきます。
兼方案之 継躰天皇之祖考上宮記之外更無所見 仍就彼記注之
母后如古事記者 彦主人王之妹也
兼方これを案ずるに、継躰天皇の祖を考うるに
上宮記のほか更に所見無し。
すなわち彼の記の注に就(つ)く。
母の后は古事記の如く、彦主人王(ひこうしのみこ)が妹なり。
(獺祭注:古事記に 彦主人王 の名は見えない。
_彦主人王 が登場するのは前記のとおり
_『日本書紀』 巻第十七 男大迹天皇(繼體天皇)紀 である。)
なお、「上宮記一云」は 凡牟都和希(ホムツワケ)と記していますが、
応神天皇なら ホムタワケ でなければなりません。
よって 凡牟都和希に ホムタワケ とルビをふる本もあるのですが、
『都』を(タ)と読むのは無理だと思います。
そこで当サイトでは漢字表記のままに ホムツワケ としておきました。
Re: 各種資料(翻訳) - (管理人)
2025/03/15 (Sat) 11:30:23
 行方不明と思っていた、
行方不明と思っていた、
「古代史獺祭」のHPを見つけました。
史料として、活用して下さい。
「上宮記」(wiki)→(一番下)
外部リンク
上宮記原文テキストなど (古代史獺祭)[リンク切れ]
「リンク切れ」のハズですが、なぜかつながりました。
いつまで使えるか分かりませんが、紹介しておきます。
***史料 大陸編***
***史料 半島編***
***史料 日本編***
***史料 列島編***
Re: 各種資料(翻訳) - (管理人)
2025/03/08 (Sat) 10:14:37
(FB談話室からの転載です。)
東アジアの古代文化を考える会 「新談話室」
Kazumi Hirai
2時間 ·・2025年03月05日(水) 10:28
漢籍の再学習:その20
「萬」「千」「百」などの合理的解釈について
漢籍に記載された、千里や万里(萬里)を実測した距離である
と信じて疑わない方々が、一部におられますので。
常識的で合理的な思考で古代中国の漢籍を読むという
共通理解を進める目的での検証作業を進めます。
1
「萬」を実測数値=数詞であるとした場合に合理的解釈が不能になる例1
1.1
もしも私が「万里の長城の長さは実際に1万里なのだ!」と
執拗に主張した場合、周囲の人間は、
「爺さんは、とうとう認知症になった」と嘆くでしょう。
1.2
世界の常識としては、英語版のWikipediaでWilliam Lindesay氏
の言葉として記載されている様に:
"Ten-thousand" (wàn) is figurative in a similar manner to the Greek and
English myriad and simply means "innumerable" or "immeasurable"
和訳すれば、
「万里の萬は、英語のmyriad(数え切れない/無数の)に
相当する言葉であり、単に「計り知れない」「膨大な」と
解釈すべきものである」
として、「万里の長城」は「計り知れない程長い城」という
意味で古代中国の人々がこの言葉を用いていたと解釈するのが
合理的であり、それを実測距離だということは、
合理的とは言えません。
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Wall_of_China...
1.3
「萬里」についての漢籍の同様な用例は夥しい数に上りますが、
代表例を下記3, 4, 5と6でご紹介します。
2
「萬」を実測数値=数詞であるとした場合に合理的解釈が不能になる例2
2.1 「万国博覧会」
令和の今、これを10,000ヶ国が参加する博覧会だと思っている
日本人はいるでしょうか?
古代中国の慣例が、現代にも引き継がれている事例です。
3
「萬」を無理に実測数値=数詞であるとした場合に合理的解釈
が不能になる例3
3.1
「漢書」「地理志上」原文の冒頭:
昔在黃帝,作舟車以濟不通,旁行天下,方制萬里,
畫野分州、得百里之國萬區。
是故易稱「先王以建萬國,親諸侯」,
《書》云「協和萬國」,此之謂也。
堯遭洪水,褱山襄陵,天下分絶,為十二州,使禹治之。
水土既平,更制九州,列五服,任土作貢。
3.2 和訳は
昔、黄帝の時代に、舟や車を作り、通行できない場所を
渡れるようにし、天下を巡行した。
国土の秩序を整え、広大な領域を治め、地域を区画して
州に分け、数多くの小国を統治下に置いた。
ゆえに、『易経』には「先王は万国を建て、諸侯を親しむ」と
あり、『書経』には「協和万国」とあるが、
これはこのことを指している。
3.3 解説:
「方制萬里」を直訳すると「国土は一万里四方に及び」と
非現実的な訳となってしまいます。
「国土の秩序を整え、広大な領域を治め」として納得のできる
文章となります。こうした合理的な翻訳を支援してくれるのが、
生成AIの大きなメリットです。
また、「畫野分州、得百里之國萬區」は直訳すると
「地域を区画して州に分け、100里四方の国を10,000区得た」
となりますが、これも実測ではなく、100里四方の国は、
「小国」、10,000区は「数多くの区」と訳すのが合理的です。
「先王以建萬國,親諸侯」「協和萬國」についても実数では
ありませんが、現代日本においても、敢えて抽象的記述を
せずに、「万」のままでも誤解は生じないのでそのままの訳と
なります。(生成AIは、そのレベルまでの理解に進んでいます)
4
「萬」を無理に実測値=数詞であるとした場合に合理的解釈が
不能になる例4
4.1
司馬遷の「史記」第123巻「大宛列傳」第6節の原文:
4.2
大宛在匈奴西南,在漢正西,去漢可萬里。
其俗土著,耕田,田稻麥。有蒲陶酒。
多善馬,馬汗血,其先天馬子也。
有城郭屋室。
其屬邑大小七十餘城,眾可數十萬。
其兵弓矛騎射。
其北則康居,西則大月氏,西南則大夏,東北則烏孫,東則扜宩、于□。
于□之西,則水皆西流,注西海;其東水東流,注鹽澤。
鹽澤潛行地下,其南則河源出焉。
多玉石,河注中國。
而樓蘭、姑師邑有城郭,臨鹽澤。
鹽澤去長安可五千里。
匈奴右方居鹽澤以東,至隴西長城,南接羌,鬲漢道焉。
4.3 和訳は
大宛(たいえん:ウズベキスタン)の地は匈奴の南西、
漢の真西に位置し、漢から極めて遠い距離にある。
その民は定住し、農耕を営み、稲や麦を栽培する。
葡萄酒を生産する。
良馬に恵まれ、馬は汗をかくと血のように見えるとされ、
その祖先は天馬の子であるという。
城郭や家屋を備えた都市があり、大小さまざまな七十余りの
城が存在し、人口は数十万に及ぶ。
兵士は弓や槍を操り、騎射に優れている。
大宛の北には康居(こうこ:カザフスタン)があり、
西には大月氏、南西には大夏、北東には烏孫(うそん)、
東には扜□(うしん)・于□(うてん)がある。
于□の西では、川は西に流れ、西海に注ぐ。
東では水は東に流れ、塩沢に注ぐ。
塩沢は地下を流れ、その南には黄河の源がある。
この地は玉石に富み、その川が玉を中国へ運ぶ。
楼蘭(ローラン)と姑師(トルファン)の城邑は城郭を有し、
鹽澤(塩沢:ロプノール)の近くにある。
鹽澤(塩沢)は長安からおよそ五千里の距離にある。
匈奴の右翼部は鹽澤(塩沢)の東に居を構え、
隴西(甘粛省の一部)の長城(万里の長城の一部)に至り、
南は羌と接し、漢への道を掌握している。
4.4 解説;
「去漢可萬里」を直訳すると「漢から約1萬里の処」ですが、
これは実測の距離では無く、「漢から極めて遠い距離にある」
と訳すのが適切ですし、「鹽澤去長安可五千里」についても
実測距離(約1,749km)では有りませんが、誤差は
15%であるので、約5千里のままで大きな誤解は生みません。
「至隴西長城」これは、直訳すると「隴西の長い城至る」ですが、
この長城は、「万里の長城」を意味しており
「長城(万里の長城の一部)」と訳すのが適切です。
5
「萬」を無理に実測値=数詞であるとした場合に合理的解釈が
不能になる例5
5.1
范曄の「後漢書」「東夷列傳」第4節の原文:
秦并六國,其淮、泗夷皆散為民戸。
陳涉起兵,天下崩潰,燕人衛滿避地朝鮮,因王其國。
百有餘歳,武帝滅之,於是東夷始通上京。
王莽簒位,貊人寇邊。
建武之初,復來朝貢。
時遼東太守祭肜威讋北方,聲行海表,
於是濊、貊、倭、韓萬里朝獻,故章、和已後,使聘流通。
逮永初多難,始入寇鈔;桓、靈失政,漸滋曼焉。
5.2 和訳は:
5.3
秦が六国を併合したとき、淮水・泗水流域の夷族はみな散り、
民戸となった。
陳勝が挙兵すると天下は崩壊し、燕の人である衛満が戦乱を
避けて朝鮮へ渡り、その国の王となった。
それから百年以上が経ち、武帝がこれを滅ぼし、ここに
おいて東夷は初めて上京(長安)と通じるようになった。
王莽が帝位を簒奪すると、貊族が辺境を侵した。
建武年間の初めには、再び朝貢に訪れた。
当時、遼東太守の祭肜は北方に威を示し、その名声は
海の向こうまで響いた。
そのため、濊(わい)、貊(ばく)、倭(わ)、韓(かん)の
諸国は遠方より遙か道を越えて朝貢を行い、
章帝・和帝の時代以降、使者の往来が盛んになった。
しかし、永初年間(107年頃)になると戦乱が多くなり、ついに侵略と略奪が始まった。桓帝・霊帝の時代には政が乱れ、
その傾向は次第に拡大していった。
5.4 解説:
「於是濊、貊、倭、韓萬里朝獻」これは直訳すると
「濊、貊、倭、韓は10,000里の道を越えて朝具を行い」と
なりますが、「遠方より遙か道を越えて朝貢を行い」と
訳す方が合理的です。
6
「萬」を無理に実測値=数詞であるとした場合に合理的解釈が
不能になる例6
6.1
范曄の「後漢書」「西域傳」第21節の原文:
安息國居和櫝城,去洛陽二萬五千里。
北與康居接,南與烏弋山離接。
地方數千里,小城數百,戸口勝兵最為殷盛。
其東界木鹿城,號為小安息,去洛陽二萬里
6.2
安息国(パルティア)は和櫝城にあり、洛陽から極めて遠方に
位置する。
北は康居と接し、南は烏弋山離と接している。国土は大変
広大で、小さな城が数百あり、人口も兵力も豊かで
最も繁栄している。
その東の境には木鹿城があり、「小安息」と称されている。
この地は洛陽から二万里の距離にある。
6.3 解説:
これも直訳すれば、25,000里と、数千平方里となり明らかに
実測値では無く、「極めて遠方に位置する」「大変広大」と
訳すのが合理的です。
(注:Gooble Earthの概算では、テヘランから西安まで
約5,000km イランの面積は、1,648,000km2。
もしも 1里=76mとすると 1,900km:西安から新疆ウイグル
自治区までの距離となります)
7 結論:
「萬」、「千」、「百」は、漢籍の場合、それが「里」など
結合して記述された場合、丸い数字で表記された場合の多くは
実測数字=数詞では無くなり、大きさ、長さ、時間などの
観念を抽象化するのが、古代中国では常識であり、
その慣用例の一部は、現代日本まで継承されています。
言い替えると、書籍や文章の全体構成や、前後の文脈を顧み
ずに、「萬」、「千」、「百」を頑迷朦朧に実測数値=数詞と
主張する限り、「三国志」を含む、漢籍の読解や正しい理解は
出来ないと私は考えます。
8 参考情報:
生成AIの回答
下記は、生成AIによる、古代漢文の「萬」、「千」、「百」に
関する意味解釈の説明です。
非常に合理的な翻訳能力を、膨大な漢籍を学習して身に
付けていることは、驚くべきことであり。
漢文の解釈上、協力なツールになっていると感じます。
以下は、その回答です。
9
古代中国における「萬」の意味
古代中国において、「萬」(wàn)は主に以下の意味を
持っていました。
9.1.1 数詞: 10,000を表す数。
これは現代まで変わらない基本的な意味です。
9.1.2 多数、非常に多いこと:
文字通りの数だけでなく、非常に多いことや無限に近い数を
表す際にも用いられました。あ
9.2 英語での翻訳
9.2.1 Ten thousand (numerical)
9.2.2 Myriad, vast number (indicating a large quantity)
9.3 語源について
「萬」の語源は、もともとサソリをかたどった象形文字で
あると言われています。
古代中国において、サソリを表す言葉と10,000を表す言葉の
発音が似ていたため、「萬」が10,000の意味で使われるようになったと考えられています。
9.4 例:
9.4.1 万歳(wàn suì)。
日本語:万歳(ばんざい)
英語:Long live...
9.4.2 萬里の長城(wàn lǐ cháng chéng)
日本語:万里の長城
英語:The Great Wall of China
9.5 後記:
このように、「萬」は数詞としてだけでなく、非常に多いこと
や広範囲であることを表す言葉としても使われています。
10 古代中国における「千」の意味
10.1 数詞としての「千」
・「一千」(いっせん):1000を表す数詞。
現代と同様に用いられた。
・「千人(せんにん)」= 千人、「千里(せんり)」= 千里(但し、遠い距離を表す意味がある)
10.2 比喩的な意味
「非常に多い」(無数、大量)を意味することがある。
例:「千秋(せんしゅう)」= 長い年月、
「千言万語(せんげんばんご)」= 沢山の言葉。
「千里馬(せんりをかけるうま)」=沢山の距離を走る名馬。
10.3 象徴的な意味
・「千」は長寿、繁栄、広がりの象徴とされることもある
例:「千歳(せんざい)」= 長寿を祝う言葉、
「千古(せん こ)」= 永遠
11 古代中国における「百」の意味
11.1 数詞としての「百」
「一百」(いっぴゃく):100を表す数詞。
現代と同様に使われた。
例:「百人(ひゃくにん)」= 百人、
「百里(ひゃくり)」= 百里(一定の距離を表す)
11.2 比喩的な意味
「非常に多い」(多数、無数)を意味することがある
例:
「百戦百勝(ひゃくせんひゃくしょう)」= すべての戦いに勝つ、
「百姓(ひゃくせい)」= 多くの民衆(農民に限らず庶民全般を指す)
11.3 象徴的な意味
「百」は多様性、豊かさ、調和の象徴としても使われる
例:「百花繚乱(ひゃっかりょうらん)」= 様々な才能や文化が花開く、
「百寿(ひゃくじゅ)」= 100歳の長寿を祝う言葉。
Re: 各種資料(翻訳) - (管理人)
2025/03/07 (Fri) 11:09:04
 翻訳資料のHPを見つけたので、
翻訳資料のHPを見つけたので、
紹介します。
「三國志修正計画」
または、「風篁楼」で
検索すると出て来ます。
「三國志修正計画」
正しくは 『駄訳計画』。
訳しつつ好き勝手に補足やツッコミ入れていくだけです。
底本は中華書局版『三國志』。
机上の友は筑摩書房『三国志』と旺文社『漢和中辞典』初版。
一般中高校 …
http://home.t02.itscom.net/izn/ea/index.html
http://home.t02.itscom.net/izn/ea/kd3/00.html
Re: 各種資料(翻訳) - (管理人)
2025/03/05 (Wed) 13:53:40
 (FB談話室からの転載です。)
(FB談話室からの転載です。)
Kazumi Hirai
東アジアの古代文化を考える会「新談話室」
2時間 ·・2025年03月05日(水) 10:38
漢籍の再学習:その20
「萬」「千」「百」などの合理的解釈について
漢籍に記載された、千里や万里(萬里)を実測した距離であると信じて
疑わない方々が、一部におられますので。
常識的で合理的な思考で古代中国の漢籍を読むという共通理解を
進める目的での検証作業を進めます。
1
「萬」を実測数値=数詞であるとした場合に合理的解釈が不能
になる例1
1.1
もしも私が「万里の長城の長さは実際に1万里なのだ!」と執拗に
主張した場合、周囲の人間は、「爺さんは、とうとう認知症になった」
と嘆くでしょう。
1.2
世界の常識としては、英語版のWikipediaでWilliam Lindesay氏の
言葉として記載されている様に:
"Ten-thousand" (wàn) is figurative in a similar manner to the Greek and
English myriad and simply means "innumerable" or "immeasurable"
和訳すれば、「万里の萬は、英語のmyriad(数え切れない/無数の)に
相当する言葉であり、単に「計り知れない」「膨大な」と
解釈すべきものである」
として、「万里の長城」は「計り知れない程長い城」という意味で
古代中国の人々がこの言葉を用いていたと解釈するのが合理的であり、
それを実測距離だということは、合理的とは言えません。
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Wall_of_China...
1.3
「萬里」についての漢籍の同様な用例は夥しい数に上りますが、
代表例を下記3, 4, 5と6でご紹介します。
2
「萬」を実測数値=数詞であるとした場合に合理的解釈が不能
になる例2
2.1 「万国博覧会」
令和の今、これを10,000ヶ国が参加する博覧会だと思っている
日本人はいるでしょうか?
古代中国の慣例が、現代にも引き継がれている事例です。
3
「萬」を無理に実測数値=数詞であるとした場合に合理的解釈が不能
になる例3
3.1 「漢書」「地理志上」原文の冒頭:
昔在黃帝,作舟車以濟不通,旁行天下,方制萬里,畫野分州、
得百里之國萬區。是故易稱「先王以建萬國,親諸侯」,
《書》云「協和萬國」,此之謂也。堯遭洪水,褱山襄陵,天下分絶,
為十二州,使禹治之。水土既平,更制九州,列五服,任土作貢。
3.2 和訳は
昔、黄帝の時代に、舟や車を作り、通行できない場所を渡れるように
し、天下を巡行した。
国土の秩序を整え、広大な領域を治め、地域を区画して州に分け、
数多くの小国を統治下に置いた。
ゆえに、『易経』には「先王は万国を建て、諸侯を親しむ」とあり、
『書経』には「協和万国」とあるが、これはこのことを指している。
3.3 解説
:「方制萬里」を直訳すると「国土は一万里四方に及び」と非現実的な
訳となってしまいます。
「国土の秩序を整え、広大な領域を治め」として納得のできる文章と
なります。こうした合理的な翻訳を支援してくれるのが、
生成AIの大きなメリットです。
また、「畫野分州、得百里之國萬區」は直訳すると
「地域を区画して州に分け、100里四方の国を10,000区得た」と
なりますが、これも実測ではなく、100里四方の国は、「小国」、
10,000区は「数多くの区」と訳すのが合理的です。
「先王以建萬國,親諸侯」「協和萬國」についても実数ではありま
せんが、現代日本においても、敢えて抽象的記述をせずに、
「万」のままでも誤解は生じないのでそのままの訳となります。
(生成AIは、そのレベルまでの理解に進んでいます)
4
「萬」を無理に実測値=数詞であるとした場合に合理的解釈が不能
になる例4
4.1
司馬遷の「史記」第123巻「大宛列傳」第6節の原文:
4.2
大宛在匈奴西南,在漢正西,去漢可萬里。
其俗土著,耕田,田稻麥。有蒲陶酒。
多善馬,馬汗血,其先天馬子也。
有城郭屋室。其屬邑大小七十餘城,眾可數十萬。其兵弓矛騎射。
其北則康居,西則大月氏,西南則大夏,東北則烏孫,東則扜[宩]、
于[竇]。于[竇]之西,則水皆西流,注西海;其東水東流,注鹽澤。
鹽澤潛行地下,其南則河源出焉。
多玉石,河注中國。而樓蘭、姑師邑有城郭,臨鹽澤。
鹽澤去長安可五千里。
匈奴右方居鹽澤以東,至隴西長城,南接羌,鬲漢道焉。
4.3 和訳は
大宛(たいえん:ウズベキスタン)の地は匈奴の南西、漢の真西に
位置し、漢から極めて遠い距離にある。
その民は定住し、農耕を営み、稲や麦を栽培する。
葡萄酒を生産する。良馬に恵まれ、馬は汗をかくと血のように
見えるとされ、その祖先は天馬の子であるという。
城郭や家屋を備えた都市があり、大小さまざまな七十余りの城が
存在し、人口は数十万に及ぶ。兵士は弓や槍を操り、騎射に優れている。
大宛の北には康居(こうこ:カザフスタン)があり、
西には大月氏、南西には大夏、北東には烏孫(うそん)、
東には扜[宩](うしん)・于[竇](うてん)がある。
于[竇] (うてん)の西では、川は西に流れ、西海に注ぐ。
東では水は東に流れ、塩沢に注ぐ。塩沢は地下を流れ、
その南には黄河の源がある。
この地は玉石に富み、その川が玉を中国へ運ぶ。
楼蘭(ローラン)と姑師(トルファン)の城邑は城郭を有し、
鹽澤(塩沢:ロプノール)の近くにある。
鹽澤(塩沢)は長安からおよそ五千里の距離にある。
匈奴の右翼部は鹽澤(塩沢)の東に居を構え、隴西(甘粛省の一部)
の長城(万里の長城の一部)に至り、南は羌と接し、
漢への道を掌握している。
4.4 解説
;「去漢可萬里」を直訳すると「漢から約1萬里の処」ですが、
これは実測の距離では無く、「漢から極めて遠い距離にある」と
訳すのが適切ですし、「鹽澤去長安可五千里」についても
実測距離(約1,749km)では有りませんが、誤差は15%であるので、
約5千里のままで大きな誤解は生みません。
「至隴西長城」これは、直訳すると「隴西の長い城至る」ですが、
この長城は、「万里の長城」を意味しており
「長城(万里の長城の一部)」と訳すのが適切です。
5
「萬」を無理に実測値=数詞であるとした場合に合理的解釈が不能
になる例5
5.1 范曄の「後漢書」「東夷列傳」第4節の原文:
秦并六國,其淮、泗夷皆散為民戸。
陳涉起兵,天下崩潰,燕人衛滿避地朝鮮,因王其國。
百有餘歳,武帝滅之,於是東夷始通上京。
王莽簒位,貊人寇邊。
建武之初,復來朝貢。
時遼東太守祭肜威讋北方,聲行海表,
於是濊、貊、倭、韓萬里朝獻,故章、和已後,使聘流通。
逮永初多難,始入寇鈔;桓、靈失政,漸滋曼焉。
5.2 和訳は:
5.3
秦が六国を併合したとき、淮水・泗水流域の夷族はみな散り、民戸と
なった。
陳勝が挙兵すると天下は崩壊し、燕の人である衛満が戦乱を避けて
朝鮮へ渡り、その国の王となった。
それから百年以上が経ち、武帝がこれを滅ぼし、
ここにおいて東夷は初めて上京(長安)と通じるようになった。
王莽が帝位を簒奪すると、貊族が辺境を侵した。
建武年間の初めには、再び朝貢に訪れた。
当時、遼東太守の祭肜は北方に威を示し、
その名声は海の向こうまで響いた。
そのため、濊(わい)、貊(ばく)、倭(わ)、韓(かん)の諸国は
遠方より遙か道を越えて朝貢を行い、
章帝・和帝の時代以降、使者の往来が盛んになった。
しかし、永初年間(107年頃)になると戦乱が多くなり、
ついに侵略と略奪が始まった。
桓帝・霊帝の時代には政が乱れ、その傾向は次第に拡大していった。
5.4 解説
:「於是濊、貊、倭、韓萬里朝獻」これは直訳すると
「濊、貊、倭、韓は10,000里の道を越えて朝具を行い」となりますが、
「遠方より遙か道を越えて朝貢を行い」と訳す方が合理的です。
6
「萬」を無理に実測値=数詞であるとした場合に合理的解釈が不能
になる例6
6.1
范曄の「後漢書」「西域傳」第21節の原文:
安息國居和櫝城,去洛陽二萬五千里。
北與康居接,南與烏弋山離接。
地方數千里,小城數百,戸口勝兵最為殷盛。
其東界木鹿城,號為小安息,去洛陽二萬里
6.2
安息国(パルティア)は和櫝城にあり、洛陽から極めて遠方に位置する。
北は康居と接し、南は烏弋山離と接している。
国土は大変広大で、小さな城が数百あり、人口も兵力も
豊かで最も繁栄している。
その東の境には木鹿城があり、「小安息」と称されている。
この地は洛陽から二万里の距離にある。
6.3 解説
:これも直訳すれば、25,000里と、数千平方里となり明らかに実測値では
無く、「極めて遠方に位置する」「大変広大」と訳すのが合理的です。
(注:Gooble Earthの概算では、テヘランから西安まで約5,000km
イランの面積は、1,648,000km2。もしも 1里=76mとすると
1,900km:西安から新疆ウイグル自治区までの距離となります)
7 結論:
「萬」、「千」、「百」は、漢籍の場合、それが「里」など結合して
記述された場合、丸い数字で表記された場合の多くは実測数字=数詞
では無くなり、大きさ、長さ、時間などの観念を抽象化するのが、
古代中国では常識であり、その慣用例の一部は、現代日本まで継承
されています。
言い替えると、書籍や文章の全体構成や、前後の文脈を顧みずに、
「萬」、「千」、「百」を頑迷朦朧に実測数値=数詞と主張する限り、
「三国志」を含む、漢籍の読解や正しい理解は出来ないと私は考えます。
8 参考情報:生成AIの回答
下記は、生成AIによる、古代漢文の「萬」、「千」、「百」に
関する意味解釈の説明です。
非常に合理的な翻訳能力を、膨大な漢籍を学習して身に付けて
いることは、驚くべきことであり。
漢文の解釈上、協力なツールになっていると感じます。
以下は、その回答です。
9 古代中国における「萬」の意味
古代中国において、「萬」(wàn)は主に以下の意味を持っていました。
9.1.1
数詞: 10,000を表す数。これは現代まで変わらない基本的な意味です。
9.1.2 多数、非常に多いこと:
文字通りの数だけでなく、非常に多いことや無限に近い数を表す際
にも用いられました。あ
9.2 英語での翻訳
9.2.1 Ten thousand (numerical)
9.2.2 Myriad, vast number (indicating a large quantity)
9.3 語源について
「萬」の語源は、もともとサソリをかたどった象形文字であると
言われています。
古代中国において、サソリを表す言葉と10,000を表す言葉の発音が
似ていたため、「萬」が10,000の意味で使われるようになったと
考えられています。
9.4 例:
9.4.1 万歳(wàn suì)。
日本語:万歳(ばんざい)
英語:Long live...
9.4.2 萬里の長城(wàn lǐ cháng chéng)
日本語:万里の長城
英語:The Great Wall of China
9.5 後記
:このように、「萬」は数詞としてだけでなく、非常に多いことや
広範囲であることを表す言葉としても使われています。
10 古代中国における「千」の意味
10.1 数詞としての「千」
・「一千」(いっせん):1000を表す数詞。現代と同様に用いられた。
・「千人(せんにん)」= 千人、「千里(せんり)」= 千里
(但し、遠い距離を表す意味がある)
10.2 比喩的な意味
「非常に多い」(無数、大量)を意味することがある。
例:「千秋(せんしゅう)」= 長い年月、
「千言万語(せんげんばんご)」= 沢山の言葉。
「千里馬(せんりをかけるうま)」=沢山の距離を走る名馬。
10.3 象徴的な意味
・「千」は長寿、繁栄、広がりの象徴とされることもある
例:「千歳(せんざい)」= 長寿を祝う言葉、
「千古(せん こ)」= 永遠
11 古代中国における「百」の意味
11.1 数詞としての「百」
「一百」(いっぴゃく):100を表す数詞。現代と同様に使われた。
例:「百人(ひゃくにん)」= 百人、
「百里(ひゃくり)」= 百里(一定の距離を表す)
11.2 比喩的な意味
「非常に多い」(多数、無数)を意味することがある
例:「百戦百勝(ひゃくせんひゃくしょう)」= すべての戦いに勝つ、
「百姓(ひゃくせい)」= 多くの民衆(農民に限らず庶民全般を指す)
11.3 象徴的な意味
「百」は多様性、豊かさ、調和の象徴としても使われる
例:「百花繚乱(ひゃっかりょうらん)」= 様々な才能や文化が花開く、
「百寿(ひゃくじゅ)」= 100歳の長寿を祝う言葉。
Re: 各種資料(翻訳) - (管理人)
2025/03/03 (Mon) 12:34:40
────────────────────────────
『三国志魏書東夷伝』
(東洋文庫:「東アジア民族史1」より)抜粋
────────────────────────────
:景初年間(237~240)、〔魏の天子は〕大軍隊を派遣して
:公孫淵を伐ち、また潜(ひそ)かに海上より軍を派遣して、
:楽浪郡と帯方郡とを支配したのである。
:(238)その後、海外〔のこと〕は静かで安らかになり、
:東夷〔の国々〕は〔魏に〕屈服したのであった。
:その後、高句麗が叛いたので、また少数の軍隊を派遣して
:征伐し、極遠〔の地〕まで追いつめ、烏丸の骨都を越えて、
:沃沮をすぎ、粛慎の国を踏み破り、
:東の大海にまで進んでいった。
:〔そこに住む〕長老が言うには、
:「〔海のかなたに〕顔つきの異なる人々が住んでいる。
:〔そこは〕太陽の昇るところに近い」と。
:こうして諸国を周(あまね)く観てまわったので、
:国々の掟や習俗、国の大小、その相違などをとり上げ、
:それぞれに名称があれば詳しく記載することができる
:〔ようになった〕。
:〔これらの諸国には、〕夷狄の邦とはいいながら、
:俎豆(そとう)〔を使う儀〕礼がある。
:中国はすでにその〔儀〕礼を失ってしまったが、
:この礼を四夷〔の地方〕で探し求めてみれば、
:〔四夷では〕今なお〔これを〕信じているようである。
:それ故、これらの国々〔のこと〕を順序を定めて記述し、
:その中で同じものや異なったものを列記して、
:前史で充分記録できなかったところに書きついでいきたい。
:
:〔『三国志』の編者である陳寿は、この東夷伝を〕評して
:〔つぎのように〕曰う。
:『史記』と『漢書』は朝鮮と両越
:(注:南越(湖北省地方)と東越(福建省地方)とをさす。)
:とのことを記録しているし、
:後漢時代には西方の羌族のことを採録している。
:魏の時代になると、匈奴は次第に衰退し、
:代わって烏丸や鮮卑が〔勢力を強めて〕いた。
:〔この魏の時代には〕東夷のことも〔記録される〕ように
:なった。〔これら東夷の諸国からは〕
:通訳を伴った使者が時々やって来るようになった。
:〔そこで、東夷の諸国からの、通訳を伴った使者の〕話に
:随って〔東夷伝を〕記述した。
:どうして〔このような記事が東夷諸族の〕一般的な
:〔事情を伝える〕ものといえようか。
────────────────────────────
Re: 各種資料(翻訳) - (管理人)
2025/03/03 (Mon) 12:32:55
Kazumi Hirai 2月16日 9:12 ·
漢籍の再学習:その9 「三国志」「東夷伝」
引き続き生成AIの力を借りて、「東夷伝」の和訳をお知らせします。
使用したデータはChinese Text Projectで
その底本は「武英殿二十四史」本「三国志」です。
------------ 三国志東夷伝の和訳 ----------
尚書に「東は海に漸(いた)り、西は流沙に被(およ)ぶ」と称される。
その九服の制度について語ることはできる。
しかし、荒れ果てた地域の外からは、重訳を経て情報が伝わるのみで
あり、人の足跡や車の轍が及ぶことはなく、
その国の風俗や異国の事情を知る者はいなかった。
虞舜・周の時代より、西戎は白環を献じ、東夷は粛慎の貢ぎ物を
奉ったが、いずれも数世代に一度のことであり、
その遠隔さはこのようなものであった。
やがて漢の時代、張騫を西域に派遣し、黄河の源流を究め、
諸国を巡り、遂には都護を設置して総領させることで、
西域の事情が明らかになり、史官が詳細に記録できるようになった。
魏が興ると、西域のすべての国を訪れることはできなかったものの、
大国である龜茲(クチャ)、于寘(ウシ)、康居(カンジュ)、
烏孫(ウスン)、疏勒(カシュガル)、月氏(大月氏)、
鄯善(ロウラン)、車師(チャシ)といった国々は、
毎年朝貢を奉じ、大略漢の制度に倣う形となった。
しかし、公孫淵は父祖三代にわたって遼東を支配し、
天子は彼を遠隔の地の統治者とし、海外の事を委ねたため、
東夷との交流が断絶し、中国と通じることができなくなった。
景初年間、大規模な軍を動員し、公孫淵を討伐するとともに、
密かに軍を海上へと進め、楽浪郡と帯方郡を回収し、それによって
海の向こうは静穏となり、東夷は服従した。
その後、高句麗が背いたため、偏師(別動隊)を派遣して討伐し、
極遠まで追撃し、烏丸(オルドス)、骨都、沃沮(オクチョ)を
越えて粛慎(しゅくしん)の地に至り、東は大海に臨んだ。
長老たちは、日が昇る近くの地には、異なる顔立ちを持つ人々がいると
語り、そこで諸国を巡り、その制度や風俗を調査し、大国小国の
区別やそれぞれの名称を詳細に記録することができた。
それらは夷狄(異民族)の国ではあるが、
中国の礼制の形は存続していた。
中国が礼を失ったとき、四夷に求めることは信ずるに値する。
そこで、各国の事情を整理し、その異同を列挙し、
前代の史書に記されていない部分を補うこととしたのである。
-------- 三国志東夷伝の原文 -----------------
書稱「東漸于海,西被于流沙」。
其九服之制,可得而言也。
然荒域之外,重譯而至,非足跡車軌所及,未有知其國俗殊方者也。
自虞曁周,西戎有白環之獻,東夷有肅慎之貢,皆曠世而至,其遐遠也如此。
及漢氏遣張騫使西域,窮河源,經歷諸國,遂置都護以總領之,
然後西域之事具存,故史官得詳載焉。
魏興,西域雖不能盡至,其大國龜茲、于寘、康居、烏孫、踈勒、
月氏、鄯善、車師之屬,無歳不奉朝貢,略如漢氏故事。
而公孫淵仍父祖三世有遼東,天子為其絶域,委以海外之事,
遂隔斷東夷,不得通於諸夏。
景初中,大興師旅,誅淵,又潛軍浮海,收樂浪、帶方之郡,
而後海表謐然,東夷屈服。
其後高句麗背叛,又遣偏師致討,窮追極遠,踰烏丸、骨都,過沃沮,
踐肅慎之庭,東臨大海。
長老説有異靣之人,近日之所出,遂周觀諸國,采其法俗,小大區別,
各有名號,可得詳紀。雖夷狄之邦,而俎豆之象存。
中國失禮,求之四夷,猶信。故撰次其國,列其同異,以接前史之所未備焉。
-----------------------------------------
(注1)烏桓(烏丸):紀元前1世紀から紀元後3世紀にかけて中国北部
(現在の内モンゴル自治区)に存在していた民族。出典はWikipedia
(注2)骨都:匈奴の首長である単于の名前の一つ。
(注3) 沃沮:紀元前2世紀から3世紀にかけて朝鮮半島北部の
日本海に沿った地方(現在の咸鏡道付近)に住んでいたと思われる民族。
出典はWikipedia
(注4) 肅慎: 匈奴の大首長である単于に従う5つの官位の一つ
------ 参考 ------ 尚書の夏書の禹貢24説の和訳 ---------------
九州は一つにまとまり、四方の辺境の地も安住し、
九つの山は整備され、九つの川は清められ、九つの湖沼は
堤防が築かれ、四方の海も交流し合うようになった。
六つの官府はよく整えられ、諸国の土地は秩序を取り戻し、
財政と賦税を慎重に管理し、三つの土地(上田・中田・下田)ごとに
租税を定めた。
中央の国には封土と姓を賜り、天子の徳を尊び、朕の施策に従うようにした。
“五百里ごとの区分と貢納制度:”
1. 500里:甸服(直轄地・最も近い地域)
1.1 百里圏内:租税を総括して納める
1.2 二百里圏内:銍(穀物の一種)を納める
1.3 三百里圏内:秸(藁など)を納める
1.4 四百里圏内:粟(あわ)を納める
1.5 五百里圏内:米を納める
2. 500里:侯服(諸侯の支配地)
2.1百里圏内:特産物を貢納
2.2 二百里圏内:諸侯に従属する小国
2.3 三百里圏内:諸侯の領地
2.4綏服(文化・軍事的影響を及ぼす地域)
2.5 三百里圏内:文教を施す
2.6 二百里圏内:武力による守備を行う
3. 500里:要服(要衝地域)
3.1 三百里圏内:夷(異民族)
3.2二百里圏内:蔡(異民族の一部族)
4. 500里:荒服(辺境の異民族地帯)
4.1三百里圏内:蛮(南方の民族)
4.2 二百里圏内:流(流浪の民)
東は海に至り、西は流沙(タクラマカン砂漠)に及び、
北から南へと天子の教化は四海の果てまで行き渡った。
禹は黒色の玉璽を授かり、その偉業を告げた。
------------尚書の夏書の禹貢24の原文---------------
九州攸同,四隩既宅,九山刊旅,九川滌源,九澤既陂,四海會同。
六府孔修,庶土交正,厎慎財賦,咸則三壤成賦。
中邦錫土、姓,祗台德先,不距朕行。
五百里甸服:百里賦納總,二百里納銍,三百里納秸服,四百里粟,五百里米。
五百里侯服:百里采,二百里男邦,三百里諸侯。
五百里綏服:三百里揆文教,二百里奮武衛。
五百里要服:三百里夷,二百里蔡。
五百里荒服:三百里蠻,二百里流。
東漸于海,西被于流沙,朔南□聲教訖于四海。禹錫玄圭,告厥成功。
Re: 各種資料(翻訳) - (管理人)
2025/03/02 (Sun) 21:58:24
生成AIの力を借りて、「扶余伝」の和訳をお知らせします。
Chinese Text Projectの底本は「武英殿二十四史」本「三国志」です。
-------------------- 夫餘伝和訳 ----------------------------
扶余(夫餘)は長城の北にあり、玄菟から千里の距離にある。
南は高句麗と接し、東は挹婁(ゆうろう)、西は鮮卑と接し、
北には弱水がある。
その国土は約二千里四方に及ぶ。
八万戸があり、その民は定住し、宮殿・倉庫・牢獄を備えている。
山が多く、広々とした平地も広がっており、東夷の地域の中で
最も開けた土地である。
土地は五穀の栽培に適しているが、五果(五種の果物)は生育しない。
その民は体格が大きく、性格は勇敢でありながら誠実で、
略奪を行わない。
国には君主が存在し、官職の名称には家畜の名が使われている。
例えば「馬加」「牛加」「猪加」「狗加」などのほか、
「大使」「大使者」「使者」といった官職もある。
村には豪族がいて、その支配下にある者は皆、奴隷とされる。
諸「加」(貴族)はそれぞれ別々の集団を統率し、
大きな者は数千戸、小さな者でも数百戸を治める。
食事の際には俎(まないた)や豆(食器)を用い、宴会の際には
爵(盃)を拝し、爵を洗い、互いに礼を交わして昇降する。
殷(商)に倣い正月に天を祭る。
その際には国中で大会が開かれ、数日にわたって飲食や歌舞が続く。
この祭りは「迎鼓」と呼ばれ、
この期間中は刑罰を停止し、囚人を釈放する。
国内では白を尊び、白布の大袖の衣、袍(長衣)、袴(ズボン)、
革製の履(靴)を着用する。
しかし国外へ出る際には、織物や錦を身に着ける。
貴族はキツネやクロテン、白テンの毛皮をまとい、
金銀の飾りのついた帽子をかぶる。
通訳は言葉を伝える際、ひざまずいて地面に手をつき、小声で話す。
刑罰は厳格である。
殺人者は死刑となり、その家族は奴婢(奴隷)とされる。
盗みを働いた者は、盗んだ額の十二倍を賠償させられる。
男女の不倫や女性の嫉妬は厳しく罰せられ、死刑に処される。
特に嫉妬は憎まれ、処刑後の遺体は国の南の山に放置され、
腐敗するまでそのままにされる。
遺族が遺体を引き取る場合、牛や馬を納めなければならない。
兄が亡くなると、その弟が未亡人を妻とするのが慣習であり、
これは匈奴の風習と同じである。
この国は家畜の飼育に優れ、名馬や赤玉(美しい赤い玉)、
クロテンやテナガザルの毛皮、美しい真珠を産出する。
真珠の大きいものはカラタチの実ほどの大きさがある。
兵器は弓矢・刀・槍を用い、各家に鎧や武具が備えられている。
国の長老たちは、古代に滅びた人々の話を語る。
城柵を築く際は円形のものが多く、牢獄のような形をしている。
道を行く者は昼夜を問わず老若男女が歌い続け、
一日中その歌声が絶えない。
戦がある際には天を祭り、牛を屠ってその蹄を見て吉凶を占う。
蹄が割れれば凶兆、合っていれば吉兆とされる。
敵が攻めてくると、貴族たちが戦い、庶民は兵糧や飲食物を担いで支援する。
戦死者が出た際には、夏でも氷を用いる。
殉葬の風習があり、殺される者は百人以上にのぼることもある。
葬儀は盛大に行われ、棺はないが槨(外棺)が設けられる。
『魏略』によれば、この国の習俗では喪に服する期間は五か月で、
長く喪に服することが名誉とされる。
亡者を祭る際には生肉と熟肉が供えられる。
喪主は急いで葬儀を終えたくないが、周囲の人々はそれを促し、
その過程で口論になることも多く、それが儀式の一部となっている。
喪に服する際には、男女ともに白の服をまとい、女性は布製の面布を
着け、装飾品を外す。
全体的に中国の喪礼と似たところがある。
扶余(夫餘)はもともと玄菟(げんと)郡に属していた。
漢末、公孫度(こうそんたく)が海東で勢力を広げ、外夷を威圧し服属
させたため、扶余王の尉仇台(いくたい)は遼東に属するようになった。
当時、高句麗と鮮卑が強大だったため、公孫度は
扶余がこの二つの勢力の間にあることを考慮し、
自らの宗女(王族の娘)を尉仇台に嫁がせた。
尉仇台が死ぬと、簡位居(かんいきょ)が王となった。
しかし、彼には正妻の子がなく、庶子の麻余(まよ)がいた。
簡位居が死ぬと、諸加(貴族たち)が協議し、麻余を王に立てた。
牛加(ぎゅうか)の兄の子で、位居(いきょ)という者が大使となった。
彼は財を惜しまず施しを好んだため、国人から支持を受け、
毎年使者を派遣して魏の都に朝貢を行った。
正始年間(240年~249年)、幽州刺史の毌丘儉(かんきゅうけん)が
高句麗を討伐する際、玄菟太守の王頎(おうき)を扶余に派遣した。
位居は大加(たいか)を派遣して郊外で迎え、軍糧を提供した。
しかし、叔父である牛加は謀反の心を抱いていたため、
位居は叔父とその子を殺し、その財産を没収し、官に送り届けた。
もともと扶余の習俗では、干ばつや水害が続き、五穀が実らないと、
その責任を王に求める習わしがあった。
そのため、「王を替えるべきだ」「王を殺すべきだ」との声が
上がることがあった。
麻余が死ぬと、その子の依慮(いりょ)がわずか六歳で王に立てられた。
漢の時代、扶余王の葬儀には玉の匣(はこ)が用いられ、
あらかじめ玄菟郡に預けておき、王が死ぬとそれを迎え取って
埋葬する習わしがあった。
公孫淵(こうそんえん)が誅殺された後も、玄菟の倉庫には玉の匣が
一つ残されていた。
現在、扶余の倉庫には玉璧(ぎょくへき)・珪(けい)・瓚(さん)と
いった数代にわたる宝物が伝えられており、それらは先代の王たちが
授けられたものだと、国の長老たちは語っている。
『魏略』によれば、扶余の国は非常に豊かであり、先祖代々、
戦乱による破壊を受けたことがなかったという。
また、扶余の王の印には「濊王之印(わいおうのいん)」と刻まれて
おり、国には「濊城(わいじょう)」と呼ばれる古城がある。
もともとこの地は濊貊(わいばく)の土地であり、
扶余王は「亡人(滅びた民の子孫)」と自称していたが、
確かにそのような背景があるようだ。
『魏略』の旧記には、かつて北方に「高離(こうり)」という国が
あり、そこに以下のような伝説があったという。
その国の王の侍女が懐妊したため、王は彼女を殺そうとした。
すると侍女は、「鶏卵のような光が空から降りてきて、それを浴びた
ために身ごもったのです」と訴えた。
やがて子が生まれたが、王はこれを信じず、赤子を便所に捨てた。
すると豚が鼻息で赤子を温めた。
次に馬小屋に移されると、今度は馬が息を吹きかけ、赤子は死ななかった。
王はこれを不思議に思い、
「天の子かもしれない」と考え、母親に育てさせることにした。
その子は東明(とうめい)と名付けられ、成長すると馬の世話を
することになった。
東明は弓の名手となった。
王は、彼が自らの国を奪うのではないかと恐れ、殺そうとした。
すると東明は逃亡し、南へ向かい施掩水(しえんすい)という川に
至った。
彼が弓で水を打つと、魚やスッポンが集まり橋を作ったため、
東明は無事に渡ることができた。
しかし、彼の後を追っていた兵士たちが渡ろうとした瞬間、
魚とスッポンは散り、追っ手は川を渡れなかった。
こうして東明は現在の王夫余(注1:おうふよ)の地に
都を定めたという。
注1)中華人民共和国、吉林省、農安県
---------------------- 夫餘伝原文 -------------------------------
夫餘在長城之北,去玄菟千里,南與高句麗,東與挹婁,西與鮮卑接,
北有弱水,方可二千里。
戸八萬,其民土著,有宮室、倉庫、牢獄。多山陵、廣澤,
於東夷之域最平敞。土地宜五穀,不生五果。
其人麤大,性彊勇謹厚,不寇鈔。國有君王,
皆以六畜名官,有馬加、牛加、豬加、狗加、大使、大使者、使者。
邑落有豪民,名下戸皆為奴僕。
諸加別主四出,道大者主數千家,小者數百家。
食飲皆用俎豆,會同、拜爵、洗爵,揖讓升降。
以殷正月祭天,國中大會,連日飲食歌舞,名曰迎鼓,於是時斷刑獄,
解囚徒。
在國衣尚白,白布大袂,袍、袴,履革鞜。
出國則尚繒繡錦罽,大人加狐狸、狖白、黑貂之裘,以金銀飾帽。
譯人傳辭,皆跪,手據地竊語。
用刑嚴急,殺人者死,沒其家人為奴婢。
竊盜一責十二。男女淫,婦人妬,皆殺之。
尤憎妬,已殺,尸之國南山上,至腐爛。
女家欲得,輸牛馬乃與之。
兄死妻嫂,與匈奴同俗。其國善養牲,出名馬、赤玉、貂狖、美珠。
珠大者如酸棗。
以弓矢刀矛為兵,家家自有鎧仗。
國之耆老自説古之亡人。
作城柵皆員,有似牢獄。
行道晝夜無老幼皆歌,通日聲不絶。
有軍事亦祭天,殺牛觀蹄以占吉凶,蹄解者為凶,合者為吉。
有敵,諸加自戰,下戸俱擔糧飲食之。
其死,夏月皆用氷。
殺人徇葬,多者百數。
厚葬,有槨無棺。
魏畧曰:其俗停喪五月,以□為榮。
其祭亡者,有生有熟。喪主不欲速而他人彊之,常諍引以此為節。
其居喪,男女皆純白,婦人著布靣衣,去環珮,大體與中國相彷彿也。
----
夫餘本屬玄菟。
漢末,公孫度雄張海東,威服外夷,夫餘王尉仇台更屬遼東。
時句麗、鮮卑彊,度以夫餘在二虜之間,妻以宗女。
尉仇台死,簡位居立。
無適子,有孽子麻余。
位居死,諸加共立麻余。
牛加兄子名位居,為大使,輕財善施,國人附之,歳歳遣使詣京都貢獻。
正始中,幽州刺史毌丘儉討句麗,遣玄菟太守王頎詣夫餘,
位居遣大加郊迎,供軍糧。
季父牛加有二心,位居殺季父父子,籍沒財物,遣使簿斂送官。
舊夫餘俗,水旱不調,五糓不熟,輙歸咎於王,或言當易,或言當殺。
麻余死,其子依慮年六歳,立以為王。
漢時,夫餘王葬用玉匣,常豫以付玄菟郡,王死則迎取以葬。
公孫淵伏誅,玄菟庫猶有玉匣一具。
今夫餘庫有玉璧、珪、瓚數代之物,傳世以為寶,耆老言先代之所賜也。
魏畧曰:其國殷富,自先世以來,未甞破壞也。
其印文言「濊王之印」,國有故城名濊城,蓋本濊貊之地,而夫餘王其中,
自謂「亡人」,抑有似也。
魏畧曰:舊志又言,昔北方有高離之國者,其王者侍婢有身,王欲殺之,
婢云:「有氣如鷄子來下,我故有身。」後生子,王捐之於溷中,
猪以喙噓之,徙至馬閑,馬以氣噓之,不死。
王疑以為天子也,乃令其母收畜之,名曰東明,常令牧馬。
東明善射,王恐奪其國也,欲殺之。
東明走,南至施掩水,以弓擊水,魚鼈浮為橋,
東明得渡,魚鼈乃解散,追兵不得渡。
東明因都王夫餘之地。
Re: 各種資料(翻訳) - (管理人)
2025/03/02 (Sun) 16:12:17
----------- 濊傳 和訳 --------------------------
濊(わい)は南で辰韓(しんかん)、北で高句麗(こうくり)・
沃沮(よくそ)と接し、東は大海に至る。
現在の朝鮮の東部一帯がその領域にあたる。総戸数は二万。
昔、箕子(きし)が朝鮮に渡り、「八条の教」を制定して
人々を教化した。
そのため、人々は家の門を閉ざさずとも盗みを働くことがなかった。
その後、四十余世代を経て、
朝鮮侯の準(じゅん)が自ら王を称するようになった。
陳勝(ちんしょう)らが挙兵し、天下が秦に背いた際、
多くの燕・斉・趙の民が朝鮮に避難し、その数は数万に及んだ。
その中で、燕人の衛満(えいまん)は、髪を髷に結び異国の衣を
まとって再び王位を得た。
しかし、漢の武帝が朝鮮を討ち滅ぼし、その地を四郡に分けた。
この時以来、胡(異民族)と漢(漢民族)の区別が明確になった。
濊には大君主はおらず、漢以降の統治機構として、侯邑君
(こうゆうくん)、三老(さんろう)という官職があり、
彼らが民を統治していた。
彼らの長老たちは、自分たちが高句麗と同じ種族であると称している。
人々は温厚で誠実であり、欲が少なく、廉恥の心を持つ。
高句麗に従属することはなく、言語・制度・風俗は概ね高句麗と
似ているが、衣服に違いがある。
男女ともに曲領(カーブした襟)の衣服を着用し、
男性は幅数寸の銀の装飾を身につける。
単単大山(たんたんたいざん)より西は楽浪郡(らくろうぐん)に属し、
山の東側には七県があり、都尉(とい)がこれを統治し、
濊の民を住民とした。
後に都尉の職が廃止されると、渠帥(きょすい)たちは侯(こう)に
封ぜられた。
現在の不耐濊(ふたいわい)は皆、彼らの子孫である。
漢の末期になると、濊は再び高句麗の支配下に入った。
彼らは山川を神聖視し、それぞれに領域が決められており、
勝手に立ち入ることは許されなかった。
同族間での婚姻は禁止されていた。また、禁忌が多く、
病気や死があると、すぐに旧宅を捨てて新たな家を建てた。
彼らは麻布を織り、蚕を飼い綿を作る。
星宿(せいしゅく)を観察して、豊作か凶作かを予測する。
玉を宝とはせず、十月の祭りで天を祭り、昼夜酒を飲み、歌舞を楽しむ。
これを「舞天(ぶてん)」と呼ぶ。
また、虎を神として崇拝する。
彼らの村々は互いに争いを起こすことがあり、その際には、
生口(せいこう)・牛・馬を賠償として要求する。
これを「責禍(せきか)」と呼ぶ。
殺人者には死刑が科される。
盗賊は少ない。
彼らは三丈(約7.2メートル)の長槍を作り、数人がかりで持ち、
歩兵戦を行う。楽浪檀弓(らくろうたんきゅう)はこの地で産する。
また、彼らの海では班魚(はんぎょ)の皮が産出され、
土地には文豹(ぶんぴょう)が多く、果下馬(かかば)も産出される。
漢の桓帝(かんてい)の時代には、果下馬が献上された。
臣・裴松之(はいしょうし)の注釈:
果下馬は高さ三尺(約70㎝)で、果樹の下でも乗ることができるため、
この名がついた。『博物志』や『魏都賦』にも記載がある。
正始六年(245年)、楽浪太守・劉茂(りゅうも)、
帯方太守・弓遵(きゅうじゅん)は、東濊を高句麗から
切り離そうと軍を起こし、不耐侯らは邑ごと降伏した。
正始八年(247年)、彼らは朝廷に朝貢し、
詔勅によって「不耐濊王(ふたいわいおう)」に封ぜられた。
彼らは民間に雑居し、四季ごとに郡へ赴き、朝謁(ちょうえつ)した。
二郡(楽浪・帯方)では徴兵・租税の負担があり、役務も課され、
一般の民と同じ扱いを受けた。
------------ 濊傳 原文---------------------
濊南與辰韓,北與高句麗、沃沮接,東窮大海,今朝鮮之東皆其地也。
戸二萬。
昔箕子既適朝鮮,作八條之教以教之,無門戸之閉而民不為盜。
其後四十餘世,朝鮮侯準僭號稱王。
陳勝等起,天下叛秦,燕、齊、趙民避地朝鮮數萬口。
燕人衞滿,魋結夷服,復來王之。
漢武帝伐滅朝鮮,分其地為四郡。自是之後,胡漢稍別。
無大君長,自漢已來,其官有侯邑君、三老,統主下戸。
其耆老舊自謂與句麗同種。
其人性愿愨,少嗜慾,有廉恥,不請句麗。
言語法俗大抵與句麗同,衣服有異。
男女衣皆著曲領,男子繫銀花廣數寸以為飾。
自單單大山領以西屬樂浪,自領以東七縣,都尉主之,皆以濊為民。
後省都尉,封其渠帥為侯,今不耐濊皆其種也。
漢末更屬句麗。其俗重山川,山川各有部分,不得妄相涉入。
同姓不婚。
多忌諱,疾病死亡輙捐棄舊宅,更作新居。
有麻布,蠶桑作緜。曉候星宿,豫知年歳豐約。
不以誅玉為寶。
常用十月節祭天,晝夜飲酒歌舞,名之為舞天,又祭虎以為神。
其邑落相侵犯,輙相罰責生口牛馬,名之為責禍。
殺人者償死。
少寇盜。
作矛長三丈,或數人共持之,能步戰。樂浪檀弓出其地。
其海出班魚皮,土地饒文豹,又出果下馬,漢桓時獻之。
臣松之案:
果下馬高三尺,乘之可於果樹下行,故謂之果下。
見博物志、魏都賦。
正始六年,樂浪太守劉茂、帶方太守弓遵以領東濊屬句麗,興師伐之,
不耐侯等舉邑降。
其八年,詣闕朝貢,詔更拜不耐濊王。
居處雜在民間,四時詣郡朝謁。
二郡有軍征賦調,供給役使,遇之如民。
Re: 各種資料(翻訳) - (管理人)
2025/03/02 (Sun) 15:40:25
------- 挹婁傳和訳 ----------------
挹婁(ゆうろう)は夫余の東北千余里に位置し、大海に面しており、
南は北沃沮(ほくよくそ)と接しているが、
その北方の果ては不明である。
その土地は山が多く険しい。
人々の姿形は夫余に似ているが、言語は夫余や句麗(高句麗)とは
異なる。
五穀や牛、馬、麻布を産し、民は皆勇敢で力強い。
大きな君主はおらず、村ごとに「大人(たいじん)」と呼ばれる長が
いる。
彼らは山林の間に住み、常に穴居生活をしている。
大きな家では、地下深くに九段の梯子を設け、
それを多くするほど良いとされる。
土地の気候は夫余よりもさらに寒冷である。
その風習として豚を飼うことを好み、肉を食べ、皮を衣服として用いる。
冬には豚の脂を厚く塗り、数層に重ねることで風寒を防ぐ。
夏には裸になり、一尺ほどの布で前後を覆うのみで体を隠す。
彼らは不潔を厭わず、排泄場を中央に設け、その周囲に人々が居住する。
彼らの弓は長さ四尺あり、その威力は弩(ど)のように強い。
矢には楛(から)を用い、長さは一尺八寸で、青石の鏃(やじり)を
備えている。これは古の粛慎(しゅくしん)氏の国であり、
弓術に優れ、射られた者は皆貫かれる。
さらに、矢に毒を塗り、当たった者は必ず死ぬ。
この国は赤玉を産し、貂(てん)の毛皮を珍重する。
今でいう「挹婁貂(ゆうろうてん)」はこれである。
漢の時代以降、彼らは夫余に臣従していたが、夫余が重い租税を
課したため、黄初年間(220~226年)に反乱を起こした。
夫余はたびたび挹婁を討伐したが、
彼らの人口は少ないながらも、地勢が険しく、隣国の人々は
彼らの弓矢を恐れ、ついに服従させることはできなかった。
彼らの国は船を巧みに操り、隣国を襲撃・略奪するため、
周辺の国々はその被害に悩まされていた。
東夷の諸国では一般的に俎豆(そとう)を用いて飲食するが、
挹婁だけはこれを用いず、法や風俗にもまったく秩序がない。
------------ 挹婁傳 原文---------------------
挹婁在夫餘東北千餘里,濵大海,南與北沃沮接,未知其北所極。
其土地多山險。
其人形似夫餘,言語不與夫餘、句麗同。有五糓、牛、馬、麻布。
人多勇力。無大君長,邑落各有大人。
處山林之間,常穴居,大家深九梯,以多為好。
土氣寒,劇於夫餘。其俗好養豬,食其肉,衣其皮。
冬以豬膏塗身,厚數分,以禦風寒。
夏則裸袒,以尺布隱其前後,以蔽形體。
其人不絜,作溷在中央,人圍其表居。
其弓長四尺,力如弩,矢用楛,長尺八寸,青石為鏃,古之肅慎氏之國也。
善射,射人皆入。
因矢施毒,人中皆死。
出赤玉,好貂,今所謂挹婁貂是也。
自漢已來,臣屬夫餘,夫餘責其租賦重,以黃初中叛之。
夫餘數伐之,其人衆雖少,所在山險,鄰國人畏其弓矢,卒不能服也。
其國便乘船寇盜,鄰國患之。
東夷飲食類皆用俎豆,唯挹婁不,法俗最無綱紀也。
Re: 各種資料(翻訳) - (管理人)
2025/03/02 (Sun) 15:31:43
---------- 韓傳 の和訳 ---------------------------------
韓は帯方郡の南にあり、東西は海をもって限りとなし、
南は倭と接触し交流している。
国の広さは四千里ほどである。
そこには三つの種族があり、
一つを馬韓、二つ目を辰韓、三つ目を弁韓という。
辰韓は、古代の辰国である。
馬韓は西方に位置し、その住民は定住して農耕を行い、養蚕を知り、
綿布を作る。
それぞれの国には首長がいて、大きな国の首長は「臣智」と自称し、
次に位する者は「邑借」と称する。
彼らは山や海の間に散在し、城郭を持たない。
馬韓には以下の国々がある。
爰襄国、牟水国、桑外国、小石索国、大石索国、優休牟涿国、臣濆沽国、
伯済国、速盧不斯国、日華国、古誕者国、古離国、怒藍国、月支国、
咨離牟盧国、素謂乾国、古爰国、莫盧国、卑離国、占離卑国、臣釁国、
支侵国、狗盧国、卑弥国、監奚卑離国、古蒲国、致利鞠国、冉路国、
児林国、駟盧国、内卑離国、感奚国、万盧国、辟卑離国、臼斯烏旦国、
一離国、不弥国、支半国、狗素国、捷盧国、牟盧卑離国、臣蘇塗国、
莫盧国、古臘国、臨素半国、臣雲新国、如来卑離国、楚山塗卑離国、
一難国、狗奚国、不雲国、不斯濆邪国、爰池国、乾馬国、楚離国――
合わせて五十余りの国がある。
大きな国では一万戸以上、小さな国では数千戸の規模であり、
全体で十万戸余りに及ぶ。
辰王は月支国に居を構え、統治している。
臣智の中には、優呼・臣雲・遣支・報安・邪踧・支濆・臣離・児不例・
拘邪・秦支・廉といった称号を加える者もいる。
官職には魏率善・邑君・帰義侯・中郎将・都尉・伯長などがある。
侯準は僭称して王を名乗ったが、燕から亡命してきた衛満の攻撃を受け、
その王位を奪われた。
________________________________________
『魏略』曰く
昔、箕子の子孫である朝鮮侯は、周王朝の衰退を目の当たりにした。
当時、燕は自らを王と称し、東方へ領土を拡大しようとしていた。
そこで朝鮮侯もまた自らを王と称し、周王朝を尊ぶために兵を起こし、
燕に対抗しようとした。
しかし、大夫の「礼」がこれを諫めたため、朝鮮侯は計画を中止した。
その後、「礼」を燕に派遣し、説得させたところ、燕も攻撃をやめた。
しかし、後の子孫たちは次第に驕慢で残虐になり、ついに
燕は将軍・秦開を派遣し、朝鮮の西方を攻撃した。
その結果、二千余里の土地を奪い、満潘汗を境界とした。
これにより、朝鮮は衰弱した。
その後、秦が天下を統一し、蒙恬に命じて長城を築かせ、遼東まで
達した。このとき、朝鮮王の否(ひ)が即位していたが、
秦の侵攻を恐れ、形式的には服属しつつも、朝貢には応じなかった。
やがて否が亡くなり、その子の準(じゅん)が王となった。
それから二十余年が経ち、陳勝・項羽が挙兵し、天下は乱れた。
燕・斉・趙の民は困窮し、次第に朝鮮へ亡命するようになった。
準は彼らを西方に移住させた。
その後、漢が盧綰を燕王に封じると、朝鮮は燕と□水(はいすい)を
境界とした。
しかし、盧綰が反乱を起こし、匈奴へ逃れると、燕の亡命者である
衛満(えいまん)もまた難を逃れた。彼は胡服(異民族の衣服)を
着て身を偽り、□水を渡り、準のもとに降伏した。
そして準に対して、「西方の国境に住まわせてもらい、中国からの
亡命者を集め、朝鮮の藩屏(防衛の盾)となる」と説いた。
準はこれを信じ、衛満を寵愛し、博士の位を与え、玉璽を授け、
百里の領地を封じ、西方の守備を任せた。
しかし、衛満は密かに亡命者を集め、勢力を拡大していった。
そしてある日、使者を派遣し、「漢の軍勢が十の道から押し寄せてくる」
と偽って報告し、王宮に宿営を求めた。
その後、衛満は突然反旗を翻し、準を攻撃した。
準は戦ったが敵わず、側近や宮人たちを伴い、海を渡って
韓の地へ逃れた。そして自らを「韓王」と称した。
________________________________________
『魏略』曰く
準の子や、彼に親しい者で国に留まった者たちは、
「韓」姓を名乗るようになった。
準は海上の地で王となったが、朝鮮とは往来しなかった。
その後、彼の血統は絶えたが、現在の韓人の中には、
なお彼の祭祀を奉じる者がいる。
漢の時代、朝鮮は楽浪郡に属し、四季ごとに朝貢し参詣していた。
『魏略』曰く
初め、右渠(朝鮮王)がまだ滅ぼされる前、朝鮮の相(宰相)である
歴谿卿(れっけいけい)は右渠を諫めたが、聞き入れられなかったため、
東方の辰国に去った。その際、彼に従って移住した民は二千余戸に及び、
それ以降、辰国は朝鮮に対して朝貢や藩属の関係を持つことはなかった。
王莽の地皇年間(8~23年)、廉斯鑡(れんししゃく)は辰韓の右渠帥
(将軍)であった。
彼は楽浪の土地が肥沃であり、人々が豊かに暮らしていると聞き、
亡命して降伏したいと考えた。
ある日、邑落(村)を出て、田で雀を追っている男を見つけた。
その言葉が韓人のものではなかったため、尋ねたところ、
その男はこう答えた。
「私は漢人で、名を戸来(こらい)と言います。我々は千五百人で
木材を伐採していましたが、韓人に襲われ、捕虜となりました。
それ以来、髪を切られ、奴隷として三年間過ごしています。」
鑡は言った。
「私は漢の楽浪に降伏するつもりだ。お前は去りたいか?」
戸来は答えた。
「それは望むところです。」
そこで鑡は戸来を連れて含資県に向かい、県から楽浪郡に報告した。
郡は鑡を通訳とし、芩中(きんちゅう)から大船に乗って辰韓に入り、
戸来を迎え入れた。
この際、同行した者のうち千人は救い出すことができたが、
五百人はすでに死亡していた。
鑡は辰韓に言った。
「残りの五百人を返せ。もしそうしなければ、
楽浪は万の兵を船に乗せ、お前たちを討つだろう。」
辰韓は答えた。
「五百人はすでに死んでしまった。その代わり、身代金を支払おう。」
そこで辰韓は一万五千人を、弁韓は布一万五千匹を差し出した。
鑡はこれを受け取って帰還した。
郡は鑡の功績と義行を称え、彼に冠幘(官位を示す冠)と
田宅(領地)を与えた。
その子孫は数代にわたり恩恵を受け、安帝の延光四年(125年)まで
免税などの特権を受け続けた。
------ ここからは陳寿の記述 --------
桓帝・霊帝の末期
桓帝・霊帝の末期(2世紀後半)、韓族と濊族が勢力を強め、
楽浪郡や帯方郡の郡県は彼らを制御できなくなった。
そのため、多くの民が韓国(韓族の地)へ流入した。
建安年間(196~220年)、公孫康は屯有県(楽浪郡南部)の南の
荒地を帯方郡として分割した。
そして、公孫模・張敞らを派遣し、流民を収容するとともに、
軍を興して韓族・濊族を討伐した。
その結果、元の住民も次第に戻り、
それ以降、倭と韓は帯方郡に属することとなった。
魏の景初年間(237~239年)
景初年間、魏の明帝(曹叡)は密かに帯方太守・劉昕および
楽浪太守・鮮于嗣を派遣し、海を渡って二郡を安定させた。
このとき、諸韓国の「臣智(しんち)」には
邑君(ゆうくん)の印綬(官位を示す印章と組紐)を授け、
次の位の者には邑長(ゆうちょう)を与えた。
韓族の風習としては、幘(さく)という冠を好んで身につけた。
下層の人々が郡へ参詣する際は、みな幘を仮につけ、
印綬や幘を身に着ける者は千人余りにのぼった。
楽浪郡の部従事・呉林は、「楽浪郡はもともと韓国を統治していた」
として、辰韓の八国を楽浪郡に分割編入した。
しかし、通訳の間で言葉の違いが生じたため、
韓族の「臣智」たちは憤り、帯方郡の崎離営(軍営)を攻撃した。
当時の帯方太守・弓遵(きゅうじゅん)と楽浪太守・劉茂(りゅうぼう)
は軍を興してこれを討伐したが、弓遵は戦死した。
その後、二郡は韓族を滅ぼした。
韓族の風俗
韓族は法や秩序が少なく、国や邑(村)に主帥(統治者)がいても、
人々は雑居し、うまく統治できなかった。
跪いて礼をする習慣もなかった。
住居は草葺きの土室で、形は冢(墳墓)のようになっており、
入口は上部にあり、一家が中で共に生活した。
長幼や男女の区別なく同じ空間で過ごした。
葬儀では棺はあったが、槨(外柩)はなかった。
牛や馬に乗る習慣はなく、家畜はすべて葬儀の際に犠牲とされた。
財宝としては瓔珞(装飾品)を重んじ、衣服に縫い付けたり、
首に掛けたり、耳から垂らしたりした。
一方で、金・銀・錦繍は珍重しなかった。
彼らの性格は剛勇であり、頭髪を大きくまとめ、露出させた。また、
兵器を帯びることを好み、布製の長袍を着て、革製の靴を履いていた。
国の事業や官府の城郭建設に従事する際、若くて力のある者は
背中の皮膚を切開し、太い縄を通し、さらに長さ約一丈(約3メートル)
の木杭を通した。
そして、昼夜の区別なく大声で叫びながら作業に励んだが、それを
苦痛とは思わず、むしろ労働の励みとし、勇敢さの証と考えた。
彼らは毎年五月に種まきを終えると、鬼神を祭る儀式を行った。
その際、人々は群れ集まり、昼夜を問わず歌舞し、酒を飲み続けた。
________________________________________
韓族の舞踊と祭祀
彼らの舞踊は、数十人が一斉に立ち上がり、互いに歩調を合わせて
踊るものである。
地面を踏みしめながら、身体を上下に揺らし、手足の動きが調和し、
リズムは鐸舞(たくぶ、鈴を持って踊る舞)に似ている。
十月に農作業が終わると、再び同じように踊る。
彼らは鬼神を信仰し、国や邑ごとに一人を祭司として立て、天神を祀る。
その者を「天君(てんくん)」と呼ぶ。
また、各国には「蘇塗(そと)」と呼ばれる特別な邑があり、
大木を立てて鈴や太鼓を掛け、鬼神を祀る。
罪人や逃亡者が蘇塗に逃げ込めば、誰も彼らを連れ戻すことはできず、
彼らはそこで盗賊となることを好む。この蘇塗の制度は
仏教の僧院に似ているが、行われる善悪の内容には違いがある。
韓族の風習と物産
北方の郡に近い国々は、多少は礼儀や習俗を理解しているが、
遠方の国々はまるで囚人や奴婢が集まったような状態である。
特別な財宝は持たず、動植物もほぼ中国と同じである。
ただし、大きな栗が採れ、その大きさは梨ほどもある。
また、尾の細長い鶏が産出され、その尾は五尺(約150cm)以上もある。
また、彼らの男子の中には、時折身体に文身(入れ墨)を施す者もいる。
馬韓の西にある「州胡(しゅうこ)」
馬韓の西の海にある大きな島には、「州胡(しゅうこ)」と呼ばれる
人々が住んでいる。
彼らはやや小柄で、言語は韓族と異なる。
皆、髠頭(こんとう、頭を剃る)にしており、
その姿は鮮卑(せんぴ)に似ている。
ただし、衣服は革製で、牛や豚を好んで飼育している。
彼らの衣服は上半身を覆うものの、下半身は覆わず、
ほとんど裸のような格好である。
船を使って韓族の地と行き来し、物品を交易している。
Re: 各種資料(翻訳) - (管理人)
2025/03/02 (Sun) 15:03:41
Chinese Text Projectの底本は「武英殿二十四史」本「三国志」です。
------------ 高麗伝原文 ----------
高句麗在遼東之東千里,南與朝鮮、濊貊,東與沃沮,北與夫餘接。
都於丸都之下,方可二千里,戸三萬。多大山深谷,無原澤。
隨山谷以為居,食澗水。無良田,雖力佃作,不足以實口腹。
其俗節食,好治宮室,於所居之左右立大屋,祭鬼神,又祠靈星、社稷。
其人性凶急,善寇鈔。
其國有王,其官有相加、對盧、沛者、古雛加、主簿、優台丞、使者、
皁衣先人,尊卑各有等級。
東夷舊語以為夫餘別種,言語諸事,多與夫餘同,其性氣衣服有異。
本有五族,有涓奴部、絶奴部、順奴部、灌奴部、桂婁部。
本涓奴部為王,稍微弱,今桂婁部代之。
漢時賜鼓吹伎人,常從玄菟郡受朝服衣幘,高句麗令主其名籍。
後稍驕恣,不復詣郡,於東界築小城,置朝服衣幘其中,
歳時來取之,今胡猶名此城為幘溝漊。
溝漊者,句麗名城也。
其置官,有對盧則不置沛者,有沛者則不置對盧。
王之宗族,其大加皆稱古雛加。涓奴部本國主,今雖不為王,
適統大人,得稱古雛加,亦得立宗廟,祠靈星、社稷。
絶奴部世與王婚,加古雛之號。
諸大加亦自置使者、皁衣先人,名皆達於王,如卿大夫之家臣,
會同坐起,不得與王家使者、皁衣先人同列。
其國中大家不佃作,坐食者萬餘口,下戸遠擔米糧魚鹽供給之。
其民喜歌舞,國中邑落,暮夜男女群聚,相就歌戲。
無大倉庫,家家自有小倉,名之為桴京。
其人絜清自喜,善藏釀。跪拜申一脚,與夫餘異,行步皆走。
以十月祭天,國中大會,名曰東盟。
其公會,衣服皆錦繡金銀以自飾。
大加主簿頭著幘,如幘而無餘,其小加著折風,形如弁。
其國東有大穴,名隧穴,十月國中大會,迎隧神還於國東上祭之,
置木隧於神坐。
無牢獄,有罪諸加評議,便殺之,沒入妻子為奴婢。
其俗作婚姻,言語已定,女家作小屋於大屋後,名壻屋,
壻暮至女家戸外,自名跪拜,乞得就女宿,如是者再三,
女父母乃聽使就小屋中宿,傍頓錢帛,至生子已長大,乃將婦歸家。
其俗淫。
男女已嫁娶,便稍作送終之衣。
厚葬,金銀財幣,盡於送死,積石為封,列種松栢。
其馬皆小,便登山。國人有氣力,習戰鬪,沃沮、東濊皆屬焉。
又有小水貊。
句麗作國,依大水而居,西安平縣北有小水,南流入海,
句麗別種依小水作國,因名之為小水貊,出好弓,所謂貊弓是也。
王莽初發高句麗兵以伐胡,欲不行,彊迫遣之,皆亡出塞為寇盜。
遼西大尹田譚追擊之,為所殺。
州郡縣歸咎於句麗侯騊,嚴尤奏言:
「貊人犯法,罪不起於騊,且宜安慰。今猥被之大罪,恐其遂反。」
莽不聽,詔尤擊之。尤誘期句麗侯騊至而斬之,傳送其首詣長安。
莽大恱,布告天下,更名高句麗為下句麗。
當此時為侯國,漢光武帝八年,高句麗王遣使朝貢,始見稱王。
至殤、安之間,句麗王宮數寇遼東,更屬玄菟。
遼東太守蔡風、玄菟太守姚光以宮為二郡害,興師伐之。
宮詐降請和,二郡不進。
宮密遣軍攻玄菟,焚燒候城,入遼隧,殺吏民。
後宮復犯遼東,蔡風輕將吏士追討之,軍敗沒。
宮死,子伯固立。
順、桓之間,復犯遼東,寇新安、居郷,又攻西安平,
於道上殺帶方令,略得樂浪太守妻子。
靈帝建寧二年,玄菟太守耿臨討之,斬首虜數百級,伯固降,屬遼東。
熹平中,伯固乞屬玄菟。
公孫度之雄海東也,伯固遣大加優居、主簿然人等助度擊富山賊,破之。
伯固死,有二子,長子拔奇,小子伊夷模。
拔奇不肖,國人便共立伊夷模為王。
自伯固時,數寇遼東,又受亡胡五百餘家。
建安中,公孫康出軍擊之,破其國,焚燒邑落。
拔奇怨為兄而不得立,與涓奴加各將下戸三萬餘口詣康降,還住沸流水。
降胡亦叛伊夷模,伊夷模更作新國,今日所在是也。
拔奇遂往遼東,有子留句麗國,今古雛加駮位居是也。
其後復擊玄菟,玄菟與遼東合擊,大破之。
伊夷模無子,淫灌奴部,生子名位宮。
伊夷模死,立以為王,今句麗王宮是也。其曾祖名宮,
生能開目視,其國人惡之,及長大,果凶虐,數寇鈔,國見殘破。
今王生□地,亦能開目視人。
句麗呼相似為位,似其祖,故名之為位宮。
位宮有力勇,便□馬,善獵射。
景初二年,太尉司馬宣王率衆討公孫淵,宮遣主簿大加將數千人助軍。
正始三年,宮寇西安平,其五年,為幽州刺吏毌丘儉所破。語在儉傳。
Re: 各種資料(翻訳) - (管理人)
2025/03/01 (Sat) 21:20:12
Kazumi Hirai
13時間 ·・2025年02月17日(月) 09:44
漢籍の再学習:その10
「三国志」「東夷伝」に続き生成AIの力を借りて、
「高句麗傳」の和訳をお知らせします。
Chinese Text Projectの底本は「武英殿二十四史」本「三国志」です。
┌(管理人補足:wikiより)
│陳寿(ちんじゅ)
│(建興11年〈233年〉? - 元康7年〈297年〉?)は、
│中国の三国時代の蜀漢と西晋に仕えた官僚。
│字は承祚(しょうそ)。『三国志』の著者として知られる。
└
------------ ChatGPTの和訳 -----(「三国志」「高句麗傳」)
高句麗は遼東の東千里に位置し、
南は朝鮮および濊貊(かいばく)、東は沃沮(よくそ)、
北は夫餘(ふよ)と接している。
都は丸都山のふもとにあり、領土は約二千里、三万戸が
暮らしている。
地形は大きな山々と深い谷が多く、肥沃な平野がない。
人々は谷沿いに住み、渓流の水を飲んで生活している。
良い田畑はなく、一生懸命耕作しても食糧が十分に得られない。
風習としては、食事を質素にしながらも、
宮殿や住居の建設を好む。
住居の周囲には大きな建物を建て、鬼神を祭り、
また天の星や社稷(国家の神)を祀る。
人々は気性が荒く、略奪に長けている。
国には王が存在し、官職には相加(しょうか)、
対盧(たいろ)、沛者(はいしゃ)、古雛加(こすうか)、
主簿(しゅぼ)、優台丞(ゆうだいじょう)、使者(ししゃ)、
皁衣先人(そういせんじん)などがあり、
それぞれの階級が厳格に分かれている。
東夷(とうい)の古い言葉では、高句麗は夫餘の別種であり、
言語や習俗は夫餘と多く共通するが、気質や服装は異なる。
もともと五つの部族(涓奴部(けんどぶ)、絶奴部(ぜつどぶ)、
順奴部(じゅんどぶ)、灌奴部(かんどぶ)、桂婁部(けいろうぶ))
があり、当初は涓奴部が王族だったが、次第に衰退し、
現在は桂婁部が王位を継承している。
漢の時代、皇帝は鼓吹楽人(音楽演奏者)を賜り、彼らは玄菟郡
(げんとぐん)から正式な官服と冠を受け取っていた。
高句麗はこれを管理する役割を持っていたが、後に横暴となり、
玄菟郡へ赴かなくなった。
そして東の国境に小さな城を築き、そこに官服と冠を保管し、
毎年受け取りに来るようになった。
現在も異民族たちはこの城を「幘溝漊(さくこうろう)」と呼んでいる。
「溝漊(こうろう)」とは高句麗の言葉で「城」の意味である。
高句麗の官制では、対盧がいる場合は沛者を置かず、
沛者がいる場合は対盧を置かない。
王族の中で最も地位の高い者は「古雛加」と呼ばれる。
涓奴部はかつての王族であり、現在は王ではないが、
依然として有力者であり「古雛加」と称され、
祖先の祠を持ち、天の星や社稷を祀ることができる。
絶奴部は代々王族と婚姻関係にあり、「古雛加」の称号を与えられる。
その他の有力者も独自の使者や皁衣先人を置くが、
彼らの名前は王に報告されなければならない。
彼らは漢の卿や大夫の家臣に相当するが、
王家の使者や皁衣先人とは同等ではない。
国の有力者たちは農耕をせず、一万戸以上の庶民が遠くから米や魚、
塩を運んで供給する。
人々は歌や踊りを好み、村々では夜になると男女が集まり、
一緒に歌い踊る。大きな倉庫はなく、
各家庭に「桴京(ふけい)」と呼ばれる小さな倉庫を持っている。
人々は清潔を好み、酒造りに長けている。
跪く際は片足を伸ばし、夫餘とは異なる。歩く際は常に走る。
十月には「東盟(とうめい)」と呼ばれる大祭があり、人々は金銀を
あしらった刺繍の衣服を着て集まる。高官の主簿は特有の帽子をかぶり、
小官は「折風(せっぷう)」と呼ばれる弁髪風の帽子をかぶる。
国の東には「隧穴(ずいけつ)」と呼ばれる大きな洞窟があり、
十月の祭りで「隧神(ずいしん)」を迎え、国の東で祀る。
神の座には木製の隧(ずい)を置く。
牢獄はなく、罪を犯した者は貴族たちの評議によって即座に処刑され、
その家族は奴隷となる。
結婚の風習として、婚約が決まると、花嫁の家の裏に
「壻屋(せいや)」と呼ばれる小屋を建てる。
夜になると婿は花嫁の家の前で名を名乗り、跪いて宿泊を願い出る。
これを三度繰り返すと、ようやく小屋に泊まることを許される。
金銭や布を贈り、子供が成長した後に正式に妻を迎える。
人々は性に奔放であり、結婚後すぐに死後の衣装を用意し始める。
葬儀は盛大で、金銀や財宝を惜しみなく使い、石を積んで墓を築き、
松や柏を植える。
馬は小型だが山登りに適している。
人々は武勇に優れ、戦闘に慣れている。
沃沮(よくそ)や東濊(とうかい)は高句麗に服属している。
また「小水貊(しょうすいばく)」という小部族もいる。
高句麗は大河沿いに建国されたが、別の支族が小さな川沿いに
国を作り、それが「小水貊」と呼ばれるようになった。
彼らの作る弓は優れており、「貊弓(ばくきゅう)」として知られる。
王莽(おうもう)の時代の初め、高句麗の兵を動員して胡(異民族)を
討伐しようとしたが、彼らは行きたがらず、強制的に派遣された。
しかし、皆こぞって塞外(国境の外)へ逃亡し、賊となった。
遼西(りょうせい)の大尹(だいいん)である田譚(でんたん)が
これを追撃したが、逆に彼らに殺された。
州・郡・県の役人たちは、句麗侯(こうりこう)の騊(とう)に
責任を負わせようとした。
これに対し、厳尤(げんゆう)は奏上して言った。
「貊人(ばくじん)が法を犯したのは事実ですが、その罪は騊に
あるわけではありません。むしろ、彼を慰撫すべきです。
今、大罪を着せれば、彼は必ず反乱を起こすでしょう。」
しかし、王莽はこれを聞き入れず、厳尤に討伐を命じた。
厳尤は騊を欺き、彼に会う約束を取り付けて捕らえ、
その場で斬首し、その首を長安へ送った。
王莽はこれを大いに喜び、天下に布告して
「高句麗(こうくり)」を「下句麗(かくり)」と改めた。
この時、高句麗は侯国(こうこく)であったが、漢の光武帝の建武八年
(32年)、高句麗王が使者を遣わして朝貢し、初めて「王」と称された。
殤帝(しょうてい)・安帝(あんてい)の時代(105年~125年)に
なると、高句麗王・宮(きゅう)はたびたび遼東を侵略し、
玄菟(げんと)の管轄に移された。
遼東太守の蔡風(さいふう)と玄菟太守の姚光(ようこう)は、
宮を両郡の害であると考え、軍を興して討伐した。しかし、
宮は降伏を装って講和を申し入れたため、両郡の軍は進軍を止めた。
その後、宮は密かに軍を派遣し、玄菟を攻撃して候城(こうじょう)を
焼き払い、遼隧(りょうすい)に侵入して官吏や民衆を殺害した。
後に宮は再び遼東を侵略し、蔡風が軽率にも少数の兵を率いて
追撃したが、敗北して戦死した。
宮が死ぬと、子の伯固(はくこ)が王位を継いだ。
順帝(じゅんてい)・桓帝(かんてい)の時代(125年~167年)にも、
再び遼東に侵入し、新安(しんあん)や居郷(きょきょう)を襲撃し、
西安平(せいあんぺい)を攻めた。また、道中で帯方郡の令(長官)を
殺し、楽浪太守の妻子を捕らえた。
霊帝(れいてい)の建寧二年(169年)、玄菟太守の耿臨(こうりん)
が討伐し、数百の首級を斬り、伯固は降伏して遼東に帰属した。
熹平年間(172年~178年)、伯固は玄菟への帰属を願い出た。
その後、公孫度(こうそんたく)が海東(朝鮮半島東部)で勢力を
拡大すると、伯固は大加(たいか)の優居(ゆうきょ)や
主簿(しゅぼ)の然人(ぜんじん)らを派遣し、
公孫度の軍を助けて富山(ふざん)の賊を討伐し、これを撃破した。
(06)<薬師如来像光背 銘文>ほか - (管理人)
2024/10/19 (Sat) 10:48:17
(06)
(参考1)
<舊唐書 卷五 本紀第五 高宗 下>
(咸亨五年)秋八月壬辰、追尊宣簡公為宣皇帝、懿王為光皇帝、
太祖武皇帝為高祖神堯皇帝、太宗文皇帝為文武聖皇帝、
太穆皇后為太穆神皇后、文德皇后為文德聖皇后。
皇帝稱天皇、皇后稱天后。改咸亨五年為上元元年、大赦。
一方、推古朝のころとする説の根拠となるのが推古朝時代に
作成されたとされるこの天寿國繍帳銘文や法隆寺金堂の
薬師如来像光背銘文に天皇という言葉がすでに使用されて
いることであった(原文中赤文字で表示)。
しかし、薬師如来像光背銘文が推古朝の作とはみられないと
いう研究結果があらわれ(参考2)、
天皇号推古朝成立説はやや力を失った。だが近年、
天寿國繍帳の銘文は推古朝の作とみてよいという研究
(義江明子:「天寿國繍帳銘系譜の一考察」『日本史研究』
325号 1989年)があらわれ、
天皇号推古朝成立説に復活の兆しがある。
(参考2)
奈良・法隆寺金堂の薬師如来像は光背に推古天皇15年(607年)
の銘があるが、銘文中の用語や像自体の鋳造技法等から、
実際の制作は7世紀後半と言われている。
ちなみに実際の光背銘文と「上宮聖徳法王帝説」が伝える
銘文は下記の通り。なお比較対象の便のために
適宜文章をスペースで区切り、改行した。
<薬師如来像光背 銘文>
池辺大宮治天下天皇 大御身労賜時 歳次丙午年
召於大王天皇与太子 而誓願賜 我大御病太平欲坐
故将造寺薬師像作仕奉詔 然当時崩賜
造不堪者 小治田大宮治天下大王天皇 及東宮聖王
大命受賜而 歳次丁卯年仕奉
<「上宮聖徳法王帝説」が伝える薬師如来像光背 銘文>
池邊大宮御宇天皇 大御身労賜時 歳次丙午年
召於大王天皇与太子 而誓願賜 我大御病大平欲坐故
将造寺薬師像作仕奉詔 然當時崩賜
造不堪者 小治田大宮御宇大王天皇 及東宮聖徳王
大命受賜而 歳次丁卯年仕奉
しかし義江説に対してこの「天寿國繍帳銘文」がはたして
繍帳作成の当初から繍帳に縫い付けられていたものか
疑問があるとする反論もしくは疑義が提出されている。
その論旨を要約すると次の通りである。
天寿國繍帳は聖徳太子の后であった橘大郎女
(推古天皇の息子である尾張皇子の娘。つまり推古からみれば
孫娘にあたる)の願いにより作成された。
銘文の内容をみると、この繍帳は橘大郎女が彼女の亡き夫を
しのぶよすがとして、彼女の身近におかれて使用されたはず
である。
そうであれば太子の系譜を述べ、繍帳作成の経緯を述べる
銘文が橘大郎女にとって必要なものであったかどうか検討
してみる必要がある。
彼女にとってこのような銘文は必要なものではなかったと
見るのが自然であろう。
したがって繍帳自体は推古朝に作成されたものとしても、
作成当初の繍帳には銘文の刺繍は無く、後の時代に追加して
縫いつけられたものである可能性は否定できない。
これに反論するには銘文の亀の刺繍と繍帳の他の部分の
刺繍技術や材料などを科学的に比較分析し、両者が同時期に
作成されたものであることを証明しなくてはなるまい。
わずか原稿用紙1枚(四百字)の文章ではあるが
議論は尽きず興味深い。
法隆寺金堂薬師如来像光背銘(ウィキペディアより)
法隆寺金堂薬師如来像光背銘(ほうりゅうじ こんどう
やくしにょらいぞう こうはいめい)は、奈良県斑鳩町の
法隆寺金堂に安置される薬師如来像の光背裏面に刻された
銘文である。
題号の「金堂薬師如来像」を薬師如来・薬師仏・薬師像・
薬師などとも称し、銘文の内容が造像の由来であることから
「光背銘」を造像銘・造像記とも称す。ゆえに
法隆寺薬師造像銘などと称す文献も少なくない[1][2][3]。
要約[編集]
文面は、「用明天皇が病気の時(用明天皇元年(586年))、
平癒を念じて寺(法隆寺)と薬師像を作ることを誓われたが、
果たされずに崩じた。のち推古天皇と聖徳太子が遺詔を奉じ、
推古天皇15年(607年)に建立した。」
という趣旨の内容である[1][2][13]。
文体[編集]
本銘文はすべて漢字で記されているが、全体として漢文と
日本語の文法が混然としており、国文の一体といえる。
このような仮名がまだ生まれていない段階の日本語文を
亀井孝は「漢字文」、吉澤義則は「記録体」と呼んでいる。
『古事記』がそれにあたる著名なものであるが、それよりも
古い本銘文にもすでに漢文の文法から脱して日本語化しよう
とする意図が窺える。
例えば、「造寺」(動詞+目的語)は漢文式であるが、
「薬師像作」(目的語+動詞)は日本語式になっている。
また、「大御(おほみ)身」、「勞賜(たまふ)」、
「仕奉(まつる)」のような日本語語順による敬語表記を
交えている[22][23][24]。
天寿國繍帳 銘文 (復元) - (管理人)
2024/10/19 (Sat) 10:41:52
(05)
メニューの先頭へ / メニューの 「天寿國繍帳」 の項へ
天寿國繍帳 銘文 (復元)
斯歸斯麻 宮治天下 天皇名阿 米久爾意 斯波留支
しきしまの宮(磯城嶋宮)に天の下治らしめしし天皇
(すめらみこと)、名は あめくにおしはるき
比里爾波 乃弥己等 娶巷奇大 臣名伊奈 米足尼女
ひろにはのみこと(天國排開廣庭尊=欽明天皇)、そが(蘇我)
の大臣いなめ(稲目)の足尼(すくね/宿禰)がむすめ
名吉多斯 比弥乃弥 己等爲大 后生名多 至波奈等
名は きたしひめのみこと(堅鹽媛命)を娶りて大后
(おおきさき)となし、名は たちばなと
已比乃弥 己等妹名 等已弥居 加斯支移 比弥乃弥
よひのみこと(橘豐日尊=用明天皇)・妹(いも)名は
とよみけかしきやひめのみ
己等復娶 大后弟名 乎阿尼乃 弥己等爲 后生名孔
こと(豐御食炊屋姫尊=推古天皇)を生みたまいき。
また大后が弟(おと)名は おあねのみこと(小姉命)を
后となし、名は あな
部間人公 主斯歸斯 麻天皇之 子名蕤奈 久羅乃布
ほべはしひとのひめみこ(穴穂部泥部皇女)を生みたまいき。
しきしまの天皇が御子、名は ぬなくらのふ
等多麻斯 支乃弥己 等娶庶妹 名等已弥 居加斯支
とたましきのみこと(渟中倉太珠敷尊=敏達天皇)、
庶妹(ままいも)名は とよみけかしき
移比弥乃 弥己等爲 大后坐乎 沙多宮治 天下生名
やひめのみこと を娶りて大后となし、おさたの宮(譯田宮/
他田宮)に坐(いま)して天の下治らしめしき。名は
尾治王多 至波奈等 已比乃弥 己等娶庶 妹名孔部
尾治王(おはりのみこ)を生みたまいき。たちばなとよひのみこ
と(橘豐日尊=用明天皇)、庶妹(ままいも)名は あなほべ
間人公主 爲大后坐 瀆邊宮治 天下生名 等已乃弥
はしひとのひめみこ を娶りて大后となし、いけのべの宮
(池邊宮)に坐しまして天の下治しめしき。名は とよのみ
弥乃弥己 等娶尾治 大王之女 名多至波 奈大女郎
みのみこと(豐聰耳皇子=聖徳太子)を生みたまいき。尾治王が
むすめ、名はたちばなの大女郎(おおいらつめ)を娶りて
爲后歳在 辛巳十二 月廿一癸 酉日入母 孔部間人
后となしたまう。歳(ほし)辛巳(かのと・み)にありし十二月
二十一(日)癸酉(みずのと・とり)の日のくれに母の孔部間人
王崩明年 二月廿二 日甲戌夜 半太子崩 于時多至
王(あなほべのはしひとのみこ)崩(かむざ)りましぬ。
明くる年の二月二十二日甲戌(きのえ・いぬ)の夜半に
太子崩りましき。時にたち
波奈大女 郎悲哀嘆 息白畏天 皇前曰敬 之雖恐懐
ばなの大女郎、悲哀(かなしび)嘆息(なげき)して白(もう)
さく「畏(かしこ)き天皇が前に曰(い)いて敬(もう)すは
これ恐れありといえども、懐(おも)う
心難止使 我大皇與 母王如期 從遊痛酷 无比我大
心止(や)みがたし。わが大皇(おおきみ)と母王(ははの
みこ)と期(ちぎ)りしが如く從遊(じゅゆ)せしめたまう。
痛く酷(から)きこと比ぶる無し。わが大
王所告世 間虚假唯 仏是真玩 味其法謂 我大王應
王の告げたまいしく
『世間は虚假(こけ)にして、ただ仏のみこれ真なり』と。
その法(のり)を玩味(あじわ)うに、わが大王は
生於天壽 國之中而 彼國之形 眼所叵看 悕因圖像
天寿國の中に生れたまうべしと謂(おも)えり。
而(しか)るに彼の國の形は眼に看(み)叵(かた)き所なり。
悕(ねが)わくは図像によりて
欲觀大王 往生之状 天皇聞之 悽然告曰 有一我子
大王が往生したまう状(かたち)を觀(み)んと欲(おも)う」
と。天皇これを聞こしめして悽然として告げて曰く
「わが子ひとり有り。
所啓誠以 爲然勅諸 采女等造 繍帷二張 畫者東漢
啓(もう)す所は誠に然なりと以爲(おも)う」と。
勅して諸の釆女(うねめ)らに繍帳二張を造らしむ。
畫(えが)ける者は東漢(やまとのあや)の
末賢高麗 加西溢又 漢奴加己 利令者椋 部秦久麻
末賢(めけ)、高麗(こま)の加西溢(かせい)、
また漢(あや)の奴加己利(ぬかこり)。令者(つかさひと)
は椋部(くらひとべ)の秦久麻(はたのくま)なり。
<読み下し文>
斯帰斯麻(しきしま)宮に天の下治ろしめしし天皇
名は阿米久爾意斯波留支比里爾波乃弥己等
(あめくにおしはるきひろにはのみこと)
巷奇(そが)の大臣 名は伊奈米(いなめ)の足尼(すくね)
の女(むすめ) 名は吉多斯比弥乃弥己等(きたしひめの
みこと)を娶して大后とし 生みませる名は
多至波奈等己比乃弥己等(たちばなとよひのみこと)
妹の名は等巳弥居加斯支移比弥乃弥己等
(とよみけかしきやひめのみこと)
復(また) 大后の弟 名は乎阿尼乃弥己等(おあねのみこと)
を娶して后と為し 生みませる名は孔部間人公王
(あなほべはしひとのひめみこと)
斯帰斯麻天皇の子 名はヌ奈久羅之布等多麻斯支乃彌己等
(ぬなくらのふとたましきのみこと)
庶妹 名は等巳弥居加斯支移比弥乃弥己等
(とよみけかしきやひめのみこと)を娶して 大后と為し
乎沙多(おさた)の宮に坐して 天の下治しめして
生みませる名は尾治王
多至波奈等己比乃弥己等(たちばなとよひのみこと)
庶妹 名は孔部間人公王(あなほべはしひとのひめみこと)を
娶して 大后と為し 濱辺の宮に坐して 天の下治しめして
生みませる名は等巳刀弥弥乃弥己等(とよとみみのみこと)
尾治大王の女 名は多至波奈大女郎(たちばなおおいらつめ)
を娶して后と為したまう
歳は辛巳に在る十二月廿一日癸酉の日入に 孔部間人母王 崩り
たまう 明年の二月廿二日申戌の夜半に 太子 崩りたまいぬ
時に多至波奈大女郎 悲哀(かな)しみ嘆息(なげ)きて
天皇の前に畏み白して曰さく
「之を啓(もう)すは恐れありと雖も心に懐いて止使(やみ)
難し 我が大王と母王と 斯りし如く従遊まして
痛酷(むご)きこと比なし
我が大王の所告(のたま)いけらく
『世間は虚仮にして 唯仏のみ是れ真なり』と其の法を玩味
(あじわい)みるに 我が大王は 応(まさ)に天寿国の中に
生まれましつらんとぞ謂(おも)う
而るに 彼の国の形は眼に看がたき所なり
稀(ねが)わくば図像に因りて大王の往生したまえる
状(さま)を観(み)んと欲(おも)う」
と天皇 之を聞こしめして 凄然たまいて告曰(のりたま)わく
「一の我が子有り 啓す 所誠に以て然か為す」
と諸の妥女等に勅して 繍帷二張を造らしめたまう
画ける者は 東漢末賢(やまとのあやのまけん) 高麗加世溢
(こまのかせい) 又 漢奴加己利(あやのぬかこり)
令せる者は 椋部秦久麻(くらべのはたのくま)なり
(上記読み下し文の大意)
辛巳の年(推古天皇29年・西暦621年)12月21日、
聖徳太子の母・穴穂部間人皇女(間人皇后)が亡くなり、
翌年2月22日には太子自身も亡くなってしまった。
これを悲しみ嘆いた太子の妃・橘大郎女は、推古天皇
(祖母にあたる)にこう申し上げた。
「太子と母の穴穂部間人皇后とは、申し合わせたかのように
相次いで逝ってしまった。
太子は『世の中は空しい仮のもので、仏法のみが真実である』
と仰せになった。
太子は天寿国に往生したのだが、その国の様子は目に見えない。
せめて、図像によって太子の往生の様子を見たい」と。
これを聞いた推古天皇はもっともなことと感じ、
采女らに命じて繍帷二帳を作らせた。
画者(図柄を描いた者)は東漢末賢(やまとのあやのまけん)、
高麗加西溢(こまのかせい)、漢奴加己利(あやのぬかこり)
であり、令者(制作を指揮した者)は椋部秦久麻
(くらべのはだのくま)である。
●このように破損したものの銘文がなぜ復元できているか
というと、いくつかの写本が残っており、また
『天寿國曼荼羅繍帳縁起勘点文』・『中宮寺尼信如起請等事』・
『法隆寺東院縁起』・『天寿國曼荼羅起因』・『斑鳩古事便覧』
・『聖徳太子伝正法論』などに引用があるからである。
また「上宮聖徳法王帝説」が「右は法隆寺の蔵に在る
繍帳二張、縫い著けし龜の背の上の文字なり」として
その全文を記録している。
ただし「上宮聖徳法王帝説」が記す銘文は
写しもれや書写の間違いなどで、本来400字であるはずの
銘文が398字になっている。
●この銘文には「わが国で『天皇』という称号がいつ成立したか」という問題が内在している。
そもそも天皇という語の由来には主に下記の三説がある。
_①中国で宇宙の主宰神とされる昊天上帝の別名、『天皇大帝』
に由来するという説。
_②道教の最高神である『天皇大帝』に由来するという説。
_③大王の権威を増すために『大』→『天』・『王』→『皇』
という具合にそれぞれの文字の画数を増して出来上がった
日本で作られた漢語であるとする説。
次に天皇号の成立時期だが、これには二説あり、
ひとつは推古朝とする説、
ひとつは天武・持統朝のころとする説である。
現在では天武・持統朝のころすなわち七世紀後半とする説が
有力である。
その根拠となるのは唐の第三代皇帝の高宗が674年
(天武三年)に皇帝に代えて天皇の称号を用いた事実があり
(参考1)、その影響によるものとされる。
またこの時期の日本では律令の制定とともに『古事記』・
『日本書紀」などの国史編纂が始まり、
これらと連動して従来の倭国を日本国と称するようになり、
また従来の大王が天皇となったとするものである。
「上宮聖徳法王帝説」(04) - (管理人)
2024/10/19 (Sat) 10:17:39
(04)
丁未(ひのと・ひつじ)の年の六七月、蘇我馬子宿祢大臣
(そがのうまこのすくねのおおおみ)、物部室屋大連
(もののべももりやのおおむらじ)を伐つ。
時に大臣の軍士、尅(たえ)ずして退く。
故、則ち上宮王、四王像を擧げ、軍士の前に建てて、
誓いて云いしく、「若し此の大連を亡ぼし得れば、四王の爲に
寺を造り尊び重く供養奉つらん。」と。
即ち軍士勝を得て、大連を取りて訖る。
依りてこれ即ち難波に四天王寺を造る。
聖王生れまして十四の年也。
志癸嶋天皇(しきしまのすめらみこと/欽明天皇)の御世、
戊午(つちのえ・うま)の年十月十二日、百済國の主明王、
始めて度りきて佛像・經敎、并せて僧等を奉る。
勅(みことのり)して蘇我稲目宿祢大臣(そがのいなめの
すくねのおおおみ)に授け、興隆せしむ。
庚寅(かのえ・とら)の年、佛殿・佛像を焼き滅ばし、
難波の堀江に流し却(う)てき。
小治田天皇(推古天皇)の御世、乙丑(きのと・うし)の
年の五月、聖徳王と嶋大臣、共に謀り佛法を建立し、
更に三寶を興す。
即ち五行に准(したが)い、爵位を定めたまう。
七月、十七餘の法(のり)を立てたまう。
飛鳥天皇(あすかのすめらみこと/皇極天皇)の御世、
癸卯(みずのと・う)の年の十月十四日、蘇我豊浦毛人大臣
(そがのとゆらのえみしのおおおみ)が児(みこ)入鹿臣
■■林太郎(いるかのおみ-文字脱落-はやしのたいろう)。
伊加留加宮(いかるがのみや)に坐して、山代大兄
(やましろのおおえ)及び其の昆第等、合わせて十五王子等
(とおあまりいつはしらのみこたち)を悉く滅す。
獺祭注:【入鹿臣■■林太郎】 日本書紀 皇極天皇二年分
注 に 「林臣(はやしのおみ)は入鹿ぞ」 とある。
また同四年に 「高向臣國押(たかむくのおみ・くにおし)、
漢直(あやのあたい)等に謂いて曰く『吾等、君の大郎
(たいろう)によりて戮(ころ)されぬべし…」 とある。
すなわち 林 太郎 は入鹿のこと。
なお以下の数行はいわゆる 乙巳(いっし)の変 を記す。
■■天皇(文字脱落して不詳。皇極天皇のこと)の御世、
乙巳(きのと・み)の年の六月十一日、近江天皇
(おうみのすめらみこと/天智天皇・当時中大兄)
【生れまして廿一年】、林太郎■■(はやしのたいろう
-文字脱落-)を殺す。
明くる日を以って、其の父の豊浦大臣
(とゆらのおおおみ/蘇我蝦夷)と子孫等、皆之を滅す。
志歸嶋天皇(しきしまのすめらみこと/欽明天皇)天の下
治しめすこと一年【辛卯の年の四月に崩りましき。陵
(みささぎ)は檜前坂合岡(ひのくまのさかあいのおか)也】。
他田天皇(おさたのすめらみこと/敏達天皇)天の下治しめす
こと十四年【乙巳(きのと・み)の年の八月に崩りましき。
陵は河内の志奈我原(しながのはら)に在り】。
池邊天皇(いけのへのすめらみこと/用明天皇)天の下治しめす
こと三年【丁未(ひのと・ひつじ)の年の四月に崩りましき。
秋七月に葬り奉る。或いは川内の志奈我中尾稜
(しながのなかのおのみささぎ)と云う】。
倉橋天皇(くらはしのすめらみこと/崇峻天皇)天の下治しめす
こと四年【壬子(みずのえ・ね)の年の十一月に崩りましき。
實に嶋大臣の滅する所と爲す。
陵は倉橋岡(くらはしのおか)に在り】。
小治田天皇(おはりだのすめらみこと/推古天皇)天の下治しめ
すこと卅六年【戊子の年の三月に崩りましき。
陵は大野岡(おおののおか)也。
或いは川内の志奈我山田寸(しながのやまだのむら)と云う】
上宮聖德法王、または法主王と云う。
甲午(きのえ・うま)の年に産れまして、壬午(みずのえ・
うま)の年の二月廿二日に薨逝したまう
【生れまして九年。小治田宮の東宮と爲す。
墓は川内の志奈我岡(しながのおか)也】。
裏書
庚戌(かのえ・いぬ)春三月、學問尼善信等、百済より還り、
櫻井寺に住む。今の豊浦寺也
【初め櫻井寺と云い、後に豊浦寺と云う】。
曾我大臣云う、豊浦大臣と云々。
觀勒僧正、推古天皇の即位十年の壬戌(みずのえ・いぬ)に來る。
佛工(ぶつし)鞍作鳥(くらつくりのとり)。
案(くら)が祖父は司馬達(しばたつ)、多須奈(たすな)なり。
或る本に云う、播磨の水田、二百七十三町五段廿四歩云々。
また本に云う、三百六十町云々。
有る本に云う、寺を造るを請願し、三寶を恭敬す。十三年
辛丑(かのと・うし)、春三月十五日、始め浄土寺云々。
注に云う、辛丑(かのと・うし)の年、始めて地を平らげ、
癸卯(みずのと・う)の年、金堂を立て云々。
戊申(つちのえ・さる)、始めて僧住む。
己酉(つちのと・とり)の年の三月廿五日、大臣害に遇う。
癸亥(みずのと・い)の年、塔を構う。
癸酉(みずのと・とり)の年、十二月十六日、塔の心柱を建つ。
其の柱の礎の中に圓き穴を作り、浄土寺を刻ね、中に蓋有る
大鋭一口を置き、内に種々の珠玉を晟る。其の中に塗壷有り。
壷の内にまた種々の珠玉を晟る。其の中に銀の壷有り。
壷の中内に純金の壷有り。
其の内に青■■瓶有り、其の内に舎利八粒を納む。
丙子(ひのえ・ね)の年の四月八日、露盤(ろばん)を上ぐ。
戊寅(つちのえ・とら)の年の十二月四日、丈六の佛像を鋳る。
乙酉(きのと・とり)の年の三月廿五日、佛眼を點ず。
山田寺これ也。
注す、承歴二年【戊午(つちのえ・うま)】、南一房を冩す。
直曜の本なり。
曾我日向子臣(そがのひむかこのおみ)、字(あざな)は
無耶志臣(むざしのおみ)。
難波長柄豊碕宮(なにはのながえのとよさきのみや)に宇
(あめのした)御しめしし天皇の世、筑紫の大宰帥に任ず。
甲寅の年の十月、癸卯(みずのと・う)の朔の壬子(みずのえ・
ね)、天皇の爲に(おも)い、般若寺を起つ云々。
■■京時、定額寺云々。
曾我大臣。
推古天皇の卅四年秋八月、嶋大臣【曾我也】病に臥す。
大臣の爲に男女、并せて一千人■■■■。
また本に云う、廿二年甲戌(きのえ・いぬ)の秋八月、
大臣病に臥す。卅五年の夏六月辛丑(かのと・うし)に薨ず。
「上宮聖徳法王帝説」(03) - (管理人)
2024/10/19 (Sat) 10:07:17
(03)
斯斯麻宮(しきしまのみや)に天の下治しめしし天皇、名は
阿米久尓意斯波留支比里尓波乃弥己等(あめくにおしはるき
ひろにはのみこと/用明天皇)、巷奇大臣(そがのおおおみ)
名は伊奈米足尼(いなめのすくね)が女、名は吉多斯比弥乃
弥己等(きたしひめのみこと)を娶して大后と爲す。
生みませる名(みな)は多至波奈等己比乃弥己等
(たちはなとこひのみこと)、妹の名は等已弥居加斯支移比弥
乃弥己等(とよみけかしきやひめのみこと)。
また大后の弟、名は乎阿尼乃弥己等(おあねのみこと)を
娶して后と爲し、生みませる名は孔部間人公主(
あなほべはしひとのひめみこ)。
斯歸斯麻天皇(しきしまのすめらみこと/欽明天皇)の子、
名は奈久羅乃布等多麻斯支乃弥己等(ぬなくらのふとたましき
のみこと/敏達天皇)、庶妹、名は等己弥居加斯支移比弥乃
弥己等(とよみけかしきやひめのみこと)を娶して大后と爲す。
乎沙多宮(おさたのみや)に坐しまして天の下治しめしき。
生れます名は尾治王(おはりのみこ)。
多至波奈等己比乃弥己等(たちばなとこひのみこと/
用明天皇)、庶妹、名は孔部間人公主(あなほべはしひとの
ひめみこ)を娶して大后と爲す。
邊宮(いけのべのみや)に坐しまして天の下治しめしき。
生れます名は等己刀弥弥乃弥己等(とよとみみのみこと)、
尾治大王(おはりのみこ)の女、名は多至波奈大女郎
(たちばなのおおいらつめ)を娶して后と爲す。
歳は辛巳(かのと・み)十二月廿一日癸酉(みずのと・とり)
に在り、日入(ひぐれ)に、孔部間人母王
(あなほべはしひとのははみこ)崩りましぬ。
明くる年の二月廿二日、甲戌(きのえ・いぬ)の夜半、
太子崩りましぬ。
時に多至波奈大女郎(たちばなのおおいらつめ)、
悲哀(かなし)び嘆息(なげき)て白(もう)さく、
「畏(かしこ)き(天皇の前に曰(い)いて敬(もう)すは
之れ恐れありと雖ども懐(おも)う心止(とど)め難し。
我が大王と母王(ははのおおきみ)、期(ちぎ)りしが如く
従遊(かむざ)りまして、痛酷(いたまし)きこと比ぶる无し。
我が大王告げたまいしく、『世の間は虚假(こけ)にして、
ただ佛のみこれ真なり。』と。
其の法を玩味するに、我が大王は謂うに、應(まさ)に
天壽國の中に生れまさんとす。
而るに彼の國の形は眼にも看(み)え(かた)き所。
願(ねが)わくは圖像に因りて大王の往生したまう状(かたち)
を觀んと欲(おもお)す。」と。
天皇(推古天皇)之を聞きて悽然として告げて曰く、
「一(ひとり)の我が子有り、啓(もう)す所誠に以って
状一(然(しか))なり」と。
諸の采女等に勅(みことのり)して、繍帷(ぬいもののかた
びら)二張を造らせたまう。
畫者(えがけるひと)は、東漢(やまとのあや)の末賢
(めけ)、高麗(こま)の加西溢(かせい)、または漢
(あや)の奴加己利(ぬかこり)、令者(うなかせるもの)は
椋部秦久麻(くらひとべのはたのくま)。
右は法隆寺の蔵に在る繍帳二張、縫い著けし龜の背の上の
文字也。更更知られざる者也。
巷奇、【蘇我也】。弥の字【或いは賣(み)の音を當てる】。
己の字【或いは余(よ)の音を當てる】。
至の字【或いは知(ち)の音を當てる】。
白畏天之は【天即ち小治田天皇(おはりだのすめらみこと
/推古天皇)也】。
太子崩は【即ち聖王也】。従遊は【死也】。
天壽國は【猶(また)は天のみ云う】。
天皇聞之は【また小治田天皇也】。令は【猶(また)は監也】。
上宮薨じたまう時に臣勢三杖大夫の歌
伊加留我乃
斑鳩の(いかるがの)
止美能乎何波乃
止美の小川の(とみのおがはの)
多叡婆許曾
絶えばこそ(たえはこそ)
和何於保支美乃
我が大君の(わがおほきみの)
弥奈和須良叡米
御名忘らえめ(みなわすらえめ)
美加弥乎須
御神(?)おす(みかみをす)
多婆佐美夜麻乃
たばさみ山の(たばさみやまの)
阿遅加氣尓
あぢ蔭に(あぢかけに)
比止乃麻乎之志
人の申しし(ひとのまおしし)
和何於保支美波母
我が大君はも(わかおほきみはも)
伊加留我乃
斑鳩の(いかるがの)
己能加支夜麻乃
この垣山の(このかきやまの)
佐可留木乃
下かる木の(さかるきの)
蘇良奈留許等乎
空なる事を(そらなることを)
支美爾麻乎佐奈
君に申さな(きみにまおさな)
「上宮聖徳法王帝説」(02) - (管理人)
2024/10/19 (Sat) 07:51:29
(02)
戊午(つちのえ・うま)の年の四月十五日、少治田天皇
(推古天皇)、上宮王に請いて勝鬘經(しょうまんぎょう)を
講ぜしむ。其の儀は僧の如し。
諸(もろもろ)の王(みこ)公主(ひめみこ)及び臣(おみ)
連(むらじ)公民(おおみたから)、信受して嘉(よろこ)ば
ざる無し。三箇日の内に、講説訖(おわ)る。
天皇、聖王に物播磨國(はりまのくに)揖保郡(いほのこおり)
佐勢地(させのち)五十万代(いおよろずしろ)を布施し
たまう。聖王、即ち此の地を以って法隆寺の地と爲す
【今、播磨に在る田三百餘町なり】。
慧慈法師、上宮御製の疏を(もたら)して、本つ國に還り歸り、
流傳する間、壬午(みずのえ・うま)の年の二月廿二日の夜半、
聖王薨逝(かむざ)りましぬ。
慧慈法師之を聞き、王命の爲に經を講じ奉(たてまつ)らんと
發願して曰く、「上宮聖王、必ず化りて逢わんと欲(おもお)
す。吾、慧慈は來年の二月廿二日に死なば、必ず聖王の面と
浄土に逢い奉らん。」 遂に其の言の如く、
明くる年の二月廿二日に到りて、病を發し命終んぬ。
池邊大宮に宇(あめのした)御(しら)しめしし天皇
(用明天皇)、大御身労(いたづ)き賜う時、歳は丙午
(ひのえ・うま)に次(やど)りし年、大王天皇
(おおきみのすめらみこと/推古天皇)と太子を召して誓願し
賜う、「我が大御病、大きに平がんと欲し坐すが故に、
寺を造り薬師の像を作らしめ仕え奉つれ」と詔りたまいき。
然るに時當(まさ)に崩(かむざ)り賜いて、造り堪(あ)え
ざりき。小治田大宮に宇(あめのした)御(しら)しめしし
大王天皇(おおきみのすめらみこと)、及び東宮聖徳王、
大命を受け賜いて、歳は丁卯(ひのと・う)に次(やど)りし
年に仕え奉つりき。
右は法隆寺金堂に坐す薬師像の光後の銘文なり。
即ち寺を造りし始めの縁の由也。
法興元世一年、歳は辛巳(かのと・み)に次(やど)る十二月、
鬼前大后(かむさきのおおきさき)崩(かむざ)りましぬ。
明くる年の正月廿二日、上宮法王、病に枕して(たのし)まず。
干食王后(かしわでのみこのきさき)、も仍(ま)た労疾
(いたづ)きたまうを以って、並びに床に著く。
時に王后・王子等、及び諸の臣と、深く懐(おも)い愁い
毒(なや)み、共に相い發願す。
「仰ぎて三寶に依り、當に釋像の尺寸王身を造る。
此の願力を蒙(こうむ)り、病を轉じ壽(よわい)を延べ、
世の間に安住したまうことを。若し是れ定業(じょうぎょう)
にして、以って世に背(そむ)きたまはば、往きて浄土に登り、
早(と)く妙果昇らせたまわんことを。」と。
二月廿一日癸酉(みずのと・とり)に王后即世(そくせい)
したまう。
翌日法王登遐(とうか)したまう。
癸未(みずのと・ひつじ)の年の三月中、願の如く敬いて
釋迦尊像、并びに侠待、及び荘厳具(しょうごんぐ)を
造り竟(おわ)る。
斯の微福に乗り、信道の知識、現在安隠にして、生れ出で死に
入るも、三主に随い奉り、三寶を紹隆し、遂に彼岸を共にせん。
普遍(あまね)く六道法界(りくどうほっかい)の含識
(がんしき)も苦縁を脱するを得て、同じく菩提に趣かん。
司馬鞍首(しば・くらつくりのおびと)止利佛師(とりぶっし)
をして造らしむ。
右は法隆寺金堂に坐す釋迦佛の光後の銘文件(くだん)の如し
【今、私に云う、これ正面中臺の佛也】。
釋して曰く、法興元世一年、此れ能く知らざる也。
但し帝記に案じて云う、小治田天皇(推古天皇)の世、
東宮厩戸豊聰耳命、大臣(おおおみ)宗我馬子宿祢(そがの
うまこのすくね)、共に平章(へいしょう=ともにはかる)して
三寶を建立し、始めて大寺を興す。故に法興元世と曰う。
これ即ち銘に云う法興元世一年也。後に見ん人、若し年号と
疑うべくも、これ然らず。然れども則ち一年と言える字、
其の意見え難し。然れども見る所の者、聖王の母の穴太部王、
辛巳(かのと・み)の年に薨逝したまうは、即ち小治田天皇
(推古天皇)の御世。故に即ち其の年を指し、
故に一年と云い、其れ異なる趣き無し。
鬼前大后(かむさきのおおきさき)は、即ち聖王の母の穴太部
間人王(あなほべのはしひとのひめみこ)也。
鬼前と云うはこれ神前(かむさき)也。
何故に神前の皇后と言うとあらば、この皇后の同母弟、
長谷部天皇(崇峻天皇)、石寸神前宮(いわむらのかむさきの
みや)に天の下治しめしき。
若し疑うらくは其の姉の穴太部王、即ち其の宮に坐すが故に
神前皇后(かむさきのおおきさき)と稱す也。
明年と言えるは即ち壬午(みずのえ・うま)の年也。
二月廿一日癸酉(みずのと・とり)、王后即世したまうは、
これ即ち聖王が妻の膳大刀自(かしわでのおおとじ)也。
二月廿一日は、壬午(みずのえ・うま)の年の二月也。
翌日法王登遐したまうは、即ち上宮聖王也。
『即世(そくせい)』・『登遐(とうか)』は、
これ即ち死の異名也。
故、今この銘文に依りて、應(まさ)に壬午(みずのえ・うま)
の年の正月廿二日、聖王病に枕すと言うべし。
即ち同じ時に、膳大刀自(かしはでのおおとじ)労を得る也。
大刀自は、二月廿一日に卒す。聖王は廿二日に薨ず。
これを以ちて明らかに知るは、膳夫人は先の日に卒し、
聖王は後の日に薨ずる也。則ち歌に證(あか)して曰く。
伊我留我乃
斑鳩の(いかるがの)
止美能井乃美豆
止美の井の水(とみのいのみず)
伊加奈久尓
生かなくに(いかなくに)
多義弖麻之母乃
食きてましもの(たきてましもの)
止美乃井能美豆
鳥見の井の水(とみのいのみず)
この歌は膳夫人(かしわでのおおきさき)の病いに臥せて将に
没する時に臨み水を乞いたまう。然るに聖王許さず、遂に
夫人卒す。即ち聖王誄(いた)みてこの歌を詠みたまう。
即ち其の證(あかし)也。但し銘文の意、夫人の卒したまう日
顕(あき)らか也。聖王の薨じたまう年月を注さず。
然るに諸の説文、分明に云う、壬午(みずのえ・うま)の
年の二月廿二日甲戌(きのえ・いぬ)の夜半、上宮聖王
薨逝したまうと。
出生入死は、若し其の往き反り、生るる所の辭也。
三主は、若し疑うらくは神前大后、上宮聖王、膳夫人、
合せてこの三所(みはしら)也。
「上宮聖徳法王帝説」(01) - (管理人)
2024/10/19 (Sat) 07:46:15
(01)
伊波礼池邊雙槻宮(いわれいけのべのなみつきのみや)に天の
下治しめしし橘豊日天皇(たちばなのとよひのすめらみこと
/用明天皇)、庶妹(ままいも)穴穂部間人王(あなほべの
はしひとのひめみこ)を娶して、大后(おおきさき)と爲し、
生みませる児(みこ)は、厩戸豊聰耳(うまやとのとよとみみ)
の聖徳法王、次は久米王(くめのみこ)、次は殖栗王
(うえくりのみこ)、次は茨田王(まむたのみこ)。
また、天皇、蘇我伊奈米宿祢大臣(そがのいなめのすくねの
おおおみ)が女子(むすめ)、名は伊志支那郎女
(いしきなのいらつめ)を娶(めと)して生みませる児は
多米王(ためのみこ)。
また、天皇、葛木當麻倉首(かつらぎのたじまのおびと)名は
比里古(ひりこ)が女子、伊比古郎女(いひこのいらつめ)を
娶して生みませる児は乎麻呂古王(おまろこのみこ)、
次に須加弖古女王(すかてこのひめみこ)
【この王は伊勢の神前を拝み祭り、三はしらの天皇に至る】、
合わせて聖王の兄弟は、七はしらの王子也。
聖徳法王、膳部加多夫古臣(かしわでのかたふこのおみ)が
女子、名は菩岐々美郎女(ほききみのいらつめ)を娶して
生みませる児は舂米女王(つきしねのひめみこ)、
次に長谷王(はつせのみこ)、次に久波太女王(くはだの
ひめみこ)、次に波止利女王(はとりのひめみこ)、次に
三枝王(さきくさのみこ)、次に伊止志古王(いとしこの
みこ)、次に麻呂古王(まろこのみこ)、
次に馬屋古女王(うまやこのひめみこ)【已上八人】。
また、聖王、蘇我馬古叔尼大臣(そがのうまこのすくねのおお
おみ)が女子、名は刀自古郎女(とじこのいらつめ)を娶して
生みませる児は山代大兄王(やましろのおおえのみこ)
【此の王、賢く尊き心有り、身命を棄てて人民を愛す。
後の人、父の聖王に相濫(みだ)るというは非也】。
次に財王(たからのみこ)、次に日置王(ひおきのみこ)、
次に片岡女王(かたおかのひめみこ)【已上四人】。
また、聖王、尾治王が女子、位奈部橘王(いなべのたちばなの
ひめみこ)を娶して生みませる児は、白髪部王
(しらかべのみこ)、次に手嶋女王(てしまのひめみこ)、
合わせて聖王の児は十四はしらの王子也。
山代大兄王、庶妹、舂米王を娶して生みませる児は、
難波麻呂古王(なにはまろこのみこ)。
次に麻呂古王(まろこのみこ)、次に弓削王(ゆげのみこ)、
次に佐々女王(ささのひめみこ)、次に三嶋女王
(みしまのひめみこ)、次に甲可王(かふかのみこ)、
次に尾治王(おはりのみこ)。
聖王の庶兄多米王、其の父の池邊天皇(いけのべのすめら
みこと/用明天皇)の崩りし後に、聖王の母の穴太部間人王
(あなほべのはしひとのひめみこ)を娶して生みませる
児は佐富女王(さほのひめみこ)也。
斯貴嶋宮(しきしまのみや)に天の下治しめしし阿米久尓於志
波留支廣庭天皇(あめくにおしはるきひろにはのすめらみこと
/欽明天皇)【聖王の祖父也】、檜前天皇(ひのくまのすめら
みこと)が女子、伊斯比女命(いしひめのみこと)を娶して
生みませる児は他田宮(おさたのみや)に天の下治しめしし
天皇、怒那久良布刀多麻斯支天皇(ぬなくらふとたましきの
すめらみこと/敏達天皇)【聖王の伯叔也。】
また、宗我稲目足尼大臣(そがのいなめのすくねのおおおみ)
が女子、支多斯比賣命(きたしひめのみこと)を娶して生み
ませる児は伊波礼池邊宮(いはれいけのへのみや)に天の下
治しめしし橘豊日天皇(たちばなのとよひのすめらみこと/
用明天皇)【聖王の父也】、妹、小治田宮(おはりたのみや)
に天の下治しめしし止余美氣加志支夜比賣天皇(とよみけかし
きやひめのすめらみこと/推古天皇)【聖王の姨母也】。
また、支多斯比賣(きたしひめ)が同母弟、乎阿尼命
(おあねのひめみこ)を娶して生みませる児は倉橋宮
(くらはしのみや)に天の下治しめしし長谷部天皇(はつせべ
のすめらみこと/崇峻天皇)【聖王の伯叔也】、姉、穴太部
間人王(あなほべはしひとのひめみこ)【聖王の母也】。
右の五はしらの天皇は、他(あた)し人を雑(まじ)えること
無く天の下治しめしき【但し倉橋は第四、小治田は第五也】。
小治田宮に宇(あめのした)御(しら)しめしし天皇
(推古天皇)の世に、上宮厩戸豊聰耳命(うえのみやうまやと
のとよとみみのみこと)、嶋大臣(しまのおおおみ)と共に
天の下の政(まつりごこ)を輔(たす)け三寶を興隆し、元興
・天四皇等の寺を起て、爵十二級、大徳・少徳・大仁・少仁
・大礼・少礼・大信・少信・大義・少義・大智・少智を制す。
池邊天皇(用明天皇)が后、穴太部間人王、厩戸に出(いで)
ましし時に、忽ち上宮王を産生(う)みたまいき。
王の命は幼少にして聰敏、智有り。長大なる時に至りて一時
(ひととき)に八人(やたり)の白し言うを聞きて其の理を
辧ず。また、一を聞き八を智る。故に号(なづ)けて厩戸豊聰
八耳命(うまやとのとよとやつみみのみこと)と曰う。
池邊天皇(用明天皇)、其の太子(みこ)聖徳王を甚だ愛しと
念い、宮の南の上の大殿に住まわしめき。故に上宮王
(うえのみやのみこ)と号(もう)す。
上宮王の師は、高麗(こま)の慧慈法師(えじほうし)なり。
王命(みこのみこと)は能く涅槃常住・五種佛性の理を悟り、
法花三車・權實二智の趣を明らかに開き、維摩不思議解脱の
宗に通じ達す。
且つは經部薩婆多両家の辨を知り、また三玄・五經の旨を知り、
並びに天文地理の道を照らす。
即ち法花等の經疏(けいそ)七卷を造りたまい、
号(なづ)けて「上宮御製の疏(そ)」と曰(い)う。
太子の問いたまう義に、師通ぜざる所有り。
太子、夜夢に金人を見る。來たりて解せざる義を敎(さと)す。
太子、寤(さ)めて後、即ち之を解す。乃(すなわ)ち
師に傳え、師また領解す。是の如き事は一・二のみに非ず。
太子、七寺を起す。四天皇寺、法隆寺、中宮寺、橘寺、蜂丘寺
【彼の宮を并せて川勝秦公(かわかつのはたのきみ)に賜う】、
池後寺、葛木寺【葛木臣(かつらぎのおみ)に賜う】。
太子、七寺を起す。四天皇寺、法隆寺、中宮寺、橘寺、蜂丘寺
【彼の宮を并せて川勝秦公(かわかつのはたのきみ)に賜う】、
池後寺、葛木寺【葛木臣(かつらぎのおみ)に賜う】。
獺祭注:【川勝秦公】 日本書紀 推古天皇十一年十一月 に
「皇太子、諸大夫に謂いて曰く『我、尊き仏像有り。
誰かこの像を得て恭拝せん』とのたまう。
時に秦造河勝(はたのみやつこ・かわかつ)進みて曰く、
『臣、拝みまつらん』という。」 とある。
「上宮聖徳法王帝説」(00) - (管理人)
2024/10/19 (Sat) 07:28:06
 (00)
(00)
むかし、「古代史獺祭」というHPがありました。
在宅(引きこもり)で、系図解読をする人間にとっては
貴重な史料の入手先のひとつでした。
残念ですが、いまは、このHPは消滅しています。
「上宮聖徳法王帝説」は、ほぼ丸々保存していました。
「古代史獺祭 列島編 メニュー」
上宮聖徳法王帝説
(じょうぐう しょうとく ほうおう ていせつ)
注:文中の■は原典に文字脱落。不詳。底本は知恩院版。
上宮聖徳法王帝説
平安初期の成立と考えられる聖徳太子の伝記を集成した
一卷より成る書。
皇極・天智朝にさかのぼる資料が使用されているとも見られる。撰者不詳。
*****
PS:
:今、「古代史獺祭」で、検索してみたところ、
┌
│日本文学 Internet Guide>データベース【分野別】>上代文学
│古代史獺祭 史料 大陸編・半島編 / 史料 列島編
│列島編では、古事記、日本書紀、懷風藻、古語拾遺、
│上宮聖徳法王帝説等のテキストを公開。 古事記関係データ
└
:が、出て来ました。クリックしてみると、
:在宅で、利用できそうな史料が、いろいろと出て来ました。
:ただ、「古代史獺祭」は、消滅しています。
:ちなみに、日本書紀と古事記の全文検索には、
:下記を利用しています。
https://www.seisaku.bz/search3/searchn.php
Re: 各種資料(翻訳) - 石見介
2023/06/22 (Thu) 20:54:03
米田喜彦さん
翻訳ソフトの不備で無かったのであれば、今後の同様の資料の翻訳についても、安心して‽読めそうなので、今後も、情報提供をお願いします。
何しろ、アナログ人間なので、折角、外国の有益な論文や論考を投稿されても、貧弱な英語力での読解以外の、他の外国語は、全く理解できません。翻訳ソフトも使用経験はありません。
勿論、国による、或いは民族による、偏見が、どのような論文にも、紛れ込んでいる可能性はあり、これは、翻訳ソフトが正しく機能していても、十分、注意すべきではありますが。
「高句麗」問題については、中国と、韓国や北朝鮮で、自国史に組み入れようとする綱引きがあり、特に、政治的に干渉されている可能性があるので、たっぷり,眉に唾を付けて、読まないと騙されます。
私は、高句麗や扶余族は、ツングース語族系だと考えており、これを先験的に、朝鮮語族とするのは、いわば、半島版皇国史観とでもいうべき、民族主義的な史観ではないか?と疑っています。
いずれにしろ、朝鮮語族の言語の文字化は、所謂、アルタイ語族(現在のトランスユーラシア語族:「大語族」としたほうがよいかも)に属すると見做される、チュルク、モンゴル、ツングース、朝鮮、日琉諸語族中、最も遅れ、その為、文献資料でまとまって言語を扱えるのは、ハングル制定時の中期朝鮮語で、正直、古い時代の朝鮮語など、全く解析などできませんし、語族或いは語派内の言語・方言の分化も少なく、その資料も少ないため、語族内、語派内の言語方言からの、祖語形再構も、殆んど、行われていません。
それで、朝鮮語で萬葉集が読解出来るとか、倭の大王は百済語を話すとか、嘘八百を言うのは、止めてほしいものです。さすがに、最近は、その手の嘘は通用しなくなり、日琉語族の言語が、朝鮮語の基層言語になっている可能性等が、論じられている状況になりましたが。
Re: 各種資料(翻訳) - 米田
2023/06/22 (Thu) 17:29:27
┌
│翻訳ソフトが、中国語と英語、日本語を、経巡るうちに、
│「現代高句麗語」という実在しない幽霊言語を、
│生みだしたように思われます。
└
スミマセンです。私の勘違いによる(私の)ミスでした。
(翻訳ソフトは、間違えていませんでした。)
「現代高句麗語」は、私は、【現代「高句麗語」】として
使っていました。(私の「造語」でした。)
国としての「高句麗」は、668年に滅亡していました。
「高句麗語」を何と間違えたかというと、
『朝鮮族(ちょうせんぞく)』の使う言葉としての「朝鮮語」でした。
*****
『高句麗(こうくり、コグリョ)』
高句麗(紀元前1世紀頃 - 668年)または
高麗(こま、こうらい、コリョ)は現在の大韓民国、朝鮮民主主義
人民共和国北部から満洲の南部にかけての地域に存在した国家
*****
『高麗人(こうらいじん)』(ウィキペディアより)
高麗人(コリョ・サラム)は、ソビエト連邦崩壊後の独立国家
共同体(CIS)諸国の国籍を持つ朝鮮民族。
曖昧さ回避
この項目では、現在の独立国家共同体における朝鮮民族について説明
しています。歴史上の高麗の民族については「高麗」をご覧ください。
*****
『高麗 (こうらい、こま:曖昧さ回避)』(ウィキペディアより)
高麗は、朝鮮半島・満洲に存在した複数の王朝・王国。
また、そこから転じた様々な用法がある。
王朝・国家
高句麗の別称。同時代には「高麗」がもっぱらこの王朝を指した。
渤海の別称。当時の日本では高句麗の再興とみなしたため、
六国史などで「高麗」と記す。
高麗 - 10世紀から14世紀に朝鮮半島に存在した国。←←←←←:※
元来は高句麗の後継国家を称して「高麗」を国号とした。
便宜上、李氏朝鮮または朝鮮半島そのものを高麗と呼ぶ場合がある
(高麗茶碗など)。厳密には誤り。
*****
『朝鮮民族(ちょうせんみんぞく)』(ウィキペディアより)
朝鮮民族は、朝鮮語をそのアイデンティティー・母語とする民族。
大韓民国における自称は韓民族。
この項目では、朝鮮民族全般について説明しています。
中国国籍の朝鮮系少数民族については「朝鮮族」をご覧ください。
*****
『朝鮮族(ちょうせんぞく)』(ウィキペディアより)
朝鮮族は、中華人民共和国(以下、中国)の民族識別工作にて
定義される中国の少数民族の一つ。
この項目では、中華人民共和国の少数民族としての「朝鮮族」について
説明しています。民族全般については「朝鮮民族」をご覧ください。
****************************
668年に滅亡した「高句麗」の言葉(読み方)が、21世紀の現代でも
分かるという事に、(あらためて)驚かされます。
私の勘違い(ミス)で、失礼しました。
Re: 各種資料(翻訳) - 石見介
2023/06/21 (Wed) 22:36:52
米田喜彦さん
お答え有難うございます。
ところで
〈「現代高句麗語」と「古代扶余語」の読み〉
という文章も、おそらく、「現代韓国語」あるいは「現代朝鮮語」即ち,modern Koreanに相当する中国の言葉(現代高麗語とか)が、まわりまわって、「現代高句麗語」と翻訳されたように思われます。
「高麗」という語は、「高句麗」の別称でもあり、三国時代の高句麗の後裔を称した、王氏高麗が、モンゴル帝国の属国となって、西方に伝わって,[Korea」のような半島国家・地域を表わす語彙になりました。
翻訳ソフトが、中国語と英語、日本語を、経巡るうちに、「現代高句麗語」という実在しない幽霊言語を、生みだしたように思われます。
Re: 各種資料(翻訳) - 米田
2023/06/21 (Wed) 14:11:23
 *****************
*****************
Re: 各種資料(翻訳) - 石見介
2023/06/20 (Tue) 23:24:01
FBの方は、全く開けず、前に読んだ
覚えのある「濊貊」しか、見れませんでした。
しかし、翻訳ソフトの不備なのか、当方の知識不足なのか、
一つ理解できなかったのは、扶余語の「山」を意味する語彙に、
「ヤプマ」なる言葉がある、という件でした。
私の知る限り、扶余語の語彙に、そのような単語を、文献的に、
見た記憶が、一切ありません。
どの文献の何処の記述なのか、出所が不明だと、信頼性は、ありません。
抑々、扶余語なるものが、どこかにまとめて、収載されている、と言う
事の記憶がありませんので、或いは、史書で扶余系とされる、
高句麗、濊、扶余関連の語彙を、まとめて、「扶余語」と称している
のかも知れませんが、その場合は、既に、言語学的ないくつかの問題点
を、無視したのか、どうクリアしたのかが、検証されるべきです。
*************************
中国のサイトの文章は、リンクが強すぎて、なかなか
思ったように、表示が出来なくて、てこずっています。
画面のコピーを眺める限りでは、
現代「高句麗語」と、古代「夫余語」の読みを同じように
扱っているような印象を受けます。
「検証」云々については、その通りだと思います。
(私の手には負えませんが、頭の片隅に入れておきます。)
Re: 各種資料(翻訳) - 石見介
2023/06/20 (Tue) 23:24:01
米田喜彦さん
翻訳有難うございました。
FBの方は、全く開けず,、前に読んだ覚えのある「濊貊」しか、見れませんでした。
しかし、翻訳ソフトの不備なのか、当方の知識不足なのか、一つ理解できなかったのは、扶余語の「山」を意味する語彙に、「ヤプマ」なる言葉がある、という件でした。
私の知る限り、扶余語の語彙に、そのような単語を、文献的に、見た記憶が、一切ありません。
どの文献の何処の記述なのか、出所が不明だと、信頼性は、ありません。
抑々、扶余語なるものが、どこかにまとめて、収載されている、と言う事の記憶がありませんので、或いは、史書で扶余系とされる、高句麗、濊、扶余関連の語彙を、まとめて、「扶余語」と称しているのかも知れませんが、その場合は、既に、言語学的ないくつかの問題点を、無視したのか、どうクリアしたのかが、検証されるべきです。
中国の言語学専門家のはry源ではなく、古代史マニアのような方の意見のようにも、思われます。
今、私が確実な扶余語だと認識しているのは、他ならぬ、種族名、「扶余」と「貊」の2語ですが、どちらも、ツングース語族で、「鹿」を意味する語彙だと思われます。扶余bhyoも貊bokも、同源と考えられる語彙群が、広くツングース語族の諸言語に存在します。buyoとbokmp、本体は、同源の語彙だろうと思われます。gとyの子音交代は、かなり頻繁におころ得ます。中国語では、清音と濁音の弁別が基本的にないので、bokとbogは、通音と考えて良いと思われます。後者のbogは、満州のエヴェンキ族で、「鹿」を意味する語彙として、載っています(『エヴェンキ語への招待』)。
余談ですが、貊は、「百」(百済の百)、「狛」(上代日本語の高句麗を指す語彙「こま」に宛てられる漢字)、「狢」とも音通で、「狢」は「洛」「鹿」とも音通ではないか?と考えています。
しかし、日本語のdearを意味する語彙「か」(「しか」は本來、牡鹿の語義)とは、相関がみられません。
Re: 各種資料(翻訳) - 米田
2023/06/18 (Sun) 22:49:04
 (翻訳資料ではありませんが、
(翻訳資料ではありませんが、
_何か、見えてこないだろうか・・・。)
┌
│難波秀弘 (FB)2時間
│(2023-06-16金曜日 21:31)·初歩的な質問です。
│『日本書紀』欽明紀と敏達紀を、読み直していたのですが、
│中に「みやけ(屯倉)」の記事が出ていて、その性格が、
│どのようなものなのか、どうも理解できません。
│大王家或いは、大王の直轄領と言うのであれば、
│盛んに出て来る朝鮮半島の屯倉を、どう解釈すべきか?
└
┌
│滑安房守(FB)2時間(2023-06-17 土曜日 10:48)
│難波秀弘 さん
│初歩的な質問ではない様に思えます。
│安房守の思っている事を述べさせて戴きます。
│安房守は単純に列島内の屯倉と同じと捉えていました。
│その実態は、どうだったかと言うと、判りませんでした。
└
┌
│岡嶋 隆司(FB)3時間(2023-06-17 土曜日 13:20)
│吉備には、児島の屯倉と白猪の屯倉が置かれたと記載され、
│蘇我氏が乗り込んできています。一般的にヤマト政権による
│地方を抑える拠点的なものと考えられていますね。
└
┌
│<6月の講演会のご案内> 『装飾古墳の謎に迫る』
│■講師の言葉
│発表では6世紀に勃発した「磐井の乱」と
│壁画系装飾古墳の登場の関係についての通説を再検討し、東日本と
│九州の装飾古墳に描かれた図文の類似点と相違点を比較します。
└
┌
│〇「安閑紀」:桜井田部連、県犬養連、難波吉士らに屯倉の税を云々。
│〇「宣化紀」:536年、物部麁鹿火大連が薨じた。
│〇「宣化紀」:(大伴)磐は、筑紫に留まって、その国を執し、云々。
│〇『火君』_:(日本書紀・欽明天皇紀17年・556年)
│:春正月、百済の世子恵が、帰国を請うた。(云々)
│:阿倍臣、佐伯連、播磨直を遣わして、筑紫の国の水軍をひきい云々。
│:別に筑紫の火君(筑紫君の子、火中君の弟。)を遣わし、(云々)。
└
Re: 各種資料(翻訳) - 米田
2023/06/18 (Sun) 16:13:52
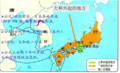 (FBからの転載)
(FBからの転載)
滑安房守 · 13時間 (2023-06-17 土曜日 23:48) ·
知乎と言う、中国のサイトの中に、邪馬台国について
中国人が述べている興味ある内容を見出しました
ので、ご紹介します。
作者:在貴州
_接:https://www.zhihu.com/question/26746625/answer/308215629
来源:知乎
著作権は著作者に帰属します。
商業的複製の場合は作者に連絡して許可を得、
非商業的複製の場合は出典を明記してください。
*****(翻訳)
大和は漢字導入前の日本国の自己呼称なのか、
これの1つに過ぎないのか。
ワワはどこから来たのですか、ヤマダイは自称ですか?
「日本の地名と人名は固有の名詞であり、漢字はYixunまたは
音声訓練のいずれかによって書かれることがよくあります。たとえば、
「大和」は大和と発音され、「彼」は「倭」で発音され、その前に
美しい名前「ダイ」が続き、イークスンである「ヤマト」を構成します。
「邪馬隊」は「ヤマダイ」と発音され、健全な訓練です。
「日本の地名と人名は固有の名詞であり、漢字はしばしば宜順または
音声訓練から取られます。たとえば、「大和」は大和と発音され、
「彼」は「倭」と発音され、その前には美しい名前「大」が付けられ、
「大和」を構成します。(すべて表示)
222人が「同意しました」と回答しました。
「ヤマ」は「山」を意味する扶余の「ヤプマ」にまでさかのぼることが
でき、「山」は言語学の中核的な言葉であり、扶余の「ヤプマ」は漢字
音声学では「邪馬」と発音することができます。
三国志記の魏書では、魏国家の正式名称は訪問者です倭女王国
国の名前、アマダイは、西暦3世紀の日本の「大和」政権
(日本の前身)の名前の正確な中国語の音訳です。
扶余語が日本語に進化する過程で」作り最初の音節の母音は徐々に
後方に移動し、「山」は漢字で「ヤマ」と発音でき、「ヤマ」は
日本語で「山」を意味し、前向きな芸術的概念を持ち、威厳を意味
することができ、日本の武士の名前で頻繁に使用されます。
たとえば、第二次世界大戦中に東南アジアの中国人の富を大規模に
略奪した日本の将軍山下鳳文 真珠湾攻撃を計画した日本の将軍、
山下智之山本五十六(山本五十六)。
「に」は「XX人」を意味することができます。大和もともとは
「大和」を意味し、大和は今日の日本語の「大和」の発音であり、
大和は三国志に由来します魏州東義の伝記ワの女王の国の名前、
和人寺院の名前、邪悪な馬泰。
したがって、「大和」は、漢字が導入される前の初期の大和の
人々によって国に付けられた名前であると考えられています。
日本人は飛鳥時代後期にのみ漢字を導入し、栄也台の王国の書かれた
漢字は「大和」という文字を採用しました。
「大きい」という言葉は理解しやすく、多くの民族グループは、
「イギリス」、「大韓民国」などの偉大さを誇示して、名前や国に
「大きい」という芸術的概念を追加することを好みます。
「大和」の国名の漢字がなぜ「へ」という文字で書かれているのか、
また「へ」と「ワ」の間に語源的なつながりがあるのか、主に史料が
不足しているため、まだ多くの議論があります。
要するに、「大和」という文章は飛鳥時代(曹魏から300年以上後)
にしか利用できず、歴史家は便宜上、
以前の大和政権を「大和王国」と呼んでいます。
扶余語が古日本語に進化した初期の段階では二重母音はなく、
今日の琉球語には二重母音がないので、「邪悪な馬タイカントリー
"タイ"(タイまたはお願いだから、二重母音)は必ずしも正確ではなく、
「to」である場合もあれば、「tai」と「to」の間で発音される場合も
あります。 「ヤマダイ」や「ヤマタイ」の発音ではないでしょう。
「悪馬泰王国」の本来の意味が「山」である理由と、「山」の意味が
国や王朝の名前として使われている理由については、著者の個人的な
意見は、これは西暦1~3世紀に「ヤマト王国」が位置していた
地域の地形学的特徴に直接関係しているというものです。
下の日本地図の緑色の部分は、ヤマト王国政権が興隆し、
成長した地域を示しています。
(:投稿図)
ヤマトの力の発祥の地は現在の日本の奈良県にあり、北は山々に
囲まれた奈良盆地を除いて、国の残りの部分は特に南の高山でした。
紀伊山地 地形学的特徴は雄大であり、いくつかのピークは
海抜1300メートルを超えています。以下は、
Google衛星地図の奈良県で、奈良県南部の緯度と経度の座標は
3733,1200フィート(<>,<>メートル以上)の高度を示しています。
作者:在貴州
来源:知乎
著作権は著作者に帰属します。
商業的複製の場合は作者に連絡して許可を得、
非商業的複製の場合は出典を明記してください。
(:グ―グルマップの図は省略)
グーグルマップで奈良県とその周辺でマウスをスライドさせると、
標高の変化は基本的に非常に大きく、約1000フィート~3800フィートは
急激に変動し、つまり、奈良県とその周辺地域は多くの山の地形である
だけでなく、峰は急で雄大であり、傾斜は大きく、谷と山は対照的です。
農業に従事していた大和の祖先は奈良盆地(現在の大阪の東)に住んで
おり、周囲の山々などの壮大な特徴を見ると、古代人は山頂の威厳を
感じ、「山」を崇拝することが容易でした。
さらに、「山」の芸術的概念は、ほとんどの民族グループの古代文化に
おいて前向きで雄大で賞賛されており、今日まで、山に住む多くの
人々は今でも山を神として崇拝しています。
したがって、西暦2世紀頃の奈良地域への移住の過程で、大和王国の
祖先は国の名前として「山」(扶余のヤプマ)に加えて、接尾辞の
接尾辞、つまりヤプマトを使用する可能性が非常に高いです、
西暦239年から248年の間に、三国時代の大和の女王と魏国の領主は
互いに使節を送り、当時の漢民族は日本の国の名前を与えました。」
ヤプマト「邪悪な馬のテラス」と音訳されます。
日本体制の形成については、日本列島を統一した「大和王国」が
存在したのは当初ではなく、紀元前3世紀から数百年間、
O2b一倍体の扶余族は朝鮮半島を踏み台として日本列島に入り、
地元のD2一倍体の先住民縄文部族同盟(古代日本のテキストは
一般に先住民縄文人を蝦夷と呼び、将軍の正名は聖義大称)を征服し、
縄文人の土地を占領し、 大小の複数のビルド扶余政権,現在の遺跡で
は、日本は紀元前3世紀~西暦2世紀に成立したとされています。
弥生人居住地は西日本全域に分布しており、九州地方、四国本島、
中国地方(中国ではなく、日本の西の本州地域を指す)。
これらの大小の扶余政権は互いに併合し(併合の正確なプロセスは
もはや不明です)、そして最終的に地域ヤマト政権統一
(すなわち後のヤマト王国)は統一を完了し、日本の原型である
ヤマト王国を形成し、ヤマト王国の王族は自然と日本の空となった。
ローヤル部族。 「大和」または「大和」というタイトルは、
後に日本の主要な民族グループ全体の名前になりました。
(戦国時代と同じように、秦国が他の6か国を統一した後、
中国はかつて「秦」と呼ばれ、中国人はかつて「秦人」と呼ばれて
いましたが、その後、中国は頻繁に王朝を変え、中国人は秦人と
呼ばれ、1つは漢と呼ばれ、1つは唐人と呼ばれます...)
ただし、日本は全世代の血統により王朝を変えず、「大和」または
「大和」の称号が続いている)扶余族による統一政府成立後も、
日本列島北東部の縄文先住民族を征服する過程は止まらず、
徳川幕府が北海道地方に管轄権を置いたのは17世紀になってからで、
日本の先住民縄文人に対する扶余族の政権は約1800年間続き、現在に
至るまで、北海道には扶余族、すなわち縄文人の生きた化石として
知られるアイヌ民族に統合・同化されていない縄文人がまだ少数いる。
このプロセスはイギリスの形成過程にいくぶん似ており、西暦4世紀
には、アングロ、サクソン、ジュート、その他のゲルマン部族が
ユトランド半島から、低地のドイツが海を渡ってイギリス諸島に向かい、
イギリス島のケルト人原住民を征服し、大小のゲルマン政権を確立し、
最終的に9つの大きなゲルマン王国に併合され(17つの王国の時代)、
西暦<>世紀には、イギリス諸島のゲルマン地域-イングランドは
サクソン王国によって分割されました ウェセックスは統一を完了します。 イングランドという言葉自体は、アングロの土地、
つまりアングランドを意味します。
イギリス諸島の先住民ケルト人はドイツ人によって征服され統合された
わけではなく、イギリス諸島の北部であるスコットランド地域は
<>世紀までケルト人の手に残り、アングロサクソン人の侵略に
抵抗し、ケルト人のこの部分はスコットランド人と呼ばれていました。
映画「ブレイブハート」は、スコットランドの国民的英雄が
イギリスと戦う様子を示しています。
作者:在貴州
来源:知乎
著作権は著作者に帰属します。
商業的複製の場合は作者に連絡して許可を得、
非商業的複製の場合は出典を明記してください。
イギリスの父方の祖先のほとんどはアングロサクソン人などの
ゲルマン人ですが、今日の英語とドイツ語の違いはすでに明らかであり、
ドイツ語を学ぶのに1年かかることがあり、英語には古低地ドイツ語や
後のヴィルヘルム征服によってもたらされたフランス語に基づいて
ケルト語の形成習慣が多数組み込まれています。
同様に、縄文民族を征服する過程で、扶余族の言語は必然的に縄文人の
オーストロネシア人的特徴に統合され、その後の漢字や慣用句が
日本語に導入され、古代日本語は現代日本語とは大きく異なり、
進化過程の研究は多くの情報ギャップに遭遇しました。
「wa」という文の起源については多くの説明があり、決定的な結論は
ありません。 「和」と「邪悪マタイ」の間には語源的なつながりは
見られず、「和」は、日本列島の政権が漢の光武帝に会うために使節を
派遣したときに漢王朝によって与えられた名前に由来しています
(西暦200年)。
「倭」の文字は古代中国語で「短い」という言葉であると信じている人
もいます(当時漢王朝に使節を派遣した日本の政権は、先住民の
縄文政権、つまり蝦夷政権であった可能性があり、D2倍体縄文人は
通常身長が低かった)。扶余文明に同化されなかった日本の最後の
先住民はアイヌの人々であり、アイヌの古い世代はまだ独立した文化と
血統を維持しています、下の写真は年配のアイヌの男性を示しています:
作者:在貴州
来源:知乎
著作権は著作者に帰属します。
商業的複製の場合は作者に連絡して許可を得、
非商業的複製の場合は出典を明記してください。
下の写真は、初期のアイヌの女性の白黒写真です
(大和民族の混合と混ざってはいけません)。
このタイプの日本人先住民はD倍体に属し、少数はアンダマン人などの
一部のオーストロネシア人と相同であるC倍数体に属します。
D一倍体とC一倍体は、主に茶色の人々に分類されます
(実際、人種の肌の色を分割する現代の方法は非常に非科学的ですが、
大多数の人々によって使用されており、今日の短い黒人の子孫は
必ずしも暗いわけではなく、それらのほとんどは茶色の肌であり、
北日本のアイヌの人々のように、皮膚は非常に白く、これは高山地域の
茶色の人々の進化の結果です)、短い黒人の声明に反対する人も多く、
彼らを古いアジア人と呼ぶ方が適切かもしれません。
日本の先住民族である縄文人は、栄養不足で育つと一般的に身長が
低くなります。少なくとも古代中国人はそれらを低身長と表現しました。
また、「倭」と「委員会」の文字はどちらも任命を意味し、おそらく
漢の光武帝によって与えられたサブシールの名前であると言う人も
いますが、著者はこの推測に同意しません。
「倭」という文字は、これらの日本の使節が自国を呼ぶための当時の
漢の発音の音訳であった可能性もあります。
要するに、北で初めて「倭国」と呼ばれ、200年後の女王の
「邪悪マタイ」と呼ばれるこの政権は政権であってはなりません。
徳川幕府時代に、漢の光武天皇から王に与えられた金印が日本の福岡で
発掘され、次の写真は福岡で発掘された「漢魏の王」の金印です。
ワヌの黄金印の発祥の地である福岡は、日本の九州の西端に位置し、
「大和王国」が台頭した奈良地方(約600キロメートル)から遠く離れて
おり、漢の光武帝と魏の明帝への<>組の日本の使節団は<>つの
政権から来たものではないという判断をさらに裏付けています。
多くの学者は、「倭」という文字は、漢民族が漢光武帝の間に初めて
日本人に会うために使用した軽蔑的な名前であり、最初の意味は
肯定的な言葉ではなく、後に「倭」という名前は漢人によって
使用され続けたと信じています。
飛鳥時代に、日本人は漢字「和」(日本語では「和」と発音され、
日本語の倭字の発音は古代中国の日本語「倭」の発音と同じです)に
切り替えました。ヤマト民族の形成、O2B種族、D種族については、
以下の記事をご参照ください。日本人は中国人が黒人より劣っていると
感じているというのは本当ですか?
これは国民全体の意見ですか、それとも地元の人の意見ですか?
4218 はい · 801 レビュー答える
日本は「現代の封建社会」であるという声明をどのように評価する
のですか?
3904 はい · 493 レビュー答える
「ディ・レンジエの神都竜王」は、東島国の人々による唐王朝の
破壊の背景をデザインしました。
851 はい · 114 レビュー答える
なぜ古代の日本の女性は美しさのために歯を黒く染めたのですか?
515 はい · 147 レビュー答える
下の写真は、初期のアイヌの女性の白黒写真です
(大和民族の混合と混ざってはいけません)。
このタイプの日本人先住民はD倍体に属し、少数はアンダマン人などの
一部のオーストロネシア人と相同であるC倍数体に属します。
D一倍体とC一倍体は、主に茶色の人々に分類されます
(実際、人種の肌の色を分割する現代の方法は非常に非科学的ですが、
大多数の人々によって使用されており、今日の短い黒人の子孫は
必ずしも暗いわけではなく、それらのほとんどは茶色の肌であり、
北日本のアイヌの人々のように、皮膚は非常に白く、これは高山地域の
茶色の人々の進化の結果です)、短い黒人の声明に反対する人も多く、
彼らを古いアジア人と呼ぶ方が適切かもしれません。
日本の先住民族である縄文人は、
栄養不足で育つと一般的に身長が低くなります。
少なくとも古代中国人はそれらを低身長と表現しました。
また、「倭」と「委員会」の文字はどちらも任命を意味し、
おそらく漢の光武帝によって与えられたサブシールの名前であると
言う人もいますが、著者はこの推測に同意しません。
「倭」という文字は、これらの日本の使節が自国を呼ぶための
当時の漢の発音の音訳であった可能性もあります。
要するに、北で初めて「倭国」と呼ばれ、200年後の女王の
「邪悪マタイ」と呼ばれるこの政権は政権であってはなりません。
徳川幕府時代に、漢の光武天皇から王に与えられた金印が日本の福岡で
発掘され、次の写真は福岡で発掘された「漢魏の王」の金印です。
ワヌの黄金印の発祥の地である福岡は、日本の九州の西端に位置し、
「大和王国」が台頭した奈良地方(約600キロメートル)から遠く
離れており、漢の光武帝と魏の明帝への<>組の日本の使節団は<>つ
の政権から来たものではないという判断をさらに裏付けています。
多くの学者は、「倭」という文字は、漢民族が漢光武帝の間に初めて
日本人に会うために使用した軽蔑的な名前であり、最初の意味は肯定的
な言葉ではなく、後に「倭」という名前は漢人によって使用され続けた
と信じています。 飛鳥時代に、
日本人は漢字「和」(日本語では「和」と発音され、日本語の倭字の
発音は古代中国の日本語「倭」の発音と同じです)に切り替えました。
ヤマト民族の形成、O2B種族、D種族については、以下の記事を
ご参照ください。
作者:在貴州
_接:https://www.zhihu.com/question/26746625/answer/308215629
来源:知乎
著作権は著作者に帰属します。
商業的複製の場合は作者に連絡して許可を得、
非商業的複製の場合は出典を明記してください。
日本人は中国人が黒人より劣っていると感じているというのは
本当ですか?
これは国民全体の意見ですか、それとも地元の人の意見ですか?
4218 はい · 801 レビュー答える
日本は「現代の封建社会」であるという声明をどのように
評価するのですか?
3904 はい · 493 レビュー答える
「ディ・レンジエの神都竜王」は、東島国の人々による唐王朝の
破壊の背景をデザインしました。
851 はい · 114 レビュー答える
なぜ古代の日本の女性は美しさのために歯を黒く染めたのですか?
515 はい · 147 レビュー答える
Re: 各種資料(翻訳) - 米田
2023/06/18 (Sun) 15:19:06
『後期旧石器時代』(ウィキペディアより)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
後期旧石器時代(Upper PaleolithicまたはUpper Palaeolithic、
Late Stone Age)は旧石器時代の3番目で最後の区分である。
概して概ね現代的行動の出現に合致し農業の出現以前の
(完新世の始まりである)5万年前から1万年前に遡る。
4万年前-3万年前(そのうち:4万年前–3万5000年前)
・上スワン川の考古学的発見で明らかなように
オーストラリアパースで最初の人類居住
・この時期オーストラリアメルボルンは狩猟採集民に占領されていた。
・シュヴァーベンジュラ山脈早期文化中心、最初期の造形芸術
(ホーレ・フェルスのヴィーナス)、オーリニャック文化の始まり
・最初の笛(英語版)がドイツで現れる。
・ホーレンシュタインシュターデルから作られたライオンマン。
現在ドイツウルムのウルマー美術館にある。
・人類が到着する頃にオーストラリアの大型脊椎動物や大型動物群
(英語版)の殆どが絶滅した。
・世界で発見された最古の芸術例である洞窟壁画の例は、
約4万年前に遡る(ネルハ洞窟(英語版)参照)。
・科学者は壁画はホモ・サピエンスよりもネアンデルタール人により
作られた可能性があると推論している。(BBC) (科学)
・馬やサイ、原牛のいる壁画は、フランスアルデシュ峡谷ヴァロン=ポン
=ダルクショーヴェ洞窟で作られている。1994年12月に発見された。
・考古学的研究は3万5000年前から3万9000年前に(現在は香港国際空港
になっている)赤鱲角地域に人類がいたことを支持している。
・アゼルバイジャンのダムジリヤタゲリザル洞窟とタグラル洞窟
・日本で人類居住の最初の証拠[18]
*****
[18]^ Prehistoric Archaeological Periods in Japan, Charles T. Keally
ホーム |インデックス 日本考古学最終 改訂:2002年10月14日
先史時代の考古学時代(日本では) チャールズ・T・キーリー
先史時代の日本は、旧石器時代、縄文、弥生、古墳の4つの主要な
文化に分かれています。これらの主要な文化または期間のそれぞれは、
さらにいくつかのサブ期間(または期間)に細分されます。
文化的段階はほぼ無限です。これらの期間の日付は、
他の年代測定方法に基づく旧石器時代の始まりを除いて、
現在より前の未較正の放射性炭素年で示されています。
日本考古学における先史時代
旧石器時代 50 / 35,000-13 / 9,500年前
縄文(時代) 13/9,500-2,500年前
弥生(時代) 紀元前500年-西暦300年
古墳(時代) 西暦300年-西暦710年
日本の旧石器時代は、一般的に大物ハンターが支配していると
考えられている時期ですが、これらの人々がどのように住んでいたか
についての直接的な証拠はほとんどありません。
日本には、約35,000年前から13,000〜10,000年前の陶器技術の
出現までの後期旧石器時代があることに誰もが同意します。
35,000年前以前の日本の人間の証拠はかなり物議を醸しています。
1997年12月28日、私はここに
「支持者は日本で最も古い遺跡について60万年までの年齢を主張する」と
書いた。しかし、日本の旧石器時代前期と中期旧石器時代の主張は、
2000年11月5日日曜日、毎日新聞が藤村新一が上高森遺跡に遺物を
植えているのを捕まえたと明らかにしたときに崩壊しました。
スキャンダルに関する論文を別のページに投稿しています。
いくつかの遺跡の発掘と藤村に関連する多くの遺跡からの遺物の
再調査にほぼ2年を費やした後、日本考古学協会は、藤村の資料は
どれも研究目的に使用できないと結論付けました。これは
186のサイトからの材料に影響を与え、そのうち33は発掘されました。
デマの暴露以来、40,000〜50,000年前のいくつかのサイトが
提唱されており、「初期旧石器時代」のサイトに関する以前の主張は、
一部の考古学者によって再び検討されています。しかし、
35,000年以上前のサイトの主張はまだ広く受け入れられていません。
JOMONは、動的に適応した狩猟、漁業、採集の人々であり、
地域的および時間的に大きな変化を示しました。
縄文地方の一部の人々は、特に東日本の豊かな温帯林で、
高いレベルの物質的および社会的文化を獲得しました。
沿岸地域、特に東京湾周辺では、縄文人は海産軟体動物やその他の
海洋資源を集中的に使用していました。縄文人が植物の世話をし、
一部はおそらく家畜化され、資源のほとんどを巧みに最小限に管理して
いたという証拠が増えています。しかし、農業と家畜化が彼らの食事に
おいて重要であったという証拠はありません。一部の研究者に縄文人が
ある程度の養殖を持っていたことを示唆する証拠もあります。
海棲哺乳類は縄文人の食生活に多く含まれており、縄文中期末には海棲
哺乳類の狩猟を重視する人々が生息していた場所もあったと思われます。
西日本の縄文の後半までに、稲作は採餌生活様式に取って代わり始め
ました。九州の縄文遺跡の中には、縄文文化の他の特徴をほとんど残し
ながら、これらの人々がすでに水田を持っていたことが示されています。
しかし、紀元前最後の千年紀の半ばまでに、文化は非常に変化し、
大陸の影響が非常に明白になったため、
考古学者はそれを弥生文化として認識しています。
弥生は農民の文化として始まりました。この生活様式は東に広がり、
最終的には本州の本島の北部に達しました。
それは北海道の最北端の島に到達することはありませんでした。
何世紀にもわたって、ますます多くの大陸のアイデア、オブジェクト、
テクノロジーが島に到着しました。社会エリートが発展し、
対立が激化し、戦争がますます頻繁に発生しました。
西暦3世紀の中国の記録は、おそらくヤマタイコクの姫子女王の下で
国、または少なくとも国の西部の多くを統一することにつながった
戦争について語っています。歴史的現実がどうであれ、
弥生は確かに諸公国またはさらに複雑な政治構造の文化になっていた。
弥生は、鍵穴型の墳墓(弥生時代後期またはそれ以前からすでに
存在していた墳墓)の最初の出現によって識別される、
KOFUN文化に直接侵入することなく進化しました。
これらの墓は4世紀後半から5世紀にかけて巨大なサイズに達しました。
他の多くの変化は、西暦400年頃にかなり突然起こったようです
-村人の竪穴住居に粘土オーブンが出現し、韓国タイプの陶器(石器)、
およびその他の大陸の輸入品。これが江上氏のHORSE-RIDER理論の
基礎である。古墳時代中期までに日本が国民国家であったことは
間違いありません。
しかし、地域センターはまだかなりの独立性と権力を持っていたようで
あり、北東部はまだ征服されておらず、日本で歴史が夜明けしたように
中央管理下に置かれていませんでした。
北海道の北の島の先史時代の文化の順序は多少異なります。
後期旧石器時代はそこで最も古い発見物のようであり、これらの発見は
2万年より少し古い範囲ですが、3万年前の旧石器時代後期の発見の
主張があります。
後の発見はシベリアとロシア極東と密接に関連しています。
北海道の縄文文化は、さらに南の縄文文化とかなり平行しています。
しかし、弥生農民がさらに南に定住していたとき、エピ縄文として
知られる縄文から採餌者は北海道を占領しました。この文化に続いて、
内陸部には狩猟、漁業、採集、農業に依存したサツモン文化が、
オホーツク沿岸では、海の哺乳類の狩猟と海洋志向の人々である
サハリンのオホーツク文化が続きました。
これらの後者の2つの文化は、先史時代(原史)古墳時代と
南の史時代奈良および平安時代の両方と時間的に平行しています。
沖縄は日本で唯一の旧石器時代の骨格を産出していますが、
この南の島列では旧石器時代の遺物はよく特定されていません。
考古学的記録、そしておそらく島の占領には、約6,500年前に
縄文のような文化が現れるまでのギャップがあるようです。
日本本土の縄文、そして後に弥生との類似性にもかかわらず、
考古学者は現在、沖縄の文化を貝塚文化と呼ばれる別のスキームの下で
扱っています。
これは、小さな熱帯の島々に住むために必要な非常に異なるタイプの
適応と、沖縄の先史時代の文化と縄文人および弥生との関係が
それほど強くないように見えるという事実の両方を反映しています。
最古、初期、中期の貝塚文化は、本島の初期から最新の縄文と
現代的です。中期貝塚文化の終焉と後期貝塚文化の初期・中期は、
本島弥生時代とほぼ同時代である。