東アジア討論室
混み入った議論と一対一の論争は討論室で行いましょう。
投稿の大項目はスレッドで投稿してください。
そのスレッドに対するはレスとして投稿してください。
レスに対する意見もレスとして投稿してください。
スレッド作成での留意事項
●(新規作成の)スレッドには、タイトル(内容の紹介)と自分の名前を入れて下さい。
●みんなの関心事項については、「会」として、スレを(追加で)設けることもあります。
要望事項
●「返信・引用」を使う場合は、不要なところは削除したうえで、お使いください。(1回のみ)
●「返信・引用」は、多用すると、返信の返信となると、誰の発言か分かりにくいので、控えて下さい。
●また、文章では、適当なところで、右側に「改行マーク」を入れて下さい。(一行、45文字程度)
●また、一文(~。)の長さは、長くて3行まで、(およそ、150文字以内:推奨100文字以内)にして下さい。
●文章は、残ることを念頭に、マナーに気を付けて、楽しく(議論は熱く)投稿しましょう。
2024/07/07 (Sun) 15:02:56
纏向がどのように誕生したかを考察してみます。誤解しているかもしれませんが、寺澤薫氏(1)や石野博信氏(2)などは、その登場を日本列島の画期として、北部九州や吉備の主導によるものとしているように思います。本会の会長も(3)、詳細は分かりませんがどちらかと言えば、北部九州や瀬戸内方面からの影響を重視しておられるように思います。
一方先日講演いただいた、福永伸哉氏は見る銅鐸時代の、唐子・鍵などの奈良盆地勢力の主体的な働きがあったと考えられているようです。藤田三郎氏(4)は纏向開始後の唐子・鍵に関しての発言の中で、纏向開始時期の弥生Ⅵ-4様式時代に、環濠は埋められ集落は縮小したものの継続し、布留期に入って再び環濠が掘られ、集落も拡大するとして、単純に旧勢力が新勢力によって駆逐されたとは考えられないとの見解を示されていると思います。纏向開設に関しては、外来勢力の関与がどのようなものであるかに関して、いまだ意見が一致していないのではないでしょうか。明らかに吉備や北部九州との関係があるものの、本当に有力勢力の東遷などあったのでしょうか。
纏向の開始について、有力勢力の合議により、列島の中心地として選ばれたという考え方があります。その場合なぜそれが纏向なのかが問われることになります。日本列島の地理を俯瞰的に見ると、中部日本以東には高い中央山地があり、日本海側と太平洋側を隔てています。西日本地域には瀬戸内という内海があり、山地もさほど急峻ではなく、地勢的に東日本と好対照をなしています。古代主な物流が水運によっていたことを考えると、東日本は日本海と太平洋を隔てる障害となっていたと見ることもできると思います。一方近畿地方は、その山岳的東日本と海洋的西日本の間にあり、かつ若狭湾・大阪湾・伊勢湾という、日本海と太平洋を繋ぐ海の入り込みがあり、かつ淀川水系や木曽長良川水系、琵琶湖などの水運に恵まれ、日本列島規模の交易の中心となる条件を備えています。文化的にも東日本と西日本の間にあり、本質的にこのような場所には、交易拠点が発達しやすいと思われます。しかし日本海側との交易が重要とみた場合、交易の中心は近江になるのが自然であると思われます。
ここで一つの仮説として、纏向は本来列島規模の交易拠点として選ばれたのではなく、別の理由で選定された交易拠点だったのではないかとしてみます。その場合問題は以下の二点となります。
1.纏向開設の本来の目的は何か
2.なぜ纏向は日本列島規模の交易拠点となったのか
まず一番目の問題ですが、纏向は奈良盆地から東海に向かうルートの一つです。他にも天理方面や、南の紀の川流域から抜ける方法などありますが、奈良盆地でも最大の拠点集落である、唐子・鍵と同じ水系に属して距離も近いことは重要な点であると思われます。したがってこの仮説に従って、纏向成立の目的を考えるならば、纏向開設前の唐子・鍵の状況を考える必要があります。
藤田三郎氏(5)によると、唐古・鍵遺への土器の流入は、弥生後期の(大和第Ⅴ様式)を最後に、後期前半(大和第Ⅵ-1・2様式)では見られなくなり、後期後半(大和第Ⅵ-3様式)では近江から伊勢湾岸地域の東海系の土器が多くみられるということです。それに続く大和第Ⅵ-4様式は一部庄内式に重なる時期で、纏向の開設時期となります。つまり纏向開始直前の唐古・鍵遺の状況は、近江や伊勢湾岸との交流が開始された時期であり、これにより伊勢湾岸へ向かうルートの発端に当たる、奈良盆地東南部の重要性が増していったと考えられます。
藤田三郎(6)および金原正明氏、西村奏氏の論文(7)によると、大和第Ⅵ-3様式の後半で、奈良盆地東南部の砂礫によるとする土器が、唐古・鍵遺に流入するとされ、これが正しければ纏向開設以前に、唐古・鍵遺と纏向地域の交流が始まったということになります。すなわち奈良盆地の有力勢力が、伊勢湾岸方面との交流拠点として、その立地がまず選ばれた可能性があるということです。
次に二番目の問題ですが、纏向は開設から早々に瀬戸内系の土器は入ってくるものの、やはり東海系の土器が主流であり続けるのは、本来の目的が東海との交易であったためと思われます。しかし纏向と言う新しい祭祀の場所には、最初から瀬戸内と東海という大きな文化圏をまたぐ交易拠点としての性格があり、その存在自体が新しいものであったと思います。纏向以前の日本列島は大きな祭祀区画に分かれており、交易上のトラブルが祭祀圏をまたぐ場合には、解決が難しい可能性があり、一方で弥生後期に鉄器が次第に東方に広がるにつれて、広域交易の重要性は高まって来ていたのでしょう。しかしどの有力祭祀も、列島規模での統一を果たすことはできず、行き詰まった状況であったのではないでしょうか。
物性の世界では、相転移という現象が知られていますが、例えば水が氷りになるような現象のことです。このとき水をゆっくり静かに冷却すると、水の温度は零度以下になりますが、凍りません。ところがこの水に刺激を与えると一気に凍ります。凍ったほうが安定なのですが、きっかけがないため凍ることができないのです。別の例を挙げると、ドミノ倒しが上げられます。ドミノは倒れたほうが安定なのですが、きっかけがないと倒れません。しかし一部が倒れると、次々に倒れていきます。
纏向は大きな祭祀圏にまたがっていただけでなく、まったく新しい特性を持っていたのではないでしょうか。それは既存の拠点集落ではなく、新たに開かれた場所であり、そこでは後の纏向に見られるように、東海的な要素も瀬戸内的な要素もあり、同時にその場所は奈良盆地と言う場所だったのです。つまり複数の祭祀に属する集団が、誰が中心と言うわけでもなく、お互いに文化要素を持ち寄りで作った、過去の呪縛のない空間だったのではないでしょうか。そこに参加するのに、交易上の問題解決を委ねさえすれば、自分たちの祭祀や文化を否定されないとすれば、参加に当たっての壁は低くなります。この結果交易路に沿って、ドミノ倒し的な協賛集落が増え、それが拡大すればするほど、参加のメリットが高まることになったのではないでしょうか。庄内式文化の広がりについて、寺澤薫氏は(1)面的な広がりでなく、網目状の広がりで、集落ごとに大きな差があるとしています。開放的な海路を通して、南関東にまで広がったと思えば、すぐ近くの宇陀では旧来の文化が継続するなど、あくまで自発的な参加によるものではなかったかと思うのです。
しかし纏向にはやがて大きな転機がやってきたでしょう。纏向は広域の交易網の焦点になり、そこには人・物・情報が集積します。纏向以前には博多湾岸にしかなかったような、都市的空間が発生し、もたらされた種子や農耕技術、土器などの日用品の制作技術などが進歩し、しだいに政治的中心としての性格が強くなっていったことでしょう。この結果おそらく参加した有力勢力の間で、纏向を巡る権力闘争が発生したことでしょう。
このような出来事は、纏向が共同祭祀場から、都へと脱却するきっかけとなったと思われます。このような事件は、纏向が大きく発展する布留式期に先立つ、庄内期の終わりごろ起ったものと思います。纏向は列島規模の政治的中心となり、大和王権の確立とともに、布留一式期を最後にその歴史的役割を終えるのではないでしょうか。
(1)寺澤薫『王権誕生』(講談社 二〇〇〇年十二月)
(2)石野博信『邪馬台国の考古学』(吉川弘文館 二〇〇一年三月)
(3)北條芳隆『古墳時代像を見なおす』(青木書店 二○○〇年八月)
(4)藤田三郎「唐子・鍵遺跡周辺の趨勢」『古代おおやまとを探る』(学生社 二〇〇年十月)一五六頁
(5)藤田三郎「唐古・鍵遺跡に運ばれてきた土器(予察)」『纏向学研究』第十号(纒向学研究センター 二〇二二年七月)二二頁
(6)藤田三郎 前掲(5)二七頁図三
(7)金原正明、西村奏「纏向遺跡の形成と古墳築造による画期の様相(予察)」『纏向学研究』第十一号(纒向学研究センター 二〇二三年三月)七三頁図七
Re: 纏向誕生 - 当世奇妙
2025/06/12 (Thu) 09:27:00
六一書房から『弥生後期社会の実像』が本年5月31日に出版されました。税抜きで6000円と結構な値段ですが購入しました。古代学研究会編です。
森岡先生が前会長で、近江の位置づけも語っています。
私の邪馬台国九州説で関川尚功、坂靖の説を紹介していますが、両氏の纏向論は白石楠花さんの論とほぼ一致していると感じました。
このスレッドが再度脚光あびることを期待します。
Re: 纏向誕生 - p君
2025/02/16 (Sun) 19:53:19
白石南花さん
>主旨は纏向開設前に、奈良盆地に東方との交易の動きがあり、そのため東南部に交易拠点が開かれ、そのグローバル性の高い性格のために、吉備をはじめ多くの祭祀を受け入れて発展したというものです。<
東海土器の流入は纏向以前からあるようですから、おっしゃる通りだと思います。
>吉備が纏向を開いたのではなく、纏向が始まって多くの祭祀が流れ込んだ中で、隣接する大阪湾岸からの文化が強い影響力を持ったのではないかと考えるものです。
実際吉備の文化がそのまま入って来て、その他の文化を圧倒したという情勢ではないように思います。<
吉備の楯築墳丘墓の双方中円墳という形の最終にして最大の墳墓が、纏向の櫛山古墳であり、
それは崇神陵墓の可能性が極めて高い行灯山古墳に隣接している事、
これは崇神を生み育てたのが母親である物部のイカガノシコメである事と関連しているとも考えられ、
また楯築墳丘墓の弧帯文石の弧帯文が、纏向石塚、箸墓古墳、布留遺跡にまで見られるのは、
吉備をルーツとする集団が大和まで来ていたであろう事や、また布留遺跡が和田萃さんが言われるように物部の遺跡なら、
つまり弧帯文が物部に関わる文様であろう事とか、他にも今も残る桜井市吉備という地名、大量の桃の種、
東海と吉備に顕著にみられる人面土器が、ウマシマジや天香久山という物部・尾張の祖の東海や日本海の越後への進出(複数の神社伝承)とも重なり、それは纏向遺跡の外来搬入土器が東海と日本海で大半を占めている事とも重なるし、
白石南花さんの言われる「大阪湾岸からの文化が強い影響力」というのは、
ニギハヤヒの畿内入り伝承に、大阪湾岸の二田物部、田尻物部、久米物部などがニギハヤヒに同行していることとも関わると考えられる、などなど、【纏向遺跡を創建したのは物部である】で説明できると思います。
p君さん - 白石南花
2025/02/04 (Tue) 15:13:00
主旨は纏向開設前に、奈良盆地に東方との交易の動きがあり、そのため東南部に交易拠点が開かれ、そのグローバル性の高い性格のために、吉備をはじめ多くの祭祀を受け入れて発展したというものです。
吉備が纏向を開いたのではなく、纏向が始まって多くの祭祀が流れ込んだ中で、隣接する大阪湾岸からの文化が強い影響力を持ったのではないかと考えるものです。
実際吉備の文化がそのまま入って来て、その他の文化を圧倒したという情勢ではないように思います。
Re: 纏向誕生 - 米田
2025/01/28 (Tue) 23:14:25
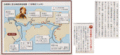 ┌
┌
│Re: 纏向誕生 - p君 2024/07/18 (Thu) 18:17:27
│
│>:年代特定の根拠が、ひとつだけでは、
│ :さみしいですね。
│ :ほかに、何か(年代特定の)根拠は、ありますか。
│
│一つだけであろうが、(云々)
│纏向石塚の177+18と、齟齬がないので、
│私的にはほぼ決定であろうと思います。
│
│Re: 纏向誕生 - p君 2025/01/28 (Tue) 06:12:02
│
│楯築遺跡や宮山遺跡などにみられる吉備発祥の弧帯文が、
│纒向石塚の弧紋円盤に、また箸墓古墳の特殊器台に
│見られるということはどう考えればよいのでしょうか。
│
│普通に考えて、纒向遺跡は、纒向古墳群は、
│吉備に深くかかわる集団、もっと言えば吉備を
│ルーツとする集団の墓ということではないでしょうか。
└
・「三角縁神獣鏡」について
┌
│(伊賀国・風土記)
│孝霊天皇の御宇の癸酉の歳(253年)に、伊賀国とした。
└
:私は、孝霊天皇=天日槍、&塞曹掾史張政、と考えています。
:「三角縁神獣鏡」は、253年以降に、孝霊天皇(天日槍)が、
:連れて来た工人たちに作らせて、配ったと、考えます。
・「纒向古墳群は、吉備に深くかかわる集団」か?
(その1):
:いわゆる「神武東征」の経路は、吉備を経由しています。
:古事記で8年。日本書紀でも、3年ほど滞在しています。
(その2):
:古事記では、孝安天皇の子は①大吉備諸進命と孝霊天皇です。
:孝霊天皇の子どもといわれる4人の皇子を並べてみます。
(「古代豪族系図集覧」より)
・日子刺肩別命
・彦五十狭芹彦命(一伝別名、②大吉備津彦命)
・彦狭嶋命(針間牛鹿臣祖)
・稚武彦命──(子)③吉備武彦命/播磨稲日大郎姫
:名前の印象から見ると、吉備の支配者は、
:①大吉備諸進命→②大吉備津彦命→③吉備武彦命、のように
:(支配者が)異動しているように見えます。
:「クニ」とか「支配者」は、日々変わっていきます。
:私は、孝霊天皇(天日槍)は、孝安天皇の娘婿だろうと
:考えています。
:そうすると、纏向石塚は、纏向遺跡の初期に近いですから、
:孝安天皇の子、臣知人命(大吉備諸進命)が、纏向遺跡に
:関わっている可能性があると考えます。
(一書⑥孝安天皇)
─伊香津臣命─┐┌─梨迹臣命(難升米)
_______│├─臣知人命(大吉備諸進命)
_______├┼─○
──天女の妹─┘└─奈是理姫─┐
_______________
──孝霊天皇(天日槍)─────┴─孝元天皇
Re: 纏向誕生 - p君
2025/01/28 (Tue) 06:12:02
 楯築遺跡や宮山遺跡などにみられる吉備発祥の弧帯文が、纒向石塚の弧紋円盤に、また箸墓古墳の特殊器台に見られるということはどう考えればよいのでしょうか。
楯築遺跡や宮山遺跡などにみられる吉備発祥の弧帯文が、纒向石塚の弧紋円盤に、また箸墓古墳の特殊器台に見られるということはどう考えればよいのでしょうか。
箸墓古墳の特殊器台は宮山遺跡の特殊器台と同型であるそうですね。(画像)
普通に考えて、纒向遺跡は、纒向古墳群は、吉備に深くかかわる集団、もっと言えば吉備をルーツとする集団の墓ということではないでしょうか。
Re: 纏向誕生 - (管理人)
2025/01/23 (Thu) 23:45:14
上げ
Re: 纏向誕生 - p君
2024/07/18 (Thu) 18:17:27
米田さん
>:年代特定の根拠が、ひとつだけでは、さみしいですね。
:ほかに、何か(年代特定の)根拠は、ありますか。
一つだけであろうが、勝山古墳の葬送儀礼に古材を使わないであろうし、伐採した年代が210年であったなら、
私の建てた「石野・豊岡纏向新編年」での纏向石塚の177+18と、齟齬がないので、
私的にはほぼ決定であろうと思います。
帥升について - 白石南花
2024/07/18 (Thu) 17:57:57
このスレで森岡秀人さんの原倭国論を取り上げました。森岡氏によると、纏向を中心とした倭国の前に、湖南を中心とした原倭国の構想があり、その時期は一世紀末から二世紀末とされています。森岡さんはこの時期が107年の帥升の朝貢時期にかかるため、帥升は北近畿にいたとの可能性を言っておられます。そこで後漢書の記事に戻って、この可能性を検討してみます。
まず後漢書に記録された地名と思われるものを列記します。
後漢書東夷伝:
倭面上国(九世紀写本)
倭国(1195年~1200年)
後漢書帝紀
倭国(1195年~1200年)
倭面国(1275年~1301年)
後漢紀
倭国(1548年)
通典
倭面土国(1101年?)
倭国土地(1573年~1620年)
倭国(1878年)
慶元刊本(1195年~1200年)ではすべて倭国になっていて、現在これをとる説が多いですが、後漢書東夷伝に関しては、「倭面上国」が最古の形になり、原則的にはこれを取るべきかと思います。実際のところ、漢書地理志の倭人に対する、魏の時代後漢書も三国志もない時代につけられた註に、「如墨委面」とあり、倭人と「委面」「倭面」を結びつけていることからも、東観漢記の記事のような古い記録に、そのような字面があったことは間違いないと思われます。
問題は帝紀のほうで、こちらにある「倭面国」をどう評価するかです。こちらも原則に従えば最古が「倭国」ですのでそれをとるべきかとも思います。実際帝紀の文面とほぼ同じ文面が、後漢紀という別の書物にあり、「倭国」となっていますから、後漢書帝紀および後漢紀が参照した、東観漢記に「倭国」とあったと考えるのが正しいと思います。実際帝紀にも「倭面国」とあったとすればその後の校勘で、しだいに国名が「倭国」に統一されていくことはないでしょう。写本や刊本では、底本が正しいかどうかを、複数の史料を基に判断し、訂正を行っていきます。したがってどこにもない表記が突然現れて、他を圧倒していくことは考え難いです。
一応東夷伝に「倭面上国」ないし「倭面土国」、帝紀に「倭国」とあったと考えておきます。すると文面がこれほど乱れた理由が分かってきます。明らかに同じ出来事の記録と思われるのに、そこに現れている国名に差があるわけですから、写本や刊本を作成する側が、判断に迷ったのでしょう。「倭面上国」「倭面土国」を採用したグループは、これを「倭面」+「上国」/「土国」のように判断し、帝紀の「倭国」を文字の脱漏として訂正したのでしょう。
さて「倭面上国」と「倭面土国」はおそらく誤写によって生じた差異であると思われますが、いずれが正しいかを決するのは困難です。日本語系の音写として考えるならば、「面」の字は音節の最後が「n」という子音で終わる陽類字であるので、そもそも適切ではないと言えますが、稲荷山鉄剣に「半弖比」という名前が見え、「半」という陽類が使われていることから、そのような用例がありうることが分かります。通常このような子音で終わる文字は、後にくる文字の頭子音と合わせて、連合仮名として用いるのですが、沖森卓也氏は末尾子音を濁音を表すものとされました。森博達氏は古代日本語では濁音は鼻濁音で、(ng)のような音が先行するという指摘を行いました。この鼻濁音の代わりに、前音節の末尾子音が利用されたとするのです。
これを「面」字に適用すると、二音節目は濁音が妥当だということになりますが、これは「土」「上」どちらも該当します。ここでこれら地名を、後の時代の地名と比定します。金石文を除いて、最古の記録は奈良朝の記録になりますので、八世紀奈良朝の地名で該当しそうなものを挙げていきます。
まず「倭面土国」ですが、同じ後漢書の「倭奴国」を「奴」を古音でナと読んで、那津にあてたのに習うならば、これは「面土」をメドと読んで関連地名を探します。有力説として和妙称の「米多郷」があります。現在の三養基郡上峰町大字前牟田で、近くに吉野ケ里遺跡があり有力視されています。しかし同時代の中心地とするには、博多湾岸の遺跡との比較で物足りないものが有ります。また「米多」及びその関連地名は清音である上、二世紀初頭なので母音はオ列甲類でメドないし清音で読んでもメトになりそうです。もう一つ中国史書に見える日本語の音写では、「土」のような次清音が用いられることは少なく、誤写の可能性も疑えます。
時代的には「倭面上国」が最初に現れます。「上」には(ng)のような鼻濁音的な子音が音節末尾につきますが、実は日本語音写において、このような文字を充てるケースがしばしば見えます。例えば「帥升」の「升」字などです。この字は倭人伝の「弥馬升」や「難升米」のような例もあり、割合によく使われています。この韻尾を無視するならば、「面上」はメジ/me(ng)zi/のような音になります。このような古代地名は存在しませんが、比較的近い地名として、延喜式「面治駅」があります。ただし「治」はヂで奈良朝まではジと区別されていました。ただジはziヂはdiで、漢字の音で言うとジは歯音で空気の摩擦音、ヂは舌音で舌先が上あごに触れる音となります。ところが「面」の末尾子音nは舌先が上あごに触れる音で、nziのようにつながると、(ng)ziに近似してくると思われます。「面治駅」はぎりぎり候補に入ります。また「面上」「面土」などと表記が揺れているところを見ると、本来「面士」だった可能性もあります。これならぴったりです。ちなみに「士」は濁音です。
問題は延喜式「面治駅」などは、ほとんどの人が知らないようなマイナーな地名だということです。「面治駅」の比定地は、兵庫県美方郡温泉町井土で、近くに延喜式内社面沼神社があります。地名としては字(あざ)米持(メヂ)、米持前(メヂマエ)があり、神社は米持(メヂ)大明神と呼ばれていたらしく、本来「面治神社」であり、延喜式の記録間違いともいわれています。近くの美方郡香美町香住区米地字にある佐受神社もかって米持(メヂ)大明神と呼ばれていたらしいので、二方国造の領域に、痕跡的にメヂの地名があるように思われます。しかしこのあたりには、有力な弥生遺跡も古墳もなく、「米多郷」以上に可能性がなさそうに見えます。
実際二世紀の初頭の地名が、痕跡程度にしても八世紀の文献記録が始まるまで残っているとは限らず、このような地名比定は意味がないのかもしれません。
ここで観点を変えて、人名のほうから迫ってみましょう。人名のほうは比較的安定しており、東夷伝の記録によれば「国王帥升等」「国主帥升等」「国王師升等」の三パターンです。文面は「献生口百六十人願請見」とつながるので、「国王」だとすると倭国の王が直々にやっていたことになりおかしいとする説があります。また三木太郎氏によると、後漢書東夷伝には夫余王がやってきたことを、来朝としており、王がやってきたはずがないとしています。最後に「等」がついており、王が複数いるはずがないとの指摘もあります。しかし倭人伝では、「倭女王遣大夫難升米等詣郡」と使者一行を代表して「難升米等」としているところから、「国王帥升等」も国王帥升の一行でよいと思います。三木氏は「国主帥升等」を採用し、国の主帥である升たちと理解しました。しかしどうも腑に落ちないのは、「倭奴国」の朝貢でも「卑弥呼」の朝貢でも、使者は太夫を名乗っていたわけで、なぜこの時だけ主帥なのかということです。
私はこのとき「帥升」ないし「師升」は、自分は太夫のような役割ではなく、国の王であると名乗ったのではないかと思うのです。ここでわれわれは大きな誤解をしていたのではないかと気づいたのです。そもそも107年の朝貢において、「倭国」と「倭面上国」のような国名が両方とも出ていたとすれば、三国志における記述のように、倭の社会に対して、全体を倭国と言う政治的まとまりとして捉える捉え方と、多くの国々がその中にあるというとらえ方の両方があったのではないかと言うことです。
つまり「帥升」/「師升」は倭国の中の小国、「面上国」/「面土国」の王だったのではないかと。いつのまにか「面上国」/「面土国」は倭国の代表で、「邪馬台国」のように最高の地位、もしくは都の有る国であると思い込んでいたのではないかと言うことです。
107年に倭国の王は、自分の配下にある小国の王を、使者として楽浪郡に差し向けたのではないでしょうか。そうすると「面上国」/「面土国」には、その時代の倭国を代表するような巨大遺跡はなく、またその王の墓はごく一般的な弥生の首長墓ということになります。もしも朝貢が大きな成果を上げたなら別ですが、「願請見」には不穏な響きがあります。しかも前回朝貢時の金印も返還できていないようです。
もしも倭国の王が、漢への使者として配下の小国の王を差し向けるとしたら、どのような地域の支配者でしょうか。おそらく自分の影響下でもっとも大陸に近いところにある国を利用するでしょう。博多湾岸の中心国が、背振山の反対側にある国を使うのでしょうか。
いま森岡原倭国論に従うと、その中心は湖南にあり、近畿式銅鐸の中心地です。原倭国の影響力がどこまで広がっていたかはわかりませんが、近畿式銅鐸圏の中で但馬のあたりは、当時有力となっていた日本海航路に面して、もっとも西となります。
兵庫県北部にかって面治(メヂ)国という小国があり、その王が少なくとも近畿式銅鐸圏やその周辺勢力をまとめた伊勢遺跡の王の指示により朝貢したとして、いかに小国と言え、重要な役割を担う以上、王権の中での地位が与えられたと思われます。ここで「帥升」/「師升」に注目してみましょう。邪馬台国の場合、第二位第三位の官名に「弥馬升」・「弥馬獲支」があります。この二つは「弥馬」に関する官位でしょうが、纏向の近くにはミマと言う地名があり、おそらく都を治める長官と副官でしょう。「帥升」/「師升」は本貫として二方のあたりに国を持つと同時に、伊勢遺跡方面の周辺に根拠地を与えられていた可能性があります。「弥馬升」がミマの長官なら、「帥升」/「師升」は「帥」/「師」の長官となります。「帥」は日本語の音写には適さないので、おそらく「師」シを根拠地として与えられていたのでしょう。伊勢遺跡の琵琶湖対岸のあたりに、日本書紀景行紀の志賀の高穴穂の宮の比定地があります。志賀の語源はシに接尾辞のガが付いたものとの説が有力です。「師升」は原倭国の王に、王権内の役割を果たすために現在の大津あたりを根拠地として与えられていたのではないでしょうか。
Re: 纏向誕生 - 米田
2024/07/18 (Thu) 10:04:33
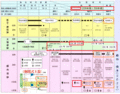 ┌
┌
│Re: 纏向誕生 - p君 2024/07/16 (Tue) 07:13:50
│
│米田さんが掲載してくれた表を見ます。
│
│この表の纏向遺跡で、勝山古墳が250~270に
│なっていますが、年輪年代で210年である事が
│無視されているように感じます。
└
:私の(加工した)表では、2種類の年代を記していました。
:つまり、「勝山古墳が250~270」には、特定していません。
:(両論併記のつもりで書き込んでいました。)
:研究者によって、年代は定まってはいないという事です。
:もともと、纏向の年代は、「卑弥呼の没年」を248年頃に
:していることから、卑弥呼を墓の主として箸墓古墳の年代を
:(基準年として)250年頃にしているように感じられます。
:日本書紀に書かれているように、「倭迹迹日百襲姫命」
:または、「倭迹迹姫命」を「箸墓古墳」の主としています。
:とすると、「箸墓古墳」の年代は、250年頃から300年頃まで
:古墳の年代は、変わってきます。
:私は、「箸墓古墳」の主は、「倭迹迹稚屋姫命」として、
:265年頃を想定しています。
:勝山古墳は、210年以降で、265年頃よりも前だろう、
:というのが、私の(個人的な)推測です。
┌
│Re: 纏向誕生 - p君
│2024/07/17 (Wed) 22:42:17
│
│そうではなくて勝山の場合は葬儀に使われ廃棄された
│板材と考えられるので、210年が葬儀の年です。
│被葬者が早世なのか長寿なのかは置いといても、
│古墳の建造開始はもう少し前でしょう。
└
:断定的な表現は、アマチュアの特権ではありますが、
:年代特定の根拠が、ひとつだけでは、さみしいですね。
:ほかに、何か(年代特定の)根拠は、ありますか。
Re: 纏向誕生 - p君
2024/07/17 (Wed) 22:42:17
米田さん
>_ただしこれは伐採時の年代であり、その後の築造との
_関連や材の使用・投棄の時期との関連が不明である[2]。
>:ヒノキ板材の年輪年代(西暦210年頃)から分かることは、
:その場所が、少なくとも「西暦210年頃」以降に
:造成され始めたということです
そうではなくて勝山の場合は葬儀に使われ廃棄された板材と考えられるので、210年が葬儀の年です。
被葬者が早世なのか長寿なのかは置いといても、
古墳の建造開始はもう少し前でしょう。
Re: 纏向誕生 - 白石南花
2024/07/16 (Tue) 18:15:19
当世さん
宣伝有難うございます。考古学は最近遠ざかっていたので自分では宣伝しませんでした。
追記
寺澤さんのイト倭国論が、近畿説では人気ですが、例えば日本の中心が、京都から南関東に移った時のことを考えると、まずそのまえに京都の政権が南関東までを支配していたこと、鎌倉に政権が移ってからも、どちらかと言えば地方政権的な性格があり、建武親政いらい京都に戻り、もう一度関東に戻ってくるのは江戸幕府になることを考えると、ヤマトに政権が移るまでには相当な試行錯誤があったと考えるべきと思います。
また平安期末には関東に相当の武士の力量が蓄えられていたことがあり、それが下地になっていたことを考えるべきと思います。
鎌倉の場合頼朝と言う、血統的に天皇に繋がる人物を頭に据えたことも考えると、前原の王族を近畿の勢力が頭にした可能性も考えてよいのではないでしょうか。
Re: 纏向誕生 - 米田
2024/07/16 (Tue) 11:20:36
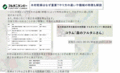 ┌
┌
│Re: 纏向誕生 - p君 2024/07/16 (Tue) 07:13:50
│
│米田さんが掲載してくれた表を見ます。
│
│この表の纏向遺跡で、勝山古墳が250~270に
│なっていますが、年輪年代で210年である事が
│無視されているように感じます。
│
│最近出た年輪セルロース酸素同位体比で追試もできる
│年輪年代という手法で科学的に出た数字なのだから、
│そのまま掲載すべきだと思います。
└
「纒向勝山古墳(まきむくかつやまこふん)」(wikiより)
年輪年代測定
・2001年(平成13年)5月30日。第4次調査において周濠
_くびれ部埋土中より検出されたヒノキ板材を(云々)、
_年輪年代測定の結果、伐採年代は、新しく見積もっても
_西暦210年頃と推定されることが判明する。
_ただしこれは伐採時の年代であり、その後の築造との
_関連や材の使用・投棄の時期との関連が不明である[2]。
・年輪年代測定以前は、周濠跡からの布留0式土器の出土に
_より土器編年を利用し年代基準を決定していた。
_土器編年による年代は西暦300年前後。
・同じく周濠跡からは布留0式よりも旧い庄内2式期土器が
_出土している。土器編年による年代は3世紀前半。ただし
_これも周濠跡からの出土のため築造時期の決め手に欠いている。
「古墳(こふん)」(wikiより)
「寿陵」説
なお、古墳自体の規模とその造営に必要な労働力や期間などを
考慮して、古墳を寿陵(生前に構築した墓)とする説がある。
『日本書紀』には仁徳天皇や蘇我蝦夷父子が生前より墓を
築いていたと記されており、『筑後国風土記』逸文にも
地元の大豪族筑紫君磐井が生前に墓を築いたとする記述が
あるからである。考古学の見地からも梅原末治や茂木雅博ら
が寿陵説を唱え、現在では通説化している。
見積もりした工程別の施工期間
・伐開除根・地山均し:3.3か月。
・測量・地割・丁張りほか:2.3か月。
・外濠掘削・盛土:11.4か月。
・内濠掘削・盛土:46.1か月。
・客土掘削・盛土:103か月。
・(以下、略)
*****
┌
│最近出た年輪セルロース酸素同位体比で追試もできる
│年輪年代という手法で科学的に出た数字なのだから、
│そのまま掲載すべきだと思います。
└
:ヒノキ板材の年輪年代(西暦210年頃)から分かることは、
:その場所が、少なくとも「西暦210年頃」以降に
:造成され始めたということです。
(これは、「伐開除根」とか「内濠掘削」の工程でしょうか。)
:または、ヒノキ板材の場所を、別の目的で使用していた時の
:残骸でしょうか。
:
:私は、「寿陵説」を支持しています。
:我々が、(古墳の時期として)一番知りたいのは、
:古墳を「いつ作り始めたか」ではなく、被葬者が、
:「いつ亡くなって、いつ埋葬されたか」になります。
:もちろん、古墳の主が誰であるのかも、知りたいわけですが。
Re: 纏向誕生 - p君
2024/07/16 (Tue) 07:13:50
米田さんが掲載してくれた表を見ます。
https://bbs1-imgs.fc2.com//bbs/img/_888000/887932/full/887932_1720648338.gif
この表の纏向遺跡で、勝山古墳が250~270になっていますが、年輪年代で210年である事が無視されているように感じます。
最近出た年輪セルロース酸素同位体比で追試もできる年輪年代という手法で科学的に出た数字なのだから、そのまま掲載すべきだと思います。
2024/07/11 (Thu) 20:05:04
米田さん
:「纏向誕生」を論ずるのであれば、「5W1H」を考えると、
:「纏向」は2世紀末に、どうして誕生したのか、になります。
二世紀末と言うのは別に定説ではなく、石野さんの纏向編年です。
:垂仁天皇25年は、垂仁天皇元年(太歳:壬辰)から、
基本的に私は日本書紀紀年は採用しません。
:纏向では、「196年」という年代が計測されたという話が
:あったと思います。
年輪年代かなんかでしたか?
私的には、二世紀中ごろと想定しています。
あくまで倭人伝の記述が正しければですが、卑弥呼が240年代末以降に亡くなったとして、在位が二十年程度、倭国乱が十年程度として、七八十年を積算すると、二世紀中ごろとなります。
実は近江の伊勢遺跡が纏向に先立って最盛期に入ります。
弥生後期前半に唐子・鍵の外来土器が見えなくなる時期がありますが、弥生後期後半になって近江や伊勢の土器が見え始めるのは、伊勢遺跡の興隆と関係するかもしれません。
纏向開始とともに伊勢遺跡は衰退します。
奈良盆地と伊勢湾方面の交易に、吉備河内など瀬戸内勢力が参画することで、纏向が優勢になったものと考えます。
この盛衰の原因が、おそらく纏向の持っていた祭祀の性格によるものと推測しています。
追記
ちなみに森岡秀人さんの原倭国論があります。(1)そこでは近江の伊勢遺跡を中心とした原倭国が存在したとしています。頁五十二左側下に
「要するに、大和や河内などの後の畿内の中枢部を除く連
携様相に気づくべきだと訴えているのです。」
とあります。
土器や青銅器からの考察なのですが、要するに原倭国構想では河内吉備大和を抜いたものとなっていて、私はこれに対抗するための吉備河内伊勢を巻き込んだ構想が、纏向の始まりだと思います。森岡さんは伊勢遺跡で卑弥呼が即位したとしていますが、私は纏向は伊勢遺跡の後半部分と並行して存在し、競合の上伊勢遺跡を負かしたのだと思います。その原動力が祭祀の内容だったと思うのです。卑弥呼の即位は纏向形成から七八十年後のこととします。
(1)森岡秀人 「倭国成立過程における「原倭国」の形成」『纏向学研究』三号(纏向学研究センター 二〇一五年三月)三十七頁
https://www.city.sakurai.lg.jp/material/files/group/54/kiyou3.pdf
Re: 纏向誕生 - p君
2024/07/11 (Thu) 19:21:10
大和において2世紀末から前方後円形の奇妙な墳墓を造っていた一族が、
6世紀末以降にはその奇妙な墳墓を突然造らなくなります。
古事記のミマキイリヒコこと崇神318年没を信用し、崇神が4世紀初頭であることを基点とするなら、
大豪族で2世紀末から大和にいたという伝承でもいいから、それを持っており、
そして6世紀末に滅亡したという事であれば、
それは蘇我に滅ぼされた物部以外になく、
纏向遺跡の瀬戸内の強い要素は、複数の瀬戸内集団を引き連れてきたという彼らの始祖伝承と重なり、
纏向遺跡の東海、北陸、日本海土器の多さは、その始祖の子が東海や北陸に進出した伝承とも重なります。
Re: 纏向誕生 - 米田
2024/07/11 (Thu) 17:16:06
┌
│纏向誕生 - 白石南花 2024/07/07 (Sun) 15:02:56
│
│纏向がどのように誕生したかを考察してみます。
│1.纏向開設の本来の目的は何か
│2.なぜ纏向は日本列島規模の交易拠点となったのか
└
┌
│「纒向遺跡(まきむくいせき」(ウィキペディアより)
│纒向遺跡は、奈良県桜井市の三輪山の北西麓一帯にある弥生
│時代末期から古墳時代前期にかけての集落遺跡・複合遺跡。
│2世紀末から4世紀前半にかけての遺跡である。
└
(その1)
:「纏向誕生」を論ずるのであれば、「5W1H」を考えると、
:「纏向」は2世紀末に、どうして誕生したのか、になります。
(その2)
:垂仁天皇25年は、垂仁天皇元年(太歳:壬辰)から、
:垂仁元年を272年/332年の両方の混在を考えています。
:そうすると、垂仁天皇25年は、296/356年となります。
:これは、布留0式・布留1式にあたっています。
:つまり、遺跡の最盛期・縮小・廃絶期に該当します。これで
:「纏向誕生」を論ずるのであれば、時期がずれています。
**********
古代史俯瞰 by tokyoblog(魚も鳥も俯瞰・鳥瞰する)ネットより
大和神社(大和坐大国魂神社)
tokyoblog 2014-10-26No Comments
大和(大倭)とはどこか?
●大和大国魂神
磯城瑞籬宮→市磯邑(桜井市穴師・箸中付近か)
→現,大和神社鎮座地(天理市)
『日本書紀』の崇神天皇条と垂仁天皇25年3月10日条に
倭大国魂神に関する記事が掲載されています。
それによれば、穴磯邑(あなしのむら)に定めて大市の
長岡岬に渟名城(ぬなき)稚姫(わかひめ)命(みこと)に
祀らせたとあります。
千田さんの話では穴磯とは今では穴師という地名が残って
いますが、巻向山を源流とする纏向川のほとりを指します。
長岡岬とは現在の長岳寺が存在するあたりは
昔、長岡村とよばれていたそうです。
岬とは ミ+サキ=神のとりつく先という意味。
大市は城上郡(しきの かみぐん)大市郷ですから
現在の箸墓のある場所付近を指します。
ですから穴磯邑とは邑=都 随分と大きな地域を指していた
事になります。
長岳寺と穴師の距離は南北3㌔、そして箸墓も含みますから
桜井市穴師から天理市柳本町の長岳寺を含み尚且つ、
大都市を示す大市の箸墓付近も含む広大な地域を
指していたと考えられる。
**********
┌
│そうであるにもかかわらず、纏向がえらばれたのは、
│本来は唐子・鍵と東海の交易の拠点が始ま地だったのでは
│ないかと言うことです。
│列島規模の拠点になったのは、地理的要因ではなく、
│そのグローバル性のある祭祀の内容だったのではないかと
│言うことです。
└
(その3)
:ほかのスレ(系図・任那)に書いてきましたが、
:6世紀に、倭国出身者(高向の娘の子孫)が、高句麗・新羅・
:百済を(内部抗争をしながら)支配していきます。ですので、
:高句麗本紀・新羅本記などの「2世紀末」の様子は、
:倭国の様子を記述していることも多いと考えています。
:
:そうすると、「2世紀末」に何があったかです。
:新羅本記173年、倭の女王が(阿達羅王を)来訪させた。
:「阿達羅王(御食津臣命)」の子が、173年頃生まれた。
:新羅本記196年、「伐休王(抜奇・手研耳命)」が薨去した。
:高句麗本記
:故国川王(卑弥呼:179~197)
:山上王(故国川王の弟:197~227)
:東川王234年、太后の于氏(卑弥呼)が薨去した。
:纏向では、「196年」という年代が計測されたという話が
:あったと思います。
:三輪山のふもとは、(短期間かもしれませんが)
:卑弥呼の生まれ育った土地です。
:纏向は、公孫氏から身を守るために、逃げ隠れるように
:作った都ではないか、と私は、考えています。
:これは、後漢書の「拘奴国」に該当します。
:以上、「2世紀末(おそらく196年)」に
:纏向遺跡が誕生したという考察をしてみました。
2024/07/11 (Thu) 15:21:54
米田さん
:風土記を読んでいると、纏向とその周辺は、(支配者階級の)
:セレブの宅地としての価値は、感じられますが、
:「交易拠点」としては、価値を感じられません。
いや現地には大市の地名が記録されています。日本書紀では倭迹々姬命を葬ったのが大市、渟名城稚姬が大倭大神を祭ったのが、大市長岡岬となっています。そのほか記紀には海石榴市と言う地名も出てきます。このあたりは初瀬川をさかのぼった地点で、隋使を迎えた場所でもあります。初瀬街道を通って伊勢へ抜ける入り口です。
:つまり、交易の拠点を論ずるのであれば、美濃や伊勢の方が
:琵琶湖を使った水運による「交易」として、重要だろうと
:考えています。
そうであるにもかかわらず、纏向がえらばれたのは、本来は唐子・鍵と東海の交易の拠点賀だったのでははじまりだったのではないかと言うことです。列島規模の拠点になったのは、地理的要因ではなく、そのグローバル性のある祭祀の内容だったのではないかと言うことです。
Re: 纏向誕生 - 米田
2024/07/11 (Thu) 06:52:18
 ┌
┌
│纏向誕生 - 白石南花
│2024/07/07 (Sun) 15:02:56
│
│纏向がどのように誕生したかを考察してみます。
│
│ここで一つの仮説として、纏向は本来列島規模の交易拠点と
│して選ばれたのではなく、別の理由で選定された交易拠点
│だったのではないかとしてみます。
│その場合問題は以下の二点となります。
│
│1.纏向開設の本来の目的は何か
│2.なぜ纏向は日本列島規模の交易拠点となったのか
└
:風土記を読んでいると、纏向とその周辺は、(支配者階級の)
:セレブの宅地としての価値は、感じられますが、
:「交易拠点」としては、価値を感じられません。
:ですので、白石南花さんの「問題の設定」に疑問を感じます。
:つまり、交易の拠点を論ずるのであれば、美濃や伊勢の方が
:琵琶湖を使った水運による「交易」として、重要だろうと
:考えています。
:ですので、白石南花さんの「問題設定」の設定自体が、
:間違っているのではないかと、私は考えます。
**********
(風土記:伊勢国)
:そもそも伊勢の国は、天日別命が平定したところである。
:(云々)
:やがて天日別命に「その国(伊勢国)」の統治をまかせ、
:宅地は大倭(やまと)の耳梨の村に賜った。(云々)
:そうしてから後、橿原の宮に復命した。
(風土記:伊賀国)
:伊賀の国は昔伊勢の国に属していた。
(常陸国風土記:P-028)
:綺日女命・常陸国_筑紫の日向→三野(美濃)
:綺(日女)=神機(姫)=かむはた(ひめ)
(常陸国風土記:P-028)
:古老がいうことには、
:「すめみまの命(皇孫瓊瓊杵命)が天からお降りになった
:とき、御服(みぞ)を織るために従って降った神、み名は、
:綺(かむはた)日女命は、もと筑紫の日向の二所(ふたがみ)
:の峯より、三野(美濃)の国の引津根の丘においでになった。
:後、みまき天皇(崇神天皇)のみ世になって、長幡部の遠祖
:多弖(たて)命は、三野(美濃)を去って、久慈に移り、
:機殿(はたどの)を造り立てて初めてこれを織った。
:その織るところの布はひとりでに衣裳(きもの)となり、
:あらためて裁ち縫う必要がなく、これを内幡(うつはた)
:(完全な服:はた)といっている。」
:あるひとはこうもいう、
:「絁(あしぎぬ:太絹)を織るときにあたって、容易に
:人に見られてしまうので、家のとびらを閉じきって暗闇の
:なかで織った。云々。」
2024/07/08 (Mon) 16:08:14
当世様
この本はお勧めのようなので買いました。
参考にしています。
「私の好きな邪馬台国九州説:再スタート」に投稿しないのは九州説ではないからです。
卑弥呼の即位年について書いた投稿で、卑弥呼の都を纏向とする説においても、纏向の登場を卑弥呼の即位に結びつける人が多数派としましたが、私は纏向登場は二世紀中ごろのことで、卑弥呼の前の男王の時代の事と考えています。
倭国乱は庄内期の終わり近くに起こった王位継承の争いで、せいぜい数年と考えます。
石野さんが布留ゼロで、多くの古墳の周濠への土器投棄があるとされていますが、これがある意味倭国乱の終わりに関連したものでしょう。
大型建物は卑弥呼以前の王宮の一つなのでしょう。
庄内期から布留期への移行の時代に卑弥呼は即位し、王宮の位置も変わり、首長の自発的協賛の中心から、権力の中心に脱皮し始めたと考えています。
その脱皮が完成したのが、布留二式の時期で、纏向が役割を終え衰退する時代だという考えです。
Re: 纏向誕生 - 米田
2024/07/08 (Mon) 12:00:34
┌
│纏向誕生 - 白石南花
│2024/07/07 (Sun) 15:02:56
│
│纏向がどのように誕生したかを考察してみます。
│
│1.纏向開設の本来の目的は何か
│2.なぜ纏向は日本列島規模の交易拠点となったのか
└
:私の専門は、系図の解読・復元です。
:纏向に関する資料としては、「古代豪族系図集覧」の系図と
:「風土記」に出てくる人物をすり合わせています。
:白石南花さんの考察と、私の人物特定の考察に、
:どの程度の接点があるか分かりませんが、
:考察は、下記スレに投稿しております。
スレ「系図・年表」での考察(図解)(2)
Re: 纏向誕生 - 当世奇妙
2024/07/08 (Mon) 08:09:12
私は坂靖さんの
『ヤマト王権の古代学』第5章ヤマト王権の誕生
に記されている纏向遺跡論はかなり説得力があると思っています。スレッド「私の好きな邪馬台国九州説:再スタート」で紹介中です。