東アジア討論室
混み入った議論と一対一の論争は討論室で行いましょう。
投稿の大項目はスレッドで投稿してください。
そのスレッドに対するはレスとして投稿してください。
レスに対する意見もレスとして投稿してください。
スレッド作成での留意事項
●(新規作成の)スレッドには、タイトル(内容の紹介)と自分の名前を入れて下さい。
●みんなの関心事項については、「会」として、スレを(追加で)設けることもあります。
要望事項
●「返信・引用」を使う場合は、不要なところは削除したうえで、お使いください。(1回のみ)
●「返信・引用」は、多用すると、返信の返信となると、誰の発言か分かりにくいので、控えて下さい。
●また、文章では、適当なところで、右側に「改行マーク」を入れて下さい。(一行、45文字程度)
●また、一文(~。)の長さは、長くて3行まで、(およそ、150文字以内:推奨100文字以内)にして下さい。
●文章は、残ることを念頭に、マナーに気を付けて、楽しく(議論は熱く)投稿しましょう。
私の好きな邪馬台国九州説:再再スタート - 当世奇妙
2024/07/23 (Tue) 19:38:00
『ヤマト王権の古代学』坂靖の
序章 ヤマト王権とは何か
第1章 神武天皇と「闕史八代」
第2章 中国史書にあらわれた倭国
第3章 倭国分立時代のヤマト
第4章 邪馬台国の所在地
第5章 ヤマト王権の誕生
第6章 「おおやまと」王墓
までを当世なりに読解して記してきた。
今までの理解をもとに先ずは
「纏向とは何か」
「ヤマト王権とは何か」について
当世の考えを記したい。
坂氏理解とは異なる可能性がある。
坂氏は既にいないので彼との情報交換は今はできない。
当会でのご講演を了解されたその同じ月に亡くなられた。残念である。
当世の上記に対する考えは、坂氏の執筆に関する今までの投稿を読み返した結果の当世流見解である。
その大筋は
纏向を反映させたのは唐古・鍵などの在来勢力ではなく、東西の交易を担っていた新たな外来勢力
との理解である。但し、弥生時代後期に最初に纏向を築いたのは現地オオヤマト勢力の可能性も十分ある。彼らは旧来の勢力よりも活力
があり、徐々に勢力を伸ばし、布留ゼロ期には
日本列島最大の勢力になった。しかし当初の支配地域は「おおやまと」古墳群の範囲であったと考える。
その考古学的根拠などを、この新しいスレッドに
先ずは記し、続いて第7章以降を記して行きたい。
Re: 私の好きな邪馬台国九州説:再再スタート - 米田
2025/03/26 (Wed) 23:58:56
 (後半)
(後半)
┌
│Re: Re: 私の好きな邪馬台国九州説
│:再再スタート - 当世奇妙
│2025/03/26 (Wed) 21:00:50
│
│米田さん得意の系図ですが、
│あれは何か纏向に関係しますか。
└
:卑弥呼が、196年頃、纏向に都を作ったと考えます。
:ポスト卑弥呼の話として、
┌
│風土記(伊賀国)の記述の中には、孝霊天皇の御宇の癸酉の歳に
│云々、という記事があり、孝霊天皇の太歳は、辛未(251±60年)
│が、分かっていますから、癸酉の歳は、253年になります。
└
:このあと、台与(倭迹迹日百襲姫命=欝色謎命)が即位します。
:夫は、孝元天皇です。
┌
│孝元天皇=烽上王、に仮に変更すると、彼は300年に自殺します。
│そして、自殺した二人の息子は、大彦命と武埴安彦命になります。
└
:これで、いわゆる、纏向政権は、終焉を迎えます。
:天日槍(孝霊天皇)の子(彦狭嶋命=景行天皇)は、
:御間城姫命(高15美川王)を立てて、新しい王権を作ります。
:夫である、祟神天皇は、味鉏高彦根命(国摩大鹿嶋命)として、
:日本武尊と一緒に、東国の平定に向かっています。
┌
│米田さん得意の系図ですが、
│あれは何か纏向に関係しますか。
└
:祟神天皇は、古事記では、
:「初国知らしし御真木天皇」とされています。
:
:つまり、300年に、纏向政権(王権)は、一度、潰れています。
:リセットされて、祟神天皇が始まります。
:
:孝元天皇に関する系図が、纏向に関係しています。
Re: 私の好きな邪馬台国九州説:再再スタート - 米田
2025/03/26 (Wed) 23:57:56
 (前半)
(前半)
┌
│Re: Re: 私の好きな邪馬台国九州説
│:再再スタート - 当世奇妙
│2025/03/26 (Wed) 21:00:50
│
│米田さん得意の系図ですが、
│あれは何か纏向に関係しますか。
└
┌
│Re: 「資料批判が足りない」という言葉 - p君
│2025/03/26 (Wed) 19:45:36
│
│纒向古墳群が物部である根拠は2世紀末から6世紀末まで
│大和に君臨した大豪族で、途中から崇神天皇がその墓制を
│取り入れ、以降天皇家の墓制となっていること、
│蘇我の台頭とともに、前方後円墳が失われていくこと、
│などを総合して物部の墓としか考えられません。
│違うというなら2世紀末から6世紀末まで
│大和に君臨したのは何者なのかお答え願いたい。
└
(その1)
:250年以降、高句麗(・新羅)の王族は、没落(壊滅)し、
:300年以降は、倭国系の王族が、半島全体を支配しています。
(その2)
:そのため、250年(孝霊天皇)~300年(祟神天皇の即位)
:の倭国の王族の系図は、そのまま、高句麗王の王族の系図に
:重なります。「川」の字の付く「王」は、「女王」です。
(その3)
:高句麗本紀では、烽上王が300年に自殺し、二人の王子も
:また、自殺した。と、書かれています。
:日本書紀で、ここに該当する部分は、
:(いまのところ)武埴安彦命の乱になります。
:系図では、烽上王を欝色雄命にしていましたが、烽上王は、
:孝元天皇OR武埴安彦命OR欝色雄命の3人で、迷っています。
:孝元天皇=烽上王、が一番良いかも知れません。その場合、
:自殺した二人の息子は、大彦命と武埴安彦命になります。
:この辺りの人物特定は、まだまだ未完成です。
(その4)
:高句麗本紀では、南部の大使者の倉助利が、沸流の川岸で、
:咄固の子を見つけて、王都に(連れて)帰った。
::日本書紀で、ここに該当する部分は、(景行天皇紀:葦北)
:山部阿弭子(あびこ)の祖である小左を召し出し、云々。
:山部阿弭子(あびこ)を系図から探すと、藤原鎌足の先祖に
:似た名前の人物がいました。「阿毘古(あびこ)」です。
:山部は、海部と対になっていて、職名(部)です。
国摩大鹿嶋命──〇──〇──〇──〇──阿毘古─‥‥─藤原鎌足
_(小左)
(その5)
:古墳の分布をみると、纏向での箸墓グループの古墳以降、
:390年頃の富雄丸山古墳(武内宿禰?)まで、
:大王クラスの古墳は、ヤマトにはないのです。
(その6)
:祟神天皇の后(妻)のメインは、二人です。
:豊鍬入姫命は、いわゆる「倭姫命」です。
─大彦命──御間城姫─┬─垂仁天皇
─開化天皇─祟神天皇─┘───────┐
─開化天皇────────豊鍬入姫命─┴─丹波道主王
***************************
<「崇神天皇の即位年(300年)」についての考察>
:崇神天皇元年=300年(干支は一致しません)
:『勘注系図』『海部氏系図』は、(定説では)後世の偽作系図
:ということになっています。
:そもそも、日本書紀そのものが、紀元前660年に、神武天皇が
:即位したという、トンデモな本ですから、私は、素人の系図解読
:マニアですので、使えるものは何でも使おうという立場です。
:ということで、『勘注系図』・『海部氏系図』は、
:正しいかどうかを確かめたいと思います。
(仮説)
:少なくとも、『勘注系図』・『海部氏系図』の(年代の)干支は
:(すべて)正しいとして、干支を基準に、並べ替えてみました。
(カッコ内の西暦は、米田が追記したものです。)
┌
│『崇神の壬戌(302年)年春三月、←:『勘注系図』
│豊鋤入姫命、天照大神を戴(いただ)き、大和国笠縫の里から、
│丹波の余社郡(よさのこおり)久志比之眞名井原匏宮に移る。
│(くしひのまないはら-よさのみや)
├
│三九年壬戌(302年)。_____←:『倭姫世紀』
│但波(たんば)の吉佐宮(よさのみや)に遷し奉る。
├
│崇神即位六年己丑(305年)。__←:『倭姫世紀』
│秋九月倭笠縫邑に、草薙剣を遷奉(うつしたてまつる)
├
│丙寅(306年)年秋七月、____←:『勘注系図』
│(四年後)に、また大和国伊豆加志本宮に遷ったとする。』
│(いずかしもとみや)
├
│四十三年丙寅(306年)。____←:『倭姫世紀』
│倭国伊豆嘉志本宮に遷し、八年齋(いつき)奉る。
│(やまとのくにいづかしもとみや)
└
:『倭姫世紀』の崇神即位六年己丑(つちのとうし:305年)を
:正しいとすると、「崇神天皇」元年は300年になります。
:そうすると、上記『勘注系図』『海部氏系図』の年代は、
:(垂仁天皇元年=332年、ですから)すべて、
:崇神天皇の時代に、収まることが分かります。
:ここで大切なことは、
:実際に歩き回っているのは、「豊鋤入姫命」です。
:『倭姫世紀』・『勘注系図』においては、まるで、
:「豊鋤入姫命=倭姫命」を前提にして年代が語られている
:ということです。
Re: Re: 私の好きな邪馬台国九州説:再再スタート - 当世奇妙
2025/03/26 (Wed) 21:00:50
米田さん
今新幹線で、大宮で漸く座れたので討論室読んでます。
文献資料色々ありがとうございます。文献派で無いので良く理解出来ませんが
米田さん得意の系図ですが、あれは何か纏向に関係しますか。
Re: 私の好きな邪馬台国九州説:再再スタート - 当世奇妙
2025/03/25 (Tue) 11:24:16
P君さん 米田さん
ありがとうございます。
ここ数日専門分野(溶接部の超音波探傷試験、MOT技術経営、医療関連ベンチャー支援、住宅免振など)で多忙なので、追ってコメントさせて頂きます。
Re: 私の好きな邪馬台国九州説:再再スタート - p君
2025/03/22 (Sat) 20:20:28
当世奇妙さん
>関川・坂両氏の考古学的考察と合致するような記紀などの文献史学のヤマト王権成立論の投稿期待します。
ここで先代旧事本紀を出せば、吉備や讃岐など瀬戸内文化の結集が纒向遺跡である、その証拠が巻第三・天神本紀のニギハヤヒが引き連れてきた多くの瀬戸内集団で説明できると思うのですが、ニギハヤヒなんて名前を出した時点で資料批判が足りない、先代旧事本紀は史料にならないと言われてしまうのでしょうね。
纒向遺跡の外来搬入土器に東海土器の多いこと、日本海土器の多いことも、これは神社伝承ですが、ウマシマジや天香山が東海を制圧し、そして日本海に抜ける事で説明できると思うのですが、これも資料批判が足りないと言われて終わるのでしょうね。
今の古代史界では「資料批判が足りない」という言葉が金科玉条のようになっています。
Re: 私の好きな邪馬台国九州説:再再スタート - 米田
2025/03/20 (Thu) 11:18:20
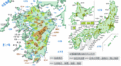 ┌
┌
│「纒向遺跡(まきむくいせき)」(ウィキペディアより)
│纒向遺跡は、奈良県桜井市の三輪山の
│北西麓一帯にある弥生時代末期から
│古墳時代前期にかけての集落遺跡・複合遺跡。
│
│2世紀末から4世紀前半にかけての遺跡である。
│一帯は前方後円墳発祥の地とする研究者もいる。
│邪馬台国の中心地に比定する説があり、
│最古の巨大前方後円墳とされる箸墓古墳と、
│それより古い5つの纒向型前方後円墳が分布する。
└
┌
│関川・坂論から(9)振り返り
│7)纏向では北部九州の土器は発見されていない。
│6)纏向を中心に吉備から東海、東日本までを含む大きな
│__動きがあり、魏志に見える「邪馬台国」を遙かに超える
│__動きが纏向中心に起こっていた。
└
:1世紀中頃以降、2世紀にかけて、半島から日本列島に、
:大量の移住(移動)が発生しています。
:九州は、1世紀中頃の段階で、すでに人が大勢住んでいて、
:移住を受け入れる余地は、あまりなかった。それに
:比べると、九州以外の地域は、港(津)が点在するくらいで、
:人を受け入れる余地(平野・盆地)が多くあった。
:
:中国・四国地域は、山が多く、平野は少ない。
:岡山平野・播磨平野・讃岐平野・徳島平野・新居浜などが
:広い平野と云えるくらいである。(掲載図参照)
(神統譜・天神系の系図)
天児屋根命(天の岩戸は、おそらく出雲。)
|
天押雲命
|
天種子命(妻は、菟狭津媛)
|
宇佐津臣命(筑紫の国の菟狭で、生まれた可能性が高い。)
|(天御中主神の12世の孫の本人か、または同世代。)
|(伊勢津彦は、天富命=事代主命だろうと推測。)
御食津臣命
|
伊賀津臣命(近江の国の伊香の郡で、天女の妹と出会い、結婚。)
|
├臣知人命(出雲醜大臣命)←①
│
└梨迹臣命(難斗米/難升米。卑弥呼の使者。出石心大臣命)
_|
_├奈是理姫(細媛命:孝霊天皇の后。子は孝元天皇。)
_│
_├彦五十芹彦命(大吉備津彦命)←②
_│
_└稚武彦←③
__|
__吉備武彦←④
(風土記:伊賀国)
:伊賀の国は、昔伊勢の国に属していた。
:孝霊天皇のみよの癸酉(253年)の歳に、これを分かって
:伊賀の国とした。もと、この名は、伊賀津姫(=天女の妹)の
:領して郡であるから、それによって郡の名とし、また国の名とした
:ものである。≪日本総国風土記≫
*****
:吉備(岡山平野)は、昔から大きな港町だったが、
:支配者が次々に替わるために、支配者と住民とのつながりは
:薄い。
:ヤマト政権の中でも、中心的な人物が、吉備を支配していたと
:思われます。(播磨もありますが。)
:
:阿波忌部氏の徳島は、支配者と住民とのつながりは強いが、
:権力闘争の中では、没落していった。
『天富命(あめのとみのみこと)』(ウィキペディアより)
(:天富命は、事代主命のことだろう。)
天富命は、日本神話に登場する神または人物。
神武東征において橿原宮を造営し、
阿波国に続いて房総の開拓をした。
概要
神武東征においては、手置帆負命・彦佐知命の二神の孫の
讃岐忌部・紀伊忌部を率い、紀伊の国の材木を採取し、
畝傍山の麓に橿原の御殿を作った。
また斎部の諸氏を率いて
種々の神宝・鏡・玉・矛・楯・木綿・麻等を作らせ、
そのうち櫛明玉命の孫の出雲玉作氏は御祈玉を作った。
そして、天日鷲命(←おそらく、脱解王)の孫の阿波忌部を率いて
肥沃な土地を求め、阿波国に遣わして穀・麻種を植え、
その郡の名は麻殖(おえ)となった。
続いて更に肥沃な土地を求めて阿波忌部を分けて東国に率いて行き、
麻・穀を播き殖え、良い麻が生育した国は総国と言われ、穀の木の
生育したところをは結城郡と言われ、阿波忌部が住んだところは
安房郡と言われた。やがてその地に祖父の太玉命を祀る社を建てた。
現在の安房神社でありその神戸に斎部氏が在る。また、手置帆負命の
孫は矛竿を造り、その末裔は今別れて讃岐の国に在り讃岐忌部氏と
して年毎に調庸の他に八百竿を奉るのは、その事のしるしである。
Re: 私の好きな邪馬台国九州説:再再スタート - 当世奇妙
2025/03/19 (Wed) 19:31:48
関川・坂両氏の考古学的考察と合致するような記紀などの文献史学のヤマト王権成立論の投稿期待します。
関川・坂論からヤマト王権論を考える(11)記紀が語る王権の支配者 - 当世奇妙
2025/03/14 (Fri) 19:36:33
今回は記紀からヤマト王権の始まる人の投稿大歓迎です。今までの考古投稿と著しく外れる投稿は歓迎しませんが。宜しく!
関川・坂論からヤマト王権論を考える(10)王権の支配者 - 当世奇妙
2025/03/14 (Fri) 10:49:08
箸墓設置からヤマト王権が始まると考えた場合、そのリーダーは誰か?どこの地域の人物かが重要。
当時、河内地域には纏向よりも大きな集落が幾つも存在した。纏向の他地域との交流は東海が50%で他に近江・北陸・山陰。河内は吉備までの瀬戸内各地との交流が多い。河内ー纏向ー東海を結ぶ古代交流道があった。
このような状況下で誰が箸墓建設をリードしたか。この問題の答えは難しい。全体をリードする人材が最大の集落出身者とは限らない。各地の人々を動かすリーダーシップを有する人物は、意外と小さな集落出身かもしれない。あるいはかなり後から参入した人物かもしれない。考古学よりも記紀神話や漢籍などを分析する方が良いのではと考える。
関川・坂論からヤマト王権論を考える(9)振り返り - 当世奇妙
2025/03/14 (Fri) 09:26:28
専門分野の執筆が多忙で昨年12月18日で投稿が止まってしまっていた。今(1)~(8)の投稿を読み返して過去の投稿を思い出してみた。
主なポイントは以下だった。
1)邪馬台国当時、ヤマトには幾つかの集落が出来ていたが、クニとして統治されている状況ではなかった。
2)纏向遺跡の始まりは弥生時代後期の後半である。その最盛期は庄内式末期~布留ゼロ。
3)纏向遺跡には吉備・東海・近江・河内など多くの外来土器が発見される。
4)纏向遺跡に「オウ」は発生するが纏向地域に限られた「オウ」。
5)纏向の外来土器の半分は東海である。山陰・北陸などの日本海の土器もある。
6)纏向を中心に吉備から東海、東日本までを含む大きな動きがあり、魏志に見える「邪馬台国」を遙かに超える動きが纏向中心に起こっていた。
7)纏向では北部九州の土器は発見されていない。
邪馬台国論ではこの事実は重要。
8)纏向遺跡時代、隣接する河内・八尾・大阪では、纏向より大きな集落が発生している。
9)纏向遺跡と河内の遺跡では発見される外来土器は大きく異なる。
10)河内では吉備系の土器が多く、特殊器台、特殊埴輪の破片も出ている。
11)纏向でも僅かに朝鮮半島南部の土器や小規模鍛冶・鉄製品がでるが、ほぼ箸墓築造時期前後のもの。
12)邪馬台国時代、キナイ地方には列島の広い範囲(北九州以外)での交流を行う集落がかなり出来ていて、ヤマト王権の芽が出始めている。
13)奈良盆地には河内ーヤマト・纏向ー東海を結ぶ道路があった。この交通網は王権発祥のキーの一つとなったと想定される。
関川・坂論からヤマト王権論を考える(8)交通路 - 当世奇妙
2024/12/18 (Wed) 14:56:51
奈良盆地を東西に結ぶ交通路の「横大路」がある。
この道路は纏向遺跡の近くを通っている。
この道路は河内と通じ、伊勢にも通じている。
河内ーヤマトー東海を結ぶ道路である。
纏向遺跡の時代、中河内には纏向遺跡を凌ぐ
中田遺跡群があった。
纏向がヤマト王権の発祥となる要素は交通網からも
推察することが出来る。
関川・坂論からヤマト王権論を考える(7)纏向遺跡 - 当世奇妙
2024/12/14 (Sat) 11:39:40
邪馬台国の時代(庄内式期の時代)、纏向遺跡は西日本では比較的大きい遺跡だが、河内、大阪、八尾にはより大きい遺跡があり、北九州の比恵・那珂遺跡は纏向より大きい規模の遺跡である。
纏向には吉備の土器も出ているが、九州の土器は発掘では出ない。纏向遺跡の外来土器のほぼ半数は東海の土器である。山陰の土器も出ていて日本海側との交流が始まっている。
纏向でも僅かに朝鮮半島南部の土器や小規模鍛冶・鉄製品がでるが、ほぼ箸墓築造時期前後のものと言われている。
纏向は東海・日本海地域、河内は瀬戸内・吉備と主に交流したと考える。当然河内と纏向にも密接な交流があったと考えられる。
このような状況から纏向遺跡が倭人伝の邪馬台国と考えることは難しい。
ただし、この時代、近畿地方に列島の広い範囲での交流を行う集落が出ていることは、ヤマト王権の芽が出始めていることを示すと考える。
関川・坂論からヤマト王権論を考える(6)纏向遺跡 - 当世奇妙
2024/10/11 (Fri) 16:34:11
1.纏向遺跡では東海の土器が大半であるが、西日本から搬入される土器は吉備と山陰が多い。吉備以西では、わずかに西部瀬戸内系があるのみ。北部九州系土器発掘では発見されていない。
2,弥生時代の唐子・鍵遺跡の土器も西限はほぼ吉備。
3.隣接する河内では吉備系の土器が多く、特殊器台、特殊埴輪の破片も出ている。河内と纏向では外来土器は大きく異なる。
関川・坂論からヤマト王権論を考える(5)纏向遺跡 - 当世奇妙
2024/09/16 (Mon) 19:14:24
1.纏向には庄内式期(邪馬台国時代)から布留式の時期、方形周溝墓などの低墳丘の墳墓が幾つかある。
2.木棺墓や土器棺墓が見つかるが副葬品はほぼ皆無。
3.石塚などの纏向型古墳は箸墓古墳とは大きな断絶がある。庄内式期には箸墓と関係ある程度の大型古墳は無い。
4.箸墓を築いた勢力は、纏向型古墳を築いた人々とは大きな隔絶がある。
5.庄内式期には土器の交流が活発で、かなり大きな社会的動向があった。
6.この大交流の中心は纏向であった。
7.纏向の外来土器の半分は東海である。
8.山陰・北陸などの日本海の土器も増える。
9.東海の土器は広範囲に拡散し東方にも拡散する。
10.纏向を中心に吉備から東海、東日本までを含む大きな動きがあった。
11.3世紀の邪馬台国を遙かに超える動きが纏向中心に起こっていた。
関川・坂論からヤマト王権論を考える(4)纏向遺跡 - 当世奇妙
2024/08/29 (Thu) 19:37:02
纏向遺跡の始まりは弥生時代後期の後半である。
唐古・鍵遺跡の上流、芝遺跡の近くに設置された。纏向遺跡の南端は芝遺跡に重なる部分もある。幾つもの川筋の間の微高地に幾つもの集落が築かれた。環濠は無い開かれた集落である。庄内式にこの遺跡は発展する。纏向遺跡の最盛期は庄内式末期から布留ゼロのころ。その後は衰える。吉備・東海・近江・河内など多くの外来土器が発見される。列島各地から交易のために集まった人々が集落を築いたのだろう。集落全体の纏め役「オウ」の館もでき、石塚のような古墳も出来る。纏向地域の「オウ」は発生するが、、纏向地域に限られた「オウ」である。この時代は邪馬台国の時代である。
関川・坂論からヤマト王権論を考える(3)弥生時代の奈良盆地 - 当世奇妙
2024/08/22 (Thu) 13:40:26
奈良盆地の弥生時代には、唐古・鍵遺跡を中心とする「おおやまと]地域以外に、北の方向では「ふる」地域、「わに」地域、「さき」地域、南の方向には「そが」地域、「かつらぎ」地域がある。各地域に拠点集落があるが、その拠点集落も地域の「オウ」的存在にはなっていない。従って広域を支配する「王」は存在していなかった。
関川・坂論からヤマト王権論を考える(2)纏向以前のヤマト - 当世奇妙
2024/08/16 (Fri) 19:33:41
弥生時代のヤマト地域の主な遺跡は唐古・鍵遺跡である。
この遺跡は弥生時代前期に始る。中期には多条の環濠が掘削されている。この遺跡は700年も継続する。弥生時代中期初頭には独立棟持柱を持つ大型建物が建てられた。これは「神殿」である。人々は集い、盛大な祭祀が行われた。この遺跡からは各地の土器が出土している。遠隔地では東(トオトウミ、シナノ)、西(北部九州)、近畿(キイ、カワチ、セッツ、オウミ、ハリア)。近隣の近畿では東(オワリ、ミカワ、イガ)、西(サヌキ、キビ)。中国との直接交渉を示す遺物は無い。唐古・鍵遺跡の周辺2キロには小規模の集落が」点在する。これらは弥生時代中期に栄えた。唐古・鍵遺跡の「オウ」はこれら周辺地域も統治した。
奈良盆地は南北27キロ、東西14キロもあった。この中で初瀬川、寺川周辺の「おおやまと地域」
(東西8キロ、南北8キロ)には唐古・鍵遺跡の他、多遺跡、芝遺跡、坪井・大福遺跡、四分遺跡の拠点集落がある。これらの拠点集落は独自に環濠を形成し、銅鐸祭祀を行っている。
従って唐古・鍵遺跡のオウが「おおやまと地域」全体を統治していたとは考えられない。弥生時代には「おおやまと地域」は「クニ」として統治されていなかった。
関川・坂論からヤマト王権論を考える(1)大和・ヤマト・やまと - 当世奇妙
2024/08/08 (Thu) 10:53:41
日本国発祥の地、奈良盆地東南部は「大和・ヤマト・やまと」などと論者によって表現が異なる。
この新しいスレッドで取上げる論者の一人、関川尚功氏は大和の字を採用している。私の持っている氏の出版物でも大和の文字の使用について特に言及はない。一方、もう一人取上げる坂靖氏は「ヤマト」、「やまと」を使用している。氏は奈良県の旧国名は「大和国」だがこれは古代律令国家の命名で、この名称に統一されたのは奈良時代以降であるとしている。氏は律令国家の国名以前の旧大和国を「ヤマト」として使用するとしている。私も坂氏と同じ理由で「ヤマト」を使用する。「ヤマト王権」か「ヤマト政権」かと言う議論がある。私はヤマト地域の勢力は長い間連立政権で、キナイの多くの地域勢力・王の間で揺れ動いて来たと思っている。そのため「王権」よりも「政権」と言う表現をしてきた。ただ王権と政権については色々な解釈・見解があるので、時によって使い分けて行きたい。