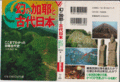東アジア討論室
混み入った議論と一対一の論争は討論室で行いましょう。
投稿の大項目はスレッドで投稿してください。
そのスレッドに対するはレスとして投稿してください。
レスに対する意見もレスとして投稿してください。
スレッド作成での留意事項
●(新規作成の)スレッドには、タイトル(内容の紹介)と自分の名前を入れて下さい。
●みんなの関心事項については、「会」として、スレを(追加で)設けることもあります。
要望事項
●「返信・引用」を使う場合は、不要なところは削除したうえで、お使いください。(1回のみ)
●「返信・引用」は、多用すると、返信の返信となると、誰の発言か分かりにくいので、控えて下さい。
●また、文章では、適当なところで、右側に「改行マーク」を入れて下さい。(一行、45文字程度)
●また、一文(~。)の長さは、長くて3行まで、(およそ、150文字以内:推奨100文字以内)にして下さい。
●文章は、残ることを念頭に、マナーに気を付けて、楽しく(議論は熱く)投稿しましょう。
スレ「FC2のロビー・談話室11」 - 管理人
2024/10/28 (Mon) 15:16:59
.
ここは、スレ「FC2のロビー・談話室10」の続きのスレです。
レスが50を超えたので、新しいスレを立ち上げました。
PS:投稿される方へ
:表紙画面(トップ画面)の投稿枠は、新規スレ作成用です。
:(各スレに対して)投稿をされる方は、
:下記の要領で、投稿をお願いします。
:各スレ(タイトル)をクリックすると、各スレが表示されます。
:画面をスクロールして、一番下まで下げていくと、
:投稿用の枠が出て来ます。
:投稿用の枠に、直接記入、あるいは、コピペで
:投稿できます。
:「環境依存の文字」や「古い文字」が含まれていると、
:投稿が出来ないことがあります。
:メールアドレス・URLの記入は、不要です。
:なお、画像ファイルには、500KBの制限があります。
:「編集/削除キー」(英数4~8文字)は、
:パスワードのことです。
:一度、登録して投稿すると、変更しない限り保存されます。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2025/03/08 (Sat) 10:49:50
 (FB談話室からの転載です。)
(FB談話室からの転載です。)
Kazumi Hirai 東アジアの古代文化を考える会
「新談話室」
1時間 ·・2025年03月07日(金) 14:58
漢籍の再学習:
その22 生成AIは「短里説」をどう判断しているか
「三国志」「魏志」の和訳ローラー作戦が終わったので、
この約2ヶ月「魏志」の和訳で生成AIの Chat GPTが、
Deep learning 技術で学習した成果を検証する為、
短里説の妥当性を聞いた回答が下記の通りです。
過去にもご説明しましたが、
生成AIの回答は、第三者が何時でも再検証出来ます。
正直、私もここまで率直な回答をしてくれるとは思って
おりませんでしたが、齢75歳の私の思考回路は
まだ合理的な考え方が出来ていると判り安堵した次第です。
------------------------------------------------------------
『三国志』(Sanguozhi)、特に
「倭人伝」における「一里」を76メートルとする説は、
歴史的・考古学的に見て問題の多い主張です。
その理由を以下に挙げます。
1. 当時の公式な基準
東漢王朝の時代、一里(里)は約415メートルと
皇帝・光武帝によって標準化されていました。歴史書は
特別な理由がない限り、この公式な尺度に従っています。
2. 他の歴史書との整合性
『三国志』が他の歴史書と大きく異なる尺度を使用している
のであれば、同時代の地理記述との間に矛盾が生じるはずです。
しかし、倭人伝において「一里」が特別な尺度であることを
示す記述は存在しません。
3. 現代の誤解や意図的な解釈
「一里=76m」説は、邪馬台国の所在地(九州説か畿内説か)
に関する議論の中で、一部の研究者や愛好者が主張する
ものです。
しかし、この主張は歴史的根拠よりも、特定の地理的解釈に
合わせるための後付けの理論である可能性が高いです。
4. 古文書における距離表現の曖昧さ
確かに「倭人伝」の距離表記には曖昧な部分があり、さまざま
な解釈が可能ですが、それを根拠に「一里=76メートル」と
するのは恣意的な変更にすぎません。
もし当時の「一里」の尺度が大きく異なっていたなら、
その旨が本文中に明記されているはずです。
結論
「倭人伝における一里は76メートルである」という主張には、
歴史的根拠がなく、合理的とは言えません。
これは歴史的事実よりも、特定の仮説に合わせた
解釈の結果であり、学術的には支持されにくい説です。
*****
2015年 4月15日
古田史学会報 127号
短里と景初
誰がいつ短里制度を布いたのか?
高松市 西村秀己
魏晋朝短里或いは魏西晋朝短里というこの概念は
古田武彦氏が三国志の分析から生み出したものだ。
古田氏によれば、漢代は長里、魏になってから短里を
採用しこれが少なくとも西晋時代まで続いた、という。
ではその魏のどの皇帝の何時の時代に短里制度は
布かれたのか?
これが本稿のテーマである。
※この「短里説」の解説は、
「邪馬台国九州説」の解説の一部です。
「短里説」を含む「邪馬台国九州説」の記事については、
「邪馬台国九州説」の概要を参照ください。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2025/03/01 (Sat) 14:34:01
☆☆☆☆<4月以降の講演会のご案内>☆☆☆☆
『「任那日本府」とは何だったか 』
―会場+オンライン (ハイブリッド)
■日 時 : 4 月 19 日(土) 14 時~16 時半 終了予定
■講 師 : 仁藤 敦史先生 (国立歴史民俗博物館)
■会 場 : 北とぴあ 901 号室(王子駅徒歩 3 分)
『 ガラス玉の産地と分析化学 』―オンラインのみ
■日 時 : 5 月 24 日(土)14 時~16 時半 終了予定
■講 師 : 田村 朋美先生(奈良文化財研究所)
■会 場 : なし(オンラインのみ)
『古代中国帝国主義と列島における二次国家形成』
―会場+オンライン(ハイブリッド)
■日 時 : 6 月 22 日(日)14 時~16 時半 終了予定
■講 師 : 水林 彪先生(早稲田大学名誉教授)
■会 場 : 北とぴあ 804 号室(王子駅徒歩 3 分)
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - 米田
2025/03/01 (Sat) 14:27:14
(つづき)
┌
│・投稿者 小林 一夫
│5週間・2025年01月21日(火) 11:14
│
│倭人伝の「東南 万2千里」の数値をどうやって得たか?
│
│_①郡使は對馬と壱岐を経て九州北岸に上陸し、云々。
│
│以上、「1万2千里」は郡使の【行程】距離である
│わけはなく、唯一の選択肢として、
│天文測量による成果であることは自明である。
│
│_❷郡使一行は史上初めて女王国を訪れるので、倭国の測量も
│重要な任務であったと考えられ、女王國に到達した時、
│【圭表(一寸千里法により距離を正確に測る器具)】で
│計測し、万2千里をはじき出した。
└
:『三国志魏書東夷伝(序文)』を読む限りでは、
:東夷の諸国の使者(と通訳:おそらく帯方郡太守の王頎)が、
:皇帝の前で話したことだけを宮廷の書記官が記録していて、
:その宮廷の書記官が残した記録を中心にして、陳寿は、
:東夷伝の記録を書いたと宣言しています。
:
:ですので、東夷伝には、郡使一行の報告や、ましてや
:倭国の測量の記録などは、(もし、あったとしても)
:陳寿の記録には、出てくるはずはありません。
:
:そして、女王国の「万2千里」よりも、
:『韓伝』〔韓の〕広さは四千里四方ほどである。
:こちらの方に怒っているように見えます。
┌
│〔『三国志』の編者である陳寿は、この東夷伝を〕評して
│〔つぎのように〕曰う。
│『史記』と『漢書』は朝鮮と両越を云々。
│〔この魏の時代には〕東夷のことも〔記録される〕ように
│なった。〔これら東夷の諸国からは〕
│通訳を伴った使者が時々やって来るようになった。
│〔そこで、東夷の諸国からの、通訳を伴った使者の〕話に
│随って〔東夷伝を〕記述した。
│どうして〔このような記事が東夷諸族の〕一般的な
│〔事情を伝える〕ものといえようか。
└
:それでは、そもそも、この東夷伝は、何かを考えてみます。
:「諸国を周(あまね)く観てまわったので
:(『三国志東夷伝』)」-は、実際には誰が観て周ったか。
:この「諸国を周(あまね)く観てまわった」人物が、皇帝
:(宮廷)に対して、うその報告をしていることになります。
:
:諸国を回ったのは、将軍王頎ですし、諸国の使者を都に
:連れて来たのも、帯方郡太守王頎です。
:(おそらく、通訳も王頎がしていたように見えます。)
『三国志韓伝』
:建安年間(196~220)に、云々。
:この後は、倭も韓も遂に帯方〔郡〕に属するように
:なったのである。
:(247年頃)〔帯方〕太守弓遵と楽浪太守劉茂は、
:軍隊を率いて〔韓諸国の臣智たち〕を伐った。
:〔この戦いで弓〕遵は戦死したが、
:二郡はとうとう韓〔族〕を鎮圧したのである。
*****
:つまり、公孫氏を滅ぼして、(楽浪郡と帯方郡は、)
:朝鮮半島を支配下に置きました。そして、倭国も帯方郡に
:属するようになりました。
:これらの成果は、ひとえに、わたくし「王頎」であります。
:
:地図を見て下さい。公孫氏が押さえていた、扶余・高句驪・
:沃沮・濊などを合わせた面積を魏のものにしたと同時に、
:これらとほぼ同じ面積の韓(方四千里)を今回、新しく
:帯方郡の支配下に置くことが出来ました。
:これは、どう見ても、「王頎」の成果に見えます。
:
:つまり、韓(方四千里)も、倭国の「万2千里」も、
:「王頎」の自慢話でしかありません。
─────────────────────────
テーマ:「三国志・東夷伝の信ぴょう性を考える。」
米田喜彦 (2019-04-21) (一部修正)
─────────────────────────
:「三国志・東夷伝の信ぴょう性を考える」ことが、
:「邪馬台国研究の打開」につながると考えました。
:『三国志・東夷伝』に見る、「うそと誇張」。
:そして、この「うそと誇張」を演出したのは誰か。
(仮説):
:「うそ」と「誇張」を演出したのは、太守の「王頎」
:(玄菟郡太守→魏の将軍→帯方郡太守→天水郡太守)だろう。
(理由):
:『東夷伝』「諸国を周(あまね)く観てまわったので云々。」
:に該当する人物は、「王頎」しか見当たらないから。
*****
・「短里説」と「長里説」の論争は、どうなのか。
:以下は、「長里説」が、正しいとしたうえでの話です。
:宮廷の記録係にとって、何が正しいかと云うと、
:「韓(方四千里)」が、面積として正しいかどうかではなく、
:皇帝の前で話された内容を正確に記録したかどうかなのです。
:
:ですから、宮廷の記録係のおかげで、正確に王頎の自慢話が
:記録されたのです。
:それを、「こんな話は、でたらめだ!」と怒っているのが
:陳寿です。
:
:帯方郡太守の「王頎」は、帯方郡太守のままでいられたら、
:最高だったのでしょうが、数年後には、天水郡太守に
:栄転(?)しています。
:(何が良かったのか、悪かったのか、分かりませんが‥‥。)
:一度、記録に残ったものは、そのあと、
:勝手に一人歩きを始めます。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - 米田
2025/03/01 (Sat) 14:24:32
 :小林一夫さんの「短里説」とKazumi Hiraiさんの
:小林一夫さんの「短里説」とKazumi Hiraiさんの
:「長里説」が出揃いました。
:
:「短里説」と「長里説」の論争には、
:あまり、関わりたくはなかったのですが、
:今回、「武英殿二十四史」本「三国志」を
:生成AIの力を借りて、和訳されたとのことで、
:少し興味がありました。
(疑問点01):「方二千里」の解釈の問題
┌
│1.6 面積も実測値ではなく、概念値である。
│
│更に言うと、方二千里という高句麗の面積は、
│千里X千里を意味せず、王城を中心にして甸服までを含む
│(バーチャルな)面積と同じ面積である事を示しているもの
└
:単純に、算数や国語の問題です。
:「方二千里」というのは、「二千里」×「二千里」の正方形
:を意味していると、私は思っています。これを
:「千里」×「千里」として、扱われていることに、違和感を
:覚えました。
(疑問点02):史書に対する接し方の問題
┌3.(FacebookのKazumi Hiraiさんの投稿より)
│陳寿は、「好太王碑」の存在を知らなかったと推定される。
│下記和訳の通り、「高句麗傳」は、高句麗と百済や倭との
│戦争の記録は一切記載しておりません。
└
:説明は難しいのですが、この文章は何かおかしいです。
(疑問点03):底本に対する疑問
:底本は「武英殿二十四史」本「三国志」ということでした。
:以下は、私の勘違いだったことが、判明していますが、
:少し、私の話にお付き合い下さい。
:三国志濊伝には、「方〇千里」という表現はありません。
:(私は、書いてあったと、勘違いをしたものですから、)
:手許にある「東アジア民族1」で、三国志濊伝を調べました。
:そうしたら、「方〇千里」という記載はありませんでした。
:手許の本は、汲古閣本を中心とし、百納本・武英殿本・南監本
:を参照した。と、書かれていました。
:比較できる(和訳)本が、手許にあって、すぐに調べることが
:出来て(自分の勘違いに気が付いて)よかったという話です。
:また、あとで、話が出て来ます。
────────────────────────────
『三国志魏書東夷伝』
(東洋文庫:「東アジア民族史1」より)抜粋
────────────────────────────
:景初年間(237~240)、〔魏の天子は〕大軍隊を派遣して
:公孫淵を伐ち、また潜(ひそ)かに海上より軍を派遣して、
:楽浪郡と帯方郡とを支配したのである。
:(238)その後、海外〔のこと〕は静かで安らかになり、
:東夷〔の国々〕は〔魏に〕屈服したのであった。
:その後、高句麗が叛いたので、また少数の軍隊を派遣して
:征伐し、極遠〔の地〕まで追いつめ、烏丸の骨都を越えて、
:沃沮をすぎ、粛慎の国を踏み破り、
:東の大海にまで進んでいった。
:〔そこに住む〕長老が言うには、
:「〔海のかなたに〕顔つきの異なる人々が住んでいる。
:〔そこは〕太陽の昇るところに近い」と。
:こうして諸国を周(あまね)く観てまわったので、
:国々の掟や習俗、国の大小、その相違などをとり上げ、
:それぞれに名称があれば詳しく記載することができる
:〔ようになった〕。
:〔これらの諸国には、〕夷狄の邦とはいいながら、
:俎豆(そとう)〔を使う儀〕礼がある。
:中国はすでにその〔儀〕礼を失ってしまったが、
:この礼を四夷〔の地方〕で探し求めてみれば、
:〔四夷では〕今なお〔これを〕信じているようである。
:それ故、これらの国々〔のこと〕を順序を定めて記述し、
:その中で同じものや異なったものを列記して、
:前史で充分記録できなかったところに書きついでいきたい。
:
:〔『三国志』の編者である陳寿は、この東夷伝を〕評して
:〔つぎのように〕曰う。
:『史記』と『漢書』は朝鮮と両越
:(注:南越(湖北省地方)と東越(福建省地方)とをさす。)
:とのことを記録しているし、
:後漢時代には西方の羌族のことを採録している。
:魏の時代になると、匈奴は次第に衰退し、
:代わって烏丸や鮮卑が〔勢力を強めて〕いた。
:〔この魏の時代には〕東夷のことも〔記録される〕ように
:なった。〔これら東夷の諸国からは〕
:通訳を伴った使者が時々やって来るようになった。
:〔そこで、東夷の諸国からの、通訳を伴った使者の〕話に
:随って〔東夷伝を〕記述した。
:どうして〔このような記事が東夷諸族の〕一般的な
:〔事情を伝える〕ものといえようか。
────────────────────────────
(つづく)
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2025/03/01 (Sat) 11:04:00
 (FB談話室からの転載です。)
(FB談話室からの転載です。)
・投稿者 小林 一夫
5週間・2025年01月21日(火) 11:14
倭人伝の「東南 万2千里」の数値をどうやって得たか?
_①郡使は對馬と壱岐を経て九州北岸に上陸し、
さらに陸路と水行(河川航路か?)で女王国に至っている。
海峡の横断では、流されたりして航路距離はもちろん測れない。
陸路もたぶん曲がりくねっており、歩測だったとしても、
測量は極めて煩雑であり、とても旅程で実測されたとは
思えない
(通った道路の記述がない。また行程区間には、
_日数で表わされたところさえある!)
以上、「1万2千里」は郡使の【行程】距離であるわけはなく、
唯一の選択肢として、
天文測量による成果であることは自明である。
_❷郡使一行は史上初めて女王国を訪れるので、倭国の測量も
重要な任務であったと考えられ、女王國に到達した時、
【圭表(一寸千里法により距離を正確に測る器具)】で
計測し、万2千里をはじき出した。
(以下、省略)
・投稿者 竹本雅昭
5週間・2025年01月21日(火) 12:25
小林さん久しぶりですね。お元気そうで安心しました。
今後ともよろしくお願いいたします。
・投稿者 小林 一夫
5週間・2025年01月21日(火) 14:28
竹本雅昭 さん、こちらこそ、よろしく。
・投稿者 小林 一夫
1日・2025年02月27日(木) 18:41
『周髀算経』(以下、省略)
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - 米田
2025/02/20 (Thu) 16:59:11
(FB談話室からの一部転載です。)
Kazumi Hirai
6時間 ·・2025年02月20日(木) 08:28
本論に入る前に、さる2月1日に投稿した
「漢籍の再学習:その5」から「その12」までの
投稿について、中間総括をさせて頂きます。
:(A) Chinese Text Projectのデータベース中の(云々)。
:要するに、中国においては、昔も今も「里」は一つのみで
:あり、その基準は昔は皇帝が定め、今は中国政府が定めて
:います。(云々。)
:「里」をメートル法に変換した場合の長さが、周の時代の
:400mから、中華民国の500mまでだんだん長くなって
:きてはおりますが、その途中のある時期に、
:突然76m(短里)になった事は、私が知る限りにおいて、
:中国の歴史上、一度も無いと考えます。
:(云々。)令和の今、
:「メートル」について勝手な解釈が許されるものか?
:「長メートル」や「短メートル」を使う日本人がいるか?
:「三国志」は、「漢書」「後漢書」などなど中国三千年の
:歴史の中で、代々の皇帝に献呈された公文書です。
:この公文書中で、「里」の定義が勝手に解釈されるなどは
:常識的に考えて有り得ない。彼の白鳥博士も内藤博士も、
:その膨大な漢籍についての知識に基づき、「長里」「短里」
:などといった非合理な論考をされていません。
:非合理な都市伝説から脱却し、常識に回帰すべきと考えます。
*****
(ウィキペディアより)
行軍(こうぐん、英: march, traveling)は、
部隊が自らの機動力を以って移動することをいう。
概要
行軍とは部隊が次の目的地に向かって機動することであり、
敵と接触するために機動する戦闘前機動(接敵機動)、戦闘に
おける機動を戦闘機動(戦場機動)として、これは区別する。
大日本帝国陸軍の場合
行軍1日の行程は普通の情況の諸兵連合の大部隊では
昼夜約24kmを標準とする。
*****
「司馬懿(しばい)」(ウィキペディアより)
司馬懿(179年 - 嘉平3年8月5日(251年9月7日))
は、中国後漢末期から三国時代にかけての武将・政治家。
公孫淵の征討
景初2年(238年)、遼東に拠っていた公孫淵が反乱を起こし、
司馬懿は征討を命じられた。
往復に要する時間については
「往路に100日、復路に100日、戦闘に100日、その他
休養などに60日を当てるとして、1年もあれば十分でしょう」
と答えた。
*****
<「後漢書郡国志」>
遼東郡:雒陽(洛陽)の東北3千6百里。
*****
:「司馬懿(しばい)」の頭の中の(行軍の)計算は、
:3600里÷100日=36里/日
:
:1里(400m)×36=14400m=14.4㎞
:1里(76m)_×36=_2736m=2.736㎞
:
:大日本帝国陸軍の場合は、昼夜約24kmを標準とする。
:つまり、魏の洛陽から遼東まで、「東北3千6百里」を
:100日で行軍できると計算しています。
:これは、長里(400m)で概算をしていると思われます。
:
:中国の史書には、行軍の距離は、どこかに書かれているかも
:知れませんが、今回は「司馬懿」の言動から調べてみました。
*****
「水行10日陸行1か月」の謎について
1日の行程は普通の情況の諸兵連合の大部隊では
昼夜約24km(60里)を標準とする。(24000÷400=60里)
水行:7000里+1000里+1000里+1000里=1万里(水行10日)
陸行:
400里×2+300里×2+500里+100里(奴国)=2000里
800÷60=13・・・20
600÷60≒10
500÷60≒8・・・20
100
)_合計31日余
:つまり、
:帯方郡から奴国(邪馬台国)までは、1万2千里であり、
:水行10日陸行1か月(1日60里)である。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2025/02/20 (Thu) 16:26:23
(FC2の管理人の追加です。)
(ウィキペディアより)
陳寿(ちん-じゅ)
(建興11年〈233年〉? - 元康7年〈297年〉?)は、
中国の三国時代の蜀漢と西晋に仕えた官僚。
『三国志』の著者として知られる。
(ウィキペディアより)
裴松之(はい-しょうし、372年 - 451年)は、
中国の東晋末・南朝宋初の政治家・歴史家。
南朝宋が成立すると、元嘉3年(426年)の文帝の代になって、
(云々)。元嘉6年(429年)、文帝に命じられて
三国時代の歴史書『三国志』の「注」(裴注)を作った。
文帝は「これは不朽となるだろう」と松之をたたえた。
また、『晋記』を著述したが散逸している。
(ウィキペディアより)
「好太王碑」
この碑は、好太王の業績を称えるため子の長寿王が作成した
もので、碑文によると「甲寅年九月廿九日乙酉」
(西暦414年10月28日)に建てたとされる。
┌3.(FacebookのKazumi Hiraiさんの投稿より)
│陳寿は、「好太王碑」の存在を知らなかったと推定される。
│下記和訳の通り、「高句麗傳」は、高句麗と百済や倭との
│戦争の記録は一切記載しておりません。
└
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - 石見介
2025/02/20 (Thu) 13:43:43
Kazumi Hiraiさんの、生成AIを利用した『三国志』の翻訳は、興味深いですが、いくつか、気になる点があります。
一つは、陳寿を「編集長」と表現しておられるように、陳寿が、人的、金銭的資源を、十分に有していたと言う、誤解です。
実際の陳寿は、郷党から排斥され、協力者としての門下生や同門の者は、存在せず、金銭的にも、窮乏していました。
二つ目は、AIの問題ですが,『三国志』に詳細な「史註」を付した、裴松之の存在について、どう認識して、陳寿の原文と裴注の部分を、区別して、訳しているかが、見えない事です。
訳文についてのHiraiさんの書き方からは、どうも、陳寿の原文と裴注の部分が、明確に区別されていないように、思われます。
私のPCからは、談話室への投稿が困難なので、どなたか、上記について、ご確認お願いできれば。幸いです。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2025/02/19 (Wed) 21:33:14
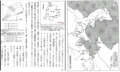 (管理人より)
(管理人より)
:「戸」などの文字で、一部の旧字体が使われていると、
:この掲示板では、その文字が表記されないだけでは
:なく、投稿そのものが、拒否されることがあります。
:ですので、投稿では、旧字体などは、
:なるべく使わないようにお願いします。
(管理人補足)
┌
│(Kazumi Hirai)1.6 面積も実測値ではなく、概念値である。
│方二千里という高句麗の面積は、千里X千里を意味せず、
│
│------------ 高麗伝原文 ----------
│・・・方可二千里,戸三萬。
│
│ChatGPTの和訳
│・・・領土は約二千里、三万戸が暮らしている。
│
│「東洋文庫・東アジア民族史1」の訳文
│・・・[国の広さは]ほぼ二千里四方で、戸数は三万である。
└
┌(管理人補足:「ヤフー知恵袋」より)
│owj********さん 2021/2/17 13:51 2回答
│
│漢文の史記に出てくる方千里(意味:千里四方)は
│各辺が千里の正方形という事を表していますか?
│
│ベストアンサー/新ミュンヘン娘さん
│カテゴリマスター・2021/2/17 15:30
│
│『史記・項羽本紀』「項王自刎」の
│「江東雖小、地方千里、衆数十万人。亦足王也」の
│下りですね。 おっしゃる通り、
│一辺が千里の正方形をいいますが、「方千里」は
│何キロ平米といった具体的な広さを言うのではなく、
│当時の慣用語で「帝王の直轄領」を意味します。
│
│【例】
│『周礼』(夏官、職方氏)に
│「乃ち九の國を辨ず。方千里を王畿(王の直轄地)と曰ふ。
│ 其の外五百里を侯と曰ふ。」
│『孟子』(梁恵王・上)に
│「海内之地、方千里者九(天下に帝国は九つある)」
│
│亭長は「江東は小さいとはいえ大王さまがお治めになるには
│十分な広さですぞ」と彼を励まして(慰めて?)いるのです。
│
│下の方がおっしゃっているのは現代中国の「里」の長さ。
│度量衡は時代と国によって大きく変わります。
│周代に用いられていた1里は76〜77メートルでした。
│それにしても具体的な数値を挙げるのはナンセンスですが。
└
*****
『周髀算経(しゅうひさんけい)』(ウィキペディアより)
『周髀算経』は、古代中国の数学書。
九章算術とともに中国最古の数学書の1つとされている。
本来は単に『周髀』(しゅうひ)と称されており、
蓋天説(周髀説)を説明するために編纂された
天文学のテキストと考えられる。
(wiki:蓋天説では、天と地は平行しており、・・・。)
数学以上に中国の暦学・天文学の発展に対して貢献する
ところが大きかった。
成立時期は不明であるが、『呂氏春秋』からの引用と
考えられる箇所があることから戦国時代末期から前漢に
かけての著作とされ、蓋天説が発生した紀元前2世紀前後の
著作と考えられている。
冒頭に周の周公旦と大夫・数学者の商高の会話が掲げられて
数学と暦の重要性が説かれ、続いて数学・暦学・天文学に
必要な知識が述べられている。
数学としては円周率が3.14に近しいこと、
ピタゴラスの定理やユークリッド幾何学に含まれる内容などが
書かれている、多くは天文のために必要な計算を扱っている。
日本にも遣唐使を通じて伝来し、算道・暦道では教科書と
して用いられた。
その後、北宋の元豊年間には刊本が出され、明以後には
多くの叢書に採録され、中国の数学・暦学における古典と
して重んじられた。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2025/02/19 (Wed) 18:57:57
 *****
*****
(参考)
┌
│1.2 更に正しく理解すべきことは、
│ 「高句麗在遼東之東千里」の語句で、
│ 「千里」が何を意味するかです。
│
│言い替えると、「千許里」「千里許」「略千里」「千余里」と
│表記していない事は、中国語の常識として、千里ちょうど
│Just 1000 miles を意味していると理解すべき事です。
│この文法解釈は反論の余地はないと考えます。
└
<「後漢書郡国志」>
遼東郡:雒陽(洛陽)の東北3千6百里。
玄菟郡:雒陽の東北4千里。
楽浪郡:雒陽の東北5千里。
遼東属国:雒陽の東北3千260里。
(真番郡)
前108年(元封3年)、衛氏朝鮮を滅ぼした漢朝により
幽州刺史部の下に設置され、15県からなり、郡治が置かれた
霅県の位置は長安を去ること7,640里[5]という。
注:『茂陵書』の記載による。計算にもよるがこれはほぼ
_:慶尚道か全羅道の中心もしくは南端に達する距離である。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2025/02/19 (Wed) 17:47:19
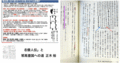 (FB談話室からの転載です。)
(FB談話室からの転載です。)
小林 一夫
1日・2025年02月17日(月) 13:49
短里は『魏志倭人伝』では一番重要な概念ですよ。
『韓伝』も短里です。
「高句麗伝」は長里であることは明らかですが、
『濊伝』は距離に関する記述がなく、丁度、
切り替わる中間地域となっています。
〈距離の単位について〉
❶「韓伝」で韓地は『方4千里』と記述されています。
もし長里(435m)としたら『1900km四方』となり、
朝鮮半島自体が中国大陸と同じ大きさになってしまいます。
→短里(76〜77m)だと『310km四方』となり
韓国の大きさにピッタリ合います。
❷「倭人伝」で帯方郡〜狗邪韓国は『7千里』と記述
されているが、長里としたら『3150km』となり、
帯方郡〜グアムまでの距離となってしまいます。
→短里とすると帯方郡〜釜山辺りでピッタリ。
以上から、韓伝と倭人伝の距離は短里で記述されて
いることは明らかです。
中国は時代と共に寸尺の尺度が違います。
これを無視して論考することはできません。
_①周代(BC10世紀頃~BC4世紀頃)
→「三百歩一里制、一歩は足の長さ25cm」
→「歩」は本来足の長さ(「人足」のサイズ25cm強)だった
から、三百歩一里は25cmx300=7500cm、75m強程度となる。
→これは中国の天文算術書「周髀算経」により1里=約76~77m
と計算できることから証明されている。
これを「短里」という。
*周代の「尺」も24cm程度だったことが知られ、
「歩」とほぼ一致する。
日く「歩は、人足を以て数と為す。独り秦制のみ然るに非ず」
と。(史記、秦始皇本紀、注)
❷秦・漢代「六尺一歩の制」→周の里の6倍に(長里)
■六尺、歩となす。(史記、秦始皇本紀)、尺を記す出土物
(物指)から一尺は23.04cmとされ、従って一歩は138cm、
一里300歩で約415mとなる。
尺は身体のサイズで時代につれ次第に伸びていく。
漢代では一里435m(一尺は24cm)。
→始皇帝は五行説に立ち「六」を好み「6尺1歩制」を敷いた。
これは右足を地に付けてから、再び地に着くまでの距離とほほ
同じ。(*静歩・動歩の基本的な考えは不二井新平氏による)
❸魏・西晋朝→周の里制(76~77m)採用。
→『魏志倭人伝』の「里」はこの長さ、
すなわち「短里」となる。
古法(夏・服・周)に復帰。
※陳寿は「夏王朝・周王朝の聖人を挙げたうえ
「陛下(西晋の第一代武帝)、古聖に厳密に従う」と記す。
『1寸千里法』による短里76〜77mが絶対尺度
(地球の大きさと北回帰線へ垂直入射する太陽光線で決まる)
であり、周の時代から、距離の単位として使われてきました。
但し秦の始皇帝が六を好んで短里を6倍した長里を使ったが、
暫定の相対尺度に過ぎません。
陳寿の魏、晋時代には、再び絶対尺度である短里に戻されて
います。
〈圭表について〉
郡使一行は史上初めて女王国を訪れるので、倭国の測量も
重要な任務であったと考えられ、女王國に到達した時、
【圭表(一寸千里法により距離を正確に測る器具)】で帯方郡
と女王国の2地点間の南北距離を計測し、東西方向も加味して
直線距離の万2千里をはじき出したとしか考えられません
(根拠は、添付した4番目の説明文をお読み下さい)。
※:青写真・設計図、地図、テキストのイラストのようです
Kazumi Hirai
1日・2025年02月17日(月) 14:08
「三国志」「魏志」第30巻の中の、14の伝書において、
バラバラな里の基準が用いられているとの説に、
合理性がありましょうか?
陳寿は認知症だったのでしょうか?
また「魏・西晋朝→周の里制(76~77m)採用」を示す
史書などの公式書籍をお示し頂きたく
小林 一夫
1日・2025年02月17日(月) 20:16
Kazumi Hirai さん、
陳寿は、魏使の報告書を見て記述しただけです。
中国は時代と共に寸尺の値が異なります。
魏・西晋時代は、周の時代に戻って短里になりました。
だから魏時代に書かれた『魏略』には、しっかりと
帯方郡〜女王国は【万二千里】とありますよ。
※:テキストの画像のようです
Kazumi Hirai
1日・2025年02月17日(月) 20:47
もしも、魏書30巻が複数の時代にわたり書かれていたので
あれば、貴方の説は納得出来ましょうが、残念ながら、
当該文書は、陳寿が1代で書き上げたものと考えるのが
合理的であり、複数の著者により書かれたという根拠が
無い限りは、この30巻で、里について、公里と短里が
混在しているとの説は非合理であると断じざるを得ません。
小林 一夫
1日・2025年02月17日(月) 21:19
Kazumi Hirai さん、
魏志倭人伝は、『魏略』逸文をほほ丸写しですので、
魚けんが書いたともいえますよ。
(陳寿が1代で書いたとは言えない!)
※:「第三章『魏志』里程記事を読む‥‥‥144」という
_:テキストの画像のようです
Kazumi Hirai
1日・2025年02月17日(月) 21:44
釈迦に説法するつもりは、更々有りませんが、
三国志の魏誌に限定しても、陳寿が「魏略」からの引用を
明記したのは、次の8書です:辰韓傳、弁辰傳、
東沃沮傳、魏畧曰、夫餘傳、韓傳、弁辰傳、倭人伝
方や、魏書からの引用を明記したのは、
次の2文書:烏丸鮮卑東夷傳、鮮卑伝
残念ながら、魏略や魏書は既に失われており、完全に
黒白つけることは不可能ですが、魏略や魏書が、複数の時代に
わたり書かれたものである事を証明出来るものか?
Wikipediaによれば、魏略の著者は魚豢であるとするのが
定説です。
それが事実とすれば、ある生きた人間が、皇帝が定めた
里の規定が複数の時代で変わって行く最中に生きることが
可能であったのか?
常識的に判断して、魏略は同一時代に書かれ、その中で
里は統一して用いられたと考えるのが合理的であり、
魏略8文書の中で、倭人伝のみが短里だという主張は、
根拠薄弱と言わざるを得ません。
小林 一夫
1日・2025年02月17日(月) 22:24
Kazumi Hirai さん、韓伝も短里ですよ。
その中の『方四千里』をどう解釈するのか?
(長里なら朝鮮半島が中国大陸より大きくなる?)
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2025/02/19 (Wed) 17:41:27
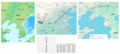 (FB談話室からの転載です。)
(FB談話室からの転載です。)
Kazumi Hirai
13時間 ·・2025年02月17日(月) 09:44
漢籍の再学習:その10
「三国志」「高句麗傳」が示す「公里」の統一的準拠
(短里説の棄却)および「非騎馬民族」の証
「東夷伝」に続き生成AIの力を借りて、「高句麗傳」の和訳を
お知らせします。Chinese Text Projectの底本は
「武英殿二十四史」本「三国志」です。
下記で刮目頂きたい点は
1.「鮮卑伝」と同様に、里はあくまでも公里(標準里)に
_準拠しており、短里などは使っていない事。
1.1注意すべき事の第1は、この高麗伝においても、里はあくま
_でも、皇帝が定めた公里(=標準里)が使われていること。
1.2 更に正しく理解すべきことは、「高句麗在遼東之東千里」
_の語句で、「千里」が何を意味するかです。
言い替えると、「千許里」「千里許」「略千里」「千余里」と
表記していない事は、中国語の常識として、千里ちょうど
Just 1000 miles を意味していると理解すべき事です。
この文法解釈は反論の余地はないと考えます。
1.3 常識的に考えれば、「千里」が、実測距離ではないことは、
_小中学生でも理解出来る話です。
ある人が、「東京からソウルまでは1000km」ですといった
として、だれがそれを実測距離だと信じるでしょうか。
1.4 では何故、陳寿は「千里」と書いたのか?
嘘か?? その答えは、陳寿が、九服の制に従って
距離を表記したという事です。
即ち、遼東は、衛服(王城から3,500里)に位置するとされ、
高句麗は夷服(王城から4,500里)に位置するとされるので、
遼東から高句麗は(4,500-3,500=1,000)で計算された
(バーチャルな)理論値の千里であるという事です。
1.5 「九服の制」はそれほど現実離れした概念ではなかった。
洛陽に暮らす、宮廷の人々にとって、夷狄とのリアルな境界は、
秦の始皇帝により建設が着手された「万里の長城」と考えられ
ます。
詳しくは、次回の投稿「扶余伝」で、述べますので、詳細は
割愛しますが、定説では中国の戦国時代末期(紀元前3世紀)に
成立したとされる「周礼」中の「九服の制」は、帝国の支配地
は長城までという共通認識の基で、「衛服」まで
3,500里として組み立てられたと、私は考えます。
洛陽から遼東までは、理論値で(3,500里1,455km)
Google map で測ると1,085kmで、その誤差は約25%と、
それほど現実離れした距離ではないといえます。
また、上記 1.4の解釈による遼東から高句麗の都までの
距離千里(416km)は、現実の距離(約398km)との誤差は
1割未満ですが、これも、現実離れしてはおりませんが、
偶然の産物とも言えます。
1.6 面積も実測値ではなく、概念値である。
更に言うと、方二千里という高句麗の面積は、
千里X千里を意味せず、王城を中心にして甸服までを含む
(バーチャルな)面積と同じ面積である事を示しているもので、
実測の面積(2 x 416 x 416 = 346,112km2)を意味していない事も
注意すべき点です。
言い替えると、「高句麗の領地(方二千里)はかなり広い」と
意味しているだけで、観念上の面積以上のものでは無い、と
解釈すべきものと、私は考えます。
1.7 短里説は棄却されるべき。
いずれにせよ、短里の場合の計算値 5,776km2を
山梨県の面積 4,465km2と比べれば判る通り、
短里を用いてはいない事は明白です。
添付図Google Mapは 遼東(中国遼寧省錦州市の北鎮市)から
高句麗の都(丸都城)までの距離を測ったもので、
約398kmで、公里の千里(416km)との誤差は、1割未満
であり、短里の千里(76km)では無いことは明白です。
2.高句麗は、いわゆる騎馬民族では無かった。
2.1 下記の記述の通り、定住し、城郭を築いていた。
「其地勢多山險,随山谷而居,依阻險阻,以作城郭。」
2.2. 畑作を営んではいたが、生産性は低かった。
_又、貴族は農民から税として穀物を収奪していた。
「無良田,雖力佃作,不足以實口腹」
「其國中大家不佃作,坐食者萬餘口,下戸遠擔米糧魚鹽供給之」
2.3 「高句麗伝」には、その記載が有りませんが、
_現存する物的証拠である「好太王碑(414年)」の碑文では、
_水軍の戦いや、歩兵による城攻めが戦の主体で有った事が
_示されている。
「軍□□首、攻取壹八城、臼模盧城、各模盧城、幹弖利城、
□□城、閣彌城、牟盧城、彌沙城、□舍蔦城、阿旦城、古利城、
□利城、雜彌城、奧利城、勾牟城、古須耶羅城、莫□城、
□□城。分而能羅城、場城、於利城、農賣城、豆奴城、沸□□
【第二面】利城、以下省略」
2.4 但し、騎馬による戦いのスキルは高かった
其馬皆小,便登山。國人有氣力,習戰鬪
2.5 上記を勘案すると、「高句麗伝」は、江上波夫の
_「騎馬民族征服王朝説」にとっては、
_極めて不都合な文書であると考えます。
高句麗で話されていた古代朝鮮語と古代日本語の関係に
ついては、種々の説がありますが、言語学会で定説として
認定されているものは一つも無く。一個人の
思いつき的な言説は排除されるべきと考えます(私見)。
3.陳寿は、「好太王碑」の存在を知らなかったと推定される。
下記和訳の通り、「高句麗傳」は、高句麗と百済や倭との戦争の
記録は一切記載しておりません。
┌(管理人補足:wikiより)
│陳寿(ちんじゅ)
│(建興11年〈233年〉? - 元康7年〈297年〉?)は、
│中国の三国時代の蜀漢と西晋に仕えた官僚。
│字は承祚(しょうそ)。『三国志』の著者として知られる。
└
4.後漢から魏までの力関係を纏めると
4.1 西暦32年(光武帝 の建武8年)高句麗は朝具し、
_漢に帰順した。
4.2 高句麗は、その後度々、玄菟郡や楽浪郡を脅かした
4.3 霊帝の熹平年間(172年~178年)に、玄菟郡に帰属
4.4 遼東に勢力を拡大した公孫氏との関係については、
_公孫度に援軍を派遣した事が記載されているのみで。
_それ以後の事案は記載が無い。
------------ ChatGPTの和訳 -----(「三国志」「高句麗傳」)
高句麗は遼東の東千里に位置し、
南は朝鮮および濊貊(かいばく)、東は沃沮(よくそ)、
北は夫餘(ふよ)と接している。
都は丸都山のふもとにあり、領土は約二千里、三万戸が
暮らしている。
地形は大きな山々と深い谷が多く、肥沃な平野がない。
人々は谷沿いに住み、渓流の水を飲んで生活している。
良い田畑はなく、一生懸命耕作しても食糧が十分に得られない。
風習としては、食事を質素にしながらも、
宮殿や住居の建設を好む。
(以下は、転載を、省略しました。)
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2025/01/31 (Fri) 21:22:08

(FB談話室からの転載です。)
小原理一郎 1月20日 23:17 ·
<東アジアの古代文化を考える会>特別研究会」案内
特集 <伽耶と古代日本>
> 開催日 2025年3月22日(土) 午後1;00~午後6時
>場所: <杉並セシオン>第8集会室
最寄りの駅 丸の内線
【東高円寺駅】または【新高円寺駅】徒歩5分
参加費:資料代と会場費 500円
研究会の 趣旨は、
> 4月仁藤敦史氏が4月19日(土)<任那日本府>という
テーマで伽耶諸国を取り上げます。
近著【加耶・任那】(中公新書)は
12月出版されたばかりでベストセラ-となっています
2022年歴博主催【伽耶】特別展では仁藤氏は
カタログ執筆者となって最新の発掘資料に接しています。
これは<伽耶諸国>を取り上げる好機と思い、【特集】
【伽耶と古代日本】というテーマで特別研究会を開催して
最新の伽耶諸国の研究成果を取り込んだ研究発表をしたいと
思います。
発表者は以下の通りです。
1小原理一郎__1;30~2;50
【伽耶文化の考古学的究明】
朝鮮半島の最近における考古学的な発掘と研究発表は
かなり掘り下げられており、
過去の研究蓄積のみならず最新の研究成果を取り込んだ
研究発表が続いている。
過去に東アジアの古代文化の会では2回
(2002年11月と2010年9月)にわたる百済、伽耶地域の
遺跡見学を行ったことがあり、早くから伽耶の歴史的な
重要性については訴えてきた。
朝鮮3国時代;高句麗、新羅、百済と伽耶諸国と古代日本
成立期倭国との関係を考古学的な資料;、博物館で入手した
図録などの資料と伽耶地域遺跡の現地調査など踏まえて
考古学な紹介をする。
特に伽耶諸国は統一国家成立に至らなかったが、古代日本の
国家成立と文化のために東アジアの古代馬匹文化、高句麗、
古代中国;漢;魏、晋の文化、技術、とりわけ、鉄技術、
馬匹文化は伽耶人と在地の倭人が共同で介在し日本列島に
伝播させたことが考古学的に証明される。
2,竹本雅昭__3;00~4;00
【 狗邪韓国の「出自」と「行方」】
朝鮮半島南部、現在の金海地方に存在していた狗邪韓国の
とらえ方には、不明な点が多い。
鉄資源があったこと、首露王伝説、大成洞古墳群などの地だが、
「出自」不明の謎めいたゾーンである。
韓国を代表する古代史家李丙壽氏は、彼らは楽浪郡から
逃れた人々であって、逃避行の際にうたわれた古歌が
「アリラン」と述べている。彼らの墓地である
良洞里遺跡を中心に考古学面から狗邪韓国を論じたい。
3.赤尾恭司__4;10~5;00
【『加耶/任那』(仁藤淳史2024)を批判的に読む】
古代史関係の論考で気になるのは、①史書にある
「国」「国家」をそのまま用いており概念が不明であること、
②例えば、広開土王碑の「碑文にみえる「倭」がヤマト王権を
背景とすることは疑いにくい」(本書p45、46など)など、
古代の日本列島ではヤマト王権が唯一無二と論証抜きで
議論していることである。そこで、この二つの視点を
軸に、本書の内容を批判的にまとめてみたい。
4,下山繁昭__5;10~6;00
【任那の成立について】
日本書紀の記述と高句麗、鮮卑族の動きと周辺諸国の
動きと合わせて考えると倭国ナショナリズムに惑わされず
冷静な目で見る見方が必要ではないかと思えてくる。
戦前から知られている倭国の力が増して来て半島南部に
進出し中国南朝に朝貢するまでになつたとしているが、
日本書紀の細かな分析だけでも違った世界がある。
又古墳時代、弥生まで遡ると朝鮮半島南部には
インドのタミール地方の文化が流れ来ている。
タミールの影響は一部の学者しか分析していないが
歴史を再構成してみる必要がある。以上
*****
藤盛 紀明
1週間・2025年01月21日(火) 13:39
当会は1989年に「講演会・伽耶シリーズ」を行い、
同年7月に<シンポジウム>
「伽耶は何故滅んだかー日本古代国家形成史の再検討」
を実施しました。
「東アジアの古代文化を考える会」にとっては
「伽耶」は非常に重要な課題ですね。
当会が出版した『伽耶はなぜほろんだか』は
大変人気の本となり、再販されました。
*****
藤盛 紀明
1週間・2025年01月21日(火) 15:47
:増補複本された『伽耶はなぜほろんだか』
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2025/01/31 (Fri) 20:28:29
(FB談話室からの転載です。)
東アジアの古代文化を考える会 · 4時間 ·
: Naoko Urushibara ·・2025年01月31日(金) 16:07
【2 月の講演会(片岡宏二先生3 回連続講演会 2 回目)の
ご案内】
『ヤマト王権への対応さまざま-九州の古墳時代前期・中期―』
―オンラインのみ
■日 時 : 2 月 15 日(土) 14 時~16 時半 終了予定
■講 師 : 片岡 宏二 先生
(小郡市埋蔵文化財調査センター 所長)
■会 場 : なし (オンラインのみ)
■講師の言葉
第 1 回目の講座はいかがでしたか。
事前に配布したレジュメを読まれた方から
「今までの私の邪馬台国=九州説は一般的な通俗の九州説
でしたが、これを読んで目が覚めました。」という
お褒めの言葉をいただき、俄然やる気を出しています。
次回は 4・5 世紀の、筑紫からみた古墳文化を扱います。
多くの研究者が、朝鮮半島との関係、ヤマト王権の九州進出と
言ったグローバルな歴史観でとらえています。
けれども、私は筑紫にとどまって、じわりと入ってくる
古墳文化を受け入れる立場で見たいと思います。
劇的な変化でないところは、皆様には面白くないかも
しれませんが、逆にそういう視点もあるのだと
新鮮に思われる方もおられることを期待しています。
■参加料:ZOOM 視聴代:1000 円
■照会先:稲垣 TEL 080-4097-1757
E-mail inagaki34214590@yahoo.ne.jp
■聴講・申込方法
:必ずメールによるお申込みをお願い致します。
・ZOOM 聴講希望者は 2 月 14 日(金)までにメールにて
「氏名、メールアドレス、携帯番号(当日の連絡用)」を
添えて下記宛に申し込んで下さい。
メール申込先:稲垣 inagaki34214590@yahoo.ne.jp
_1. 参加料 1000 円を下記までお振込み下さい
みずほ銀行九段支店 店番号 532 普通預金 口座番号 8043715
口座名 東アジアの古代文化を考える会 事務局長 嶋田晋吾
_2. 視聴方法:講演前日までに指定アドレスに講演会用の
ZOOM の URL と資料が送付されます。
☆ ☆ ☆ ☆ <3月以降の講演会のご案内> ☆ ☆ ☆
『 筑紫豪族磐井の新解釈ー九州の古墳時代後期― 』
( 3回連続講演会最終回) ―オンラインのみ
■日 時 : 3 月 29 日(土) 14 時~16 時半 終了予定
■講 師 : 片岡 宏二 先生
(小郡市埋蔵文化財調査センター 所長)
■会 場 : なし (オンラインのみ)
『「任那日本府」とは何だったか 』
―会場+オンライン(ハイブリッド)
■日 時 : 4 月 19 日(土) 14 時~16 時半 終了予定
■講 師 : 仁藤 敦史先生(国立歴史民俗博物館)
■会 場 : 北とぴあ 901 号室 (王子駅徒歩 3 分)
『 ガラス玉の産地と分析化学 』―オンラインのみ
■日 時 : 5 月 24 日(土)14 時~16 時半 終了予定
■講 師 : 田村 朋美先生(奈良文化財研究所)
■会 場 : なし(オンラインのみ)
『古代中国帝国主義と列島における二次国家形成』
―会場+オンライン(ハイブリッド)
■日 時 : 6 月 22 日(日)14 時~16 時半 終了予定
■講 師 : 水林 彪先生(早稲田大学名誉教授)
■会 場 : 未 定
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2025/01/14 (Tue) 22:05:00
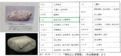 (FB談話室からの転載です。)
(FB談話室からの転載です。)
・大野克浩
20時間·2025年01月13日(月) 20:43
一度は行かねばならないと思っていた岡山の楯築墳丘墓に
行ってきました。
全然知らなかったのですが、顔のついた弧帯文石の他に、
もう一つ小さな弧帯文石があり、熱を加えられ割られている
そうですね。
(画像1 画像2の顔のついた弧帯文石は楯築神社のご神体)
以前、考古学は実証主義の学問であり、神話とは切り離して
考えると言ってた考古学者さんがおられました。
が、新聞も雑誌もテレビもネットもなかった時代、古代人の
拠り所は神話であったはずで、その古代人の眠る遺跡を発掘
する人が神話を否定するというのはいかがなものでしょうか。
顔のついた弧帯文石を私なりに神話で読み取るならば、蛇神、
つまり大物主と呼ばれた人物、あるいは神の姿だと思います。
そしてその大物主が焼かれ割られていること、この楯築墳丘墓
の近くに来た吉備津彦は姉のモモソヒメが大物主と結婚、
またモモソヒメの不思議な死に三輪山に住む蛇、
つまり大物主が絡むわけで、神話に寄り添えば、
何やら話が急に活きてくる様に思います。
・竹本雅昭
11時間・2025年01月14日(火) 05:48
この年は墳丘墓のされ、築造年は200年頃という説も
あるようですが、いつ頃作られたとお考えですか?
・竹本雅昭
10時間・2025年01月14日(火) 06:55
蛇は今年の干支、めでたい話ですね.小学生のころ遠足で
錦帯橋のある岩国白蛇神社に行った思い出があります。
蛇皮を財布に入れておくと,お金がたまると友人が
言っていました。
蛇は越人のトーテムでもありますので、被葬者の方は
越系だったのでしょうか?
難升米説などもありますが、ご神体が蛇とすると
在地の方のように思えますが…
・大野克浩
10時間・2025年01月14日(火) 07:12
竹本雅昭 さん
私は楯築は2世紀後半ごろという説を支持しています。
この双方中円墳という特異な形の、その最終にして最大の
墳墓が大和の櫛山古墳で、崇神陵(行燈山古墳)にべったり
隣接しています。
櫛山古墳は崇神の肉親、例えば母親とかではないかと想像
しています。
本文の続きですが、このことも、吉備津彦に出雲や吉備の
征伐の詔を発した崇神、大物主の霊を恐れ大神神社を
創建する崇神とも絡み、楯築の被葬者を明らかにできる
要素ではないかと思っています。
*****
(補足の表)
:神の使いのいろいろ:神社ふしぎ探検(外山晴彦著)より
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2025/01/13 (Mon) 22:04:49
(FB談話室からの転載です。)
・藤盛 紀明
1週間·2025年01月02日(木) 16:36
おめでとうございます。
1月から3月までは片岡さんの九州古代史通史
3回シリーズです。
九州、吉備、出雲、東海の古代史通史を再検討すれば、
ヤマト政権の成立プロセスに迫れると思います。
・Yasushi Tatumi
1週間·2025年01月02日(木) 16:53
藤盛 紀明 様
昨年からZOOM の講演会にさせて戴いています。
妄想、スピチュアル的なものがない事に好感が持てます。
管理人のお陰だと思っています。
・藤盛 紀明
1週間·2025年01月03日(金) 19:09
タツミさん 参加ありがとうございます。
・小原理一郎
6日·2025年01月06日(月) 22:41
仁藤敦史氏の講演会が4月19日(土)予定されています。
早速、最新著作
【加耶・任那】ー古代朝鮮に倭の拠点はあったか<中公新書>
2024年12月15日3版:を年末に購入して読んでいます。
・小原理一郎
6日·2025年01月06日(月) 22:45
下山さんから、これを機会に【伽耶】の特別研究会を
しないかという話が急に持ち上がりました。
仁藤先生の講演会前に、勉強会を開催することにしました。
2022年に歴史民俗博物館で【加耶】展が開催されています。
その時の図録に仁藤先生が記録解説があります。
・小原理一郎
6日·2025年01月06日(月) 22:47
手元には1992年国立東京博物館の【伽耶文化展】の
図録があります。
・小原理一郎
6日·2025年01月06日(月) 22:53
「さらに韓国のソウル中央博物館、金海博物館、晋州博物館、
_広州博物館、,全州博物館、扶余博物館、光州博物館など
_伽耶関係の遺跡の出土物が掲載されていますので、
_それを比較調べることができます。」
小原理一郎
6日·2025年01月06日(月) 22:57
赤尾さん、下山さんそして小生、小原の3人で
特別研究会を開催すべく会場手配中です。
3月22日(土)杉並区の会場です。
仁藤先生の最新著作と2022年の歴博の図録が
最新のものかと思います。目下勉強中です。
・竹本雅昭
6日·2025年01月07日(火) 11:26
小原さんは、伽耶関連の資料を現地の博物館を訪問され、
お持ちのことと伺っております。
いい企画と考えています。
・小原理一郎
1日·2025年01月11日(土) 22:32
「仁藤敦史さんの近著【加耶.任那】(2024年12月刊)
_読了しました。
_<日本書紀>の注釈が重要な資料ですが、その解釈:
_改竄されておるので採用と利用が<柔軟>になります。
_歴史は改竄されるものであるが鉄則ですが、
_あとは考古学的な比較研究と物的証拠だけです。」
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - 石見介
2025/01/10 (Fri) 21:33:05
土田章夫さんの、youtubeを、拝読しました。
私は、遺伝人類学のデータから、騎馬民族渡来説には、否定的で、「来たのは騎馬民族ではなく、馬飼部だ」と、言っていますが、勿論、部の設置は、4世紀以降でしょうから、正確には、後に馬飼部に組織される人々の祖先の渡来という意味です。
その渡来時期が、卑弥呼の時代に遡る可能性は、考慮する必要がある、と感じました。
本論の公孫恭が、大和朝廷の祖先だとか、扶余族の渡来については、遺伝人類学的に成立し得ない、という点については、自説を変更する必要は、感じませんでした。
基本的に、遺伝人類学に対する誤解があるように思いますが、これは、人類学者側が、きちんと説明していない事に、原因があるように、思われます。
他に、資料批判の問題もありますが、それ以上に、言語学や、神話学を含む文化人類学も、古代史愛好家諸氏に、理解されていないように、私には、思えます。これは,土田氏というより、私も含めた一般の古代史愛好家というか、ファンの、宿命かもしれません。
卑弥呼論 - 当世奇妙
2025/01/06 (Mon) 19:45:30
倭の五王のスレッドで卑弥呼は誰かなどで盛り上がっている。出来れば「卑弥呼とは何か?誰か」などの「卑弥呼論」スレッドが期待される。
これは大変興味深いテーマである。
安本氏の数理学的推論の卑弥呼=天照大神論は成立するかも興味ある。
米田さんが今までの「卑弥呼論」を整理して頂けるとありがたい。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2025/01/02 (Thu) 12:08:18
(FB談話室からの転載です。)
東アジアの古代文化を考える会「新談話室」
・諸岡 かおりさんの投稿
2時間·2025年01月02日(木) 09:14
意外なところで、かねてから疑問だった武内スクネとも
解釈されている弥五郎どんの正体にせまれた。
720年の隼人征伐の影響はかなり大きかったと思われる。
阪急交通のツアーのガイドさん、とてもユニークな方で、
インドでサイババに会ったときの時の不思議な体験談を
話してくれた。
これから、高千穂神社。
・土田章夫
2時間·2025年01月02日(木) 09:36
諸岡かおりさま 明けましておめでとうございます。
宮崎にいらっしゃるなら、ぜひ宮崎市内の阿波岐原
(あわきがはら)にある「みそぎ池」を訪問されることを
お勧めします。
ここは天照大神の生誕地で日本一のパワースポットです。
シーガイアの近くです。
また時間があれば生目古墳群史跡公園もお勧めです。
私は生目一号墳を卑弥呼並びに天照大神の墓と想定しています。
生目一号墳は道が未整備で公開されていませんが、
付近からお参りするとご利益満載だと思います。
生目古墳群には日向三代の古墳があると考えています。
・諸岡 かおり
2時間·2025年01月02日(木) 09:44
土田章夫 明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
今回は10名ほどの阪急交通のツアーなので、
みそぎ池には行けませんが、生目古墳群は2023年に
レンタカーで、宮崎から佐賀県の主人の実家に行った時に
行きました。どうしても
ヤマトとの関係がどうだったのか、考えたくなりますね。
・土田章夫
1時間·2025年01月02日(木) 09:52
宮崎市の古墳と纏向の古墳は相似形です。ご参考まで
●生目1号墳(137m)は箸墓古墳(278m)と1対2
●生目3号墳(143m)は
______行燈山古墳(崇神天皇陵)(242m)と 3対5
●生目22号墳(101m)は
______渋谷向山古墳(景行天皇陵)(300m)と1対3
●檍(アオキ)1号墳(52m)は
______ホケノ山古墳等纏向の5基の 古墳は相似形
・諸岡 かおり
15分·2025年01月02日(木) 11:30
土田章夫 ありがとうございます。
実は、私もそれが気になっていました。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2025/01/02 (Thu) 12:07:00
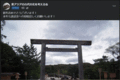 (FB談話室からの転載です。)
(FB談話室からの転載です。)
東アジアの古代文化を考える会「新談話室」
・諸岡 かおり
2時間 · ·2025年01月02日(木) 09:02
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
・岡嶋 隆司
2時間·2025年01月02日(木) 09:14
明けましておめでとうございます
本年も宜しくお願いします
・諸岡 かおり
2時間·2025年01月02日(木) 09:25
いつもいいね!ボタンをくださり、
投稿の励ましになっています。
新幹線で新横浜から南九州に向かう途中、岡嶋さまのこと
が思い出され、実は岡山の遺跡巡りをまだしていないので、
行きたいなあと思っております。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
・岡嶋 隆司
2時間·2025年01月02日(木) 09:48
諸岡 かおり さん、御来岡の際はご連絡ください。
日程が合えば車でご案内します。
・諸岡 かおり
36分·2025年01月02日(木) 09:48
岡嶋 隆司 ありがとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2024/12/29 (Sun) 11:11:23
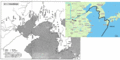 (FB談話室からの転載です。)
(FB談話室からの転載です。)
東アジアの古代文化を考える会 「新談話室」
土田章夫さんの投稿
·23時間·2024年12月28日(土) 11:02
邪馬台国の船は中国まで行っていた
洛陽まで行っていたか?
『魏志倭人伝』の「持衰」の文の初めに「其行来渡海詣中国」
(その一行が海を渡って中国に来るときは)とあります。
すなわち邪馬台国の船は中国に行っていました。
少なくとも帯方郡までは行っています。
その先、海岸に沿って進み、渤海を南北に縦断して中国まで
行っていた可能性もあります。
渤海を南北に縦断したところには島が点在しています。
当時の魏の都は洛陽です。
洛陽には黄河の支流が流れていて、黄河は渤海に注いでいます。
現在黄河の河口は泥が堆積していて、大型船は航行できません。
当時、渤海から直接、船で黄河に行けたかよくわかっていません
が(今調べています)、一旦、陸行してから黄河を利用して
洛陽に行った可能性があります。
従って邪馬台国の船が直接、洛陽まで行けたとは思いません。
難升米(ナシメ)はこのルートを通ったのではないかと
考えています。
また邪馬台国には南に連なる島があります。
種子島、南西諸島、奄美黄島、沖縄まで航路を持っていたと
考えられます。
邪馬台国は沖縄から九州を経て朝鮮半島の海岸を通って
中国までの約2500㎞に及ぶ航路を持っていたことになります。
邪馬台国は大海洋国家でもありました。
私は古代史ノンフィクション作家で邪馬台国宮崎市説を
提唱しています。
地図は邪馬台国宮崎市を想定した邪馬台国の航路です。
*****
岡嶋 隆司・22時間·
2024年12月28日(土) 11:18
私は、直接渡航したと言うより、寄港地で
船を乗り換えて行った可能性を考えています。
土田章夫・17時間
2024年12月28日(土) 16:31
岡嶋さま
帯方郡の太守劉夏が洛陽まで送り届けていますから、
ここからは魏の船を使ったと思います。
*****(参考)
[PDF]邪馬台国宮崎市説からヤマト王権の成立を考察する …
ID 10472 土田章夫 2023年4月5日 1.はじめに
ヤマト王権の成立については様々な説があるが、
邪馬台国の場所が特定していな現在、
根拠を持ってヤマト王権の成立を論ずることは出来て …
https://zenyamaren.net/wp-content/uploads/2023/04/yamaren23-202.pdf
「水運(すいうん)」(ウィキペディアより)
:水運(すいうん。)とは、水面を利用した運送のこと。
:水面を利用した人の運送(人の移動)や貨物の輸送のこと。
:別の角度から言うと、船舶類を利用した運送のこと。
:歴史
:アジアに目を向けると、中国では、すでに紀元前4世紀ころ
:までには、内陸水運を用いて大都市間で食糧の運送が開始
:されており、その後大運河(京杭大運河)の本格的な建設も
:行われ、それにより本格的に内陸水運が一層推進され、
:6世紀にはそれが完成した。
:中国では西暦200年ころには複数のマスト(帆柱)を
:立てた船舶で海運を行っていた。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2024/12/29 (Sun) 00:12:50
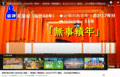 「越年称元法」と「無事績年」について(紹介)
「越年称元法」と「無事績年」について(紹介)
※:私などは、「越年称元法」という言葉を
_:知らなかったので、「翌年即位」という言葉を
_:当てて勝手に使っています。
※:「無事績年」は、紀年論の中で使われる概念のようです。
「改元(かいげん)」(ウィキペディアより)
:改元とは、元号を改める(変更する)こと。
:概要
:中国や日本など東アジアでは、紀年は、60年周期の干支の外に、
:君主(皇帝や王、天皇)の在位期間を基準に定められ、
:治世途中で再び元年から始めることを改元と呼んだ。
:元号を使うようになってからは、元号も同時に改められて
:新元号の元年とされた。このため、改元が元号を変えること
:(改号)と同一視されることもある。
:
:なお、帝王の退位により新帝王が即位すると、再び元年から
:始められ、一般的にこれも改元と呼ぶことがあるが、
:専門的には、治世途中の改元だけを改元とし、新帝王の即位による
:元年は称元(しょうげん)と呼んで区別することがある。
*****
「無事績年」
:無事績年というのは、天皇の治世のうち
:何の事績も出来事も記されない年のことです。
*****
(以下、ネットで偶然見つけた、紀年論の紹介になります。)
M・ITOさんのHP
無事績年というのは、天皇の治世のうち何の事績も出来事も
記されない年のことです。
例えば、応神天皇の治世は41年間だったとされますが、
事績や出来事が記されているのは23年間です。
18年間の無事績年が存在します。
この18年が紀年延長操作によって挿入されたものであり、
実際の応神天皇の治世は23年間だったと考えるのです。
原日本紀仮説による新・紀年論~無事績年削除短縮法 ...
ameblo.jp/yamatai-nihongi/entry-12718435328.html
グローバル Web アイコン
sce-net.jp
https://sce-net.jp › main › wp-content › uploads
[PDF]220616 E-163 rev07 鹿子島様 - SCE・Net
ページ数: 7
ファイル サイズ: 1MB
ここで『紀年論』とは、『日本書紀』や『古事記』に記載された
古代天皇の在位期間 や寿命は、何故不自然に長いのか。
この紀年の正否を明らかにする試みをいう。
グローバル Web アイコン
wixsite.com
https://egretec1101.wixsite.com › go-haya…
古代天皇紀年論の新考察
2023年12月26日 · ここで『紀年論』とは、『日本書紀』や
『古事記』に記載された古代天皇の在位期間や寿命は、
何故不自然に長いのか。
この紀年の正否を明らかにする試みをいう。
その論点は、次の2つと考える。
_a.古代天皇の在位期間や寿命(享年)における
非現実的数字(次頁 表-1を参照) b.諸外国史料 …
グローバル Web アイコン
asablo.jp
https://ancient-history.asablo.jp › blog
紀年論: 新古代史の散歩道 - AsahiNet
2023年7月1日 ·
紀年論 (きねんろん、chronology)は『日本書紀』『古事記』に
記載された紀年に実年代との矛盾があるため、これを
学問的手続によって解決しようとするための方法論であ …
グローバル Web アイコン
アメーバブログ
https://ameblo.jp › yamatai-nihongi
「紀年論」史上最もシンプルな紀年復元法!
【無事績年削除法 ...
2024年10月25日 · いま発売中の『古代天皇たちの真実』
(ワニブックスPLUS新書)で提唱した新しい紀年復元法
ですが、少し複雑な手法だと感じている方もいらっしゃると
思います。 そ…
グローバル Web アイコン
Kyoto University Research Information Repository
https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp › dspace › bitstream › ...
[PDF]関する新研究 - Kyoto U
上代紀年に関する新 研究(笠井) 次に清寧天皇から
継体天皇に至る五代の治世年数であるることなので、
ここぞは問題にしない。 上代紀年に関する新研究
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - 米田
2024/12/24 (Tue) 15:34:16
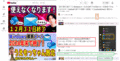 Windows・メール(Outlook)完全終了について。
Windows・メール(Outlook)完全終了について。
私のパソコンは、9年前に買ったWindows10
(8.1のアップ版)で、実装RAMを数年前に、
8GBから16GBに増設して使っています。
(充分に、使えています。)
最近、ネットを見ていたら、トピックスに、
「今年で、メール完全終了」というものを
見つけました。(どうも、該当しているみたいなので)
最近、あわてて(Outlookを)バージョンアップをしました。
(三段階の一番古い物から、新しい物「new」にしました。)
(バージョンアップは、したつもりです。)
マイクロソフトは、「広告付きの無償」か、「定額制の有料」の
二択の選択を利用者に迫っているようです。
Gメールなどのソフトなどでは、
「複数のアカウントを一つのソフトで管理できます。」
という方法もあるみたいです。
(画面に、コマーシャルがいっぱい出てきて不便ですが)
「光ケーブルの契約」以外は、無償で、インターネットを
(これからも)使っていきたいなと、思っています。
(Windows11への買い替えも迫ってきていますが・・・。)
古いパソコン(Outlook)をお使いの方は、
ぜひ調べてみて下さい。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2024/12/23 (Mon) 23:05:42
(FB談話室からの転載です。)
東アジアの古代文化を考える会
作成者: Naoko Urushibara
·4時間·2024年12月23日(月) 17:33
☆ ☆ ☆ ☆ <1月・2月・3月のテーマ> ☆ ☆ ☆ ☆
『 邪馬台国時代の倭―九州の弥生時代中期・後期― 』
―オンラインのみ
■日 時 : 1 月 25 日(土) 14 時~16 時半 終了予定
■講 師 : 片岡 宏二先生(小郡市埋蔵文化財調査センター所長)
■会 場 : なし(オンラインのみ)
『ヤマト王権への対応さまざま―九州の古墳時代前期・中期―』
―オンラインのみ
■日 時 : 2 月 15 日(土) 14 時~16 時半 終了予定
■講 師 : 片岡 宏二先生(小郡市埋蔵文化財調査センター 所長)
■会 場 : なし(オンラインのみ)
『 筑紫豪族磐井の新解釈ー九州の古墳時代後期― 』
―オンラインのみ
■日 時 : 3 月 29 日(土) 14 時~16 時半 終了予定
■講 師 : 片岡 宏二先生(小郡市埋蔵文化財調査センター 所長)
■会 場 : なし(オンラインのみ)
☆ ☆ ☆ ☆<4月以降の講演会のご案内> ☆ ☆ ☆ ☆
『「任那日本府」とは何だったか 』
―会場+オンライン (ハイブリッド)
■日 時 : 4 月 19 日(土)14 時~16 時半 終了予定
■講 師 : 仁藤 敦史先生 (国立歴史民俗博物館)
■会 場 : 未 定
『 ガラス玉の産地と分析化学 』―オンラインのみ
■日 時 : 5 月 24 日(土)14 時~16 時半 終了予定
■講 師 : 田村 朋美先生(奈良文化財研究所)
■会 場 : なし(オンラインのみ)
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2024/12/22 (Sun) 10:12:02
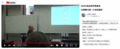 .
.
紹介ついでに、4年前の管理人の発表(約33分)も
紹介します。
全国邪馬台国連絡協議会 会員研究発表会 令和2年3月
・発表者:白崎勝___(00:00:00からスタート)
演題:神武東征などの戦いを、由来としての破鏡の検討
・発表者 川崎一仁___(00:39:20頃からスタート)
演題:古代史から見た邪馬台国
・発表者 米田喜彦___(01:26:00頃からスタート)
演題 「古代天皇の年代観に対する新視点」
___~中臣氏の系譜から見た「記紀の紀年論」~
https://www.youtube.com/watch?v=aLbN2rybIPA&t=5090s
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2024/12/22 (Sun) 09:43:42
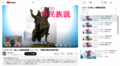 ┌
┌
│2023年秋から24年秋にかけて
│4つの古代史の会で講演した
│『新しい騎馬民族説』をまとめてシリーズ化しました。
│だいぶ進化していると思います。
│この説は邪馬台国が九州にないと成立しません。
│今回の動画では3つの動画の第1回目として
│『邪馬台国は九州にあった』ことを簡単に説明します。
└
皆様
当会で開催したの会員研究発表会で、云々。
発表者の槌田鉄男さんが当日の発表を動画に
まとめてくれました。以下で視聴できます。
東アジアの古代文化を考える会
ーーーーーー以下槌田さんのメールのコピーーーーーーーー
基本的には発表内容と同じですが、長くなるので
シリーズ・新しい騎馬民族説としてその後新たに得られた
情報も加えてアレンジして5分~20分の
6つの短い動画に分けあります。
下記のURLをクリックして下さい。
シリーズ・新しい騎馬民族説(1/3)
『邪馬台国は筑紫平野』
https://www.youtube.com/watch?v=zeu0MdH0tgw&list=PL3F4ZC-NEpDOzYgbpExr3wosbdCcRKlzE&index=1
シリーズ・新しい騎馬民族説(2/3)
その1『3世紀生じた大きな変化』
https://www.youtube.com/watch?v=K6AUhcqoe54&list=PL3F4ZC-NEpDOzYgbpExr3wosbdCcRKlzE&index=2
シリーズ・新しい騎馬民族説(2/3)
その2『遺伝子学の新説から考える新しい騎馬民族説』
https://www.youtube.com/watch?v=i5vjlNw4WfA&list=PL3F4ZC-NEpDOzYgbpExr3wosbdCcRKlzE&index=3
シリーズ・新しい騎馬民族説(2/3)
その3『3世紀の日本に騎馬民族・扶余がやってきた』
https://www.youtube.com/watch?v=uO5ScrpC0bU&list=PL3F4ZC-NEpDOzYgbpExr3wosbdCcRKlzE&index=4
シリーズ・新しい騎馬民族説(3/3)
誰が纒向遺跡を作ったか・その1『公孫氏とは』
https://www.youtube.com/watch?v=PToYBo5Z3m4&list=PL3F4ZC-NEpDOzYgbpExr3wosbdCcRKlzE&index=5
シリーズ・新しい騎馬民族説(3/3)
誰が纒向遺跡を作ったか・その2『公孫恭奈良に入る』
https://www.youtube.com/watch?v=7ddyTONkTrA&list=PL3F4ZC-NEpDOzYgbpExr3wosbdCcRKlzE&index=6
以上よろしくお願いいたします。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2024/12/22 (Sun) 09:28:59
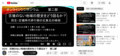 2024年度北東北歴史懇話会シンポジウム
2024年度北東北歴史懇話会シンポジウム
お申込者 様
【北東北歴史懇話会】
「古墳のない地域の歴史をどう語るか?」
Youtubeにアップロードしました。
今年度のシンポジウムについて、Youtubeに動画を
アップロード致しましたのでお知らせ致します。
見逃しなどが有れば是非ごらんください。
(長時間のシンポジウムで
_あったため、3分割となっております)
************************
古墳のない地域の歴史をどう語るか?
第一部 基調講演
続縄文文化と古墳文化との出会い
東京大学大学院人文社会系研究科 根岸 洋准教授
https://www.youtube.com/watch?v=Sf6tfN9RJKU
第二部 講演
秋田の南の古墳文化
横手市教育委員会 藤原 正大主任(学芸員)
秋田の北の続縄文遺跡
大館市教育委員会 嶋影 壮憲主査
https://www.youtube.com/watch?v=CyWWIHHHaxs
第三部 トークセッション
コーディネーター
藤盛 紀明(北東北歴史懇話会会長)
パネリスト
根岸 洋 (東京大学大学院 准教授)
島田 祐悦(横手市教育委員会)
榎本 剛治(北秋田市観光文化スポーツ部)
嶋影 壮憲(大館市教育委員会)
https://www.youtube.com/watch?v=mUYjfGmsgTw
************************
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - 米田
2024/12/19 (Thu) 23:41:43
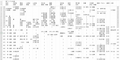 ┌
┌
│白石南花
│2日·2024年12月17日(火) 21:43
│
│倭の五王の朝貢
│ご下問の内容とずれてしまいますが、
│最近倭の五王に関して
│気づいたことがあるので、ご参考までに。
│
│ある意味当たり前なのですが、倭の五王の朝貢は、
│東アジア史の中で考えるべきことです。
└
┌
│倭の五王の朝貢は、東アジア史の中で考えるべきことです。
└
:私も、【東アジア史の中で考えるべきこと】と考えます。
:それで、約20年前に作った年表を提示したいと思います。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2024/12/19 (Thu) 23:08:37
(FB談話室からの転載です。)
白石南花
2日·2024年12月17日(火) 21:43
倭の五王の朝貢
ご下問の内容とずれてしまいますが、最近倭の五王に関して
気づいたことがあるので、ご参考までに。
ある意味当たり前なのですが、倭の五王の朝貢は、
東アジア史の中で考えるべきことです。
討論室に書いた内容に関係しますが、まず基本資料として
好太王碑についてみてみると、少々引っかかるのが、
「百済・新羅はもと高句麗に服属してきたが、倭が辛卯年
(391年)以来海をこえて襲来し、百済や新羅などを破り、
臣民とした」と言う部分です。
まず新羅や百済が高句麗の臣民であったかどうかが
問題ですが、晋書には前燕の咸康七年(341年)の記事に、
高句麗と百済の捕らえた兵を植民した記事が出てきます。
前燕は439年以来高句麗と戦い、高句麗は和を乞ています。
つまり百済は高句麗とともに前燕と戦ったということです。
さらに380年に前秦の苻洛が反乱を起こした際に、高句麗や
百済や新羅などの兵を集めるという記事も出てきます。
これらの記事からは、前秦や前燕の首長らは、高句麗や百済や
新羅を、属国のように扱っていたことが分かります。
広開土王の末年近く、北燕に高句麗系の王が立ち、
高句麗も朝貢しています。
この経緯から、多少の誇張はあるものの、高句麗が百済や
新羅を臣従させていたという主張は、少なくともその死後の
好太王碑の建立時点では、まったく根拠のないものとは
言えないと思います。
また辛卯年(391年)以来倭が渡海してきて、百済や新羅を従え
たというのは、『日本書紀』を見ると倭の半島進出は肖古王の
時代で、これは『三国史記』の近肖古王の時代にあたり、
『日本書紀』紀年を干支の二巡下げると、366年となります。
倭が半島に進出したのは、四世紀も中頃に遡ると思われ、
好太王碑は四世紀末の広開土王即位後としています。
これは四世紀中には、倭と結んだ百済によって、故国原王が
敗死したことに触れられたくないということであると思います。
好太王碑の碑文は、政治的目的を持ったものであることは、
考慮すべきであると思います。
また広開土王の後を継いだ長寿王の時代に、
どうも高句麗は対百済の方針を転換しているようです。
劉宋の永初元年に武帝劉裕は、高句麗王は征東大将軍となり、
百済王は鎮東大将軍となって、並びに義を持って海外を執り、
遠く貢職を修め、国を休めるようにとしています。
また472年に百済王が北魏にあてた上表文では、祖先が
故国原王と戦い敗死させたのちは、高句麗が南を顧みることが
無くなったが、馮氏が滅んでから圧迫を受け、三十余年で
財も力も尽きたとして、助力を求めています。
故国原王の死後に広開土王があらわれて、百済は一度漢城を
落とされているのに、それに言及しないのは、この上表文が
事実を述べようとしているのでなく、北魏に対する政治的
プロパガンダのためのストーリーを述べているためです。
この馮氏というのは後燕の残党で、破れて高句麗に逃れた
ところ、劉宋文帝が迎え入れるように求めたのに、
長寿王はこれを殺してしまったものです。
劉宋が馮氏をかくまうことを求めたのは、河北を平定した
北魏に対するけん制でしょう。
高句麗がそれを断ったのは、劉宋よりも高句麗と隣接した北魏
に気を使い、後願の憂いを絶って南下策を進めるためでしょう。
馮氏が滅んだのは、元嘉十五年(438年)のことで、このころ
までは高句麗は百済に対して敵対的ではなかったと思われます。
そして百済と同盟を結んでいた倭に対しても、敵対的では
なかったと思われます。
これが倭王武の上表文につながります。
そこでは武の父の斉が、高句麗が南朝朝貢路を塞いだために
怒って、高句麗征討を行なおうとしたとしています。
438年まで高句麗が親和的であったとしたら、438年の倭国王
珍の朝貢は高句麗領を通っていった可能性があります。
大海を渡ることが当たり前になっている現代人から見れば、
なぜ高句麗領を通るのか分かりませんが、黄海を渡ろうと
すれば、一度陸地の見えない海の上に出ます。
このような大海の航路は、『三国志』呉書に見える亶州への
遠征が失敗したことでもわかる通り、古い時代には困難な
ものでした。
五世紀ころまでの東北アジアでは、陸に沿った航海が
普通だったのです。
陸の見えない海の上で、嵐などに合えば位置を見失い
難破する可能性が高いです。
遣唐使が生きて帰れない覚悟をもって、
東シナ海を渡ったことでもわかります。
開けた海の航路が安定してくるのは、造船技術と航海技術の
進歩に伴い、ようやく九世紀の終わりごろでしょう。
初期の南朝への安全な朝貢路は、朝鮮半島西岸を北上し、
遼東半島から島伝いに山東半島に行くルートだったので、
高句麗領を通ったわけです。
443年に朝貢しようとした斉は、その安全なルートを
使えなくなったので怒ったわけです。
しかし443年に朝貢路を塞がれ、危険な渡海ルートで
朝貢したのに、なぜその時高句麗を攻撃しなかったのでしょう。
斉は451年にも朝貢しています。
そして462年には世子の興も朝貢しています。
一体高句麗征討はどこに行ってしまったのでしょう。
このことから、倭王武の上表文も、歴史的事実を伝えようと
するものではなく、南朝に対する政治的主張のための
ストーリーを語っていることが分かります。
以上金石文であろうとも、漢籍であろうとも、その内容を
そのまま受け取るべきではないことが分かります。
朝貢路に関しては、おそらく倭の五王の朝貢が途絶した
理由も説明できるのですが、長文に過ぎるので
ここまでにしておきたいと思います。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2024/12/19 (Thu) 23:06:14
 (FB談話室からの転載です。)
(FB談話室からの転載です。)
藤盛 紀明
· 3日·2024年12月16日(月) 08:24
(気軽な歴史談話です!)
討論室でのakaosaさんの投稿「倭の五王」は「応神~雄略」
などの「天皇では無い」との投稿が話題になっています。
石見介さんや当世奇妙さんからは、では倭の五王はダレ??
との質問が出されている。
(akaosa説の詳細は討論室を見てください)
倭の五王と応神天皇の以下の系図は「WIKIPEDIA]からの
借用です。
皆さんはどう思いますか。
私は「倭の五王は天皇ではない」のakaosaさんの投稿は
かなり論理的な内容と思います。
(ただし賛成か否かは保留です)
藤盛 紀明
2日·2024年12月17日(火) 12:48
最近の討論室はスレッドのタイトルは異なっても、
倭王、倭の五王関連の投稿が集中している。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2024/12/03 (Tue) 19:21:33
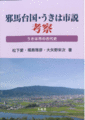 (FB談話室からの転載です。)
(FB談話室からの転載です。)
東アジアの古代文化を考える会 「新談話室」
福島雅彦 · 2時間 ·2024年12月03日(火) 16:51
著書紹介
『邪馬台国・うきは市説考察』 ―うきは市の古代史―
2023年9月30日 初版 著者:三人共著
・ 松下愛(元・久留米大学講師)
第1章 うきは市の古代史を読むために<1頁~9頁執筆>
・福島雅彦(古代史研究家・一級建築士)
第2章 邪馬台国は高天原(1)<11頁~43頁執筆>
第3章 邪馬台国は高天原(2)<49頁~53頁執筆>
・大矢野栄次(久留米大学名誉教授)
第4章 うきは市の双方中円墳(西の城古墳)の意味
<75頁~101頁執筆>
第5章 うきは市の賀茂神社(103頁~111頁執筆)
第6章 邪馬台国と神武東征(113頁~129頁執筆)
発行者:株式会社五弦舎 定価(本体1,400円+税)
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2024/11/24 (Sun) 14:07:28
(FB談話室からの転載です。)
東アジアの古代文化を考える会
作成者: Naoko Urushibara
·15時間·2024年11月23日(土) 22:21
【12 月の講演会のご案内】
『古墳時代の吉備』―オンラインのみ
■日 時 : 12 月 7 日(土) 14 時~16 時半 終了予定
■講 師 : 亀田 修一先生 (岡山理科大学)
■会 場 : なし(オンラインのみ)
■講師の言葉
弥生時代後期、吉備には当時日本列島最大の推定約 80m の
楯築弥生墳丘墓が築かれる。
その後、古墳時代の吉備はヤマト王権と近い関係を持ちながら、
地方では突出した規模を持つ超大型前方後円墳を築くように
なる。
350m の備中造山古墳、282m の備中作山古墳、そして
二重周濠を持つ 206m の備前両宮山古墳などである。
5 世紀初めから中頃までの約 50 年間にこれらが続けて
築かれるのである。
しかし、5 世紀後半の雄略大王の時代のいわゆる
「吉備の反乱伝承」を経て、備前ではその規模が 100m以下に
なり、備中では約 110 年間大型前方後円墳が築かれなくなる。
そして、6 世紀半ばに白猪屯倉と児島屯倉がおかれ、
ヤマト王権の直接的な支配下に置かれたと考えられている。
このように地方で大きな力を有した吉備の弥生時代後期から
古墳時代終末期までの様相を近畿地方や朝鮮半島との関わりを
踏まえてお話ししたい。
■参加料:ZOOM 視聴代:1000 円
■照会先:080-4097-1757 inagaki34214590@yahoo.ne.jp 稲垣
■聴講・申込方法:ZOOM 聴講希望者は 12 月 6 日(土)
までにメールにて「氏名、メールアドレス、携帯番号
(当日の連絡用)」を添えて下記宛に申し込んで下さい。
メール申込先:稲垣 inagaki34214590@yahoo.ne.jp
1 参加料 1000 円を下記までお振込み下さい
みずほ銀行 九段支店 店番号532
普通預金 口座番号 8043715
口座名 東アジアの古代文化を考える会 事務局長 嶋田晋吾
2 視聴方法:講演前日までに指定アドレスに講演会用の
ZOOM の URL と資料が送付されます。
☆ ☆ ☆<2025年1月以降の講演会のご案内> ☆ ☆ ☆
『邪馬台国時代の倭―九州の弥生時代中期・後期―』
―オンラインのみ
■日 時 : 1 月 25 日(土) 14 時~16 時半 終了予定
■講 師 : 片岡 宏二 先生
(小郡市埋蔵文化財調査センター 所長)
■会 場 : なし(オンラインのみ)
『ヤマト王権への対応さまざま-九州の古墳時代前期・中期―』
―オンラインのみ
■日 時 : 2 月 15 日(土) 14 時~16 時半 終了予定
■講 師 : 片岡 宏二 先生
(小郡市埋蔵文化財調査センター 所長)
■会 場 : なし(オンラインのみ)
『筑紫豪族磐井の新解釈ー九州の古墳時代後期―』
―オンラインのみ
■日 時 : 3 月 29 日(土) 14 時~16 時半 終了予定
■講 師 : 片岡 宏二 先生
(小郡市埋蔵文化財調査センター 所長)
■会 場 : なし(オンラインのみ)
『「任那日本府」とは何だったか』
―会場+オンライン(ハイブリッド)
■日 時 : 4 月 19 日(土) 14 時~16 時半 終了予定
■講 師 : 仁藤 敦史先生(国立歴史民俗博物館)
■会 場 : 未 定
『ガラス玉の産地と分析化学』―オンラインのみ
■日 時 : 5 月 24 日(土) 14 時~16 時半 終了予定
■講 師 : 田村 朋美先生(奈良文化財研究所)
■会 場 : なし(オンラインのみ)
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2024/11/22 (Fri) 22:08:04
(FB談話室からの転載です。)
・有田守
9時間·2024年11月22日(金) 12:40
おめでとう
中国の歴史書の考証を研究することをおすすめします。
絶対的な歴史書は、中国にありません。
『史記』も絶対的な書物ではありません。
・土田章夫
7時間·2024年11月22日(金) 14:54
有田守さま コメントありがとうございます。
近畿説も北部九州説もその他の説も魏志倭人伝の記述に
合致していません。
そのために自説に合うように魏志倭人伝の記述が
間違っているとか不正確としています。
ほとんどすべての説が自説に合わないために、
魏志倭人伝が不正確だという説が定説になっています。
ほとんどの人がこれを信じています。
邪馬台国研究は魏志倭人伝がいかに不正確かを考証すること
が目的になっています。
これはいかがなものかと思っています。
同様に近畿説も北部九州説もその他の説も
古事記・日本書紀の記述と合いません。そのために
古事記・日本書紀は創作神話だとして無視しています。これら
によって邪馬台国はどこでもありの状態にになっています。
邪馬台国研究が混乱しているのはこのためです。
唯一、宮崎市説だけが魏志倭人伝の記述に全て合致しています。
また唯一、宮崎市説だけが古事記・日本書紀と矛盾しません。
┌
│「邪馬臺國」オタクの呟き - 福島雅彦
│2024/11/22 (Fri) 20:41:57
│
│談話室に投稿を試みましたが不成就でしたので、
│此処へ投稿します。
│土田章夫さん、ご上梓おめでとうございます。
│(以下、略)
└
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - 米田
2024/11/22 (Fri) 15:32:13
 米田です。初めまして。
米田です。初めまして。
昔作った地図を(参考までに)紹介します。
(条件01):楽浪郡は、雒陽(洛陽)の東北5千里にある。
(条件02):韓の広さは、4千里四方である。
狗邪韓国の位置を、上記二つの条件を満たす場所として
探すと、宮崎市の南東の【E】の位置になります。
倭国(邪馬台国)は、この【E】から
さらに南に(5千里)いくことになります。
ここまでで、私の「邪馬台国」探しの旅は終わりました。
「韓の広さは、4千里四方である。」という情報を
報告したのは、帯方郡太守の「王頎」だろうと推測しています。
「韓の広さは、4千里四方である。」は、(5千里に比べて)
朝鮮半島があまりにも大きすぎます。
ということで、
この(魏書東夷伝の地理的な)情報は、(陳寿と同じように)
正確さに欠けると、私も、考えました。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2024/11/22 (Fri) 15:03:18
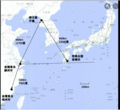 (FB談話室からの転載です。)
(FB談話室からの転載です。)
土田章夫
5時間·2024年11月22日(金) 09:24
「会稽東治の東」と「帯方郡から12000里」は
宮崎市を指す
前回投稿した「ChatGPTが宮崎を示しました」を
補足します。
私は古代史ノンフィクション作家で
邪馬台国宮崎市説を提唱しています。
魏志倭人伝が記す邪馬台国の条件に「会稽東治の東」と
「帯方郡(平城付近)から12000里」があります。この
二つの条件だけで邪馬台国は宮崎市にあったことが示されます。
宮崎市は直線距離で帯方郡から12000里に当たります。
会稽東治は現在の蘇州市とされています。
その東は鹿児島県を指します。
すなわち宮崎市はこの二つの条件を満たします。
反対に言うとこの条件を満たすのは宮崎市説だけです。
「会稽東治の東」「帯方郡から12000里」は強く
邪馬台国宮崎市説を強く支持しています。
今までは会稽東治の東については
中国の東くらいの認識でほとんど議論されていません。
それは近畿(奈良)も北部九州も正確には
会稽東治の東には当たらないからです。
なぜ会稽東治というピンポイントの場所を
示しているのでしょうか。
近畿(奈良)も北部九州も当時の魏の都である「洛陽の東」に
当たります。「洛陽の東」と書かれるはずです。
近畿(奈良)も帯方郡から直線距離で12000里です。
北部九州は行程をつないでいくと12000里になります。
しかし会稽東治の東ではありません。
どのような方法で直線距離を計測したかを考察します。
中国では紀元前500年ごろから駅伝制が整備されていました。
街道沿いに駅を設けて人、軍隊、物資、情報の伝達が
行われていました。
駅と駅の間の距離と方位は分かりますから、
これらをつなげていくと大まかな地図ができます。
古代中国の統一王朝は朝鮮を含めて
大まかな地図を作製していたと考えられます。
すなわち2地点間の距離と方位は地図で把握できました。
そうすると帯方郡から朝鮮半島南岸の狗邪韓国までの
距離と方位は分かります。
魏の使者の一行は毎日の旅程を記録していました。
毎日進んだ距離と方位は目視と歩測等で大体わかります。
それを狗邪韓国から海を渡って唐津に上陸して
邪馬台国までつなげていけば簡単な行程地図ができます。
伊能忠敬が地図を作製したのと同じ方法です。
帯方郡から邪馬台国までの大まかな距離と方位は分かります。
当時中国では「一寸千里法」という方法が開発されていました。
「一寸千里法」は夏至の太陽南中時に、南北 2 地点で
8 尺の棒の影の長さを測り、その日影長さに 1 寸の差が
あるとき、2 地点間の南北距離を千里とするというものです。
帯方郡から邪馬台国までの大まかな距離と方位がわかった上で、
これを駅伝制等から得た情報で作成した中国の大まかな地図と
照らし合わせて、一寸千里法も用いて、会稽東治(蘇州市)
の東、帯方郡(平城付近)から12000里としたのです。
280年に晋は呉を滅ぼして中国を統一します。
『魏志倭人伝』が書かれた3世紀末には中国全土の
大まかな地図は作成されていたと考えられます。
(拙書『邪馬台国は宮崎市にあった!』より)
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2024/11/22 (Fri) 14:58:39
(FB談話室からの転載です。)
・有田守
3日·2024年11月18日(月) 17:34
おめでとう
・藤盛 紀明
1日·2024年11月21日(木) 09:42
Chat GPTへの質問文教えて貰えませんか?
・土田章夫
1日·2024年11月21日(木) 09:51
藤盛 紀明 さま 投稿文に書いてあります。
分かりにくくて申し訳ありません。この部分だけ再掲します。
<AI(ChatGPT)への質問>
魏志倭人伝に邪馬台国の場所の条件が書いてあります。
邪馬台国はどこでしょうか教えてください。
・_北朝鮮の平壌から直線距離で約900kmの距離
・_中国の蘇州市(北緯31.2度)のほぼ東
・_糸島市から見て南にある。
・_北部九州から南に船で200㎞、
__さらに船で100㎞あるいは徒歩で100㎞
・_温暖な気候、冬でもはだし
・_邪馬台国の東に80km海を渡ると倭種の国がある
・_邪馬台国から南に300㎞で島がある。
__さらにそこから南東に連なる島がある
・_長さ約350kmの島の上にある
・大野克浩
19時間·2024年11月21日(木) 19:40
・土田章夫 さん
う〜ん、宮崎に誘導してるような(笑)
・土田章夫
5時間·2024年11月22日(金) 09:26
大野克浩 さま コメントありがとうございます。
別途補足する投稿をしましたのでご参照ください。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2024/11/22 (Fri) 14:57:07
(FB談話室からの転載です。)
土田章夫
3日 ·2024年11月18日(月) 15:15
AI(ChatGPT)が邪馬台国は宮崎県にあることを示しました。
私は古代史ノンフィクション作家で邪馬台国宮崎市説を
提唱しています。
今回ChatGPTで邪馬台国の場所を検索しました。
魏志倭人伝には邪馬台国の条件として次の条件が記載されて
います。これを簡素化してChatGPTに質問しました。
AI(ChatGPT)は結果として
邪馬台国は邪馬台国は宮崎県だと示しました。
邪馬台国が宮崎県にあった可能性が高いと言えます。
これは客観的事実です。
ChatGPTは回答に振れがありますが
誰が質問してもほぼ同じ結果が得られるはずです。
<魏志倭人伝にある邪馬台国の条件>
・帯方郡から12000里 (直線距離 約900㎞)
・会稽(郡)東治の東にある
_(江蘇省蘇州市の東 北緯31.2度)
・女王国の北の伊都国に一大率を置く
・不弥国から南水行20日で投馬国に至る。
_投馬国から南水行10日陸行1月で邪馬台国に至る
・東に1000里海を渡ると倭種の国がある
・温暖である 冬でもはだし
・南に4000里に侏儒国がある。
_さらに東南には連なる島がある
・周旋可5000里の島である
<AI(ChatGPT)への質問>
魏志倭人伝に邪馬台国の場所の条件が書いてあります。
邪馬台国はどこでしょうか教えてください。
・〔北朝鮮の平壌から直線距離で約900kmの距離〕
・〔中国の蘇州市(北緯31.2度)のほぼ東〕
・〔糸島市から見て南にある。〕
・〔北部九州から南に船で200㎞、
__さらに船で100㎞あるいは徒歩で100㎞〕
・〔温暖な気候、冬でもはだし〕
・〔邪馬台国の東に80km海を渡ると倭種の国がある〕
・〔邪馬台国から南に300㎞で島がある。
__さらにそこから南東に連なる島がある〕
・〔長さ約350kmの島の上にある〕
<AI(ChatGPT)からの回答>
魏志倭人伝に基づく邪馬台国の位置条件について、
以下のように詳しく解説します。
〔北朝鮮の平壌から直線距離で約900kmの距離〕
邪馬台国は平壌から約900kmの距離にあるとされています。
九州南部、特に宮崎県はこの距離に該当します。
〔中国の蘇州市(北緯31.2度)のほぼ東〕
九州南部は中国の蘇州市(北緯31.2度)の
ほぼ東に位置しています。
〔糸島市から見て南にある〕
九州南部は糸島市の南に位置しています。
〔北部九州から南へ船で200km、さらに徒歩で100km〕
北部九州から南へ船で約200km移動し、さらに
船で100㎞あるいは徒歩で100kmの距離にある場所です。
九州南部がこの条件に適しています。
〔温暖な気候、冬でもはだし、〕
九州南部は温暖な気候で、
冬でも裸足で過ごせるような気候条件があります。
〔邪馬台国の東に80km海を渡ると倭種の国がある〕
九州南部から東に約80km海を渡ると倭種の国がある
という条件も満たしています。
〔邪馬台国から南に300kmで島があり、
_さらにそこから南東に連なる島がある〕
九州南部から南に約300kmの距離には奄美大島などがあり、
その南東にはさらに島々が連なっています。
この条件も適合します。
〔長さ約350kmの島の上にある〕
邪馬台国は長さ約350kmの島、つまり九州の上に位置して
います。九州の長さが約350kmで、この条件にも合致します。
これらの条件をすべて満たすのは、九州南部、特に宮崎県です。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - 米田
2024/11/20 (Wed) 11:26:30
.
<当会会員研究会発表会>
■発表者 (各発表の内容は、コメント欄に掲載)
1)10:00~10:45 諸岡 かおり 『神武天皇論 ―「神武
天皇=徐福説(衛挺生)」と現在の神武天皇論から考える―』
2)10:50~12:00 赤尾 恭司 『三国時代における
「栄山江流域」とは何か……「栄山江流域」=任那 説』
3)13:00~14:00 槌田 鉄男 『新しい騎馬民族説の提案』
4)14:10~15:20 下山 繁昭 『川原寺の国際性について』
5)15:30~16:50 小原 理一郎『イタリア、
___サルデーニア島の古代遺跡とヌラーゲNuraghe文明』
6)17:00~17:50 河原 宏
_______『邪馬台国から平安時代までの経済成長』
:三番目以降の方の、感想を書きたいのですが、
:実際のところ、ほとんど聞いていませんし、
:いただいた資料も、ほとんど見ておりません。
:ですので、感想は、書けませんでした。
:
:ということで、一連の講演会・シンポジウムの感想は、
:これで終わりにしようと思います。
:後日、スレが立ち上がった時には、
:参加して勉強しようと思います。
:一気に書いたものですから、
:1年分のエネルギーを使い切った感じです。
:少し休憩します。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - 米田
2024/11/19 (Tue) 15:51:59
.
<当会会員研究会発表会>
二番目の発表の「任那」については、まとまりしだい、
別スレの方に、投稿しようと思います。
一番目の追加。
┌
│ここで注目すべきは徐福が琅邪の人であることだ。
└
:琅邪の出身には、いろんな人がいたと思います。例えば、
:「楽浪王氏」の出身は、「琅邪王氏」ではないだろうか。
:
:半島の伝承に、下記があります。
「BC 209年、豊の 69世孫・蘇伯孫が辰韓を建国したと言う。」
:彼は、蘇因高(小野妹子)の先祖に当たると、思っています。
:このBC209年の「蘇伯孫」こそ「天御中主神」ではないかと
:考えています。
┌
│BC57年、13歳の朴氏・赫居世が即位した、
│国号を「徐那伐」といった。
└
:朴氏の赫居世が作った国は、「徐那伐(徐氏の国)」です
:ので、徐福とは、何らかの関係があるかも知れません。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - 米田
2024/11/19 (Tue) 12:43:15
<当会会員研究会発表会>
11月17日(日)ZOOM参加。当会会員研究会発表会(部分参加)
:11月14日(木)、メールの添付で、資料が送られてきました。
:発表会の3日前で、6人の発表で、各人の資料が多く、
:文字の多さに、読むことを断念しました。
:
:当日は、午前中、普段とは違うノートPCを使ったところ、
:音が小さく、発表を聞くのに苦労しました。
:午後は、スマホを利用して、ほぼ音声だけをイヤホンで
:聞いていました。画面は小さいので、目が痛くなるので、
:(画面は)諦めました。
:一番目は「神武天皇論」。(以下は、私の印象、感想です。)
:
:神武即位BC660年説。神武天皇=徐福(BC203年頃即位)説。
:皇祖太白説。渡会神道(による系図改ざん)。など。
:諸岡さんは、色々な説を紹介していたのだろうと思います。
*****
『環濠集落(かんごうしゅうらく)』(ウィキペディアより)
弥生時代
環濠集落は稲作文化と同時に大陸から伝来し、
列島東部へ波及したと考えられている。
しかし、2世紀後半から3世紀初頭には、弥生時代の
集落を特徴付ける環濠が各地で消滅していく。
この時期に、西日本から東海、関東にかけて政治的状況が
大きく変わったことを示すものとして考えられている。
*****
:「神武天皇」を論じるには、色々あるとは思います。
:とはいっても、「池上・曽根遺跡」や「唐子・鍵遺跡」を
:調べる中で、「神武天皇」が存在していたとすると、または、
:「神武東征」があったとすると、「環濠集落」の変遷から、
:その時期は、「2世紀後半から3世紀初頭」が一番有力です。
:
:10代祟神天皇を300年頃として、1代30年で、9代遡ると、
:AD30年頃です。これでも、(神武天皇は)1世紀前半です。
:この時点で、
:BC660年説と、神武天皇=徐福(BC203年即位)説の二つは
:(即座に)除外(却下)されると思います。
:
:いろんな「神武天皇説」が、過去から現在まで、色々あって
:面白いね、という感想を(発表者が)期待しているのであれば
:発表会での発表の価値は、あったのでしょう。
(個人的な感想でした。)
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - 米田
2024/11/18 (Mon) 11:43:57
 「古代出雲文化シンポジウム」
「古代出雲文化シンポジウム」
「六世紀の出雲とヤマト(出雲の大型古墳を語る)」
表題が漠然としていたのと、
以前、YouTubeでみた「松木」さんの講演が
あまりにも素晴らしかったので
今回のシンポジウムには、あまり期待は
していませんでした。
感想をまとめて書きます。
先生方の講演は、素晴らしかったです。
出雲の魅力の再発見が出来ました。
また、近畿・九州とのバランス(比較)も大変良かったです。
講演だけでしたら、来年には、YouTubeで公開されると
思いますので、見る価値はあると思います。
約4時間、坐ったままだったので、少しきつかったです。
シンポジウムという形式でしたが、私には、「紅白歌合戦」
(テレビ番組)の現場収録に立ち会った、という感じでした。
パネルディスカッションも台本通りに進んでいて、
まさに(テレビ放送の)収録現場の様相でした。
YouTubeで公開されるものを、約4時間、坐ったままで見ている
価値があったかどうかは、意見は分かれると思いますが、
39頁の資料をいただいて、約700人(満席)の多くの方が
来場されている雰囲気を味わうことが出来たので、
参加して良かったと思っています。
私は、系図オタクですので、仁徳天皇紀に出てくる
「淤宇宿禰(意宇足奴命)」の墓が、出雲の前方後方墳の
主らしい、という発表が、一番記憶に残っています。
手元の系図集には、「毛呂須命」が出て来ます。私は、
これは、「母呂須玖(但馬諸助・モロスク)」ではないかと。
そうすると、「淤宇宿禰(意宇足奴命)」は、
「母呂須玖(但馬諸助・モロスク)」の子孫ではないだろうか。
これは、楽しみです。ワクワクしています。
うまくいけば、前方後方墳の謎が解けるかも知れません。
系図オタクとして、楽しみがひとつ出来ました。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - 米田
2024/11/18 (Mon) 10:39:17
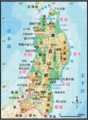 :北東北歴史懇話会。
:北東北歴史懇話会。
*****
古墳のない地域の歴史をどう語るか?
ー弥生・古墳時代併行期の北東北の様相ー
主旨
稲作農耕や青銅器で知られる弥生時代には社会階層が生まれ、
やがて畿内を中心に巨大前方後円墳を築く初期国家が形づく
られます。中国の史書に描かれる倭の五王が、東アジアを
相手に活躍した古墳時代の到来です。
この激動の時代、北東北では何が起こっていたのでしょうか。
この地域では縄文文化に系譜をもつ本州北端の弥生文化と、
北海道から南下した続縄文文化が共存していました。
その後に古墳文化の集落が北上しますが、大規模な古墳は
最後まで築かれませんでした。
*****
:「えみし」といわれる人たちは、どんな人たち?
:「えみし」は、どうなったの?
:「えみし」は、本当に、秋田県人の祖先(ルーツ)なの?
:秋田県人たちの祖先である。「えみし」って何だろう?
:という疑問に対する、何回目かのシンポジウムでした。
:パネリストの方々は、懇話会会長の意図を汲んで、
:悪戦苦闘している様子が(終わり頃になって)分かりました。
:最後の方で、北緯39度40度の話になって、急に話が
:盛り上がりました。
:結局、「えみし」は、分かりません。これが結論でした。
:私がこだわったのは、下記の記述でした。
┌
│横手盆地における竪穴建物跡の特徴…
│①カマドがなく、炉が設けられる(地床炉または灰穴炉?)
└
:この表現(表記)は、専門家向けの現場の報告書としては、
:ベストの表記です。
:でも、この表記は、素人の私には、つらいです。
*****
『竪穴式住居(たてあなしき-)』(ウィキペディアより)
:竪穴式住居、または竪穴建物(たてあなたてもの)・竪穴住居
:は、地面を掘り下げて床とし、その中に掘立柱を建てて
:梁(はり)や桁(けた)、垂木(たるき)を組み、
:土や植物(葦など)で屋根を葺いた建物である。
:
:炉(地床炉・石囲炉・土器埋設炉・土器囲炉・粘土床炉・
:石床炉など)は、煮炊き(調理)や照明、鍛冶作業などに使用
:され、特に地床炉は縄文時代から古代まで普遍的に存在した。
:古墳時代中期にカマドが出現すると、調理施設としては
:カマドに交代していくが、炉自体はなお存続した。
:縄文時代中期末から後期にかけての新潟県から福島県以北の
:地域では「複式炉」と呼ばれる特殊な石囲炉が存在した。
:
:カマドは、主に竪穴壁に造り付けられた調理施設で、粘土を
:盛り上げてトンネル状の燃焼部(焚口)をつくり、上に開けた
:穴(掛口)に甕と甑を掛けて蒸し米作りや煮炊きを行ったもの
:である。
:竪穴壁をくり貫いて建物外に排煙する煙道(えんどう)を持つ
:ものが多い。
:古墳時代前期(4世紀)に九州北部や近畿地方で徐々に
:出現し、同時代の中期(5世紀)から後期(6世紀)にかけて
:東日本まで急激に普及した。
*****
┌
│横手盆地における竪穴建物跡の特徴…
│①カマドがなく、炉が設けられる(地床炉または灰穴炉?)
└
:これは、同じ時代の西日本の状況と比較してみるとか、
:同じ場所での、違う時代のと比較(変化)の中で
:説明がないと、素人には、伝わらないものです。
:考古学の同業者には、伝わるレベルの話でした。
:
:「かまど」と「炉」という切り口で、
:「えみし」を語ることも出来たのではないか。
:たとえ、結論は「分からない」であったとしても、
:興味が湧いたような気がします。
:
:また、「北緯39度」「北緯40度」の話は面白そうでした。
:今年は、
:「古墳のない地域の歴史をどう語るか?」という演題でした。
:
:ぜひ、来年は、リベンジとして、
:『古墳のない古墳時代。北緯39度40度の「えみし」のくらし』
:(こんな感じのシンポジウム)をしてほしいなと感じました。
:こんな表題でしたら、多くのひとが関心を持たれるのでは
:ないでしょうか。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - 米田
2024/11/18 (Mon) 10:32:02
:今までは、月1回のZOOM参加でも体力的には少しきつい
:かなと思って、講演会の参加を控えめにしていました。
:この1か月は、久しぶりに、会場参加をして、さらに
:ZOOMも参加しました。
10月19日(土)ZOOM参加。当会講演会『土器を掘る』
10月27日(日)会場参加_。古田史学の会・講演
11月10日(日)ZOOM参加。当会講演会「和鉄」
11月16日(土)ZOOM参加。北東北歴史懇話会・シンポジウム
11月17日(日)会場参加_。古代出雲文化シンポジウム
11月17日(日)ZOOM参加。当会会員研究会発表会(部分参加)
:17日には、シンポジウムの会場での休憩時間とか、帰りの
:電車の中まで、イヤホンで音声のみですが、会員研究の発表を
:聞いたりと、気力・体力の限界を感じた一日でした。
:持病の慢性腎臓病が悪化しそうで、怖いです。(笑)
:この一か月の印象(感想)を書きます。
:「古田史学の会」は、創立30周年でした。
:「九州王朝」的な結論に、こだわるあまり、理論武装が、
:言葉通りの理論武装になっているような気がしました。
:
:
:「古墳文化」・「鏡」・「土器」・「和鉄」については、
:「騎馬民族説」の探求と邪馬台国はどこか、日本人のルーツ。
:当会の目的は、この三つだろうと思います。
:結論を急がず、いろいろな方面からアプローチしていて
:良いとは思っています。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - 米田
2024/11/16 (Sat) 09:32:55
 (予習)
(予習)
┌
│北東北歴史懇話会 2024 年度
│オンラインシンポジウム(2024/11/16)
│「古墳のない地域の歴史をどう語るか?
│―弥生・古墳時代併行期の北東北の様相―」
└
『末期古墳(まっきこふん)』(ウィキペディアより)
:末期古墳とは、7世紀から10世紀にかけて東北地方北部と
:北海道道央の石狩低地帯に造られた、円形を基本とし、
:土盛りが余り高くなく、周濠を伴う墳墓である。
:
:分布と築造年代
:末期古墳は東北地方の青森県、岩手県、秋田県と宮城県北部、
:そして北海道道央の石狩低地帯に分布している。
:
:築造年代は7世紀初頭から10世紀にかけてとされる。
:末期古墳は多くの墳墓が密集して造られる群集墳のような
:形で造られ、青森県の阿光坊古墳群のように、多い場合
:では100基を越える末期古墳で構成されることもある。
:
:一方、末期古墳が造営された地域の南にあたる宮城県
:中南部では、4世紀頃から7世紀にかけて、
:前方後円墳をはじめとする古墳が造られており、・・・。
:
:墳形と規模について
:形は楕円形のものや方形に近いものも少数見られるが、
:基本的に円形をしている。
:墳丘の周囲には周溝があるのが基本である。
:墳丘の規模は直径5メートルから10メートルのものが
:ほとんどで、最大でも17メートル程度である。
『終末期古墳(しゅうまつきこふん)』(ウィキペディアより)
:終末期古墳は、古墳時代末から飛鳥時代にかけての
:7世紀頃の古墳を指す。
:
:墳形
:墳形には、円墳・方墳・八角墳・上円下方墳などがある。
:天皇陵に限っては、前方後円形から大型方墳に変わり、
:次に八角墳が採用されることになる。
*****
横手盆地における竪穴建物跡の特徴…
_①カマドがなく、炉が設けられる(地床炉または灰穴炉?)
「かまど」と「炉(いろり)」の違い
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - 米田
2024/11/15 (Fri) 23:43:21
「夜見ケ浜人」の人骨の番組を見ました。
日経新聞の内容以上の話はありませんでした。
日経の記事から半年が経っているので、
何か進展があるかと期待していたのですが、
(記事以上の)進展の話はなかったです。
「化石骨」という話は、面白かったです。
年代測定などの詳しい研究の成果は、
年代測定が可能かどうかを含め、
数年先のお楽しみ、ということのようです。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2024/11/15 (Fri) 08:18:09
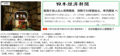 (番組の紹介です。)
(番組の紹介です。)
#日本最古の人骨発見!?
初回放送日:2024年11月15日
(日経新聞の記事)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE113ZB0R10C24A5000000/?msockid=2ee29a7b514766823623923950cd67d6
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - (管理人)
2024/11/02 (Sat) 17:15:05
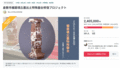 (FB談話室からの転載です。)
(FB談話室からの転載です。)
岡嶋 隆司
4日前 ·2024年10月28日(月) 23:03 ·
清家 章
5日前·2024年10月28日(月) 14:45 ·
クラウドファンディングにご協力いただき、
ありがとうございます。
クラウドファンディング期間も残すところ、10日となりました。
引き続きご協力の程どうぞよろしくお願いいたします。
Re: スレ「FC2のロビー・談話室11」 - 管理人
2024/10/28 (Mon) 15:21:27
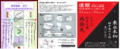 (FB談話室からの転載です。)
(FB談話室からの転載です。)
東アジアの古代文化を考える会
作成者: Naoko Urushibara
1日前 ·2024年10月26日(土) 21:08
中島庄一
3日前 · 2024年10月 24日(木) 13:49
韓半島製の渦巻装飾付鉄剣・韓半島製の土器が出土
北信濃弥生時代 東アジアの歴史の舞台に足をのせている
**********
北信州 木島平村(長野県下高井郡木島平村)
https://www.vill.kijimadaira.lg.jp/articles/2024102400016/
令和6年度 根塚遺跡シンポジウムについて
公開日 2024年10月25日
根塚遺跡シンポジウム開催のお知らせ
令和の再整理調査の結果、新たな展開があった根塚遺跡に
ついて、シンポジウムを開催いたします。
弥生時代研究の最前線で活躍される先生方をお招きし、新しい
根塚遺跡の発見やその魅力についてご講演いただきます。
開催日時・会場
シンポジウムは、次のとおり東日本編、西日本編の2回に
わけて開催します。
東日本篇
日時:11月17日(日曜日)午前10時から午後4時45分
会場:若者センター1階研修室
西日本篇
日時:11月30日(土曜日)午前10時から午後4時30分
会場:若者センター1階研修室
シンポジウム詳細
詳細はチラシをご確認ください。
根塚遺跡シンポジウムチラシ[PDF:4.31MB]
申込方法
電話、またはGoogleフォームにより、
村教育委員会生涯学習課へお申込みください。
※イベントは完全予約制です。
電話で申し込む場合
木島平村農村交流館 教育委員会生涯学習課
電話:0269-82-2041
受付時間:平日の午前9時から午後4時
Googleフォームで申し込む場合
下記のGoogleフォームリンク又はチラシ・ポスターに
掲載のQRコードからお申込みください。
Googleフォームリンク別ウィンドウで開きます
お弁当の申し込み
予約時に弁当(お茶付き800円)の希望も承ります。
ご希望の方は合わせてお申し込みください。
申込締切
11月8日(金曜日)
※11月8日以降の空席確認は電話連絡のみ承ります。
この場合、お弁当の予約はできませんのでご了承ください。