東アジア討論室
混み入った議論と一対一の論争は討論室で行いましょう。
投稿の大項目はスレッドで投稿してください。
そのスレッドに対するはレスとして投稿してください。
レスに対する意見もレスとして投稿してください。
スレッド作成での留意事項
●(新規作成の)スレッドには、タイトル(内容の紹介)と自分の名前を入れて下さい。
●みんなの関心事項については、「会」として、スレを(追加で)設けることもあります。
要望事項
●「返信・引用」を使う場合は、不要なところは削除したうえで、お使いください。(1回のみ)
●「返信・引用」は、多用すると、返信の返信となると、誰の発言か分かりにくいので、控えて下さい。
●また、文章では、適当なところで、右側に「改行マーク」を入れて下さい。(一行、45文字程度)
●また、一文(~。)の長さは、長くて3行まで、(およそ、150文字以内:推奨100文字以内)にして下さい。
●文章は、残ることを念頭に、マナーに気を付けて、楽しく(議論は熱く)投稿しましょう。
「資料批判が足りない」という言葉 - 米田
2025/03/24 (Mon) 22:14:01
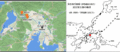 ┌
┌
│今の古代史界では「資料批判が足りない」という
│言葉が金科玉条のようになっています。
└
:史料や資料は、「資料批判が足りない」のであれば、
:「資料批判」をすれば良いのであって、
:その上で、使える処は、使いましょう。
:というのが、「史料・資料」に対する私のスタンスです。
Re: 私の好きな邪馬台国九州説:再再スタート - p君
2025/03/22 (Sat) 20:20:28
>関川・坂両氏の考古学的考察と合致するような
記紀などの文献史学のヤマト王権成立論の投稿期待します。
(その1)
ここで先代旧事本紀を出せば、吉備や讃岐など瀬戸内文化の
結集が纒向遺跡である、その証拠が巻第三・天神本紀のニギハヤヒ
が引き連れてきた多くの瀬戸内集団で説明できると思うのですが、
ニギハヤヒなんて名前を出した時点で資料批判が足りない、
先代旧事本紀は史料にならないと言われてしまうのでしょうね。
(その2)
纒向遺跡の外来搬入土器に東海土器の多いこと、
日本海土器の多いことも、これは神社伝承ですが、
ウマシマジや天香山が東海を制圧し、
そして日本海に抜ける事で説明できると思うのですが、
これも資料批判が足りないと言われて終わるのでしょうね。
(その3)
今の古代史界では「資料批判が足りない」という
言葉が金科玉条のようになっています。
Re: 「資料批判が足りない」という言葉 - 米田
2025/03/27 (Thu) 11:03:39
p君さんへ__小休止のお知らせ
(その1)
:ちょっと、この数日、ハイペースの投稿が続きました。
:このまま、続けると、私の頭と体がもたないです。
(その2)
:まだ、レジメは貰っていませんが、
:29日(土)の講演会の予習をしたいです。
(その3)
:30・31日に、一泊二日の予定で、(自分の所有でもないのに、)
:リアル管理人(除草・草刈り)の仕事をする予定です。
:ということで、頭をリセットしたいと思います。
:手を広げすぎました。(花粉もきついです。)
:回答を書くには、いろいろと調べなくてはなりません。
:自分の中で未解決にしている部分も、いろいろとあります。
:纏向に関しては、一部、当世奇妙さんのスレに書きました。
:
:気が向いたら、何かしら書こうとは思います。
:4月に入ったら、再開したいと思います。
Re: 「資料批判が足りない」という言葉 - p君
2025/03/26 (Wed) 19:45:36
>:その最古の前方後円墳は、「鶴尾神社4号墳」の事でしょうか。
違います、香川県丸亀市綾歌町の平尾墳墓群で古く見る人で紀元前の造営になります。
広島県福山市にも同じ時代の墳墓があるとの情報を得ましたが、詳細は分かりません。
どちらにしても前方後円墳のルーツは瀬戸内でしょう。
>:私は、個人的には、「神門5号墳」が、一番古いと思っています。
こういう話は考古学の先生方が年代を決めているので、米田さんが個人的に思う思わないではなくて、
神門古墳群は3世紀中ころ、纒向古墳群の纒向石塚、ホケノ山、勝山の方が古いです。
その纒向の各古墳よりさらに阿波の萩原墳丘墓の方が古いようです。
纒向型の神門古墳群が突然関東に現れること、ちょうど卑弥呼の死後に立つ千人が死ぬ騒乱の男王の時代です。
7世紀の朝廷は卑弥呼が誰なのかはもちろん、この騒乱の男王も誰なのかわかっていて、
そのまま書くと時代を古くした卑弥呼が分かってしまうので、この騒乱の男王の話を神話にしたのでしょう。
それがタケミナカタとタケミカヅチの神話です。
神門は関東の千葉市原、物部系と言われる経津主神こと香取大神ゆかりの墓だと私は推測しています。
保存問題で揺れる沼津の高尾山古墳の被葬者はこの神門古墳群被葬者の臣下のような人物で、
熊野神社、また穂積が訛ったのであろう穂見神社があること、これはやはり物部と思われ、
千葉の市原も沼津も銅鐸が出土しているイズモと呼べる土地ですので、これらを物部たちが抑えに行ったのでしょう。
>:特殊器台をはじめとする文化(技術)が、
>:ニギハヤヒのオリジナルかどうかは、不明です。
纒向古墳群が物部である根拠は2世紀末から6世紀末まで大和に君臨した大豪族で、
途中から崇神天皇がその墓制を取り入れ、以降天皇家の墓制となっていること、
蘇我の台頭とともに、前方後円墳が失われていくこと、などを総合して物部の墓としか考えられません。
違うというなら2世紀末から6世紀末まで大和に君臨したのは何者なのかお答え願いたい。
Re: 「資料批判が足りない」という言葉 - 米田
2025/03/25 (Tue) 23:55:29
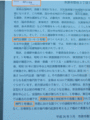
┌
│(その3)
│そして前方後円墳の最古は瀬戸内です。
└
:その最古の前方後円墳は、「鶴尾神社4号墳」の事でしょうか。
┌
│「鶴尾神社4号墳(つるおじんじゃよんごうふん)」wikiより
│鶴尾神社4号墳は香川県高松市西春日町に所在する
│古墳時代前期の前方後円墳。
│国指定の史跡「石清尾山古墳群」の一つで、
│香川県最古の古墳と見られている。
├
│「神門古墳群(ごうどこふんぐん)」wikiより
│神門古墳群は、千葉県市原市惣社にある古墳群。
│5号墳は千葉県指定史跡に指定されている。
│その造営年代は3世紀中葉から後葉とする説が有力であるが、
│3世紀前半まで遡ると見る見解もあり
│邪馬台国の時代の古墳と目されている。
└
:私は、個人的には、「神門5号墳」が、一番古いと思っています。
:共通点は、二つとも、天背男命(一書イザナギ)の子孫の
:「阿波忌部氏」の流れをくむ氏族(阿波・安房)の可能性があります。
┌
│(その4)
│他にも特殊器台、弧帯文(蛇ですが)、
│竪穴式石槨、土器の内面削り、ことごとく瀬戸内です。
└
:特殊器台をはじめとする文化(技術)が、
:ニギハヤヒのオリジナルかどうかは、不明です。
┌
│(その5)
│出されたその物部分布図、時系列が書かれてません。
│
│ざっくりいうと、
│筑紫→瀬戸内→畿内→全国です。
└
:原典を見ると、日本書紀や姓氏録、万葉集などとなっています。
:時系列でいいますと、氏族の分派による集団での移動を
:1世紀の後半以降と考えています。
:考えると、鴨族(スサノオの系統:金氏)、
:忌部氏(天背男命や脱解王の系統:于氏)、
:物部氏(ニギハヤヒ、天児屋根命の系統:朴氏)、が、
:大きく分けられます。解氏や弥生人については、不明です。
:彼らは、氏族単位で移動していました。
:この時は、首長と民衆は、地縁・血縁で固まっていました。
:
:これが、3世紀後半から、景行天皇が全国に、70余子の子どもを
:作り始めると、各地の首長層は、オセロのように氏(血統)が
:替わっていきます。これが、4世紀の武内宿禰(成務天皇)まで
:続きます。
:5世紀から6世紀に入ると、屯倉の制度が始まります。
:簡単にいうと、中央から代官がやってくるのです。
:「部民」の制度は、首長層が入れ替わる制度です。
:これらによって、首長と民衆は、地縁・血縁の関係が
:切り離されていきます。
:
:と、云うような歴史の流れの中で、神社の氏子の形態を取ったり、
:昔の首長層の没落で、在地化して、氏子代表になったりします。
:昔の氏族の出自を大切に残しているのが、この図表での全国の
:物部ということになります。(他の氏族のもあるみたいです。)
:7世紀後半以降、日本書紀の編纂に合わせて、
:各氏族が分割されて、氏族の系図も再編が行われています。
:その時に、残ったのものが、これらの記録です。
┌
│ざっくりいうと、
│筑紫→瀬戸内→畿内→全国です。
└
:物部氏は、そうだろうと思います。
:ほかの氏族では、
:越の国から、諏訪地方に向かったグループもあります。
Re: 「資料批判が足りない」という言葉 - 石見介
2025/03/25 (Tue) 23:42:16
米田さん
>史料や資料は、「資料批判が足りない」のであれば、「資料批判」をすれば良いのであって、その上で、使える処は、使いましょう。というのが、「史料・資料」に対する私のスタンスです。〈
というのは、私も同じであり、おそらく専門家を含む多くの古代史愛好家諸氏も、その立場でしょう。
しかし、「資料批判」の方法論についての考え方の相違や、実際の個々の事例では、その「程度」が、方法論の評価も含めて、大きく異なる為、「資料批判」が「不足」している、という「評価」が、「他者」によって、下されることになります。
専門の研究者であれば、資料批判も、「深い」が、我々のような古代史愛好家では、学史、研究史を踏まえた専門家並みの水準から、到底「資料批判をしました」とは思えないような「低い」「薄い」「浅い」水準まで,様々なのが、実情です。
その自覚が、どの程度あり、自身の資料批判後の、「解釈」「仮説」への「客観性」を、どのように判断しているのかも、問題です。
しかし、その部分については、今回は触れずに、『先代旧事本記』という「史書」についての、「資料批判」を、私流に行います。
①『先代旧事本記』という資料の成立年代について
平安時代初期に成立し、「本朝最古の史書」を、称したが、記紀や『古語拾遺』より、成立が遅い事は、定説である。
②同書の著者、撰述者について
不明であるが、物部氏所縁の人物で、目的は物部氏の顕彰目的であり、物部氏に関する伝承や記録を保有した,史官的人物だと思われる。
安本美典氏説の矢田部公望などが、考えられる。
③内容の信頼性については、饒速日後裔を称する氏族系譜には、一定の伝承が反映されており、又、平安時代初期で、他史書に無い国造本記等は、使用せざるを得ないが、個々の事項ごとの入念な資料批判を要する。
④本書の撰述目的が物部氏の栄光を、称える目的なので、「物部氏」という、部民制成立後の「氏族名」を持つ「伴造宰領氏族」が、部民制の存在しない時代の配下の氏族群と、「古くから」主従関係を有していた、という伝承は、後代の可能性が強く、信頼できない部分である。
はっきり言えば、筑紫や吉備の物部は、大和王権確立後に、屯倉設置や地方豪族牽制の為に、設置されたものを、時代を逆転させて、饒速日の最初からの従者に仕立てられた可能性が高い。
まあ、ざっとこんなところです。
Re: 「資料批判が足りない」という言葉 - 米田
2025/03/25 (Tue) 23:20:01
 ┌
┌
│(その1)
│播磨の物部、讃岐の三野物部がニギハヤヒに
│伴ってやってきたと書かれてますが。
│
│(その2)
│先代旧事本紀にニギハヤヒが多くの瀬戸内集団を
│伴って畿内に来たことが書かれています。
└
(その1):掲載図の「コトバンク」をお読みください。
┌
│(その2)
│先代旧事本紀にニギハヤヒが多くの瀬戸内集団を
│伴って畿内に来たことが書かれています。
└
:この文章が正しければ、ニギハヤヒが瀬戸内に来る前から、
:瀬戸内集団が、現地に存在していたことになりますが、・・・。
Re: 「資料批判が足りない」という言葉 - p君
2025/03/25 (Tue) 17:34:09
>:「瀬戸内要素の強さ」を物部氏と云えますか?
言えます。
先代旧事本紀にニギハヤヒが多くの瀬戸内集団を伴って畿内に来たことが書かれています。
そして前方後円墳の最古は瀬戸内です。
他にも特殊器台、弧帯文(蛇神です)、竪穴式石槨、土器の内面削り、ことごとく瀬戸内です。
>:「吉備・播磨・讃岐」に物部氏はいますか?
います。
播磨の物部、讃岐の三野物部がニギハヤヒに伴ってやってきたと書かれてますが。
米田さんが出されたその物部分布図、時系列が書かれてません。
ざっくりいうと、
筑紫→瀬戸内→畿内→全国です。
Re: 「資料批判が足りない」という言葉 - 米田
2025/03/25 (Tue) 16:19:05
 ┌
┌
│纏向遺跡なんて、あの瀬戸内要素の強さは
│ニギハヤヒや物部以外に解けないです。
└
:掲載図を見て下さい。
(近くの図書館で見つけた、寄贈本より)
:
:この物部氏族の分布図を見て、
:「瀬戸内要素の強さ」を物部氏と云えますか?
:「吉備・播磨・讃岐」に物部氏はいますか?
PS:寄贈本の詳細
「物部氏族の研究資料」(非市販)_昭和53年5月1日発行
編集者兼発行人_石上光太郎
印刷所_有限会社 北成社
Re: 「資料批判が足りない」という言葉 - 米田
2025/03/25 (Tue) 15:59:50
┌
│Re: 「資料批判が足りない」という言葉 - p君
│2025/03/25 (Tue) 14:09:14
│
│結局、資料批判という概念自体が人によってバラバラなんです。
│
│みんな自説の都合が良いように使ってる気がします。
│ある人によれば神武を出すこと自体、資料批判が
│足りないとなるし、神武は良いが、ニギハヤヒ、スサノオを
│出すと資料批判が足りないとなる。
│
│纏向遺跡なんて、あの瀬戸内要素の強さは
│ニギハヤヒや物部以外に解けないです。
└
:p君さんへ。下記の掲載図をよく見て下さい。
┌
│Re: 「資料批判が足りない」という言葉 - 米田
│2025/03/24 (Mon) 22:48:24
└
:事実関係を(ひとつひとつ)押さえて行きましょう。
:
:(その1)
:ニギハヤヒは、「天の岩船」で、畿内に到着後、1年後に死亡。
:
:(その2):長スネ彦を殺したのは、誰になっているか。
:
・日本書紀:ニギハヤヒが、長スネ彦を殺した。
・皇孫本紀:宇摩志麻冶命は、長スネ彦を殺した。
・古事記_:登美毘古を殺したのは、神武天皇。
・(某偽書):ニギハヤヒは、158年没。長スネ彦は、159年没。
:
:私の予想では、長スネ彦殺害は、作り話。
:(ついでに、神武東征も、主役から戦果まで、すべて、作り話。)
:事実に近いのは、風土記の記述だけだろうと思います。
:(これが、私の資料批判です。)
:
:(その3):ニギハヤヒは、長スネ彦をいつ知ったか。
:「天の岩船」で、畿内に到着後、初めて会った(???)。
:系図をよく見て下さい。
:宇摩志麻冶の母親は、長スネ彦の妹ですよ。
:(その4):いつ・どこで・長スネ彦の妹を妻にしたか。
:
:いつ_?:「天の岩船」の、20数年前。
:どこで?:半島か、九州か、・・・。
:
:当然、20数年前から、長スネ彦のことを知っていたはずです。
┌
│纏向遺跡なんて、あの瀬戸内要素の強さは
│ニギハヤヒや物部以外に解けないです。
└
:吉備や河内は、紀元前の時代から、栄えていた国際貿易都市です。
:(おそらく、BC1世紀は「解氏」が支配していたと思います。)
:
:1世紀の中頃、「天背男命(一伝イザナギ)」が、やって来ます。
:天日鷲命(脱解王)の子孫の一部は、阿波忌部氏になります。
:長男の櫛明玉命(「天の岩戸」の「天明玉」)は出雲に残ります。
:
:2世紀の初めから中頃に掛けて、大規模な移動が始まります。
:系図にしてみると不思議なのです。(追いかけっこなのです。)
────事代主命──┐___神武天皇──┐(薩摩で誕生)
_陶津耳命─玉櫛媛命┴─媛蹈鞴五十鈴媛命┴─手研耳命
(三嶋溝咋)
─溝咋耳命───活玉依毘売─┬─五十鈴依媛命─┬─卑弥呼
────事代主命──────┘_神武天皇───┘(三輪で誕生)
:「陶津耳命」と「三嶋溝咋」と「溝咋耳命」は、同一人物です。
:私の推測では、
:帥升(遂成・次大王)の命令で、神武天皇(新大王)は、
:ほかのメンバーと一緒に、東征をしていた、と考えています。
:ほかのメンバーというのは、
:ニギハヤヒとか長スネ彦のグループが、ひとつあります。また
:天富命(事代主命)は、忌部氏のグループを率いています。
:系図をいじっていると、まだまだ、登場人物はたくさんいます。
Re: 「資料批判が足りない」という言葉 - p君
2025/03/25 (Tue) 14:09:14
結局、資料批判という概念自体が人によってバラバラなんです。
みんな自説の都合が良いように使ってる気がします。
ある人によれば神武を出すこと自体、資料批判が足りないとなるし、
神武は良いが、ニギハヤヒ、スサノオを出すと資料批判が足りないとなる。
纏向遺跡なんて、あの瀬戸内要素の強さはニギハヤヒや物部以外に解けないです。
Re: 「資料批判が足りない」という言葉 - 米田
2025/03/24 (Mon) 22:53:24
┌
│(その3)
│今の古代史界では「資料批判が足りない」という
│言葉が金科玉条のようになっています。
└
:「資料批判が足りない」というのであれば、自分で
:「資料批判」をして、使える処は使えば良いのです。
:まあ、私の資料批判も、多少、暴走気味だろうとは思います。
:とにかく、
:「資料批判」を他人任せにしていては、議論は進みません。
:討論室で、論を書くのでしたら、どんどん、「資料批判」をして、
:どんどん、資料を使っていきましょう。
Re: 「資料批判が足りない」という言葉 - 米田
2025/03/24 (Mon) 22:48:24
 ┌
┌
│(その2)
│纒向遺跡の外来搬入土器に東海土器の多いこと、
│日本海土器の多いことも、これは神社伝承ですが、
│ウマシマジや天香山が東海を制圧し、
│そして日本海に抜ける事で説明できると思うのですが、
│これも資料批判が足りないと言われて終わるのでしょうね。
└
:伊勢国の風土記によると、神武東征の前に、伊勢津彦が
:伊勢の国にいた。そして、神武東征の後に、伊勢津彦は
:信濃の国に移った、ということが記されています。
:この伊勢津彦とは、誰か、が問題になります。
:
:(日本書紀・神武天皇紀)
:黒速を磯城の県主にした。←←←←←←←←←「ニギハヤヒ」
:道臣命を築坂邑(橿原市鳥屋町辺)に、云々。←「宇佐津臣命」か
┌
│ウマシマジや天香山が東海を制圧し、
└
:ウマシマジや天香山が東海を制圧したかどうかは、不明です。
:東海は、(一番には)伊勢津彦の影響が強いと思われます。
┌
│そして日本海に抜ける事で説明できると思うのですが、
└
:ウマシマジや天香山が、越のくにや出雲に向かったのは、
:事実だろうと思います。しかし、
:ウマシマジが誰か、という処に目を向けないといけないと
:思います。(それが、史料批判だろうと思います。)
(日本書紀と古事記と先代旧事本紀での続柄の違いは、図を参照)
:「ウマシマジや天香山」と「物部氏」について云うと、まず、
:物部氏の系図は、本来は、ニギハヤヒの男系が本家筋だった
:ようです。それを、日本書紀編纂のときに、御食津臣の男系が
:婿養子の形で、系図を書き替えて、系図を乗っ取っています。
:まず、これが一つ目です。(物部氏の棟梁は誰か。)
:二つ目は、
:「葉江」と「猪手」のどちらが嫡流になるかということです。
:どちらの男系も、没落はしていますが、自分たちの先祖が
:本家筋で「ウマシマジ」であるというプライドがあるようです。
┌
│そして日本海に抜ける事で説明できると思うのですが、
└
:これには、もうひとつ、問題があります。
:葉江(天香山)の娘である「天女の妹」は、
:190年よりも後に生まれています。
:(二男の梨迹臣命=難升米は、210年頃の生まれでしょうか。)
:
:そうすると、伊賀津臣が天女の妹を妻にするのは、幼女だったと
:しても、190年から200年の間になります。
:これは、纏向が作られた時期に、重なります。
:そうすると、196年頃に、卑弥呼が都を作った時に、
:「葉江」も「猪手」も、ヤマトから追い出されています。
:沿岸の防衛のために、越や出雲に異動させられたのか、
:それとも、謀反の恐れがあるために、追い出されたのか。
:それとも、単に、纏向の土地を、明け渡しただけなのか。
:この辺りは、興味があるところです。
Re: 「資料批判が足りない」という言葉 - 米田
2025/03/24 (Mon) 22:35:48
┌
│(その1)
│ここで先代旧事本紀を出せば、吉備や讃岐など瀬戸内文化の
│結集が纒向遺跡である、その証拠が巻第三・天神本紀のニギハヤヒ
│が引き連れてきた多くの瀬戸内集団で説明できると思うのですが、
│ニギハヤヒなんて名前を出した時点で資料批判が足りない、
│先代旧事本紀は史料にならないと言われてしまうのでしょうね。
└
高皇産霊尊は
「葦原中国の敵が神を拒絶して待ち戦うものが有れば、
よく策略を用いて欺き防いで、治め平らげよ。」と仰った。
三十二人に指示して共に防ぎ守るよう天下りの伴に命じた。
【天の岩戸】に登場
天鈿賣命(あめのうずめのみこと)
______猿女君(さるめのきみ)等の先祖
天太玉命(あめのふとたまのみこと)
______忌部首(いんべのおびと)等の先祖
天児屋命(あめのこやねのみこと)
______中臣連(なかとみのむらじ)等の先祖
天櫛玉命(あめのくしたまのみこと)
______鴨県主(かものあがたぬし)等の先祖
天糠戸命(あめのぬかどのみこと)
______鏡作連(かがみつくりのむらじ)等の先祖
天明玉命(あめのあかるたまのみこと)
______玉作連(たまつくりのむらじ)等の先祖
【神武東征】に登場する「宇摩志麻冶命」のこと
天香語山命(あめのかごやまのみこと)
______尾張連(おわりのむらじ)等の先祖
『古代豪族系図集覧』神統譜・天神系の系図より
(↓天御中主神の8世の孫)
居々登魂命
|
天児屋根命__【天の岩戸】
|
天押雲命
|
天種子命___【神武天皇紀】
|
宇佐津臣命__【神武東征】天香語山命は、ニギハヤヒの子。
(↑天御中主神の12世の孫)
(風土記:12世の孫の〇が伊勢の国を平定した。)
『古代豪族系図集覧』忌部(阿波忌部)氏の系図より
天太玉命__(三十二人のひとり)
|
天櫛耳命
|
天富命___『先代旧事本紀』では、神武天皇の条に登場。
|
飯長媛命
:「天孫降臨」とは、「天照大神」の孫が降臨する話です。
:そもそも、本来の話は、「天照大神」の子がだめだから
:孫を降ろすという話です。それを、
:その孫(ニギハヤヒ)が子ども(天香語山命)を連れて
:降臨するという話は、どう見てもおかしいのです。
:さらに、【天の岩戸】の段に登場する人物たちが、
:ニギハヤヒ親子と一緒に、東遷するというのは、
:年代的に無理でしょう。
:「天照大神」の孫を降ろすという話はあったと思います。
:それを、紀では、神武天皇も「天照大神」の孫だから、
:神武東征の話を「天孫降臨」の話に変えてしまおう、と
:なって、さらに、先代旧事本紀では、それを、ニギハヤヒの
:「天の磐船」の話にすり替えて、しまっています。
:天鈿賣命(あめのうずめのみこと)と猿田彦が、おりていく
:話が「天孫降臨」でしたら、登場人物も違和感はありませんが、
:さすがに、ニギハヤヒを天孫だと言い始めると、さすがに
:【天の岩戸】の登場人物は、とっくに亡くなっています。
:とはいっても、だからと言って、「先代旧事本紀」全体を
:否定するのは、史料としては、もったいないですね。
:せっかくの史料なのですから、
:使える処はしっかりと使いましょう。
:
:この程度の資料批判は、自力でしたいですね。