東アジア討論室
混み入った議論と一対一の論争は討論室で行いましょう。
投稿の大項目はスレッドで投稿してください。
そのスレッドに対するはレスとして投稿してください。
レスに対する意見もレスとして投稿してください。
スレッド作成での留意事項
●(新規作成の)スレッドには、タイトル(内容の紹介)と自分の名前を入れて下さい。
●みんなの関心事項については、「会」として、スレを(追加で)設けることもあります。
要望事項
●「返信・引用」を使う場合は、不要なところは削除したうえで、お使いください。(1回のみ)
●「返信・引用」は、多用すると、返信の返信となると、誰の発言か分かりにくいので、控えて下さい。
●また、文章では、適当なところで、右側に「改行マーク」を入れて下さい。(一行、45文字程度)
●また、一文(~。)の長さは、長くて3行まで、(およそ、150文字以内:推奨100文字以内)にして下さい。
●文章は、残ることを念頭に、マナーに気を付けて、楽しく(議論は熱く)投稿しましょう。
スレ「4月講演会:仁藤 敦史先生」 - 管理人
2025/04/02 (Wed) 11:13:03
 .
.
【4月の講演会のご案内】
『「任那日本府」とは何だったか
~「日本書紀」編纂史料としての「百済本記」~』
■講師の言葉
朝鮮半島の南部には三世紀から六世紀にかけて
「加耶」と呼ばれる小国群が存在しました。
交易活動や鉄資源にもめぐまれていたため、東西の強国である
新羅や百済に挟まれても、長く独立を保つことができました。
倭国との交流も密接で、『日本書紀』には百済系の史料
「百済本記」に「任那日本府」や「任那の調」などと
表現された記載が残されています。
戦前以来の通説では、「任那日本府」は直轄支配をおこなった
証拠とされてきました。
従来の議論を塗り替えるためいくつかの説が提起されましたが、
まだ決定的な議論は提起されていないのが現状です。
そこで今回は、『日本書紀』からうかがえる任那の範囲や用例を
考察し、滅亡に至るプロセスを再検討します。
Re: スレ「4月講演会:仁藤 敦史先生」 - 管理人
2025/04/02 (Wed) 11:39:44
 (スレ「西日本新聞から」から転載)
(スレ「西日本新聞から」から転載)
スレ____:西日本新聞から
投稿者___:オヤジッチ
件数(投稿数):12
作成日時__:2023/01/12 (Thu) 13:42:15
最終更新日時:2023/01/28(Sat) 10:08:36
西日本新聞から - オヤジッチ 2023/01/12 (Thu) 13:42:15
磐井の乱「中央と地域王権の衝突」
福岡・飯塚市で古代史連続講座 2
023/1/12 6:02 [有料会員限定記事]
考古学者の高島忠平氏が監修する古代史連続講座
「古代から未来のトビラを拓(ひら)く
-遠賀川の古代文化と邪馬台国」(全9回)の第7回講座が
昨年12月10日、福岡県飯塚市のイイヅカコミュニティセンターで
あり、国立歴史民俗博物館(千葉県佐倉市)の
仁藤敦史教授と高島氏が講演した。
6世紀に九州の豪族筑紫君磐井とヤマト王権との間で起きた
「磐井の乱」などを通し、日本の古代国家の形成について論じた。
仁藤教授はまず磐井の乱が「中央のヤマト王権に対する
地方豪族の反乱」という説の根拠になっている日本書紀について、
「8世紀につくられ、天皇中心の政治体制がはるか昔から
続いていたように書いてあるが、そうではない」と指摘。
実際にはヤマト王権と磐井は「五分五分の対立」だったと主張した。
その根拠として、磐井は独立した外交権を持って(朝鮮半島の)
新羅などと交流があったとし、「かなり国家に近い形態を
持っていたとイメージしていいのではないか」と指摘。
また7世紀に編さんされた中国の「隋書」などの記述を根拠に、九州
地方はヤマト王権から独立した存在である時期が長くあったとした。
また、磐井の乱当時の継体天皇は、朝鮮に進出する軍事路線を進め、
北部九州に過重な兵力の負担を強いたといい、
このため磐井がヤマト王権よりも新羅と手を結ぶ方を選び、
磐井の乱につながったのはないかという説を唱えた。
高島氏は古代国家の形成について、8世紀に確立し、北海道、
東北、沖縄以外の日本列島を版図とした初期律令国家の領域と、
弥生人の環濠(かんごう)集落や青銅器の分布が同じ範囲で
あったことに注目。
「古代国家の形成とは日本列島の弥生人社会、
つまり(中国側の呼称である)倭人の政治的統一だった」
と持論を語った。
磐井の乱については、ヤマト王権と、当時日本各地に成立していた
地域国家の一つである「ツクシ(磐井)王権」の衝突だとした。
その上でツクシ王権の特色として、
「文官群、武官群で構成された統治組織を整えていたのではないか」
と主張した。
一方で、ツクシ王権は世襲的ではなく、傘下の有力豪族による
擁立だったとし、桂川町の国特別史跡「王塚古墳」に葬られて
いるのは一時、王権を担った人物ではないか、と推察した。
Re: スレ「4月講演会:仁藤 敦史先生」 - 管理人
2025/04/02 (Wed) 11:21:15
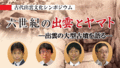 (FB談話室からの転載・再掲です。)
(FB談話室からの転載・再掲です。)
島根県古代文化センター
7時間 ·・2025年03月07日(金) 13:31
【古代出雲文化シンポジウム
「六世紀の出雲とヤマト―出雲の大型古墳を語る―」
の動画を公開しました!】
昨年11月17日に東京・有楽町朝日ホールで行われた
古代出雲文化シンポジウム
「六世紀の出雲とヤマト―出雲の大型古墳を語る―」の
動画を公開しました。
当センターyoutubeチャンネル「しまこだチャンネル」、
もしくは当センターHPの特設ページ
(https://shimane-kodaibunka.jp/sympo/r6sympo2024/)から
ご覧いただけます(視聴期限はありません)。
基調講演では、国立歴史民俗博物館教授の仁藤敦史氏が、
東西出雲の統一という視点から
出雲国の形成過程について語ります。
報告①~③では島根・近畿・九州の研究者が、それぞれの地域
における六世紀の大型古墳について独自の視点から解説します。
各講演者が登場するパネルディスカッションでは、
「六世紀の大型古墳を語る」と題して
熱い議論を繰り広げます。
計3時間に及ぶ大ボリュームの
シンポジウムを是非ご覧ください!
Re: スレ「4月講演会:仁藤 敦史先生」 - 管理人
2025/04/02 (Wed) 11:16:23
 .
.
【4月の講演会のご案内】
『「任那日本府」とは何だったか
~「日本書紀」編纂史料としての「百済本記」~』
―会場+オンライン(ZOOM)
■日 時 : 4月19日(土)14時~16時半 終了予定
■講 師 : 仁藤 敦史先生(国立歴史民俗博物館)
■会 場 : 北とぴあ901号室(王子駅徒歩3分)
■参加料:
会員1500円、一般1800円、学生500円、ZOOM視聴代:1000円
■照会先 : 080-4097-1757 inagaki34214590@yahoo.ne.jp 稲垣